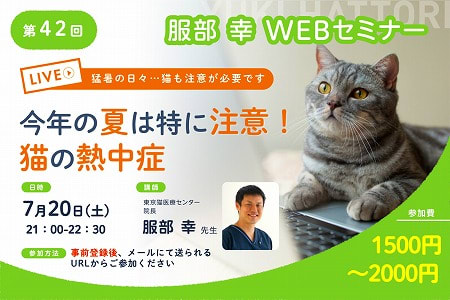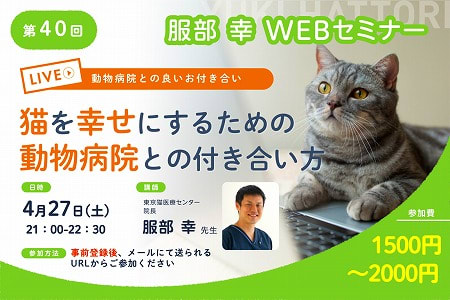今さっきまた神奈川県西部を震源とする地震がありました。
災害対策が現実味を帯びてきている気がします。
家庭の獣医学~災害と日常の健康管理~
佐伯潤先生
帝京科学大学アニマルサイエンス学科教授/(公社)日本獣医師会 理事/
帝京科学大学アニマルサイエンス学科教授/(公社)日本獣医師会 理事/
(公社)大阪府獣医師会 会長/くずのは動物病院 院長
ペットの災害対策に引き続き、聴講しました。
この講座の内容は公表できないので、
いままで私が学んだところから投稿しますね。
ふだんからペットたちの健康管理がなぜ大切かというと
ペットたちが健康に暮らすことはもちろんのこと
私たちにとっても無関係ではないからです。
(1975年、世界保健機関(WHO)では
「脊椎動物と人間の間で通常の状態で伝播しうる疾病(感染症)」と
定義付けをしています。)
以前シェルターメディスンの講座を受けた時、
避難所もシェルターと同じ。
しかもシェルターのように衛生管理ができにくい場所。
そのような場所では動物間の病気が蔓延しやすいわけです。
動物間だけでなく、人も同様衛生管理ができにくかったり、
体調も万全でなかったりと病気を予防する力が落ちているはずです。
ペットたちも同じと思うので予防できることはしておいてほしいです。
ふだんから予防できる病気については、
それぞれの生活に合った予防手段をとっておいてほしいです。
混合ワクチンを何種にするかなど。
狂犬病予防接種は絶対に飼い主の義務ですからね。
ワクチンと狂犬病予防接種の接種記録はどこでも見せられるように、
スマホで画像を保存しておくといいですよ。
畜犬登録票と済票はかならず犬の首輪に付ける。
家にいるときに首輪ごとはずす人が結構いるのですが、
万一の時のために登録票や迷子札をつけた首輪を
いつもつけてあげてくださいね。
迷子になった時にも首輪があれば捕まえやすいです。

川の氾濫や、市街地での浸水、土砂災害地での泥なども要注意です。
そういう場所で、釘やガラスを踏み抜いてしまったり、
手指を切ったり、とげをさしてしまったり、
できるだけ、準備するときにそうならない注意が必要ですよね。
靴の中敷きを踏み抜きしにくいものにするとか、
軍手より革の手袋にするとかね。
犬のシューズもあった方がいいかもです。
避難所に行く道歩かせるならなおさら。
横浜市地域防災拠点におけるペット災害対策(ダイジェスト版)
避難所では、犬猫が苦手な方、
いろんな世代の方、いろんな持病のある方、
ふだんは健康であっても自分も皆さんも
精神的肉体的に疲労困憊な方ばかりです。
たぶんずっとザワザワしているでしょうし、
大きな声でお知らせがあるかもしれません。
そんなところに飼い主さんのそばだからと
犬や猫が落ち着いて静かにしていられるとは思えません。
吠えたと言っては叱られてばかりいたら犬だって飼い主だって
辛いですよね。
同室で避難は、なかなかハードルが高いと思います。
いつも言ってることですが、
ぶっつけ本番は絶対に無理ですから、
なんでもない時からコツコツと
練習しておいてくださいね。

クレートカバーもあるといいですよ