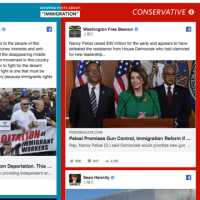| グローバリズム以後 アメリカ帝国の失墜と日本の運命 (朝日新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 朝日新聞出版 |
エマニュエル・トッド氏へのインタビュー記事をまとめた、「グローバル以後 アメリカ帝国の失墜と日本の運命」という書籍を、ご紹介いただいて読む機会を得た。
大変興味深い視点に富んだ書籍で、世界的に高名な文化人類学者・人口学者であるエマニュエル・トッド氏の、ひいてはフランスのエリート層の、底力を目の当たりにした。
今日昼頃散髪したのち、カフェで一気に読んでしまった。
これほど夢中になって本書を読んだ背景には、僕が、現在の日本の政治情勢に、まったく期待を持てていないという側面がある。
今朝の日曜討論における、テロ等準備罪新設法案に関する与野党代表者の議論がそれを象徴していた。
それはもはや討論ではなく、自分の立場の主張、言葉じりを捉えたくだらない掛け合いでしかなかった。
国会の討論をじっくり眺められるほど時間的余裕を持たない僕だけれど、おそらく国会で繰り広げられている議論も同レベルのものだろう。
そこに、政治家が自分の信念、信ずるものを国民をに理解してもらおうという意思は感じられず、傲慢な態度が目についた。
さらに僕を落胆させるのは、ツイッターを中心とするインターネットにおける、目の当てられない罵詈雑言、相手陣営への罵り合いである。
そこに知性は感じられず、全く言語が通じない者同士が、狭い空間で叫びあっているような、おぞましい、大いなる消耗が繰り広げられている。
そうした虚脱感の中で、エマニュエル・トッド氏の知的主張は、僕の知的好奇心に興奮を与えてくれる。
彼の重要な主張のひとつは、日本、および先進諸国は、
①共同体的な信仰の喪失、②高齢化、③社会を分断する教育レベルの向上、④女性の地位の向上、
による、「人類学的な革命の時代」におかれているというものである。
①は、「経済的合理性」しか「信仰」をもてない現代の「良い生き方」の規範、「集団が共有する展望」の欠落;
②は、ナルシシズムの高齢者間での蔓延;
③、④については、高等教育の広がりによる、「教育という点で階層化された社会」すなわち「文化的に不平等な社会」の再出;
をそれぞれ意味している。
また、彼の発言の中には、「民主主義は、エリートなしでは機能しない」「責任感あるエリートを必要としている」というものがあった。
上記①~④の課題を乗り越えるためには、エリート(高等教育を受けた人)が、国民国家の枠組みの中で、高等教育を受けていない人と「共通しているところがあるのだ」という理解にたどり着き、(ウルトラリベラルな幻想を捨て、)「責任ある、理にかなった、節度ある民主主義」を成立させることが必要だと説いている。
さもなければ、「社会の崩壊」「無秩序への回帰」「社会の粉砕」「暴力の高まり」が待っているだろうと。(p57)
一方で、彼は、「グローバル化の影響」により「高等教育を受けながら経済的にはみじめな人生を送ることになるだろうと気づいている人がいます」という。
こうしたなかで、日本の「エリート」がそうした役割を発揮するためには、何がキーになるのか。
カフェからの帰りの電車の中で考えてみた。
だいぶ長くなってしまったので、結論だけ述べてここは終わりにしようと思うが、
自分が公的機関で働いた経験も踏まえて達した、現時点の結論は、
①エリート層が適切なモチベーションをもって競争環境に身を投じ、選抜されたものが適切な社会的地位につけるようにすること、
②その実現のために、まずは公的機関の構成・構造を適正化し、流動性を持たせること、
③特に、官民含めてエリート同士が幅広く交流し、正しいモチベーションを維持しあう場を持てるようにすること
の3つがキーなのではないかと感じている。