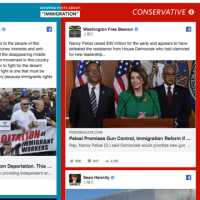IE Global MBAの体験談をご紹介している本ブログ。
2016年夏の卒業後、大企業からの転職を経て東京のスタートアップ企業での生活をしている僕ですが、
MBAとスタートアップ経験を通じて「成功するスタートアップとは何か」ということをよく考えるようになりました。
現在放映中のNHK大河ドラマ「西郷どん」が面白く、幕末の歴史への興味が再燃したこともあり、先日、山口県に旅行に行きました。
旅行中に滞在した宿が幕末志士たちとのつながりを強みとしてアピールしていた宿だったのですが、その宿に以下の本が置いてありました。
何気なく手に取ったのですが、とても考えさせられる本で、数時間で一気に読んでしまいました。
この本は、「南洲翁遺訓」という書物の解説を通じて、西郷隆盛の哲学、政治観を読み解くものです。
「南洲翁」とは西郷隆盛の号をとった敬称で、「南洲翁遺訓」は西郷隆盛の生前の言葉を、西郷の死後、旧庄内藩(現在の山形県)の藩士たちがまとめた本だということです。
この本で紹介されている西郷隆盛の考え方は、世の中にインパクトを与える組織をつくって経営する上で欠かすことのできない要素を含んでいると感じました。
例えば、「敬天愛人」という言葉と、陽明学からきているという「知行合一」という言葉。
「敬天愛人」というのは、「天を敬い、人を愛す」ということですが、「天」とは簡単に言えば生まれながらに自分が持つ使命を指すと考えてよいでしょう。
「人を愛す」とは文字どおりに捉えていいと思います。
組織を経営する上で、経営者は組織という器を利用して自分がどのような社会的使命を果たすのか、常にその目的意識がなければ社会的インパクトを持つ組織経営はできないと、僕は考えます。
また、人を愛せないと、組織経営はできないと痛感することも多いです。
愛する人の対象範囲はいろいろあるとは思いますが、少なくとも従業員を含む自分の身近にある人へ愛を持って接することができないと、
まず組織が大きくならないし、大きくなる過程で壁にぶつかるだろうと、自らの経験からも多くの人のお話からも感じます。
「知行合一」とは、知(知ること)と行(行うこと)は同じ心の良知(人間に先天的に備わっている善悪是非の判断能力)から発する作用であり、分離不可能であるとする陽明学の考え方です(wikipedeiaより抜粋)。
この考え方が経営において重要であることは、僕がここで駄文を記述するまでもないことですが、特に経営上の決断をするときに周りの情報に流されすぎて決断できない・しない、または誤った決断をすることを避ける意味でも、心に刻んでおきたい考え方です。
さて、「知行合一」という陽明学から発している言葉が、西郷隆盛の言葉で引用されているように、西郷隆盛の思想のバックボーンには、当時の一般的な日本の教養人と同様、儒教を中心とする伝統的な東洋思想があります。
振り返れば、僕が学んだIE Global MBAのカリキュラムには(そしておそらく世界のほとんどのMBAもそうかと推察するのですが)、東洋思想が探求するような、個人の修養に関する授業がありませんでした。
米国のエンロンに端を発する経営者の職業倫理に関するようなものはありましたが、すべての考え方のベースになるような哲学を学ぶものではありませんでした。
もちろん、哲学はMBAの学びの前に、個々人で深めておくべき科目とも感じますし、多様な人間の集まるMBAで「克己」を体得するなどという授業があったとしても、まとまりのない結果に終わるのが目に見えています。
しかし、MBAで経営戦略や組織体制整備について学ぶ際には、組織を取り巻く「仕組み」の整備等、「個人」外側の事象に目が行きがちで、個人の全ての判断基準になる「世界観」を持つことの重要さが忘れられがちなのではないかと、「南洲翁遺訓」を読みながら感じました。
西郷隆盛は、「天」の使命に従う過程の前で、自らの生死も重要ではないと考えていたようです。
我々がイメージする武士が持つ死生観に近いように感じますが、
僕は経営という文脈では、文字どおりの「生死」の問題というよりも、目的達成のための「時間軸」の取り方の問題、という捉え方の方があっていると感じます。
この点についても最近感じることが多いのですが、今回はかなりのボリュームになってしまったので、また別の機会にお話しできればと思います。
2016年夏の卒業後、大企業からの転職を経て東京のスタートアップ企業での生活をしている僕ですが、
MBAとスタートアップ経験を通じて「成功するスタートアップとは何か」ということをよく考えるようになりました。
現在放映中のNHK大河ドラマ「西郷どん」が面白く、幕末の歴史への興味が再燃したこともあり、先日、山口県に旅行に行きました。
旅行中に滞在した宿が幕末志士たちとのつながりを強みとしてアピールしていた宿だったのですが、その宿に以下の本が置いてありました。
何気なく手に取ったのですが、とても考えさせられる本で、数時間で一気に読んでしまいました。
 | 西郷隆盛『南洲翁遺訓』2018年1月 (100分 de 名著) |
| クリエーター情報なし | |
| NHK出版 |
この本は、「南洲翁遺訓」という書物の解説を通じて、西郷隆盛の哲学、政治観を読み解くものです。
「南洲翁」とは西郷隆盛の号をとった敬称で、「南洲翁遺訓」は西郷隆盛の生前の言葉を、西郷の死後、旧庄内藩(現在の山形県)の藩士たちがまとめた本だということです。
この本で紹介されている西郷隆盛の考え方は、世の中にインパクトを与える組織をつくって経営する上で欠かすことのできない要素を含んでいると感じました。
例えば、「敬天愛人」という言葉と、陽明学からきているという「知行合一」という言葉。
「敬天愛人」というのは、「天を敬い、人を愛す」ということですが、「天」とは簡単に言えば生まれながらに自分が持つ使命を指すと考えてよいでしょう。
「人を愛す」とは文字どおりに捉えていいと思います。
組織を経営する上で、経営者は組織という器を利用して自分がどのような社会的使命を果たすのか、常にその目的意識がなければ社会的インパクトを持つ組織経営はできないと、僕は考えます。
また、人を愛せないと、組織経営はできないと痛感することも多いです。
愛する人の対象範囲はいろいろあるとは思いますが、少なくとも従業員を含む自分の身近にある人へ愛を持って接することができないと、
まず組織が大きくならないし、大きくなる過程で壁にぶつかるだろうと、自らの経験からも多くの人のお話からも感じます。
「知行合一」とは、知(知ること)と行(行うこと)は同じ心の良知(人間に先天的に備わっている善悪是非の判断能力)から発する作用であり、分離不可能であるとする陽明学の考え方です(wikipedeiaより抜粋)。
この考え方が経営において重要であることは、僕がここで駄文を記述するまでもないことですが、特に経営上の決断をするときに周りの情報に流されすぎて決断できない・しない、または誤った決断をすることを避ける意味でも、心に刻んでおきたい考え方です。
さて、「知行合一」という陽明学から発している言葉が、西郷隆盛の言葉で引用されているように、西郷隆盛の思想のバックボーンには、当時の一般的な日本の教養人と同様、儒教を中心とする伝統的な東洋思想があります。
振り返れば、僕が学んだIE Global MBAのカリキュラムには(そしておそらく世界のほとんどのMBAもそうかと推察するのですが)、東洋思想が探求するような、個人の修養に関する授業がありませんでした。
米国のエンロンに端を発する経営者の職業倫理に関するようなものはありましたが、すべての考え方のベースになるような哲学を学ぶものではありませんでした。
もちろん、哲学はMBAの学びの前に、個々人で深めておくべき科目とも感じますし、多様な人間の集まるMBAで「克己」を体得するなどという授業があったとしても、まとまりのない結果に終わるのが目に見えています。
しかし、MBAで経営戦略や組織体制整備について学ぶ際には、組織を取り巻く「仕組み」の整備等、「個人」外側の事象に目が行きがちで、個人の全ての判断基準になる「世界観」を持つことの重要さが忘れられがちなのではないかと、「南洲翁遺訓」を読みながら感じました。
西郷隆盛は、「天」の使命に従う過程の前で、自らの生死も重要ではないと考えていたようです。
我々がイメージする武士が持つ死生観に近いように感じますが、
僕は経営という文脈では、文字どおりの「生死」の問題というよりも、目的達成のための「時間軸」の取り方の問題、という捉え方の方があっていると感じます。
この点についても最近感じることが多いのですが、今回はかなりのボリュームになってしまったので、また別の機会にお話しできればと思います。