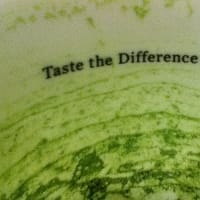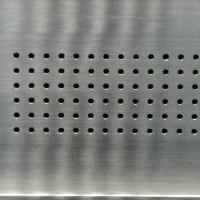ドラムキッズ(ドラムが好きな子供)であるヒビキが、キッズドラマー(コドモなんだけどれっきとしたドラマー)になるためには、どんなレッスンを受けさせるのがいいのだろうか?
ま、親というのは往往にして、このような思考回路でおるもので、当の私がそうであった。
しかしながら、誰々先生のレッスンを受ければ「誰もが」キッズドラマーになれるわけでなく、クラシック界のように音大とかそういう突破しなければいけない狭き門があって、そのためには誰々先生のレッスンを受けなければならない/受けたほうがいいというようなコワイ話も聞かない。リズム感だのノリだのタメだのが、先生の叩くのを観たからといって途端に身につくとも思えない。
じゃあつぶすのは簡単で伸ばすのが難しいジャンルなのかというと、コドモというのは案外そういうところはしたたかで、自分の中から自然と出てくるものには、結構抵抗を受けても自信を失わず、平気である。もちろん個人差はあると思うし、程度にもよると思う。しかし、オトナから見ると一見自信がなくおとなしくしているようでも(ヒビキだって基本的にはこういうタイプだ)、いったん演奏が始まったら、やはり自分というものをしっかりキープできなくて、どうしてドラムが叩けようか? そういう意味ではキッズドラマーはどのみち老成した存在なんじゃないかと思う。
有名スポーツ選手の、特にフィギュアスケートとか体操とかマラソンとかのコーチが、選手に負けず劣らず有名なのとは対照的に、スティービー・ワンダーの音楽の先生とか、ヴァン・ヘーレンのアドバイザーとか、リンゴ・スターのコーチなどというものは別に有名ではない。ことばのあややに失しているかもしれないけど、音楽は影響を受けるもので、指導されるものではない、ということなのかもしれない。
逆に言うとドラムの先生という存在は、そこも含めて指導ということを担当してくださっているわけである、従ってそちらの側から見ると、またさまざまなコドモがおり、さまざまな対策がありという具合で、非常に深いノウハウが蓄積されているものと察される。
つまり、である。門を叩いて、先生がコドモを教えてもいい、と言ってくださるとしたら、そこんとこ大丈夫ですよ、という意味だと思う。やってみてうまくいかなかったら、やめてもきっと大丈夫だろう。こういったことは初めからわかっていたわけじゃなかったんだけれども、今はおおかた、そんなふうに考えている。コドモに音楽的で、いい影響を与えてくれそうな先生に出逢うこと、それが大事なことだと思う。
ま、親というのは往往にして、このような思考回路でおるもので、当の私がそうであった。
しかしながら、誰々先生のレッスンを受ければ「誰もが」キッズドラマーになれるわけでなく、クラシック界のように音大とかそういう突破しなければいけない狭き門があって、そのためには誰々先生のレッスンを受けなければならない/受けたほうがいいというようなコワイ話も聞かない。リズム感だのノリだのタメだのが、先生の叩くのを観たからといって途端に身につくとも思えない。
じゃあつぶすのは簡単で伸ばすのが難しいジャンルなのかというと、コドモというのは案外そういうところはしたたかで、自分の中から自然と出てくるものには、結構抵抗を受けても自信を失わず、平気である。もちろん個人差はあると思うし、程度にもよると思う。しかし、オトナから見ると一見自信がなくおとなしくしているようでも(ヒビキだって基本的にはこういうタイプだ)、いったん演奏が始まったら、やはり自分というものをしっかりキープできなくて、どうしてドラムが叩けようか? そういう意味ではキッズドラマーはどのみち老成した存在なんじゃないかと思う。
有名スポーツ選手の、特にフィギュアスケートとか体操とかマラソンとかのコーチが、選手に負けず劣らず有名なのとは対照的に、スティービー・ワンダーの音楽の先生とか、ヴァン・ヘーレンのアドバイザーとか、リンゴ・スターのコーチなどというものは別に有名ではない。ことばのあややに失しているかもしれないけど、音楽は影響を受けるもので、指導されるものではない、ということなのかもしれない。
逆に言うとドラムの先生という存在は、そこも含めて指導ということを担当してくださっているわけである、従ってそちらの側から見ると、またさまざまなコドモがおり、さまざまな対策がありという具合で、非常に深いノウハウが蓄積されているものと察される。
つまり、である。門を叩いて、先生がコドモを教えてもいい、と言ってくださるとしたら、そこんとこ大丈夫ですよ、という意味だと思う。やってみてうまくいかなかったら、やめてもきっと大丈夫だろう。こういったことは初めからわかっていたわけじゃなかったんだけれども、今はおおかた、そんなふうに考えている。コドモに音楽的で、いい影響を与えてくれそうな先生に出逢うこと、それが大事なことだと思う。