それよりも、羨ましいのは中国のコンテスタントから受ける揺るぎない自己肯定感である。あれは日本人にはなかなか持ち得ないものだ。日本人が言う「自分らしく」というのは、他者に対するコンプレックスや自信のなさやアイデンティティの不安から逃れようとして口にするものであり、「自分らしさ」はさまざまな葛藤の上に手に入れるものであるのに、彼らは最初から当たり前のように持っているのは中華思想と一党独裁体制のせいかしらん、などと考えてしまう。
凄い、全然余力がある。音楽がおっきい。
体験。これはまさに体験だ。彼の音楽は、「体験」なのだ。
本当に、全くもって人間の記憶の仕組みがどうなっているのか分らない。
いったいどこがどう繋がって、遠い日のひとコマを引っ張り出してくるのだろう。
声を掛けられた瞬間、アッという間に歳月は巻き戻され、亜夜の脳味噌の開けたことのない引き出しがパッと開くのを感じた。
演奏者たちの中に、その自然はあった。彼らの故郷の風景や心象風景は、脳内に、視線の先に、十本の指先に、唇に、内臓に蓄積されている。演奏しながら無意識のうちになぞっている記憶の中に、彼らの豊かな自然は存在していた。
「知っている」のさ。最初からね。
それは、塵にとってはよく知っているタイプの人間だった。農家や園芸家など、自然科学に従事する人たち、特に植物を相手にしている人々に共通するのは気の遠くなるほどの辛抱強さである。自然界が相手では、人間ができることなどたいしたことではない。
そう直感する。恐らく、これはこの子が自分で作ったプログラムだろう。彼には、天性の編集能力がある。編集、という言葉はいろいろに使えるが、こんにちの音楽家には絶対に必要なものだ。自己プロデュース能力と言い換えてもいい。どういう音楽家になりたいか、どういう音楽家として見せたいか。そういう客観的視点を備えている音楽家だけが他と区別され、生き残ることができる。
プロとアマの音の違いは、そこに含まれる情報量の差だ。
一音一音にぎっしりと哲学や世界観のようなものが詰め込まれ、なおかつみずみずしい。それらは固まっているのではなく、常に音の水面下ではマグマのように熱く流動的な想念が鼓動している。音楽それ自体が有機体のように「生きて」いる。
やっぱりこの子は、生来音がいい。大きな景色を持っている。
音楽家というのは、自分のやりたい音楽が本当に自分でわかっているとは言いがたい。長くプロとしてやってきていても、自分がどんな演奏家なのか実は見えていない部分もある。
何かが上達する時というのは階段状だ。
ゆるやかに坂を上がるように上達する、というのは有り得ない。
弾けども弾けども足踏みばかりで、ちっとも前に進まない時がある。これがもう限界なのかと絶望する時間がいつ果てるともなく続く。
しかし、ある日突然、次の段階に上がる瞬間がやってくる。
なぜか突然、今まで弾けなかったものが弾けていることに気付く。
それは、喩えようのない感激と驚きだ。
素晴らしかった、素敵だった、ではなく、面白かった。
なるほど、この子の頭の中では、「版画」と「鏡」は繋がっているわけだ。つまりは、曲の風景からの連想なのか?
世界が、自分の知らない秘密の法則で出来ていると気付いた瞬間、窓の外の高く遠いところに感じた畏れ。
こんなにはっきりとすべてを感じ取り、何もかもを把握していると感じることは初めてであった。「覚醒している」というのは、こういう状態のことを言うのではないだろうか。
小野寺は、素晴らしいソリストと演奏していると、自分がイタコ状態になるのを感じる。
音楽。それはたぶん、人間を他の生物とは異なる、霊的な存在に進化させるために人間と一緒に生まれ落ちてきて、一緒に進化してきたのだ。
*印象的な人物たち
栄伝亜夜・風間塵・高島明石
*平成二十九年七月二十七日抜粋
*自分の立ち位置、ポジションがわからないまま彷徨い続けているだけなのかも知れない。途上にあるまま……
*小説としての構想力、筋の展開、読ませてしまう技術等々、素晴らしかった。













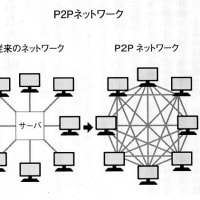
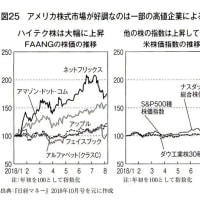

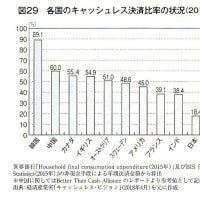
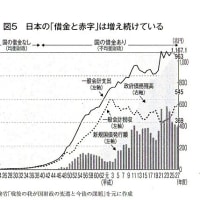

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます