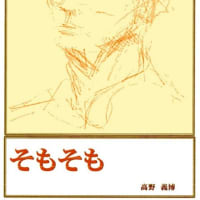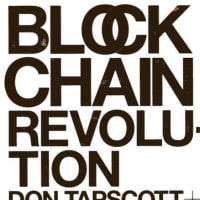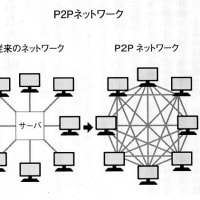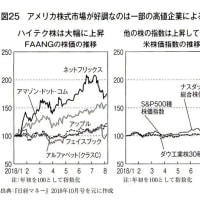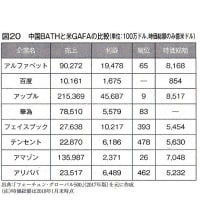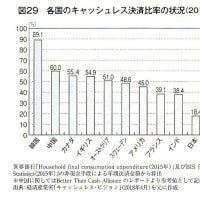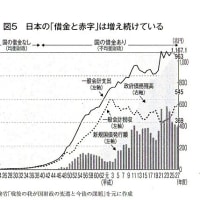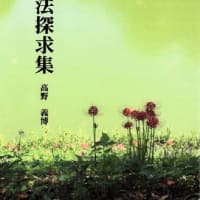「思い悩むは人の業」、どなたでも、それに憑りつかれるのがごくごく自然なことのようです!
どのような風景、状況、場面でも、大古より今、そしてこれからも人の業は続きます。
先人哲学者も、さまざまに思い悩んだようです。「無知の知」を説いたソクラテス、人間にとっての「真善美」を追究したプラトン、概念探求のカント、絶望の哲学者キルケゴール、「暗号解読」のヤスパ-ス、「存在のなぞ」を解明しようとしたハイデガー等々。
しかし、哲学はこのような難解晦渋、分厚い書物、高名な人物たちの中にあるとは限らないでしょう。むしろ、それはあなたの日々の生活の中にあり、それをあなたはそれと知らずにあなたなりのやり方で哲学しているのです。つまり、哲学は知るや知らずを別にしてすべての人びとの中にあるのです。
あなたの「はじめての哲学」は、孔子をはじめ多くの人が言っているように13~17歳頃のある特別な経験からすでに始まっているのです。未完成観・意識過剰・思案・意気阻喪・病的内省・罪悪感・死後不安・懐疑・現実出現・自意識誕生・外部世界突入……孔子はそれを「十有五にして学に志す」といいました。すべては志学元年の経験から始まっているのです。生活はそこから立ち上がり、論理の首尾一貫性を経て形成されます。
あなたの「志学元年の経験」は何でしょう?
この「はじめての哲学」では、それを発見するお手伝いをしております。
この本に、すばらしい書評をいただきましたので、下でご覧ください。
ハ-ドカバ- 352頁 近代文藝社 1995年 定価1800円→800円
初版発行、帯びつき、著者取り置き本。書評コピーを同封いたします。
Syncsell










Book Review 情緒の力業 高野 義博著
針生清人(東洋大学文学部教授、校友会副会長)
世の識者は屡々(しばしば)「哲学が今こそ必要だ」という。それは現代社会に「哲学」が欠如しているからだという。しかし他方で、『ソフィーの世界』の爆発的な売れ行きを見て、「哲学が流行している」ともいわれている。しかし哲学は他者に要求されて始めるものでも、流行となるようなものでもあるまい。
「生きるに値する人生とは何か」、「世界とは何か」、「かく生き、かく問う私とは何か」を問うことから始まるのが哲学の元来だとすれば、各自が内発的に「哲学する」ことにこそ意義があるのであって、本書はその好個の例だといえる。前述の問いは、概念が先か個物が先かの如き抽象的な形式で問いを立て、それに対して客観的な答を用意して教説する講壇哲学者とは異なって、問わずにおれぬが故に問うところのものであり、真に「哲学する」ことを示す重味が本書にはある。そうであれば、本書の内容を要約して紹介するよりは、本書が成立した所以のことを紹介した方がより意義があると思われる。
高野義博氏はヤスパースの「暗号について」を卒業論文(百枚)として提出した(主査故飯島宗享教授)。すでにロマン派の文学は自然と歴史を神の暗号と見なしていたが、ヤスパースも哲学と宗教の歴史、超越者との出会いという人類の最も重要な経験がいわば暗号で書かれていると主唱し、自己の哲学的な経験こそがこの暗号を解読し得るのであって、そうでない者にとっては暗号で書かれている深部はないかのようである。いうならば、科学的、合理的な目には歴史の表層しか見えぬということである。この問題を取り上げていた著者には、理性を万能とする知的な、科学的な客観主義への懐疑が既にあり、「私とは何か」の問いの暗号解読を試みていた。このことに関わって、校庭に遊ぶ友人達に突如、意識が集中して、「存在の事実として、客観的対象として、そこに彼等が居る事実を認めさせられた」という中学生時代の経験を卒論に記述していた。これが著者の哲学することの原点であったが、硬直した客観主義に批判的な実存主義者であった指導教授の故飯島教授は、後に、『気分の哲学―失われた想像力を求めて―』という著書に於いて著者のこの「経験」を引用されたのである。このことは、著者にとって卒論に記述された私的な問題であったものが、公刊、公開されたことによって社会的営為となったため、更に深くこの問題を問いつめることを不可避としたのである。
その追求は三十代を貫いて六百三十枚の『述語は永遠に…』となったのであるが、そこでの結論は、「私とは何か」を問うには知的な、科学的な客観主義に基く探求では限界があるということであり、概念ならざるものによる探求が更に進められ、本書となったのである。著者は社会人として生きながら、思索と読書と執筆に明け暮れ、「人生から三十代が抜け落ちていた」といわしめるほど、「哲学する」ものが格闘してきた軌跡を示すのが本書である。
本書の成立を支えたのは膨大なる読書量である。それは巻末に「文献一覧」として示されている。著者によると「三百冊程の本全てが一冊一冊有機的繋がりを持ち、読み進む度に新たな可能性が現れ細部が強固になる異常な精神の興奮の渦中で、意図せずに、自然に、幾多の啓示を受けたかのように、帰納的に或るヴィジョンが塊となった」というものである。しかも、読了した一冊一冊について、著者の心を深く捉えたと思われる箇所を引用し、列挙している。一読書人の読書記録としても壮観である。
著者が「哲学する」ことは更に続くであろうから、本書は尚「途上にあるもの」であるが、その論述されているところは的確であり、説得的である。著者が身辺を見回し、人生の意味を問い始めたのは、中学生時代の体験を問い直すことによってである。
このことについて、著者は孔子の「吾十有五而志干学」における「志学」を考える。それまで与えられた環境、習慣、伝統等にただ順応して生き、全てを「見て見ず」であった事象を初めて意識的にそれを「それ」として「そこ」に見るということによって、即有的な状態に外部世界=現実が出現し、主客分離が始まるという。このことが「志学」の意味だという。我々は本書を読むことで、「哲学する」志学一年を始め得るといえよう。
(東洋大学校友会報第一八八号 平成八年七月三十一日発行)