
今日の北海道新聞9面、各自核論(毎週金曜日に掲載)からのアップです
『子どもたちのために』作家 高村薫 「未来見据え環境整備を」
東日本大震災は日本が大きな岐路にさしかかっている時に起きました。
阪神大震災の時とは時代状況が変わっています。
当時、既にバブルは崩壊していましたが、ここまで日本の先行きが不透明になるとは誰も想像していなかった。
国力が落ち、人口が減少し、財政が傾き、その回復の見込みもない。
こんなにも、未来が見えなくなるとは。
今回の震災は三陸沿岸の過疎の町を襲いました。
人口が減少す中で、これから社会インフラをどうするんだという時にです。
限りある復興資金で行われるのは、道路であり、港湾であり、住宅の「元通り」の再建です。
失ったものを取り戻したいという気持ちは分かりますが、仮に実現したとしても、その先に未来はあるのか。
でも「元通りではだめだ」と政治もメディアもなかなか言わない。
被災者にはつらい選択ですから。
自分が現地の中高年だったらと考えると私自身も言えない。
これが今の日本社会の限界であり、私たちが直面しているのは「世の中にはどうしようもないことがある」ということではないか。
そんな、ある種の諦観があります。
でも一方で、理性がやっぱり、「このままじゃだめだ」って言うんです。
なぜなら、子どもたちがいるからです。
復興資金は当然、未来のために使わなければなりません。
未来とは何か。それは子どもたちです。
子どもたちのために、今何とかしなければならないことがある、と。
例えば、教育です。港湾や道路と違い、教育は形のないものです。
でも、子どもの教育に手厚いと言う環境がひとつあると、必ず大人が子どものために定着します。
そして、東北を中心に、雇用だけでなく、産業や研究機関、先端技術が集まってくる。
そういう生活圏が築けたら理想的です。
財政難の中で各自治体の要求をひたすら吸い上げる今のやり方では、すべてが中途半端に終わり、新しい廃墟があちこちに残されることになりかねない。
住宅や漁港などの社会インフラを集約することで、復興資金を子どもたちの方に振り分けるべきです。
そして、問題は原発です。
これまで地震国に54基もの原発があるという現実を眺めながら、いろいろな文章を書いてきました。
でも、それは頭で書いてきたもの。それがもはや、原発事故は、私が身体で受け止めた事実になっている。
そうなってしまった今...言葉がないんですよね。
私もこの時代をつくり、生きてきた一人なのですから。
無垢ではありません。
私たち中高年は子どもたちに対し、本当に頭(こうべ)を垂れるべきです。
再び大地震が起きた時の被害とその先の未来を考えたら、電力が少々足りなくても、生活活動が制限されても、原発は止めなければならない。
理性の出番です。
私たちは「どうしようもない」現実を認めた上で、先に進まなければなりません。
さまざまな価値観と欲望に動かされる世の中で、どうやったら最低限の合意点を見いだせるか。
とても難しいことですが、子どもたちのことであれば、私たちは一致できるはずです。
高村薫 53年大阪生まれ。国際基督教大卒。93年に「マークスの山」で直木賞受賞。「神の火」「新リア王」では原発問題を題材として扱っている。
3・11を前に、いろいろな方の考えをアップしたいと思っています。
作家 高村薫 原発



ご訪問ありがとうございます

 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
















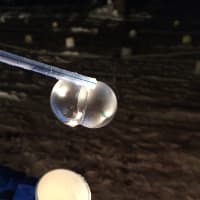


people
unbelievable
一人の力ではどうにもなりませんが
何とかしたいものです
日本の将来一体どうなるのでしょうか
誰もが判らないですね
体調大丈夫ですか?
考えさせられますね
本当に
知らぬふりは出来ないのは本当だと思います
日本の将来
変わってほしいです
ここに来ると考えさせられます
震災から1年が経とうとしていますね。
すごく考えさせられました。
日本人として、少しでも何かが変わっていくこと
を望んでいます。
東日本大震災で被災した福島県立いわき総合高校の演劇部の公演があったそうです。
震災直後、多くの不安と怒りを抱えていたと生徒たちは、
原発事故への国の対応に「福島は見捨てられているのでは」と感じたそうです。
政府や東京電力への怒りや不満を込めた風刺劇で、
震災と原発事故といった重いテーマを明るく熱演した高校生たちに、会場の拍手は鳴りやまなかったそうです。
公演が終わって 「震災直後の私たちの怒りを形にした。
あの時、福島がこんなに怒っていたということを知っていただけたら」と顧問の先生のお話です。朝日新聞記事より一部抜粋
現在国を動かしている大人たちの被災地の復興の対応の遅さスピードを見るに見兼ねて、
高校生は居た堪れない気持ちで行動を起こしたんでしょうね。
「子供は国の宝」大人が言った言葉ですよね。
これからの日本を未来永劫支えてくれるのは子供たちですよね。
教育なくして国の繁栄はありません。
被災地の復興と同時進行で子供たちの教育環境を早急に整備し不公平の無い教育が最重要課題です。
一人ひとりが今出来る事は何か考え行動しなければなりませんね。
今回の記事も、
とても考えさせられました。
ありがとうございます。m(_ _)m
原発、放射能といった脅威から、
国や政府は僕らを守ってくれない、守らない、
と僕ら大人はよく言いますよね。
何年後、何十年後、子供たちや自然や動物が、
政府や自治体はもちろん身近の大人たちさえも何もしてくれなかった・・
それだけではなく、
大人たちのそのツケを僕ら子供が払っている・・
と言っている姿が既にイメージできてしまいます。
地震列島、狭い島国の中に、
原発は現在54基、建設中や計画中のものも含めると、一体どんだけ~。(+ +)
誰かや何かをあてになんかできないですけど、
高村さんのような大人がいるということに
まだ希望を感じました。
僕はたかが一個人ですが、
一個人としてできることをしていこうと思いました。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
また書いてください