20/ 6/28(日)
○二宮神社(にのみやじんじゃ)
兵庫県養父市大屋町大杉865 拝観自由
鳥居を潜り階段を上がると正面に拝殿があり、
その奥の覆屋の中に本殿が置かれています。
本殿は、1828年(文政11年)に建てられ、
神社の屋根は、入母屋造りで屋根の正面に
千鳥破風と唐破風を付けた建物です。
本殿彫刻は、中井権次正貞、中井清次郎正用、久須真助正笑。
拝殿は、中井貞胤(9代目喜一郎)作。
鳥居
拝殿







2015/ 6/28(日)
○一宮神社(いちのみやじんじゃ)
兵庫県養父市大屋町中209 拝観自由
神社裏山はカシ類、ケヤキ、イチョウなどの
木々に覆われ、石垣を配した神社の厳かな
雰囲気と相まって、鎮守の森として静寂な
佇まいを感じさせます。
平成16年に発生した台風23号で裏側の山が
土砂崩れを起こし、エノキの大木2本が本殿に
倒れて壊れました。
拝殿の龍は九代目中井権次喜一郎の作。
鳥居から
拝殿






壊れた本殿 拝殿横の建物に保管されています。




2015/ 6/ 6(土)
○高峰寺 (こうほうじ)
兵庫県朝来市物部448 拝観自由
趣のある石段を上がるとこじんまりとした本堂が正面にある。
作品は、龍の他に唐獅子、象、鶴、小鳥があり、
六代正貞の弟の中井清次郎正用の作。




刻銘 「彫物師 中井清次良正用」







2015/ 5/31(日)
○大原神社(おおばらじんじゃ)
京都府福知山市大原191-1 拝観自由
2014年の秋(11月9日)にも訪れたとこですが
主に安産祈願の神様として知られる神社で
創建は、仁寿2年(852)と伝わり、
現在の社殿は、寛政8年(1796)に再建された。
拝殿正面の迫力のある龍は、6代目中井権次橘正貞の作。
拝殿側面の龍は、久須善兵衛政精と中井丈五郎正定による天保8年の作。
拝殿














2015/ 5/24(日)
○光明寺(こうみょうじ)
京都府綾部市睦寄町君尾1-1 拝観自由
Wikipediaより
『君尾山略記』には、推古天皇7年(599年)、聖徳太子による開創と伝える。
大栄7年(1527年)、大栄の乱の兵火を受けて本堂、鎮守拝殿等を焼失した。
天文2年(1533年)以後、地元の有力者である上林氏により伽藍が再建されるが、
元亀3年(1572年)と天正7年(1579年)に明智光秀の焼き討ちにあい再び焼失。
現存する本堂の再建は天保7年(1836年)である。
本寺は、君尾山(581m)の中腹にあり、
駐車場から木々に覆われた急な石段を上がると
閑散としたなかに本堂があります。
本堂の正面中央には、力強い龍、左右に狛犬の彫刻があり、
他に象、兎、鯉、雲等。
作者は刻銘より、6代目中井権次正貞、中井清次良正用。
本堂










刻銘「彫物師 中井権次橘正貞、 同 清次良正用」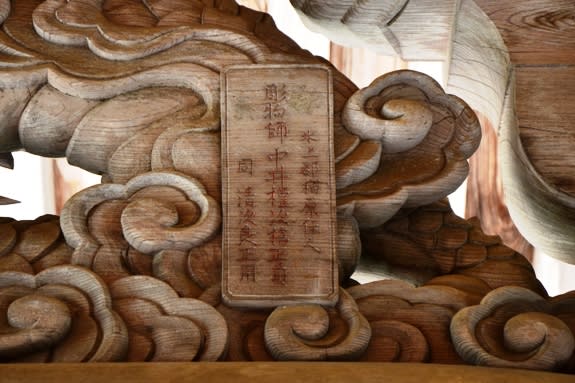
お堂
2015/ 5/24(日)
○八津合八幡宮(やつあいはちまんぐう)
京都府綾部市八津合町西谷 拝観自由
八幡宮の祭神は応神天皇で、伝えによると
建武二年(1335年)に元八幡の地より遷座
して再建、本殿は文化十二年(1815年)に
再造営された一間社流造りの建物である。
一の鳥居、二の鳥居を潜ると広い境内の奥に
拝殿と本殿があります。
本殿には、今にも動きそうな龍が睨みをきかし、
その周りに狛犬、鶴、象、力士、鳥、牡丹、菊、
雲等々の作品があります。
保存状態も良く、芸術性、文化財として
素晴らしい見栄えのある作品と思います。
彫り師は中井政忠、中井正貞親子による作。
二の鳥居から拝殿へ
拝殿
本殿















龍の後には刻銘なし
2015/ 5/23(土)
○額田一宮神社(ぬかたいっきゅうじんじゃ)
京都府福知山市夜久野町額田 拝観自由
創建は、欽明天皇15年(629年)とのこと。
神社に着くと、彫り物がないので場所を間違えたかなと
思いましたが、後ろに立派な建物があり、
龍が鋭い眼光で睨みをきかせていました。
龍の上にあるのは唐獅子でしょうか。
鬼ではないでしょうね。
刻銘がないので作者不明かな?











刻銘なし
2015/ 5/23(土)
○円了寺(えんりょうじ)
兵庫県朝来市山東町矢名瀬町622 拝観自由
階段を上がり釣鐘堂の中を潜って境内に入ります。
本堂はこじんまりとして親近感が感じられます。
隣が居住地と思われ、小学生らしい子供さんが
境内の掃き掃除をしていました。
暫くすると、住職さんが出てこられ、
「良い写真を撮って下さい。」
と挨拶される。
刻銘が屋号の「青龍軒」であることから
五代目丈五郎橘正忠以降の作品と思われます。












刻銘「栢原住 中井 青龍軒 彫刻」
2015/ 5/ 9(土)
まえがき
北近畿各地の社寺に龍や霊獣など数々の彫り
物の作品を残した彫物師、中井権次の足跡を訪
ねていきたいと思います。
中井権次顕彰会発行 ガイドブックより
「丹波の名彫物師」としてその名をはせる
柏原・中井家は、江戸時代の中頃から昭和初期
にかけて、丹波、但馬、丹後、播磨などの神社
仏閣に、龍や霊獣などの数々の彫り物の作品を
残した。
初代道源を祖とする柏原・中井家。
彫物師として活躍するようになったのは四代目
言次君音からで「権次」と名乗るのは、六代目
正貞からである。
中井権次一統による彫刻の特徴は龍にある。
龍の姿には力強さがあり、今にも動きそうな
躍動感がある。
4代目・・・中井言次君音(1722~1787没)
5代目・・・青竜軒中井橘正忠(1818没)
6代目・・・青竜軒中井権次橘正貞(1791~1855没)
7代目・・・中井権次正次(1823~1883没)
8代目・・・青竜軒中井権次橘正胤(1854~1928没)
9代目・・・青竜軒中井貞胤(喜一郎)(1872~1958没)
○長安寺(ちょうあんじ)
京都府福知山市奥野部577 拝観料300円
山門をくぐって境内に入ると拝観者は私一人。
住職さんが「こんにちわ」と挨拶され、
「中井権次の龍の作品を見に来たのです。」
と言うと、
嬉しいことに「ガイド作品マップ」を頂きました。
薬師堂の中に入るとうす暗く、薬師如来像が
鎮座している。
天井一面には、絵ではなく、彫り物の龍が鋭い
目で下界を睨みつけている。
山門
大方丈
薬師堂

薬師堂の天井彫刻 中井丈五郎正忠の作

刻銘「柏原之住人 中井正忠」
唐獅子でしょうか





開山堂













