環境省のホームページで手に入るIPCCの第4次報告書の概要およびそのもとになったIPCCの報告書によれば、大気中の二酸化炭素濃度は産業革命前の280ppmから2005年の379ppmに増加している。およそ、1.3倍である。この二酸化炭素の濃度増加という長期的トレンドは、化石燃料の消費及び土地利用の変化にともなう人間活動由来の二酸化炭素排出によるものである。
さて、依然として日本で盛んな地球温暖化懐疑論には、そもそも気温は増加していない、気温の増加は二酸化炭素の増加が原因ではないなど、さまざまなアイデアがインターネット上に散在する。さらには、「二酸化炭素濃度の増加がそもそも人間の排出した二酸化炭素量では説明できない」というアイデアまである(たとえば、これ)。
このアイデアには「数理モデル」が登場する。そのモデルの誤りについてここでは紹介したい。
このモデルは、以下のような炭素循環に関する科学的知見にもとづいている。
少し引用が古いがIPCCの第三次報告(2001)によれば、大気中の炭素の「現存量」は730ギガトン、陸上生態系および海洋との年間あたりの「相互」交換量はそれぞれ、120、90ギガトン/年とされている。現存量のうちの約三割(210 / 730 = 0.287…)が相互に交換されていることになる。
では、人為由来の二酸化炭素はどれだけの量が大気中にたまっていき、実際の濃度上昇に貢献しているのだろうか?
上のことから、非常に単純化して考えると70%の二酸化炭素が一年当たり大気に留まる。しかし、一年目に大気中に留まった大気のうちのさらに70%しか次の年に大気中にとどまらない。したがって、毎年の二酸化炭素の排出量が一定であるとすると、長期間の間に溜まりつづける二酸化炭素の総量は、離散モデルを用いれば、簡単な等比級数の総和として計算できて、
0.7 + 0.7^2 + 0.7^3 + ... + 0.7^n + ...= 0.7/(1.0-0.7) = 2.33
つまり、2.33年分の排出量となる(槌田 2007)。
IPCCの第4次報告書によると2000-2005年の期間の平均排出量は7.2ギガトン C/yearなので、これが2~3年分溜まったところで、大気中の現存量約700ギガトンの数十パーセントの変化を説明はできない、というのがこの数理モデルの主張である。
さて、分かりやすいように、このモデルを、連続時間の微分方程式にして考えてみよう(結果は定性的には変わらない)。大気中の炭素の現存量をC_A, 陸上及び海洋に移る速度を一年当たりk_AtoLO, 人為由来の排出量を一年当たりI_hとすれば、大気中炭素の現存量の時間変化は、以下の微分方程式で表される。
dC_A/dt = -k_AtoLO*C_A + I_h (1)
この方程式は平衡点がひとつ存在し、dC_A/dt = 0より、その平衡現存量(C_Astar)は
C_Astar = I_h/k_AtoLO
となる。k_AtoLO = 0.35とすれば(exp(-0.35)=0.7)なので、上の離散モデルにだいたい一致する。
このモデルの何が問題か? それは、
大気と陸上・海洋との「相互」交換プロセスが正しく捉えられていないことである。つまり、陸上・海洋から大気への炭素の流れが捉えられていないのである。方程式(1)の右辺第一項により大気から出て行く炭素(k_AtoLO*C_A)は、消えてなくなるのでもないし、地球のどこかに留まり続けるわけでもない。 これは、上のモデルで、ひとつの炭素原子に注目したとき、大気中に永遠に留まり続けるわけではないのと全く同じロジックである。
このプロセスを考慮するには最低、陸上・海洋における炭素の現存量(C_LOとおく)の動態および、陸上・海洋から大気への炭素の流れる速度k_LOtoAというパラメータが必要である。すなわち方程式(1)の代わりに、以下の二つの方程式が必要である。
dC_A/dt = -k_AtoLO*C_A + k_LOtoA*C_LO + I_h (2)
dC_LO/dt = k_AtoLO*C_A - k_LOtoA*C_LO (3)
この新しいモデルももちろん非常にシンプルであり、実際の二酸化炭素の濃度を定量的に予測できるはずはないが、(1)のモデルとの挙動の違いを定性的・直感的に理解するためには、非常に有効である。
なぜなら、方程式系(2)-(3)は平衡点を持たないことが明らかだからだ。方程式2-3は簡単な「連立線型微分方程式」(この単語でググればすぐ解説が見つかる)なので、紙と鉛筆で厳密解を求めることも容易であるが、ここではより直感的な説明にとどめる。
方程式2-3の右辺・左辺をそれぞれ足してみよう。すると、
d(C_A + C_LO)/dt = I_h (4)
が得られる。この方程式が意味しているのは、大気・陸上生態系および海洋全体に存在する炭素の総量は常に一定の速度で増加し続けるということである。実際にそれがどのように割り振られるかが問うべき問題であり、この簡単なモデルでも「連立線型微分方程式」を解けば、大気中で増える速度も分かる。
実は、こんなことは「数理モデル」を持ち出すまでもなく少し考えれば、当たり前のことである。100-1000年スケールの陸上生態系・海洋・大気間の炭素循環の外側にある化石燃料のプールから、人間は一方的に二酸化炭素を排出しているのだから、その分はほぼすべて生態系の中に溜まっていくと考えるのがきわめて自然である。
以上が数理モデルのトリックと逆にその有効性を示す一例である。
また、数理生態学の文脈で言えば、方程式が「閉じていること」がしばしば重要な場面があるともいえるだろう。
要注意!!
さて、依然として日本で盛んな地球温暖化懐疑論には、そもそも気温は増加していない、気温の増加は二酸化炭素の増加が原因ではないなど、さまざまなアイデアがインターネット上に散在する。さらには、「二酸化炭素濃度の増加がそもそも人間の排出した二酸化炭素量では説明できない」というアイデアまである(たとえば、これ)。
このアイデアには「数理モデル」が登場する。そのモデルの誤りについてここでは紹介したい。
このモデルは、以下のような炭素循環に関する科学的知見にもとづいている。
少し引用が古いがIPCCの第三次報告(2001)によれば、大気中の炭素の「現存量」は730ギガトン、陸上生態系および海洋との年間あたりの「相互」交換量はそれぞれ、120、90ギガトン/年とされている。現存量のうちの約三割(210 / 730 = 0.287…)が相互に交換されていることになる。
では、人為由来の二酸化炭素はどれだけの量が大気中にたまっていき、実際の濃度上昇に貢献しているのだろうか?
上のことから、非常に単純化して考えると70%の二酸化炭素が一年当たり大気に留まる。しかし、一年目に大気中に留まった大気のうちのさらに70%しか次の年に大気中にとどまらない。したがって、毎年の二酸化炭素の排出量が一定であるとすると、長期間の間に溜まりつづける二酸化炭素の総量は、離散モデルを用いれば、簡単な等比級数の総和として計算できて、
0.7 + 0.7^2 + 0.7^3 + ... + 0.7^n + ...= 0.7/(1.0-0.7) = 2.33
つまり、2.33年分の排出量となる(槌田 2007)。
IPCCの第4次報告書によると2000-2005年の期間の平均排出量は7.2ギガトン C/yearなので、これが2~3年分溜まったところで、大気中の現存量約700ギガトンの数十パーセントの変化を説明はできない、というのがこの数理モデルの主張である。
さて、分かりやすいように、このモデルを、連続時間の微分方程式にして考えてみよう(結果は定性的には変わらない)。大気中の炭素の現存量をC_A, 陸上及び海洋に移る速度を一年当たりk_AtoLO, 人為由来の排出量を一年当たりI_hとすれば、大気中炭素の現存量の時間変化は、以下の微分方程式で表される。
dC_A/dt = -k_AtoLO*C_A + I_h (1)
この方程式は平衡点がひとつ存在し、dC_A/dt = 0より、その平衡現存量(C_Astar)は
C_Astar = I_h/k_AtoLO
となる。k_AtoLO = 0.35とすれば(exp(-0.35)=0.7)なので、上の離散モデルにだいたい一致する。
このモデルの何が問題か? それは、
大気と陸上・海洋との「相互」交換プロセスが正しく捉えられていないことである。つまり、陸上・海洋から大気への炭素の流れが捉えられていないのである。方程式(1)の右辺第一項により大気から出て行く炭素(k_AtoLO*C_A)は、消えてなくなるのでもないし、地球のどこかに留まり続けるわけでもない。 これは、上のモデルで、ひとつの炭素原子に注目したとき、大気中に永遠に留まり続けるわけではないのと全く同じロジックである。
このプロセスを考慮するには最低、陸上・海洋における炭素の現存量(C_LOとおく)の動態および、陸上・海洋から大気への炭素の流れる速度k_LOtoAというパラメータが必要である。すなわち方程式(1)の代わりに、以下の二つの方程式が必要である。
dC_A/dt = -k_AtoLO*C_A + k_LOtoA*C_LO + I_h (2)
dC_LO/dt = k_AtoLO*C_A - k_LOtoA*C_LO (3)
この新しいモデルももちろん非常にシンプルであり、実際の二酸化炭素の濃度を定量的に予測できるはずはないが、(1)のモデルとの挙動の違いを定性的・直感的に理解するためには、非常に有効である。
なぜなら、方程式系(2)-(3)は平衡点を持たないことが明らかだからだ。方程式2-3は簡単な「連立線型微分方程式」(この単語でググればすぐ解説が見つかる)なので、紙と鉛筆で厳密解を求めることも容易であるが、ここではより直感的な説明にとどめる。
方程式2-3の右辺・左辺をそれぞれ足してみよう。すると、
d(C_A + C_LO)/dt = I_h (4)
が得られる。この方程式が意味しているのは、大気・陸上生態系および海洋全体に存在する炭素の総量は常に一定の速度で増加し続けるということである。実際にそれがどのように割り振られるかが問うべき問題であり、この簡単なモデルでも「連立線型微分方程式」を解けば、大気中で増える速度も分かる。
実は、こんなことは「数理モデル」を持ち出すまでもなく少し考えれば、当たり前のことである。100-1000年スケールの陸上生態系・海洋・大気間の炭素循環の外側にある化石燃料のプールから、人間は一方的に二酸化炭素を排出しているのだから、その分はほぼすべて生態系の中に溜まっていくと考えるのがきわめて自然である。
以上が数理モデルのトリックと逆にその有効性を示す一例である。
また、数理生態学の文脈で言えば、方程式が「閉じていること」がしばしば重要な場面があるともいえるだろう。
要注意!!











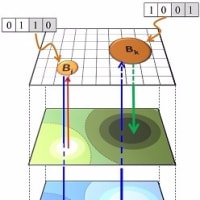
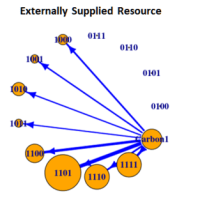



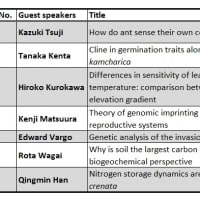



ではなく。
「温暖化問題懐疑論」の内の一つの、
『「二酸化炭素濃度の増加がそもそも人間の排出した二酸化炭素量では説明できない」というアイデア』
の数理モデルの誤りですよね。