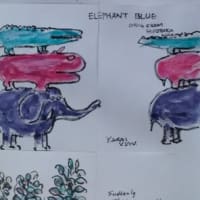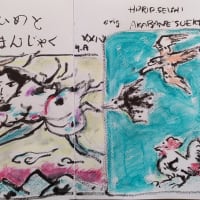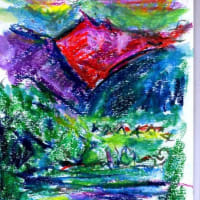朝日記240325 4.(その2)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その2)
表紙へ返る 朝日記240325 私が2023年に書いた報文コレクト
朝日記240325 4.(その1)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その1)
本文
1.社会的知性Social Moralityについて
モラリティ、晒し、社会的知性
ガウアンロックJohn Gouinlockというアメリカの社会哲学者の以下の著への筆者からの書評で、Amazon Bookreviewに投稿掲載されたものです。[1]
J.ガウアンロック著(小泉 仰監訳) 公開討議と社会的知性 ミルとデューイ(御茶ノ水書房)[2]
John Gouinlock; Excellence in Public Discourse ~John Stuart Smith,Jaon Dewey,and Scial Intelligence. 1986
このひとの名前は、たまたまネットで moralityとrationalityについてしらべていたときに知った。(記事名は’Instrumental ratinality and Value rationality’であった)
J.ガウアンロックは、手段的(もしくは道具的)合理性(Instrumental rationality )の理論の指導的哲学者であるという。かれの理論は社会道徳性の考えにつよいつながりを持っている。 人びとは各自の徳の意識に沿って行動する合理性を発現すべきであるという。特に、人びとが問題案件に対しての争論が敵対的対決の状態レベルになる以前に議論をとどめ置き、己の行動を律することの道義的弁術を提唱する。 考えてみれば、これまで、科学や技術の分野では問いかけからの受け入れについては、しばしば「概念の’晒し’(concept disposition)」が行われてきた。これと同様に、社会的案件についてもある期間、その合理的な結論を醸成させるために’晒される’べきであると説く。これを成立させるためには、最終的にして敵対的感情決裂のレベルまでに至らぬ抑制が条件であるとする。 この考えのながれは、現在アングロ・アメリカン系の主流であるInstrumental Rationality(手段的もしくは道具的合理性哲学 ) と呼ばれている哲学のものである。 J.ロールズ、R. ノジック、J.ガウアンロック、A.セン等によって代表されている。
ところで社会道徳(morality)が、時代的な中心命題となって久しい。とくに、19世紀の英国で、成熟した民主主義にあって、権力の中心が政府や権威機関にあるのではなく、それが実は与論にあり、メディアで代表されるということを彼らは気づいている。
Joh Sturt Mill(ミル)は、その「自由論」で、社会的な合意形成とその道徳について、その社会のコミュニケーションによって柔軟に形成されることを洞察して、そこから形成される知性のあるべきことと、その基礎的仕組みとを提唱している。
この流れは、米国のプラグマティズムのデューイの哲学に継がれ発展していくが、それをこの著ではわかりやすく解説している。この著の中心は、なんといっても第五章の社会的知性であろう。
「社会的知性」は、成熟した民主主義社会と、価値多様化への社会的合意についての知性(功利、権利と義務、徳と悪徳)を意味している。
著者は述べる;社会的合意について、 事態の解決に先が見えないときは、無理せずにdisposition(寝かすとか晒す)という概念を提唱する。 ある状況に遭遇したとき、人びとはコミュニケーションによって意見の相違について学習し、理解し、変化し、成長するということを説く。
公開討論などはその一つの例であるが、ここでの野蛮さ、低劣さについても承知の上で、ここでのレベルを如何に引きあげうるか、リーゾナブルな方向へ収束しうることは可能であるのかを論じる。著者は、ミルやデューイのこれまでの思想的な流れを評価し、成熟した民主主義の社会で、そのような知性(社会的知性)が育ちうるかを述べる。
(筆者(レヴューア)としての所感として)
個人的な経験であるが、英国人の知人たちが、彼らがひとが集まったときに議論の方向について、しばしば優れたリーダーシップの発揮していた状況にふと思い起こす。 これは英語の世界だからだと単純に着せられない高い素養を感じたものであった。
そういう社会的素養の教育(学校教育も)についてもこの著を通じて、あらためて思いを致す。著のなかで直接的に表現として使ったかどうかは別に、’If I were you ...' つまり、「もしも私があなたの状況にあったら」、という道徳観moralityであろう。
人間は、基本的に誤るものであり、弱い存在であるというミルの哲学であり、自分が考えたからということを以ってそれに固執するのではなく、意見が異なる状況でも、それを相手の立場に自分を置いて考え、ますは肯定的に議論する。その過程で、相手を蔑んだり、罵倒するような感情暴発に至らないそういう社会的文化ルールのありかたとして理解した。
筆者の畏友のひとり安部忠彦氏が以前に、個人の社会生活が孤立した「無縁社会」と表現した現今の都市生活社会で、これをどう考えていくか、ネットでの交流がこのような「社会的知性」を育て得るか、等々そういう思いをこの著から考えることに強く啓発を受けたと反応してきた。
この本は、原著は1986年の出版であるが、和訳への監訳者の小泉 仰氏は、1988年ケンブリッジ大学にて、原著をみつけ、強い共感を覚え、同門の有志たちと翻訳に取り組んだたことを記している。翻訳出版が1994年である。 ネット社会が急速に展開を開始したころの出版ではあった。
社会的情報交流(コミュニケーション)は、それまでの新聞紙面、やTVなどを中心にしたメディアから、SNS等ネットへの急激な展開の時機に入った年代の出版ではあるが問題の本質の方向をただしくとらえているといえよう。 「公開討論」という語のもつ時代的な意味論的な変遷もあり、あゝあれかと見がちであるが、かれが提唱する「社会的知性」は、公開討論の卓越性のための基礎になるという意味で、時代をこえて本質的視点をもち、なお新鮮である。
因みに、この本の構成概要は以下である;(本著の意味するもの);
第一章 序論
第二章 ミル、社会的所産としての知識と道徳的評価
第三章 古典的自由主義の欠陥
第四章 ミルの教育哲学
第五章 社会的知性
第六章 ミルとデューイの挑戦
以上
2.「制度論とモラリティ」Institution and Morality
制度論、モラリティ、悪意と善意
(2021/01/16 )
「制度論とモラリティ」
(2017/11/06)
制度の概念について[3]
制度とそれがもつ社会的な道徳性について語ってみたいと考えた。
(その1)「制度の概念について」Institution as a concept
徒然こと1 Institutionって?
徒然こと2「Social Institutionについて」
スタンフォード・哲学百科から
徒然こと3 所感 Institutionについて
(その2) 「社会道徳性ということについて」Social morality as a concept
徒然こと1 敬愛する友人からの問いかけ‘Moral revolution’
徒然こと2 Moralityについての見解
徒然こと3 所感 「悪意」と「善意」についての論の切り口Virial and Good
~~~~~
(その1)「制度の概念について」
徒然こと1 制度Institutionって?
話しはとびますが、英語の文献のなかでInstitutionとこれと対になる語でagencyに出会いました。これらの日本語訳と意味がかねがね気になっていていました。特に、Institutionについて、ブリタニカ辞書あたりでは、かなり丁寧な説明がみられました。 また、現代の社会学では、なにを意味するかという視点で、筆者の座右の岩波哲学・思想事典とさらにスタンフォード大学の哲学百科[1]で見比べることをしたりしています。日本語では、「制度化」ということに収まらざるを得ないのですが、我々日本人がこの言葉をどのように捉えているか自分を含めて、大変 おぼつかないところです。 多分、政府など公的機関での「制度化」としての意味論のなかで漠然としておさまっています。 具体的に指させば、政府、家族、言語、大学、病院、企業、そして法体系ということで一定の意味を表すことができます。
スタンフォードの解説を頭のなかでのkeywordsで反芻しますと、以下のようになります。まずJohn Turnerという学者の定義をご紹介します。
Institutionの定義をつぎのように与えます;
1. 社会的構造の特定の形式において内在している位置づけ、役割り、規範および価値の複合体、および
2.以下を基本的課題としてもち、組織化過程にある人間活動で比較安定的な範疇のもの;①生命系の持続資源を生み出すことにおいて、②「個人」の再生産することにおいて、および③所与の環境の中での生きがいのある社会構造を持続することにおいてです。さらに加えて Giddensという学者は
3.それ自身が、社会生活の永続的な形態をもつものとします。
4.Harreという学者は、さらに、明示的で、かつ実践的な結果を伴う構造として表現しています。たとえば、学校、店、郵便局、警察署、亡命、および英国君主をあげます。
ずいぶん まわりくどい定義をしていますね。これには現代西側社会の基本問題への取り組みのパラダイムを含んでいるからであると考えます。世界は、経済のグローバル化や持続型地球環境論議などを通じて、異なる文化的な価値の所有者間の問題不調性(共約不可能性(incommensurability))問題がさまざまな局面で登場します。
このようなことを研究するのは、社会学者の専業ですが、価値の根源問題を含むので哲学的な思考と行動枠組みとしての位置付が必要で、その意味で際立って学際的ならびに総合知による理念と概念構築が必要となっていると理解します。
そこで さらに加わるのが
5.Institutionの思考モデル概念としてはつぎの4つがあがります;
構造(structure)、機能(function)、文化(culture)、認可(sanction)
Institutionという概念は、そういう意味では、これまでの「制度化」ということは 異なる意味論をもっているということに気が付きます。 とくに文化が入ってくりところ際立った特徴です。 (sanctionの本来の意味が、聖なる至上の権威からの許しという意味をもつものに改めて興味を感じました。本来、 相手に対して単なる敵対や妨害の意図ではなく、義を護るためへの 対象への制限付与を意味するものであったようです)。
徒然こと 2 「Social Institutionについて」
スタンフォード哲学百科でのSocial Institutionの解説は、全体が5章からの構成になっています。 上述の定義にはじまり、社会学的な背景であるつぎの二つが説明されます。ひとつは、Institutionの集合的受容論からの形成根拠(Collective Acceptance Theory of Institution)と、もうひとつはInstitutionとしての特定目的論追及根拠(Teleological Accounts of Institution)であります。
これを受けて、Institutionとそれを担う主体者であるAgency(任務者)との関係が第4章で登場します。 終章の第5章は法的つまり Social Institution and Distributive Justiceが置かれます。
全体を通してみて、おもしろいと思ったのは、このDistributive Justiceです。
正義(a right)と合法(a just)は異なる概念として説明します。ホロコーストは、正義(right)ではないが、合法(justice)ということはありうるというものです。 正義と合法は同義ではないところです。もうひとつあげますと、刑法(Penal law)の基本は復讐法(Retreat law)であるおして、Institutionでの問題次元とは、きりはなします。 ここで出てくるのは、共約不可能性問題のように、問題ごとに 公正的(just)であるか、非公正的(unjust)であるかがわかれるような懸案が日常に表れる場合です。これを Distributive Justice分散的合法と呼んでいます。(日本語では如何に訳されていますか?)この典型的な例は、社長が一般従業員の50倍の給与をもらうのは、正義(a right)であるか、公正(a just)であるかという問題としてでてきます。西側の世界では 特に米国でのルール意識として'primo facie unjust'という原則がここで紹介されます。上のような事実が出てきたときに誰も、非公正unjustとしてなにも言わないならば、これは合法(認可)justiceとされるとします。 メンタルの根底では 道義的(moral)な正しさ(a right)としてどうなのかの問題をのこすことは想像されます。ここでの解説で一番おもしろいのは,アメリカは、ときに、「非公正社会」といわれていると言い切るところです。(the USA is sometimes said to be an unjust society.) よくいえば、justとunjustのせめぎ合いの弁証法的な展開をしているとみるべきでしょう。(問題があるから建設的という逆説にもなります)
正しさや正義の問題は、宗教や道徳をふくむ価値の規範問題と考えられます。 その不調性が知的枠組みの外に置かれることが、共約不可能性として社会的な不安定性を発生(emergence)することになるというものです。 この問題は、'Absence of Social Institution'として基本問題の認識とその取組みの社会的認知(認可)をすること(a sanction )の重要性を説きます。(ある意味で「問題の発見」であるともいえます)
徒然こと 3 所感; Institutionについて
所感としては、つぎのことをあげておきます。
1.Institutionを、構造~機能~文化~認知のシステムとしてとらえるところが、これまでの情報システム論に対して、あたらしいシステム論へと向かわせることになるものであると理解しました。 つまり、これまでのサイバネティックスの思考枠組みは 基本的には、目的関数(政策変数(自由度を持つ変数)の最適化式)+制約条件(構造~機能)でありました。ここでは、「文化」とその「認可」が加わります。つまりこれまでの市場効用主義的価値または目的の選択の自由のなかに、社会道徳な制約をつよく意志することが要求されてきます。別の表現をすれば 思考の二大構成領域であるNoumenon(思弁系、理念系)とPhenomenon(現象系、概念系)で観るなら、後者については思考モデルとしては明示的に努力するが、前者については人間の自由という名において、切り離し、思考の対象の外に置かれました。前者を対象にするためには、 別途に文系学問のなかでの組織機能論として区分し、自然学系であるPhenomenon(現象系、概念系)とは独立的な別枠として考えられてきたようにおもいます。
2.ところでやや唐突であるが日本の近代産業社会は、ある側面で、きわめてinstitutiveであったという思いがあります。たとえば以下の例です;
*明治期に東京帝国大学に工科大学を世界で初めて設立したこと、科学技術を制度的Institutiveに位置づけています。
*また、第二次大戦後は、(TQC 話はすこし古いかもしれませんが)日本の品質管理運動でいう、全社的品質管理の理念は、企業文化を上下のカウンターカレントな活動を顕在し、欧米の品質保証を一気に凌駕してきたことがあげられます。 これは’初期的 Institution ’でもあったとも顧みるものであるといえます。 一方、
3.Social Institutiveという思想・哲学上の枠組みへの発想は未発達で来たのではないかと思われます。 たとえば日本の近代産業社会全体をInstitutionの設計として依然として、まとめ得ていない。
*ISOなど世界標準、Industry 4などのロボットネット産業や、太平洋パートナーシップTPPは、地球次元でのSocial Institutionであるとみることができます。これを設計していく実力が当然期待される。このような筋を通して、はじめて国際社会での説得力や指導力が確保されるとおもいます。
以上です。大分ながくなり、目下、思考過程の段階にあります。Institutionが実効に移るときに一番重要なのは、人間社会において運営していくときの判断根拠が明らかになっている必要があります。次の稿で、社会道徳性Moralityの問題を述べてみたいとおもいます。(2017/11/3稿)
[1] Stanford Encyclopedia of Philosophy ネットで公開されています。
[1] 朝日記171218 Amazon書評投稿「J.ガウアンロック著公開討議と社会的知性」と今日の絵
[2]https://www.amazon.co.jp/gp/product/427501569X/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
5つ星のうち4.0ガウアンロック 社会的知性への展開を考える本である
投稿者あらいやすまさ2017年12月3日
[3] 朝日記171106 「制度論とモラリティ」(その1)制度の概念についてと今日の絵
2017-11-06 18:27:53 | 社会システム科学