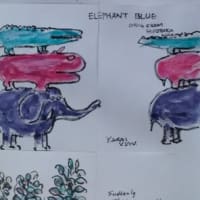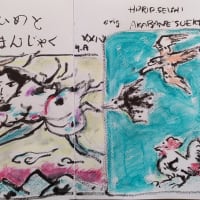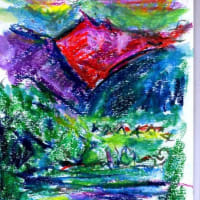朝日記240325 4.(その3)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その3)
表紙へ返る 朝日記240325 私が2023年に書いた報文コレクト
朝日記240325 4.(その1)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その1)
本文
(その2)「制度とモラリティ」
~社会道徳ということについて~[1] Social Morality
前回の「制度の概念について」に続いて、 (その2)として「社会道徳Morality」の問題を述べてみます。
あえて、道徳のうえに社会という語を冠したのは、社会という視点に思考の重心を置くという単純な意味からです。以下の三つでお話します;
徒然こと1 敬愛する友人からの問いかけ「道徳革命」‘A moral revolution’
徒然こと2 社会道徳Moralityについての見解
徒然こと3 所感 「悪意」と「善意」についての論の切り口
~~~~~
徒然こと1 敬愛する友人からの問いかけ「道徳革命」‘ A moral revolution’
敬愛する友人神出瑞穂氏(以降、K.M.氏)[1]から つぎのような問い掛けがありました。
~~~~
オバマ大統領の広島原爆被爆地演説(2016)の中で使われている「道徳革命( a moral revolution))という言葉です。
彼は言います;物質の基本である原子からさらに内部構造へと導いた科学革命は、人文分野においても、道徳革命へと及ぶことが要求される)[2]という文脈です。 この言葉を小生は初めて知りました。博学の貴殿なら意味をご存じではないかと存じます。 K.M.
~~~~~
K.M.氏(2016・6・13)への返書
私見ですが、社会道徳moralityについての哲学的な捉え方において、西側世界では、アングロ・アメリカン学派系と、ドイツを中心とする大陸のカントの学派系との二つの流れがあり、大分趣が違うようです。切り口の違いの典型例として「アダム・スミス問題」というのがあり、いまも思想的および実践的な考え方の違いとして、良きつけ、悪しきつけ、相互に歴史的な緊張感があるようです。 ネットで ’Adam Smith Problem’ と引くとおもしろい解説がでてきます。 カントの流れからは、アダム・スミスの著名な二つの著である「国富論」と「道徳感情論」との内容的なかい離を揶揄したようです。 ご承知のようにスミスの前提には、ミツバチが分業で一生懸命働いているが、全体としては自然合目的に調和がとれた社会になっているとして、功利的市場主義を説いていますが、スミスは一方で 「道徳感情論」でキリスト教社会の社会道徳moralityがその前提として存在していることの意味をつよく意識し論じています。
そのmoralityを実現するのは、「同意」agreementや「同情」sympathyであり、それぞれが住む社会において営みとして存在している。 社会的になにかの不調な問題が起きた時に、その社会現場で、それを問題として共有をし、交流・交渉を通じて、解決策を見出していくことを、ルール化して行こうというものでした。したがって、人間が相互に生きていくうえでの‘おとしどころ’(rationality)を常に用意優先することになるとおもいます。裁判でも裁判員制度や陪審員制度はすぐれて、アダム・スミス的です。
一方、大陸系のカントの方は、超越主義的道徳律です。 これは、価値の意識には二つあって、ひとつは超越的存在(神)によって、与えられるであろう正しさへの直観(道徳律)と、他方には、この世に現実に生きる自分の嗜好・傾向からの価値意識(格律)がある。当然ながらこの二つにギャップがあることを認める。そして、その前提のもとで、その差を明示的(観念的)に表わして、縮めるべく、努力することを実践的な正しさつまり道徳moralityとして位置づけます。在るべきこと(Sollen)と現にあること(Sein)との違いから始まる主体的な意思(自由意思)を経過しないと、逆に身動きがとれないことになります。したがって、彼らは、ルール規範を極力明細(形式知)に顕わにする努力を是とすることになります(理念拘束型といえましょう)。そのための論理展開し、形式知としてルール化した果実である「合法」justificationを判断根拠として優先することになります。
たとえば、メルケル首相が原子力発電の廃止の決定は、内なる道徳律に耳傾けるという結論からのものであり、いかにもドイツ的であったともみています。 その意味では、ドイツの「独創」でもありますが、一方で「独走」?でもあるとも見ます。ときに、彼らのその価値観を他に、押し付けてくることもあり得るとみます。 私見ですが、アングロ‐アメリカン系は、多分 メルケルの結論に対して、当分冷やかであるとおもいます。
~~~~
今回の友人との交流をとおして、すぐ思い起こしたことはやはり、西洋近代の思考方式がDescriptive(理念を語る)とNormative(ルールとして行動規範化する)ことの二元的なmoralityの論理構造でありました。 この二元的な位相を怜悧にとらえておくことは 私たち日本において、これからも大切であるとみています。
たとえば、現下(2017年6月時点)、話題になっている東京都の豊洲市場移転案件に、新都知事が、劇場型といわれるメディアとの連携で、前任者たちの政策決定がルールにのっているか、いないか、取組への態度がどうかなど、「都民ファースト」の旗印で国民運動的な次元での総検証しようとするものでありました。 結果は、ご承知のようなポピュリズムで、単なる形式的な言行一致次元political collectが先行したように思います。 そこのなかで、メディアの報道は 問題の本質から離れ、冷静な思考ができず、逆に世の中全体が判断の金縛りでなった観があります。 規範に違反しているなら、とりあえず、その 違反の程度の罰penaltyがあってよい。手続き論上の痂疲が本当にあったのか、その影響度は工学技術的にどう処理可能であるか、また 現在の規範が不十分であるなら、これから改訂することが詳らかにするべきで課題であります。 規範問題Normativeと理念問題Descriptiveに悪く言えば情念的に一括りにして、仕上げてしまっていることには、無理が見えてきます。 理念と規範とのギャップがあるから悪いのではなく、 ギャップをきちんと位置づけ、これをどこまで、科学技術的に埋めていく姿勢があったかで判断すべきものであるといえます。現状は 上述のように形式的な矛盾、 ものごとを狭く考えるとトラップ(落とし穴)、 思考のモラトリアム(休止)、そして、やがてこの案件の世論に飽き疲れ具合の頃合いみて、結局レベルの低い出口へと落ちるようにおもいます。そして さんざんに騒いだあとに メディアも、都民も、けろりとわすれ、結果は、問題となった理念も掘り下げられず、規範も形式的に触る程度で 実質には、なんら変わらないというところでことを収めるであろうとおもいます。 あとはなにもなかったかのように、さわやかに前向きに行こう! 建設的にいこう!という言辞のもとで、あのメディアも処理済み問題として衆目から見えなくしてしまうことが必定のものとみています。
徒然こと2 社会道徳Moralityについての見解
社会道徳moralityについて、スタンフォード哲学ネットなどのいくつかの探索の結果として、現代哲学からでの共通の文脈らしいものをまとめると以下ようになると考えます。
1.Morality = no harm
社会道徳とは人を傷つけないことをもって正しいとする。人間は誰も、誤りやすい(fallible)く、且つ傷つきやすい (vulnerable)存在であることから社会道徳性を出発させる。
2.Morality = rationality
社会道徳は、その判断根拠を合理性rationalityにおくことによって正しいとする。複雑な社会にあって、ひとびとの多くに 多様な情報と専門用語が行き交かう。 そこでは問題になる事態を予測したり、経過を理路整然、一貫して考えることが困難な状態にある。 また、それ故に それに付け込む悪しき小賢しい人間(権謀術数)も出来する。(悪が常に跋扈する)。しかも、正邪の識別は、難しい。
3.The third of person of rational(利害に超然とした「知性的な第三者」)の存在を社会道徳は期待する。世の賢人たちの活動が重要なポイントになります。上の理念Descriptiveと規範Normativeとの溝やズレを埋める歴史的な役割りを、このような人々が奮起して担うというものです。彼らは 相互に 異なる筋道のrationalityとの間で、ときに熾烈な合理性論争と観測経験報告を経て、テーマが止揚され、共通解への進化展開が期待されることになります。(成熟した民主主義の社会でこれがほんとうに成功しうるのかについては、また別の課題とします)
たとえば、原子力発電の廃絶問題は、あるべき将来への人類史論的な次元での理念の深化(Descriptive)と現に巨大にして複雑精緻な文明を支える科学技術による制度論的役割(Normative)とが 嫌でも並行していくべきものであります。 これは人類の生存に課せられた命題として迫ります。
たとえば、判断の課程には、存続と廃止の二つ以外に、然るべき期間、世に晒す、あるいは保留(disposition)することもひとつの選択肢でもあります。そのうえで、社会道徳morality課題の理念Descriptive課題に、国民が精神を傾け、意識を継続矜持して、学び、考え、取り組む姿勢を勇気づけ、これを賞揚することであるとおもいます。その意味では、私たちは「哲学の時代」に厳然としてあるのであり、オバマが示唆するmoral revolutionの時代にあるともいえます。同時に、似非哲学や独断的な宗教からの誘惑も多くなります。
一方、規範的Normativeな相は 制度(論)主義Institutionalismに徹して 問題の在り所と方向性について透明公開に論議を進めていくことに専念するべきと考えます。
これが「知性的な第三者」が関与する広い意味での機関Agentの役割りです。 その意味では、情報システム論あるいは文理融合的な総合知次元の社会情報システム技術のinstitution化は重要な意味と役割りを担います。(情操的な道義主義と、利己的な功利主義への「落とし穴」を如何に躱していくか、おおげさにいえば人類の死命を画する、知恵の出し合いの勝負です)
国際社会において、日本がこれからも名誉ある主導的な存在として世界が平和で活力のある発展をするのための役割りの立ち位置もここに置べきであると考えます。
西側世界での現在は、キリスト教的な超越的なモラル前提を暗黙裡の前提としていますが、教会からの宗教的教義は明示的ベースおしては、公共の場に出てきません。この場合、社会的に実際にあらわれる、道徳問題moralityは、常に自由意思の保証と 弱き無辜の人への‘思いやり’(No- Harm)が基盤になります。しかし、いまは、世界的にも、それに対する掘り下げが不十分であるとみます。その意味では「道徳革命」が求められているといってよいとおもいますが、オバマ氏が「a moral revolution」と表現している特定の社会思想上の立場や運動が実際に存在しているかは、寡聞にして、わかりません。筆者が理解するこの課題としては、価値の多元化で、異なる文化背景間での理解未達の問題(共約不可能性 incommensurability )に 今後さらに焦点があてられることになるとおもっています。
徒然こと3 所感 「悪意」と「善意」についての論の切り口
本年2017年5月には「組織的犯罪処罰法改正案」(「テロ等準備罪」法案)が成立いたしました。この共謀関連について、社会道徳moralityに関連しての話題としては、やや唐突ですが、「確信犯」という語に視点をおくことはおもしろいとおもいます。 多分この言葉は、「犯」というからには、刑法上の術語であろうと思いますが、拡張して広い意味での社会的道徳性moralityに対する態度と実行を考えてみます。そうすると、以下の2x2のマトリクスになります。(マトリクスの図を平行にご覧ください)
(A)違法の意図から合法の実行手段をとる。
(B)合法の意図から違法の実行手段をとる。
(C)違法の意図から違法の実行手段をとる。
(D)合法の意図から合法の実行手段をとる。
もともと「確信犯」は合法の意図のために、実行手段として非合法的手段をとる(B)との意味であったようですが、巷では、(C)か(A)の意味になっているでしょうか。
一番、憎むべきは(A)の非合法の意図で、合法的手段に乗ってしまうことでしょうか。
意図の合法性つまり正しさは、実行手段から現れたものが第一義的に判断されるから(B)と(C)に対する峻別から、社会的制裁の軽重が裁かれることになります。 いずれにしても社会的制裁は避けられませんね。 隠れた問題は、(A)です。 意図の非合法性を、社会がどう見るかですが、
目下、私の思考射程域はここに留まっている状態でこれからの思考課題です。
|
意思と実行手段の合法性についての マトリクス |
実行手段 |
||
|
合法 |
非合法(含違法) |
||
|
意思 |
合法 |
(D) |
(B) |
|
非合法(含違法) |
(A) |
(C) |
|
話がそれてはいけませんが、広い意味で「共謀」conspiracyも、意図と行動において、この二つを含むと考えます。ここまでくると、ここでいう社会道徳性moralityを 「非合法」unjusticeと「違法」illegal,violationとの区別が必要になってきます。
この「非合法」については、アメリカ社会でよく使われる判断形式として、prima facie unjusticeと語があり、これに筆者の目は留まりました。 これは、ともかくルールがきまっていない状態では、発話者が自分の価値判断で自分のルールを宣言する。それからルール作りがはじまる。決まっていないことは、はじめは非合法unjusticeであってよいといったものです(アメリカは、しばしば非合法の社会と呼ばれている[3])。
複雑な都市社会などで分散化された合法概念distributed justiceとして、位置づけこれを合法として実現を図るというものです。こういうのは、相当に高度に知的sophisticatedでないとできない。また、できる人間が専門家あるいは事業者などが必要になります。 この‘できるひと’あるいは‘できる能力のあるひと’が、rational personの姿です。
一方で、私たちは、発話者が、他者の関係において、自己の主張を論理化できないひとたち、つまりinnocentな人たちがいることを知ります。 その発話者のprima facie rational な自分が、他の 無辜のひとを傷つける(harmful)かもしれない。もしそうであるならば、それは修正されるべきであると主張する、そういうmoralityがあります。
つまり、道徳の基本は‘思いやり’(morality = harmless)というものであろうと考えます。具体的な案件や課題では、当然ながら、rationalistの間で論理的な合法性への筋でのたたかいがおこなわれことになります。(この思考方式の論争での主役は、「帰着主義」Consequentialismと「価値自由主義」Value Liberalismの二つといわれますがここではこれ以上触れません)。 これが、なにが、どのように、いまの社会で機能しているかに注意する必要があります。 特にこういう状況を一つの立場のひと(a rationalist)によって、結果として、ものごとの機会均等が崩れ、独り勝ちになって非公正になっているかどうかを検証する意味は出てきます。
このように考える時に、一般人としての私の希望は、二つありそうです。ひとつは制度(論)的社会institutive societyとして、現実の社会のなかでの役割りを担う機関agentとその問題の所在に関わる制度institutionの両方が機能しているかという問題の見方です。それが弱者を貶めharmfulであるか検証し、yesなら、キチンと修正のために機能し、あるいは修正作動に向かう「免疫」機能が存在していること、あるいはそれが存在しても名目的でなく、適格に働いているか、検証し、理解をし、修正を発議していく意味でのモラリティmoralityの存在に着目すべきであると考えます。
もうひとつは、もう一度既存のinstitutionの存在意義を問い直し、改廃をふくめて基本問題をみなおし、そこからの、問題の根源、あり方を問い直そうとするものであります。 ドナルド・トランプが出てきたのは、マイナーな修正や改良では立ち行けないということが選挙民のなかで、特に白人中下層が気付いた現象ともいえるかもしれません。とはいえ、嘗ての日本の政権での「予算仕切り」などのどたばた劇の悪しき思い出もかさなり複雑な思いではあります。
(2017/11/3稿)
[1] 朝日記171106 制度とモラリティ (その2) 社会道徳ということについてと今日の絵
2017-11-06 20:15:56 | 社会システム科学
表紙へ返る 朝日記240325 私が2023年に書いた報文コレクト
朝日記240325 4.(その1)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その1)