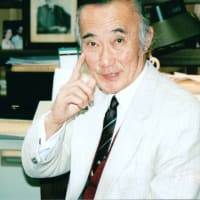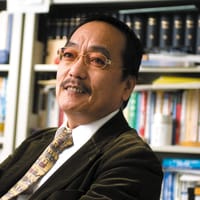2009年10月5日「心理学研究法2回目」は、医療心理学という分野の研究法を概観しました。
添付のパワポスライドの1枚目に、授業スケジュールを掲載します。
来週から二週授業がありませんので、注意してください。
次回は10月26日となります。前日にベルリンから帰国します。ドイツの現状などもお話できるでしょう。
授業展開を楽しみにしておいてください。
今回の授業では、医療に生かすための心理学研究についてお話ししました。
医療心理士は医療現場で心理の専門家として働くわけですから、他の医療スタッフとうまくやっていくためには、心理学の専門知識だけでなく、幅広い知識と医療用語の理解、コミュニケーションスキルなどが求められます。
また、日々研鑽が求められます。研究者の態度と視点は常にもっておくべきなんですね。
ところで、医療心理士という用語について医療心理師とどうちがうんですかという質問があったのでお答えします。
医療心理師ということばは、2005年に議員立法で国会に提出される予定だった心理士法案での用語です。臨床心理士と医療心理師の2資格1法案のなかの医療心理師。
一方、医療心理士ということばは、日本心身医学会認定資格です。今年で認定試験は6回目となります。
心身医学会認定の医療心理士という資格については、
http://www.interq.or.jp/japan/shinshin/
を参考にしてください。
現在90名の認定資格をもった医療心理士が実際に活躍されています。
本学出身者の、めざす資格の1つに入れたいとおもっています。
この春に出版された「医療心理学を学ぶ人のために」(世界思想社)などを参考にしてください。
2009/10/06・記
添付のパワポスライドの1枚目に、授業スケジュールを掲載します。
来週から二週授業がありませんので、注意してください。
次回は10月26日となります。前日にベルリンから帰国します。ドイツの現状などもお話できるでしょう。
授業展開を楽しみにしておいてください。
今回の授業では、医療に生かすための心理学研究についてお話ししました。
医療心理士は医療現場で心理の専門家として働くわけですから、他の医療スタッフとうまくやっていくためには、心理学の専門知識だけでなく、幅広い知識と医療用語の理解、コミュニケーションスキルなどが求められます。
また、日々研鑽が求められます。研究者の態度と視点は常にもっておくべきなんですね。
ところで、医療心理士という用語について医療心理師とどうちがうんですかという質問があったのでお答えします。
医療心理師ということばは、2005年に議員立法で国会に提出される予定だった心理士法案での用語です。臨床心理士と医療心理師の2資格1法案のなかの医療心理師。
一方、医療心理士ということばは、日本心身医学会認定資格です。今年で認定試験は6回目となります。
心身医学会認定の医療心理士という資格については、
http://www.interq.or.jp/japan/shinshin/
を参考にしてください。
現在90名の認定資格をもった医療心理士が実際に活躍されています。
本学出身者の、めざす資格の1つに入れたいとおもっています。
この春に出版された「医療心理学を学ぶ人のために」(世界思想社)などを参考にしてください。
2009/10/06・記