キャンプでやる焚火であろうと、BBQでの炭火であろうと、火を扱う事というのは人それぞれスタイルがあり、使う道具もバラバラです。
自分の焚火スタイルにおいて欠かせない「三種の神器」とも言える道具があります。
皮手袋、火箸、そして火吹き棒です。
今回はその「火吹き棒-ファイアーブラスター-」について紹介したいと思います。

最初に自作して使い始めたのは、このような昔ながらの竹を使ったモノ。
炭でBBQをする時、着火はなかなか難しい物ですが、この火吹き棒で酸素を送り込んでやることで比較的着火がスムーズになります。
焚火で最も活用するのは、薪の継ぎ足しをする時。
後から入れた薪はそれ自体が燃焼するまで、モクモクと煙を出すことがありますが、ピンポイントで着火位置に酸素を送り込むことで、これもスムーズに燃焼へと移行できます。

材料は、近所の竹林から拾ってきた枯れ竹。
好みの長さでカットして、鉄の棒を突っ込んで途中の節を抜きます。
火口側の節に、キリやドライバーで極小の穴を開けて完成です。
用途に応じて長さや穴の大きさを変えて、複数作りました。
最初は結構バカにしてたんですが、他の工作で使った竹が余ったので試しに使ってみると・・・
いや、これは便利!
炭おこしも楽だし、焚火でも大活躍!
作るのも簡単だし、もう手放せない! ・・・と、活用してたんですが・・・
長さのある物なので、結構かさばるんですよねぇ。
短いと、火との距離が短くなるわけですから、息を吹く際に顔が熱くなっちゃうんですよ。
なんで、使いやすい長さとなると40センチ前後になっちゃうんですよね。
市販の物では、金属製で伸縮機能もあり、使わない時にはコンパクトに収納できるファイアーブラスターが沢山あります。
・・・しかし、意外とお値段はそれなり。
だったら自作すればいい!

という訳で、自分で作ってみました。
材料その一、100均にある自撮り棒。
ダイソーは大きめの物が300円でしたが、こちらの物はセリア・シルクなどで100円で売られています。
まず、本体の先っちょのスマホホルダー部分を外します。
力任せでも良いですが、金属部分とのつなぎ目の所をライターで少し炙ると取れやすいです。

本体の金属棒は中空で伸縮するので、工作が面倒な方はこのままでも使えます!
しかし、無加工では空気の噴出量が大きすぎますし、なにより全体を縮めてしまうと、次に伸ばす際に先をつまむのがすごく大変です。

そこで、もう一つの材料、ペンシルキャップです。
これも同じく100均で購入。
材質は、アルミの物と真鍮の物を確認しています。
どちらのタイプも使ってみましたが、使い心地に差はないです。
ただ、アルミニウムは融点が600度くらいなので、真鍮の方が良いかもしれません。

ペンシルキャップの先にドリルで穴を開け、自撮り棒の先端にねじ込みます。
さらにドリルで横穴をあけ、針金で固定します。

針金を巻きつけることで、縮んだ状態から伸ばす際のツマミとなります。

最後に針金を数回巻きつけて完成。
この時、ペンシルキャップと自撮り棒パイプに大きなスキマがある場合は、自撮り棒パイプの先端に切れ込みを入れて針金をきつく縛ると隙間が多少改善されます。


グリップのお尻部分を切り飛ばし、吹き口にしています。
縮んだときは20センチ弱、全体を伸ばすと75センチ近くまで長くなります!
伸縮機能があるので、節ごとのパイプ同士に若干隙間があるので、吹く息の効率は竹タイプに劣りますが、コンパクトに収納できるし、使い勝手も悪くありません。
また、全体が金属製なので、簡単な火かき棒代わりに薪をつついたりできます。

さらに、セリアで見つけたより短いタイプの自撮り棒でも作ってみました。

最初のタイプと比べると、収納時は半分近くまで短くなります。
ただし、伸ばした時は45センチくらいなので、大きな火に向かって使う時には顔を火傷しないように気をつけなければいけません。

このタイプはリモコン操作のボタンと配線があるので、それを除去しなければいけません。
これがなかなか外し難くて、結局グリップのウレタンを切って外しました。

切り外してしまったグリップの代わりに、ワインのコルクで持ち手を付けます。
自撮り棒のパイプをコルクに押し付け、ゆっくり力を込めながら廻していくことで、このようにキレイにくり抜くことが出来ます。

先端部分の加工は、最初のファイアーブラスターと同じです。
よりコンパクトなファイアーブラスターが完成しました。
ソロキャンプやブッシュクラフトなどの軽量装備向けですね。
使う際のコツとして、しばらく使用すると、パイプ内を通る呼気に含まれる水分が結露してくるので、たまに洗って干してあげると良いです。
市販のメーカー品ではそのような現象が起きるのか不明ですが。
材料費は200円程度ですし、加工も15分もあれば終わる簡単な構造ですが、威力は絶大。
焚火ライフには欠かせない道具となりました。
これを使っていると、まるで自分が自在に火を操れるような気持になってくるんです。
わずかに焚火台の底に残った、赤々とした熾き火に、細い焚き付けを乗せファイアーブラスターでプーッと長く息を吐き空気を送る。
すると、熾き火に面した所からチロチロと炎が上がり、焚き付けが燃え始める。
こんな体験をすると、もうファイアーブラスターが手放せなくなりすよ!
【1分解説】100均の虫取りあみからファイアブラスターを作る
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/168265ea.92bc397c.168265eb.7a9ffdda/?me_id=1197896&item_id=10257410&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesportskenko%2Fcabinet%2F9284%2F9284310990014.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesportskenko%2Fcabinet%2F9284%2F9284310990014.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext) ファイヤーサイド FIRESIDE ファイヤーブラスター FB1価格:3386円(税込、送料別) (2018/3/15時点) |
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16826602.783a2801.16826603.e67d3135/?me_id=1321929&item_id=10000209&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmileymarket%2Fcabinet%2Fitem_img%2F05573925%2Fimgrc0071116924.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmileymarket%2Fcabinet%2Fitem_img%2F05573925%2Fimgrc0071116924.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext) 【送料無料】火起こし 火吹き ふいご 焚き火 ファイヤーブラスター 暖炉 炭 薪 ポケットふいご 火吹き棒 火吹きだけ バーベキュー BBQ 炭火 暖炉 薪 炭価格:980円(税込、送料無料) (2018/3/15時点) |
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1682663d.1157b0df.1682663f.f607e123/?me_id=1245361&item_id=10005232&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbrain556%2Fcabinet%2Fsyumi%2Fzdr_00.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbrain556%2Fcabinet%2Fsyumi%2Fzdr_00.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext) 自撮り棒 選べる3カラー【自撮りスティック mono pod ZDR-01】自分撮りスタンド 自撮りモノポッド iPhone6,iPhone6 Plus,スマートフォンにも セルカ棒 セルフィースティック価格:100円(税込、送料別) (2018/3/15時点) |











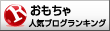
















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/164f0fde.6598febc.164f0fdf.34218aba/?me_id=1309149&item_id=14936414&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmega-star%2Fcabinet%2Fkc%2F90%2Fe496583h_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmega-star%2Fcabinet%2Fkc%2F90%2Fe496583h_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/164f107c.bf2302a8.164f107d.7837a8ea/?me_id=1231819&item_id=11851639&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmao%2Fcabinet%2Fencoder%2Fmarumotonet%2Fm_00000001_05%2Fni0001418997.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmao%2Fcabinet%2Fencoder%2Fmarumotonet%2Fm_00000001_05%2Fni0001418997.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/164f1097.7a5d92b8.164f1098.d159f237/?me_id=1247876&item_id=10001382&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fm-k-world%2Fcabinet%2Fisigaki%2Fimgrc0067951247.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fm-k-world%2Fcabinet%2Fisigaki%2Fimgrc0067951247.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1603f8e6.65e441dd.1603f8e7.f60d29e6/?me_id=1313202&item_id=10001132&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-prendre%2Fcabinet%2Fimg8%2Fpr-nature-kas-01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-prendre%2Fcabinet%2Fimg8%2Fpr-nature-kas-01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1603f8f3.d6cb14e4.1603f8f4.19248db4/?me_id=1301940&item_id=10034220&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmirain%2Fcabinet%2Fitem%2Foutdoor%2Fb0624-1a_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmirain%2Fcabinet%2Fitem%2Foutdoor%2Fb0624-1a_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1603f931.39360880.1603f932.5ca14639/?me_id=1205497&item_id=10001536&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmakiclub%2Fcabinet%2Foutd%2Fss%2Fsst.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmakiclub%2Fcabinet%2Foutd%2Fss%2Fsst.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)













![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16036bbb.92485d21.16036bbc.4068ee47/?me_id=1192233&item_id=10102912&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesports%2Fcabinet%2F0003%2F0003103001628.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesports%2Fcabinet%2F0003%2F0003103001628.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16036be7.6c3527df.16036be8.5c63d9ff/?me_id=1211173&item_id=10006247&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fphantom%2Fcabinet%2Fgoods1%2F09226056_01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fphantom%2Fcabinet%2Fgoods1%2F09226056_01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/09b534ca.f4ad5576.09b534cb.e7ade141/?me_id=1213310&item_id=17891227&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6881%2F9784416516881.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6881%2F9784416516881.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16029588.20e5b631.16029589.dfb50ae2/?me_id=1274848&item_id=10006199&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcarymo%2Fcabinet%2Fzakka%2Fimg2%2Fstepdoril3set.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcarymo%2Fcabinet%2Fzakka%2Fimg2%2Fstepdoril3set.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/160295a5.714dca5e.160295a6.8a1d540c/?me_id=1213855&item_id=10003372&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fs-deco%2Fcabinet%2Fe%2Frevolver_a.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fs-deco%2Fcabinet%2Fe%2Frevolver_a.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/160295c0.e688af95.160295c1.a0d298b2/?me_id=1317859&item_id=10002229&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fideali-store%2Fcabinet%2Foutdoor%2Fgrill%2Fover-camel-ws004-.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fideali-store%2Fcabinet%2Foutdoor%2Fgrill%2Fover-camel-ws004-.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f49af6.c1d347b8.15f49af7.9007a4f5/?me_id=1264309&item_id=10136082&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhimaraya%2Fcabinet%2F3103001602%2F3103001602set_r1_01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhimaraya%2Fcabinet%2F3103001602%2F3103001602set_r1_01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f49b25.7a5692cc.15f49b26.518fe6b1/?me_id=1317590&item_id=10000592&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsportsbing%2Fcabinet%2F04692631%2Fimgrc0076300831.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsportsbing%2Fcabinet%2F04692631%2Fimgrc0076300831.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)






















