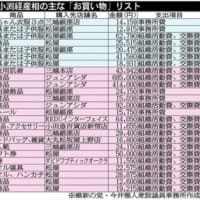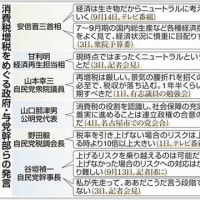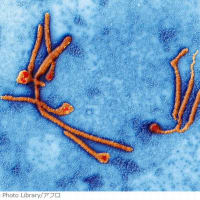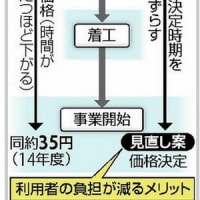http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140424542.html へのリンク
2014年4月24日(木)12:33
(産経新聞)

日に焼け、がっちりとした体格の男(33)は法廷で終始、無表情だった。
昨年11月、大阪地裁で開かれたストーカー規制法違反事件の判決公判。懲役6月、執行猶予3年を言い渡された男は、約3カ月ぶりの「自由」を取り戻した。
男が飲食店員の女性にストーカー行為を始めたのは平成17(2005)年ごろ。23年以降は女性宅近くで毎日のように待ち伏せするようになった。昨年7月、大阪府警の警告を受けたがやめず、翌月に逮捕された。
判決の1週間前に行われた検察側の被告人質問に男はこう答えた。「彼女を忘れるのは無理だと思う。好きという気持ちは死ぬまで変わらない」
静かで抑揚に乏しい声。むしろ病的なまでに女性への執着心がにじみ、再犯への不安が渦巻いた。
◆強制的に転居も
再犯率が高いとされるストーカー犯罪。再犯防止策を考える上で示唆に富むデータがある。ストーカー犯に警察がどう対応したかという7年前のオランダの調査結果(複数回答可)だ。
警告46・0%▽裁判所送致31・8%▽勾留24・9%-などと並ぶ中、日本にはない措置として目を引くのが「ストーカーを引っ越しさせた」の11・0%。ストーカー犯全体の1割が転居を強いられていた。
ストーカーをめぐる法制度に詳しい常磐大大学院の諸沢英道教授(被害者学)は「本当に被害者を守ろうとするなら、ストーカーに引っ越しを命じるぐらいの強制力は必要だ」と語る。
戦前の反動から、戦後の刑事法で主流だった考え方は「処罰範囲は限定的に」「刑は軽く」という国家権力の発動を制限するものだった。近年は、治安への国民の不安を反映するように処罰範囲の拡大や厳罰化、そして被害者目線の方向に舵を切りつつある。
ストーカー規制法もその一環だが、加害者の行動を強制的に縛る再犯防止策には踏み込めていないのだ。
◆「警察判断任せ」脱却を
「ストーカー規制法は、被害者にとって不透明で分かりにくい」。女性への暴力問題に取り組む雪田樹理弁護士(大阪弁護士会)は、規制法の抜本的な改正を提言している。
手本の一つがドメスティックバイオレンス(DV、配偶者間暴力)対策のDV防止法。被害者の申し立てで裁判所が判断し、接近禁止や住居からの退去などの保護命令を出せる。電話やメールも禁じることが可能だ。違反すれば刑事罰の対象となり、全国で年間約3千件の申し立てがある。
ストーカー規制法は、被害者からの申告で警察が加害者に警告を行い、次の禁止命令も警察の申し立てで公安委員会が出す仕組み。刑事罰の手続きに移るまで裁判所は関与しない。
雪田弁護士は「警察に裁量権がありすぎる。不適切なストーカー対応が多かった警察に今後もすべての判断を任せる形でいいのか」と語る。警察の対応が鈍い場合、被害者の申告で裁判所がDV防止法の保護命令に相当する救済的な強制措置を出せる仕組みの導入を訴えるのだ。
ストーカー行為は時代の変化によって多様化している。インターネットやツイッターへの書き込み、恋愛感情などを満たす目的以外のトラブル…。今は規制対象でない行為にも「網」を広げるなど、柔軟に法制度を見直すべきだという声は高まっている。