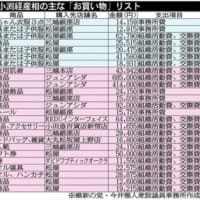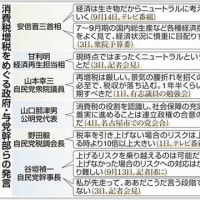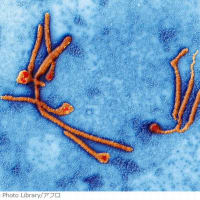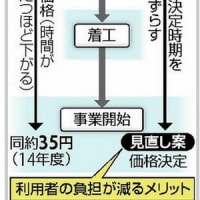http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20141001602.html へのリンク
産経新聞:2014年10月2日(木)12:03
 学校も、行政も居場所をつかめない。そんな子供が日本全国に約2900人もいる。政府は8月、「居所不明」となっている子供の今年5月時点の数字を公表した。実際は記録などがないだけでどこかで暮らしていて、行政側の“追跡調査”が甘いため居所不明扱いになっている子供も多いとみられる。だが、家庭ごと音信不通になるなどして、忽然(こつぜん)と世間から消えてしまった子供が一定数いることも確か。居所不明の子供は親から虐待を受けているリスクが高く、近年は育児放棄の末に衰弱死したり、暴行を受けて雑木林に捨てられたりした事件も発覚した。危機感を抱いた全国の市町村は、家庭訪問などによる確認作業を急ピッチで進めている。
学校も、行政も居場所をつかめない。そんな子供が日本全国に約2900人もいる。政府は8月、「居所不明」となっている子供の今年5月時点の数字を公表した。実際は記録などがないだけでどこかで暮らしていて、行政側の“追跡調査”が甘いため居所不明扱いになっている子供も多いとみられる。だが、家庭ごと音信不通になるなどして、忽然(こつぜん)と世間から消えてしまった子供が一定数いることも確か。居所不明の子供は親から虐待を受けているリスクが高く、近年は育児放棄の末に衰弱死したり、暴行を受けて雑木林に捨てられたりした事件も発覚した。危機感を抱いた全国の市町村は、家庭訪問などによる確認作業を急ピッチで進めている。
■事件の苦い記憶
「一度も乳幼児健診を受けていない子供がいる」
愛知県豊橋市。子育て支援課の担当者に、健診を所管する市こども保健課から連絡があったのは昨年秋のことだ。未受診だったのは4歳児。通常であれば「生後4カ月」「1歳半」「3歳」の段階で健診を受けているはずだが、いずれも未受診だった。
早急に所在を確認する必要があり、父親のもとに担当者を向かわせたが、「どこにいるのかさっぱりわからない」。父親によると、母親はアジア系の外国人で、すでに2人は離婚しており、児童は母親が引き取ったという。
入国管理局に照会すると、母親が出国した記録はあったが、児童の確認は取れなかった。児童は日本名以外でパスポートを取得していた可能性があったが、父親が外国人名を知らず、日本名でしか照会ができなかったことも理由と考えられている。
もちろん、出国しておらず、何らかの事件に巻き込まれている恐れもある。市は愛知県警に相談したが、児童は所在不明だと判明してから1年近くが経過した今年9月現在でも行方不明のままだ。
豊橋市では平成24年、女児(4)が両親に食事を与えられないなどのネグレクト(育児放棄)を受けた末、衰弱死したという事件があった。亡くなった加藤杏奈ちゃんは、市の健診を受けておらず、健診を担当する部署は所在もつかめていなかった。
一方、両親は、児童手当や子ども手当を受け取っていた。健診とは別の部署に提出された書類には父親の健康保険証の写しが添付されており、そこには勤め先も記載されていた。
杏奈ちゃんの所在を調べる重要な手がかりだったが、市内部で情報は共有されず、対策は取られないまま、杏奈ちゃんは命を落とした。
苦い記憶。事件以降、市は居所不明の子供の問題に積極的に取り組んでいるが、冒頭のような事例はまだ残っている。
市の担当者は「杏奈ちゃんの事件を重く受け止め、居所不明の児童がいればできる限り追跡している。だが、手がかりが途切れてしまうと、それから先には進めなくなってしまう」。
■居所不明、大阪が発端
居所不明の子供がクローズアップされたのは、大阪がきっかけだった。
24年4月、大阪府富田林市で、住民登録上は9歳のはずの男児が生後まもなくから行方不明になっていたことが発覚。14年9月生まれの男児は、実際は1歳になる前に死亡しており、祖母らによって15年2月、同市内の河川敷に埋められていた。
この事件により、男児と同じような居所不明の子供が全国に1千人以上いることが取り上げられ、社会問題化した。
これ以前から、文部科学省では学校基本調査で、居所不明の小学生や中学生を集計していた。ただ、同調査は「学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的」としており、主な調査項目は「学校数、在学者数、教員数、卒業者数、進学者数、就職者数」など。居所不明児童・生徒に重きは置かれていなかった。
それが、富田林の事件により転換した。事件に巻き込まれた子供がいたことに国は危機感を強め、富田林の事件が発覚してから半年後の24年11月、学校や警察などの関係機関と連携して行方が分からなくなっている子供の実態を把握するよう、厚生労働省が市町村に通知した。
だが、その後も、25年2月に大阪市東住吉区で住民登録上は6歳の女児が実際は出産直後に殺害されていたことが分かり母親が逮捕されるなど、悲惨なニュースが報じられた。このため同省は今年4月、乳幼児を含めた18歳未満にまで対象を拡大し、居所不明児童・生徒の数を報告するよう市町村に要請。その結果、冒頭の2900人という数字が浮かび上がったという。
ただ、文科省の学校基本調査では、小中学生に調査対象が限られているものの平成23年度の1191人が26年度に397人となるなど、3年連続で減少している。
■行政-学校-警察
現場を預かる市町村は試行錯誤を続けている。
昨年4月、所在不明となっていた女児=当時(6)=が遺体で見つかった横浜市。過去に事件のあった自治体では関係機関の情報共有が失敗している傾向があったことを教訓に、市や児童相談所、学校、警察などそれぞれの役割をはっきりさせたフロー図を作成。今年4月からは、学校などから上がってくる長期間不登校の子供の情報などを、虐待を担当するこども家庭課に報告する仕組みも取り入れた。
親との関係の強化を模索する動きもある。
奈良県宇陀市は昨年度から、生後2カ月の子供がいる家庭に対し、予防接種の段階で、市内限定の1万円分の商品券を配るというユニークな取り組みを始めた。地域振興や子育て支援が主な目的だが、居所不明児童・生徒の問題への効果も期待されている。
一つは、生後2カ月時点での所在を確認できる点で、昨年度は新生児が148人いたが、全員が予防接種に訪れ、所在を確認することができた。
もう一つが、親との関係強化。この場をきっかけに家庭と自治体とのつながりを作り、その後、親が育児相談などをしやすい関係性の構築へとつなげる-。そうすることで、市側は小さな子供を持つ家庭の状況を把握でき、将来的に居所不明の子供が発生した場合も、その家庭に応じたアプローチができる、という想定もあるという。
同市の担当者は「子育ての状況を確かめることができ、コミュニケーションの場にもなる。自治体と親の関係強化につながる」と期待を込める。
花園大の津崎哲郎特任教授(児童福祉論)は「居所不明の子供は非常に多い。市町村のマンパワーでは調査にも限界がある」と指摘。それを踏まえ、効果的な対応を取る必要があるとして「虐待のリスクのある子供を見極め、重点的な対策を取る必要がある」と求めている。