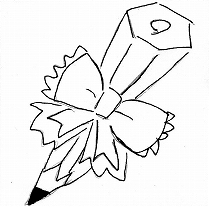1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。

本文詳細↓
エルゼノーラさんが何もないところから取り出した小さな花束を、反射的に受け取ってしまった。薔薇は淡く華やかなピンク色で、絹よりも柔らかそうな花びらが幾重にも重なりあって寄り添い微笑んでいた。
「……そんな奴は知らん。我にはアダムという名がある。最初にこやつが言うたであろう」
なんとなく、武器を孕んだようなひんやりとした空気を感じたので僕は黙った。
「それは失礼を。それで、あなたも私に何か?」
「森を挟んで隣の町に魔法をかけたのはおぬしか? 女子(おなご)の体に薔薇の紋様が浮き出てきて、やがて死に至らしめるという魔法だ」
「? ……ああ、そういえば昔そんなことをしたような。それがどうかしましたか?」
「解いてやれ。どうせたいした理由などないのだろう。あの町はもう何十年もその魔法で死者を出している」
「死者を? でもあれは……ああ、もしかして……そういうことなのかしらね」
最初は困惑、次に納得して、最後は何かを残念がるような表情へ変わった。差し支えなければ詳しく教えて欲しいと言うと、エルゼノーラさんは肩をすくめた。
「あれはね、本当は可愛らしい少女(おとめ)たちに昔から人気があった恋のおまじないなのよ」
薔薇姫の呪いはもっと恐ろしかったはず、と混乱しているのが顔にはっきり出ていたようだった。

本文詳細↓
太陽はまたもう少し西に流れて、黄色やオレンジの光が端からにじみつつあった。
「『彼女』は危険な人なんですか? でも、僕が昔会ったときは全然そんな感じしなかった。だからかな、あなたにそう言われても、ピンとこないんです。『彼女』のことは、僕が直接『彼女』と話して、知りたい」
じゃあどうして女性に縋り付いたのか。言えなかったけど、僕はちゃんとその答えを知っていた。
……あの蒼い月夜が夢ではなかっのだと、はっきりさせたかった。それだけだ。
文献を探して、流れの商人に聞いてみて、旅人に言伝を頼んで、それでも十年以上何もなかった。ただの妄想だったら、そう考えて怖くならなかった日はなかった。けど、そんなまとわりつく悪夢の霧も、今日晴れた。
『彼女』は――天使ナイトウォーカーは、この世界に実在する。
「……ありがとうございます。『彼女』の名前を、教えてくれて」
姿勢を正して、僕はただ頭を下げた。女性は何も言わずに僕の頭から手を離した。
「時に、おぬしは魔女だな?」
もう用はないからと辞そうとしたら、肩の上で器用にふんぞり返りながらアダムが女性に訊いていた。
「ええ、エルゼノーラと申します。初めてお目にかかりますわね、《雲を歩き海を呑む放浪者》」

本文詳細↓
女性は何故かしばらくアダムを見て、それから僕の髪を撫でた。
「そう、あなたは彼女に会ったことがあるのね。そして再会を渇望している……。私は人間という種族にも、あなたという個体にも、特に興味なんてないから、今のあなたを応援するべきなのか哀れむべきなのか、決めきれない。だけどせっかく来てくれたんだもの、何も無しというのもね」
僕の目を覗き込んできた彼女の瞳は宝石のように美しく、意思がまったく読めなかった。
「彼女の名前はナイトウォーカー。か弱い人間をただ愛でていたいだけの天使たちの中で、最も歪んだ愛し方をする異端の天使。それだけを教えてあげる」
それはどこか、あの暗い谷の夜を思い出させた。
「たとえば、他の天使たちが嘘の縦糸と真実の横糸でこの《世界》という巨大な布を織り上げているとすれば、ナイトウォーカーはそれに鋏を入れて切り刻もうとしている。きっと今もね。性悪でしょう? あなたはそんな彼女に禁断の知恵の果実を与えられたのよ。この意味が分かるかしら。絶望と狂乱と破滅を招くそれを、あなたは飲み込むことができて?」
廃墟に吹く風は、どこか砂っぽかった。
それに気づくまでに、僕はどれだけの時間を要したのだろう。
「あなたの言うことは、よく分からない」
ようやく出てきた最初の言葉は、そんなものだった。

本文詳細↓
どれだけ像を見つめていたかは分からなかった。そんな僕が我に返ったのは、アダムに振り下ろされた特性木槌が頭にクリーンヒットしたからだった。
「いいかげんにせんか! いつまでそのマヌケ面を晒すつもりだ!?」
「いっったい! え、というかなんだそのハンマー⁉」
「凄かろう。我の七つ道具のひとつよ」
「どこに隠し持ってるんだ、そんなの!?」
「秘密だ!」
思わず状況も忘れてアダムと言い争っていると、朗らかな笑い声が響いた。
「アハハッ。あぁ、おかしなこと……。久しぶりに笑ったような気がするわぁ」
それはたぶん独り言だったのだと思う。ひとしきり笑ったあと、女性は揶揄うように呟いた。
「それに憧れるのは止めておいたほうが賢明よ、坊や。彼女は数いる天使の中でも一番のろくでなしと言われてるんだから」
天使。ろくでなし。
「っ、もっと詳しく教えてください、『彼女』のことっ! ずっとずっと探してて……でも何も分からなくて……お願いします! 僕はもう一度、『彼女』に会いたいんです!」
我ながら、なんとも拙いセリフだった。これじゃあ分かるものも分からなかったろうに。僕は何も考えず、ただ必死で女性に縋り付いていた。

本文詳細↓
なんとか二人で心臓を宥め、意を決して踏み出せば、砂礫かガラスか、靴の下で擦れた何かがジャリッと音を立てた。
「はじめまして。僕はトルヴェール・アルシャラールと言います。風の精霊エアリエルの導きでここまで来ました。こいつは僕の旅の連れのアダムです」
祭壇に腰掛けていた女性は僕より少し年上なだけにも見えるし、でも雰囲気は悠然としていて、まさに時の艶をまとった妙齢な、と呼ぶのがふさわしい女性だった。
「へえ、エアリエルの。いったいどんな導きかしら」
「はい。僕はある人を探していて、その人について聞いて……みたく、て……」
「トルヴェール?」
訝しそうなアダムの声も聞こえてはいた。でも、耳を通り抜けるだけで脳には記憶されなかった。そのとき僕の目は一体の像に吸い寄せられ、他の全ては溶けるように消えていったからだ。
教会の壁に沿って、人の姿をした石造りの何かの像が並んでいる。風雨に晒されたせいか、目鼻立ちや細やかな衣装の輪郭は曖昧になっていて、元は美しかったであろう彩色も剥げてしまっていた。
それでも僕には分かった。祭壇の最も近くに立つ、輝く翡翠の玉を瞳に埋め込まれた像。真昼と夕暮れの間に横たわる白い光を浴びたその像が、
『彼女』を模したものだということが。