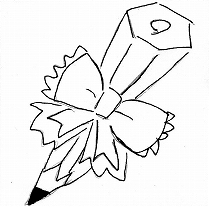本日は『大雪』です。
「おおゆき」ではなく、二十四節気のひとつ「たいせつ」です(笑)
雪が降り始めて本格的に冬が到来することを指します。
例年、大雪が過ぎたあたりから気温が下がり始め、スキー場がオープンしたりブリなどの冬の魚の漁が盛んになったりします。
ただし、今年2020年12月の頭に発表された一ヶ月予報では、11日までは平年より高い気温になるようです。
朝晩はストーブをつけるほど寒くなりましたが、昼間は晴れが続いてあったかいどころか、歩いてると汗ばむぐらいですからねえ。
平安時代に活躍した清少納言は、随筆「枕草子」の中でこう言っています。
冬は、つとめて。
雪の降りたるは、言ふべきにもあらず、霜のいと白きも、またさらでも、いと寒きに、火など急ぎおこして、炭持てわたるも、いとつきづきし。
昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も白き灰がちになりて、わろし。
超意訳すれば、
冬は早朝が一番よ!
雪が降っているのも霜が白いのも良いし、寒いから急いで火をおこして炭を持って廊下を歩いているのも良いわね。
昼になって暖かくなっていくと、火鉢の炭が白くなってダサい。
こんな感じでしょうか。
現在の私たちからすると、(仕事などを除いて)冬の早朝に外に出ようものなら物好きと言われそうなものですがねえ...。
そもそも高温多湿の日本では、「家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にも住まる。(徒然草)」と言われているように、風通しの良さを重視していました。
平安時代の貴族が暮らした寝殿造の屋敷なんか壁がほとんどなく、戸や障子などで間仕切りして生活していたと言います。
絶対寒いやろ。
地球規模で見れば、温暖期と寒冷期とを繰り返していて平安時代は温暖期にあったという説もあるそうですが、それにしたって寒いやろ。
雪は、上空1500m付近の温度が-6℃以下で地上付近の温度が3℃以下の場合に降ることが多いとされています。
つまり雪が降ってたってことは、いくら温暖期とはいえ外気温は3度ぐらいだったはず!
吹きっさらしの部屋で火鉢抱いて重ね着してても、寒いもんは寒いやろ!!!
昔の日本人頑丈かよぉ...😭(暑いのより寒い方がダメなタイプ)。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。