ミャンマーシンポジウム 子どもたちが教えてくれたこと 第二部

楠木真次監事
最初に、第一部では関口さんに素晴らしい写真を見せていただきました。われわれはミャンマーの支援をしているが、いろんな支援が必要だと思う。パネラーの皆さんは、なぜミャンマーの支援をしているのか、教えてください。
日本が本当に支援するべきは、この親日国ではないか

安倍昭恵顧問
私がミャンマーに関心を持ったのは主人(安倍晋三元首相)がきっかけ。主人たち国会議員の皆さんが「アジアの子どもたちに学校を贈る会」という会を運営しています。当時は50人ほどのメンバーがいましたが、毎年、アジア各国に学校を寄贈していました。主人はそうした学校の開校式にタイミングよく出席する機会がありませんでしたが、開校式に出席した人からは、本当に現地の人々が喜び、日本人も感動するものだと聞かされていました。主人も開校式に行きたがっています。
私も、何か自分にできることはないかと思うようになり、主人に「私も学校を作りたい」と相談しました。そうしたら、「ミャンマーが良いのではないか」と答えたのです。「親日的な人々が多く、日本が支援していくべき相手はミャンマーではないか」というのです。
主人は過去に2度、ミャンマーに行きました。最初は中曽根総理大臣時代に、父の安倍晋太郎が外務大臣をしており、中曽根首相に同行しました。当時は、アジア各国はどこを訪問しても戦後補償の問題が山積していました。行く先々でいろいろな要求を突き付けられていた。最後に訪問したのがミャンマーで、中曽根首相は帰国しなければならず、父と主人がミャンマーに入国しました。すると、今までの国と違って大歓迎で、おまけに日本語の歌として軍歌まで飛び出しました。軍歌がどうこうということではなくて、現地の人が歌える日本語がその当時は軍歌であったということです。それくらい、日本に良い感情を持ってくださっていた。主人はこの感動を、身を持って体験したことで、「何かしてあげたい。こんな国にこそ、日本は支援するべきだ」と思ったそうです。
今、日本とミャンマーは国と国のレベルでは関係は難しいものがありますが、民間としては大いに何かしたいと思うのです。
そんな経緯があって、私は主人に「私も学校を作る」と言いました。皆さん御承知の通り、太平洋戦争では約20万人がビルマで亡くなりました。そんな人々がいて、今の私たちがある。そういうことも含めて、ミャンマーに学校を建てたいと思ったのです。
学校建設の根拠
袖山榮眞理事長
私は個人的には、古い仏教経典を日本で研究するとき、「ブッダゴーサ(仏音/覚音)」という有名な翻訳家の翻訳を読むことになります。この人はスリランカに住んでいたが、実はミャンマー人だった。ミャンマーにこそ古い仏教が伝わっていたことに関心を持っていました。私は今、浄土宗報恩明照会という財団の理事長をしています。先代理事長、先々代理事長は戦後まもなくミャンマーの僧院で生活をされていました。こういうこともあって、私個人はミャンマーに親近感を持っていました。
私たち浄土宗報恩明照会はミャンマーに学校を建設していますが、「その後のこと」について、どうなっているんだと思う人も多いでしょう。メコン総合研究所と協力関係を築くことで、われわれは今までに7校、開校することができた。ここには校医がいないので日本人医師、看護師らの団体とメコン総合研究所が提携して、校医をしてもらっている。われわれは学校を造り、ソフトの部分でメコン総合研究所にお願いしている。だから、われわれは堂々と皆さんにご寄付をお願いできる。
箱モノ行政ではダメ。ソフトとの並立が大切
関口照生顧問
ミャンマーは、日本とは大変形態が違う国。日本は単一民族ではないが、歴史的に、そんなにたくさんの民族は入ってきていない。昔、ヨーロッパで欧米人から「君はチャイニーズか?」と聞かれると、「アイム・ジャパニーズ。アイム・ピュア・ジャパニーズ」と答える日本人がいた。私は、「ピュアな日本人」という存在はありえないんだけれど…と思いながら聞いていました。日本は何かあるとひとつの民族としてまとまっているように見えるが、それは長い間鎖国していたから。
「日本文化」という共通の価値観を持っていて、これを介してコミュニケーションすることで互いに日本人を認識している。阿吽の呼吸で理解が成立するわけです。
一方、ミャンマーは人種のるつぼ。130以上の民族が集まっています。最大規模のビルマ族が政権を担っているというだけのことです。私が育った昭和20年以前の日本は、軍国主義です。だから、私たちの世代は、日本とミャンマーは、何ら変わりがないことを知っています。
戦後、私たちは民主主義を与えてもらった。しかし、日本の中で本物の民主主義が育っているのかと考えれば、ハイとは答えにくい。それは、国民が血を流して勝ちとった自由ではないからです。だから、私はいつも思うのです。
ミャンマーに学校などを寄贈するときは、私は、箱モノを作ればそれで良いとはまったく思っていません。ソフトの充実が大切なのです。しかし、学校があれば、子どもたちが考えるようになる。教育の良いところは、自分で考えることを知ることができるということです。日本のように守られてばかりいては、自分で考えられなくなる。貧しい国が考えるようになると、時間がかかっても自分たちで考え、進むようになる。余分な経済的な支援よりも教育支援が大切なのです。
そんなふうに思うので、私はミャンマーに肩入れしています。
また、カンボジアなどは、著名人が寄ってたかって支援しています。一方、ミャンマーは敬遠しがちです。この差も重要なポイントですね。
華やかな明治時代は、江戸の寺小屋があればこそ
楠木真次監事
学校の話が尽きませんが、われわれ日本人は明治に大改革を断行しました。これは、江戸時代の寺小屋教育の発達が要因。寺小屋が明治という時代を生み出したといいます。
教育は大切ですね。
ところで、メコン総合研究所の岩城事務局長は、見た目も日本人だが、ミャンマー出身。4年前に帰化された経歴をお持ちです。今まで、日本人の言い分を聞かれてきて、どんなことを思っておられるのでしょうか。
子どもたちが学ぶ環境を作ってあげたい
岩城良生事務局長
私はミャンマー人だったからミャンマーの支援をしていたこともありますが、今は日本人として、メコン総合研究所としてメコン川流域全体にかかわる活動をしています。
関口先生のおっしゃったとおり、教育は力です。
私の場合はミャンマーで教育を受けられなかったからこそ、日本に来ました。1988年に大学が閉鎖され、小学校から大学まで、すべての教育機関が閉鎖されたので日本に来ました。ミャンマーでは教育が犠牲になっています。国民の勉強をサポートしているのが寺小屋であり、その寺小屋をサポートしているのが私たちだという関係です。
私たちは、運よく勉強できて、こんな活動をしていられますが、国から出られない子どもたち、授業を受けられない子どもたちが学校に行けるような環境を作ってあげたいです。
楠木真次監事
岩城さんがいた20年前よりも教育に関する環境は悪化しているといいますが、それはどのような感じですか。
教育は時代の波に飲み込まれ…
岩城良生事務局長
88年の民主化運動は学生運動から始まり、小学校から大学院までの教育機関が3年近く閉鎖されました。当時の政府は2年半から3年にわたって、大学をはじめ、すべての高等教育機関をヤンゴン市内から市街の僻地に移築しました。学校が再開した時には戻れなくなった学生も大勢いました。
これが「88年世代」で、今40歳前後、ちょうど私たちの世代に当たり、その多くは海外に移住しました。
再開した公的な学校では、適切な教育を受けられなくなっていたので、1990年以降は寺小屋がたくさん誕生しました。
楠木真次監事
本日のテーマは「ミャンマーの子どもたちが教えてくれたこと」です。皆さんの子どもたちへの支援の内容を教えてください。
私は何も知らなかったが、何かしたかった
安倍昭恵顧問
ミャンマーには学校を作りたかったのですが、私ははじめ、ミャンマーに関する人をまったく知りませんでした。学校というものはどうやって作ればよいのかも知りませんでした。どこかの団体にお金を渡して建設をお願いすることはできたのでしょうが、私は現地に行き、現場を知りたいと思いました。自分で見て、本当に必要とされている場所に建てたかった。とりあえずミャンマーに行こう。と、何のあてもなく、友人と行ってきました。
誰も知っている人がいないと困るので、今日も来てくださっている「日本ウズベキスタン協会」での知人に、ミャンマーに関係のある人がいないかと尋ねたら、すぐに、岩城さんを紹介してくださったのです。関口先生とはもともとはワインの飲み友達で、たまたまワインの席でミャンマーの話をしたら、先生もミャンマーに行ったことがあるので協力するよと言ってくれたのです。私がミャンマー、ミャンマーと言っているうちに人が集まってきてくださって何人かでの訪問が実現したのです。岩城さんもメコン総合研究所の前身団体で寺小屋を建設されていましたし、浄土宗の先生方もすでに建設されていました。
力をもらったのは、私の方だった
私は、紹介された候補地を2カ所回ってきました。
関口先生の写真もありましたが、屋根だけで壁がない小屋を学校にしていたり、子供の人数がとても多く、小中学校が併設されている場所に建設することにしました。
日本に帰り、様々な方面に呼びかけ、学校を建設できました。私はその学校の開校式には行けませんでしたが、昨年は現地を訪問できました。子どもたちの勉強する姿を見てやって良かったのだと思いました。
最初に行ったときには、子どもたちは本当に粗末な服装だったし、モノもない。しかし、皆、目を輝かして元気だった。そのエネルギーをたくさんもらって、「私はこの子たちに何かしてあげたい」という力をたくさんもらって帰国したのです。
教育支援は無条件で良いことなのか
実は、関口先生の写真を見ながら思っていたことがあります。
日本は欧米の価値観を受け入れて社会を作っていますが、私たちははたしてしあわせなのでしょうか。経済は発展したけれどしあわせなのか。と、根本的なところで疑問を持っています。
ブータンから始まったGNH(グロス・ナショナル・ハピネス)という基準があります。しあわせの点数をつけると日本は経済的発展にくらべて多くの人がしあわせだとは思っていないこともわかっています。
そうすると、子どもたちにとって教育とは何なのか。
教育の機会を平等に与えてあげるということは必要だが、私たちの価値観が正しいのか?
年間3万人が自殺しているが平均寿命は延びている。
平均寿命は延びているが痴呆症の方々が増えている。
長年働いて稼いだお金も医療費に消える…。
私たちがそういう結果をもたらす教育を押し付ける。
学校を作って教育を広めることが正しいのかと、考えているのです。
さきほどは少数民族の写真がたくさんありました。皆素晴らしい笑顔で個性的な恰好をしています。でも、少数民族の子どもが教育を受けて標準化されていくと、耳に穴をあけることについて宜しくないだとかそういう西洋的な標準化された価値観を学んでいくかもしれない。
関口先生は、ビーズで装飾した民族衣装を買い取ったとおっしゃったが、彼女たちが教育を受けて賃金の高い職業に就きたいと思うようになったら、あのような伝統的な衣装がすたれていくのではないか。そう思うと、何が良いことなのかと悩んでしまうのです。
楠木真次監事
私も安倍さんが作った寺小屋の開校式に出席しました。子どもたちが割れんばかりの大声で音読しながら勉強していました。日本人が忘れたことがあの学校にはありました。今日のタイトル通り「子どもたちに教えられたこと」を実感しました。
スタディツアーで日本人はショックを受ける
袖山榮眞理事長
いろいろと言いたいことはあります。今年8月に2度目のスタディツアーを実施します。私は東海学園大学の学長もしていますので、ここの先生方にも参加するように呼びかけています。1度目のツアーは評判がよかったのです。
われわれが当初に狙ったこととは違う結果でしたが、現代の日本人にショックを与えるという意味で価値があった。
最初は、寺小屋をもっと作る。ということを目的にしていました。
私は長野県の出身で、同和問題について考える宗教者の団体でも役員をしていました。
その時に、「これは気付かなかった」と思わされたのが、当時、不当な扱いを受けていた方々が「自分たちは学校で教育を受ける機会がなかったので、自分たちで地道に識字教育を重ねてきた」とおっしゃった。英語でリテラシーと言うが、読書の能力を人から奪うのは基本的人権を侵していることです。
われわれが、お金を集めてミャンマーに学校を建てるというと、軍事政権がいる国じゃないかという答えが返ってくるが、そうではなくて、文字を読むことができる人を一人でも増やしていくことが、国の力になる。と私は考えています。
私は政権の在り方について議論しているのではなく、読み書きの力を発展、成長させていきたいのだと訴えているのです。皆さんにはこの観点から協力をお願いしたいのです。
楠木真次監事
メコン総合研究所では様々な立場の方々からご寄付を頂いて現地とのハシゴの役目をしています。岩城さんからその活動を紹介してください。
子どもたちが寺小屋に来る理由。食事の確保
岩城良生事務局長
メコン総合研究所は、法人化してからの4年間で10校の学校を建設しました。そのうちの5校は浄土宗の先生方の御力によるものです。
ただし、私たちの前身団体時代にも2校、建設していますので、浄土宗報恩明照会としては7校になります。ほかに、安倍さんやほかの方々と建設した学校があります。
関口先生のお話しにありましたが、「なぜ、寺小屋に子どもが来るのか」という問題です。
子どもは弁当を持参できない。ミャンマーの学校には給食がない。弁当を持参するのが基本です。しかし、寺小屋に来る子供には、弁当を持参する子はいない。
これはなぜかと言いますと、父母が日雇い労働者で朝4時には働きに出て、9時頃に日当をもらって帰ってきます。それから、その日の食事を作る。という生活です。だから、子どもたちは昼ご飯を食べに帰宅します。そうすると、午後の授業には帰ってこない子どもも珍しくないのです。
公的な学校ですと、出席率など厳しく、家庭の事情と学業が並立しません。寺小屋の場合は午後に学校に戻れない子どもでも面倒を見てくれます。小学校の中高学年になると、弟や妹を連れてくる子が増えます。兄、姉として、下の子の面倒を見ているのです。これも寺小屋の特長です。
先ほども識字率の話が出ましたが、ミャンマーの識字率は89・9%。これほど高いのは寺小屋があるおかげです。ミャンマーは昔から寺小屋があって、公的な学校に行けない子が来ています。
1食でも給食を提供できれば、子どもは学校に通える
ここで、皆さんに知って頂きたいことがあります。
一食でもこの子どもたちに与えることができたら、もっと学校に来ることができるようになります。
できるだけ、子どもたちに給食を上げたいのです。
メコン総合研究所として、これからの活動の柱としていきます。今までに開設した学校で、給食の問題に取り組みたいと考えています。
日本円で100円あれば、5人の子供に一食与えることができます。今まではハードだけでしたが、これからはソフト面でも活動していきたいのです。
楠木真次監事
給食は単に、ご飯を上げるのではなく、通学しやすい環境を整えてあげるという意味があるのですね。
教育支援はデリケートな問題でもある
関口照生顧問
寺小屋というセイフティーネットを支援することで落ちこぼれていく子どもを拾い上げることができる。寺小屋支援はこういうことだと思う。ただ、どうしても、支援は、実行しやすい地域に集中するものです。
先ほどお見せした少数民族は、実は、政府関係者にお聞きしても、あの人たちがどのような生活をしているのかよく分かっていない。支援をする側としてはなるだけ、そういう場所にまで届くように努力したいものです。それから、「箱モノ行政」から脱却して、ソフトの充実に注力するべきだと思います。
地域ごとに、大切なものの順位が変わる。地域によっては給食が一番大事だとか、学習が最優先だとか、変わるわけです。そういう問題。しかし、教育に外国人がかかわるのは難しい。もし、日本ならば、外国人が教育支援をしてきたら怒るでしょう。そういうことも勘案しながら、ソフトの充実を図っていくのがこれからの支援の在り方だと思います。
私は、こういうことを考えると同時に、ミャンマー人の人柄の良さを痛感しています。
こういう人々から、将来、今度は私たちが彼らからの支援を受ける未来もあるのだということを頭に入れておくことも重要です。われわれがミャンマー人介護スタッフから、介護を受ける。ということです。こういう人々が働ける場所を日本に作っておくのも重要です。これは双方にとって励みになるでしょう。
また、ミャンマーというと寄付が集まりにくい。ということもあります。お金がなければ支援できない。ということも事実です。
楠木真次監事
私は経験がないのですが、たとえば、ミャンマーで財布を落とす。パスポートを落とす。そうすると、ほぼ間違いなく返却される。という話を聞きます。ほかの国、日本でさえも難しいでしょう。なかなかできることではないです。そんな人柄の良さがあります。
編集注 パネルデスカッションが終了し、ここで聴講者からの質問を受け付けました。
今泉記念ビルマ奨学会の今泉清詞会長が次のようにお話しされ、大きな話題を提供されました。
われわれに命を与えてくれた恩返し
今泉清詞会長
私は、大東亜戦争の時に従軍しました。
今、一般的には支援の在り方について、人道的な感覚として、相手が貧しい国だから、支援してやろうじゃないかという認識だと思います。しかし、私たちからすれば、「恩返し」なのです。
戦時中、32万人が進駐して19万人が戦死した。13万人が帰国した。19万人の遺骨はほとんど帰っていません。現地の人々に埋葬してもらっています。よく、19万の英霊に対して、「安らかに眠れ」と言いますが、やはりミャンマーの大地で安らかに眠るには、その国が繁栄していないと彼ら英霊も安らかに眠れないのです。そのために、ミャンマーが平和であってほしい。繁栄してほしい。
復員した13万人は、皆、同じことを言います。
「もし、ミャンマーでなかったら、私たちは帰国できなかった」ということです。
皆さんご存知の通り、ビルマ戦線の悲惨さは筆舌に尽くしがたいものがあります。
食べるモノがない。それを現地の人々が、自分の食べ物を分けて与えてくれた。
このことを思うと、「相手が貧しいから支援してやろう」なんて、とんでもない傲慢ですよ。
若い人にも、われわれに命を与えてくれた恩返しだという気持ちを持って、ミャンマーを見てほしい。気持ちが逆なんです。与えてやっているのではない。恩返しなんです。われわれの世代は、皆、そう考えているのです。
袖山榮眞理事長
私が最初にお話ししたことですが、ミャンマー人僧侶が子どもたちに対して、われわれ寺小屋に来た日本人を指して、「前世で君たちに世話になった人たちが、今度は君たちの世話をしに来たよ」という説明をしました。その目線、その発想で活動をするのが大切です。良いお話しを頂きました。ありがとうございました。
私たちは、もっと素晴らしいものを受け取っている
安倍昭恵顧問
今泉先生に、恩返しという言葉をもらって、そういう気持ちが私の中にもあることが分かりました。
ミャンマーがほかの国と違うのは、この気持ちがあるかないかですね。
私が岩城さんに最初に会った時、彼は、「自分はミャンマーで戦死した19万人の日本人のなかのひとりだ」と言いました。大変感動したのを覚えています。ミャンマーに関係した日本人がなくなり、今度はミャンマー人として生まれた。それが自分だと。
子どもはどこに生まれても夢を持つ権利があります。
ミャンマー語には「夢」という言葉がないそうです。将来何になりたいという夢を聞かれると多くの子どもは教師や軍人になると答えます。
日本で使う、目標やあこがれを意味する「夢」という言葉はないそうですが、私は、ミャンマーの子どもにも「夢」を持ってほしいと思っています。
私がミャンマーに行くと言うと、怖い国だと言われるのですが、とんでもない。やさしい人々の国ですよ。我慢強く、明るい人々の国です。
今日、皆さんは写真を見て、ミャンマーに対して共感を持ってもらえたと思います。ぜひ、多くの人に今日のことを話してあげてください。
相手が貧しいからしてあげるのではなく、もちろん、その側面があるのは事実ですが、それだけではないのです。
今日も、愛知県から来てくださった先生がおられます。この先生はミャンマーでの遺骨収集に携わっておられる。日本の小学校で、この先生と私で講演をしました。ミャンマーの話をして、最後に子どもたちが感想文を書いてくれました。涙が出るような文章ばかりでした。ミャンマーに行っていない子どもも、私たちの話を聞いて、共感してくれたのです。
私たちは、与えるだけではない。もっと素晴らしいものを受け取っているということも知ってほしいと思います。
今の日本人がなくしたモノが何だったのか、ミャンマーから教えてもらってほしいと思います。
ここで、第2部は終了。懇親会へと移り、私は今泉会長のもとへ行きこんな話をしました。
――私は、今泉先生のおっしゃった、恩返しは、行動のきっかけにすぎないと思っています。なぜかと言いますと、先生たちの恩返しを、私の恩返しとして共有するにはすこし無理があるからです。ですから、壇上で皆さんが口々におっしゃった「ああ、恩返しだ。素晴らしい発想だ」という賛同には、抵抗があります。恩返しが結論になってしまうと、そこから先に進めなくなってしまう。でも、恩返しだと思っていたけれど、その先には、いのちの共感があった。ということだろうと思っています。自分の存在が相手の存在と共感し合う。そうでなければ、支援なんてできないです。私は自分の支援活動については、それ以外の想いや願い、理想などは持ち合わせていないのです。
恩を受けてあなたが今を生きていることは、それだけで大切なことなのです
今泉清詞会長
その通りですよ。私たちの恩返しがそこに到達するきっかけだと観ていただいて結構ですよ。私たち戦争を体験した者は、恩返しという気持ちから離れることはできないのです。
恩返しについて、こんなことがありました。奨学金を用立てて、ミャンマー人青年を育てる。この私のやっていることについて、昔、近しい人がこんなことを言いました。
「あなたは自分の資産を投げうってそんなことをやっているが、だれか一人でも、ミャンマー人がありがとうと言いに来たことがありますか?誰も感謝を示さないじゃないですか。そんな活動はやめてしまえばよいのです」ということです。
一隅を照らす、これ国宝なり
ですから、私はその人に言いました。
「では、君は、君を育ててくれた両親や祖父母、その先の先祖たちに、今までありがとうと言ったことがありますか?一度も言ったことがないでしょう。責めているのではなく、それはそれで構わないのです。ありがとうが出てこなくても、その恩を受けてあなたが今を生きていることは、それだけで大切なことなのです」と言いましたら、それ以降、その話は出なくなりました。
伝教大師の「一隅を照らす、これ国宝なり」じゃないですが、心はそう思ってやっていることです。
Fin.
本原稿は、仏法僧Buddhist On Stage からの転載です。

楠木真次監事
最初に、第一部では関口さんに素晴らしい写真を見せていただきました。われわれはミャンマーの支援をしているが、いろんな支援が必要だと思う。パネラーの皆さんは、なぜミャンマーの支援をしているのか、教えてください。
日本が本当に支援するべきは、この親日国ではないか

安倍昭恵顧問
私がミャンマーに関心を持ったのは主人(安倍晋三元首相)がきっかけ。主人たち国会議員の皆さんが「アジアの子どもたちに学校を贈る会」という会を運営しています。当時は50人ほどのメンバーがいましたが、毎年、アジア各国に学校を寄贈していました。主人はそうした学校の開校式にタイミングよく出席する機会がありませんでしたが、開校式に出席した人からは、本当に現地の人々が喜び、日本人も感動するものだと聞かされていました。主人も開校式に行きたがっています。
私も、何か自分にできることはないかと思うようになり、主人に「私も学校を作りたい」と相談しました。そうしたら、「ミャンマーが良いのではないか」と答えたのです。「親日的な人々が多く、日本が支援していくべき相手はミャンマーではないか」というのです。
主人は過去に2度、ミャンマーに行きました。最初は中曽根総理大臣時代に、父の安倍晋太郎が外務大臣をしており、中曽根首相に同行しました。当時は、アジア各国はどこを訪問しても戦後補償の問題が山積していました。行く先々でいろいろな要求を突き付けられていた。最後に訪問したのがミャンマーで、中曽根首相は帰国しなければならず、父と主人がミャンマーに入国しました。すると、今までの国と違って大歓迎で、おまけに日本語の歌として軍歌まで飛び出しました。軍歌がどうこうということではなくて、現地の人が歌える日本語がその当時は軍歌であったということです。それくらい、日本に良い感情を持ってくださっていた。主人はこの感動を、身を持って体験したことで、「何かしてあげたい。こんな国にこそ、日本は支援するべきだ」と思ったそうです。
今、日本とミャンマーは国と国のレベルでは関係は難しいものがありますが、民間としては大いに何かしたいと思うのです。
そんな経緯があって、私は主人に「私も学校を作る」と言いました。皆さん御承知の通り、太平洋戦争では約20万人がビルマで亡くなりました。そんな人々がいて、今の私たちがある。そういうことも含めて、ミャンマーに学校を建てたいと思ったのです。
学校建設の根拠
袖山榮眞理事長
私は個人的には、古い仏教経典を日本で研究するとき、「ブッダゴーサ(仏音/覚音)」という有名な翻訳家の翻訳を読むことになります。この人はスリランカに住んでいたが、実はミャンマー人だった。ミャンマーにこそ古い仏教が伝わっていたことに関心を持っていました。私は今、浄土宗報恩明照会という財団の理事長をしています。先代理事長、先々代理事長は戦後まもなくミャンマーの僧院で生活をされていました。こういうこともあって、私個人はミャンマーに親近感を持っていました。
私たち浄土宗報恩明照会はミャンマーに学校を建設していますが、「その後のこと」について、どうなっているんだと思う人も多いでしょう。メコン総合研究所と協力関係を築くことで、われわれは今までに7校、開校することができた。ここには校医がいないので日本人医師、看護師らの団体とメコン総合研究所が提携して、校医をしてもらっている。われわれは学校を造り、ソフトの部分でメコン総合研究所にお願いしている。だから、われわれは堂々と皆さんにご寄付をお願いできる。
箱モノ行政ではダメ。ソフトとの並立が大切
関口照生顧問
ミャンマーは、日本とは大変形態が違う国。日本は単一民族ではないが、歴史的に、そんなにたくさんの民族は入ってきていない。昔、ヨーロッパで欧米人から「君はチャイニーズか?」と聞かれると、「アイム・ジャパニーズ。アイム・ピュア・ジャパニーズ」と答える日本人がいた。私は、「ピュアな日本人」という存在はありえないんだけれど…と思いながら聞いていました。日本は何かあるとひとつの民族としてまとまっているように見えるが、それは長い間鎖国していたから。
「日本文化」という共通の価値観を持っていて、これを介してコミュニケーションすることで互いに日本人を認識している。阿吽の呼吸で理解が成立するわけです。
一方、ミャンマーは人種のるつぼ。130以上の民族が集まっています。最大規模のビルマ族が政権を担っているというだけのことです。私が育った昭和20年以前の日本は、軍国主義です。だから、私たちの世代は、日本とミャンマーは、何ら変わりがないことを知っています。
戦後、私たちは民主主義を与えてもらった。しかし、日本の中で本物の民主主義が育っているのかと考えれば、ハイとは答えにくい。それは、国民が血を流して勝ちとった自由ではないからです。だから、私はいつも思うのです。
ミャンマーに学校などを寄贈するときは、私は、箱モノを作ればそれで良いとはまったく思っていません。ソフトの充実が大切なのです。しかし、学校があれば、子どもたちが考えるようになる。教育の良いところは、自分で考えることを知ることができるということです。日本のように守られてばかりいては、自分で考えられなくなる。貧しい国が考えるようになると、時間がかかっても自分たちで考え、進むようになる。余分な経済的な支援よりも教育支援が大切なのです。
そんなふうに思うので、私はミャンマーに肩入れしています。
また、カンボジアなどは、著名人が寄ってたかって支援しています。一方、ミャンマーは敬遠しがちです。この差も重要なポイントですね。
華やかな明治時代は、江戸の寺小屋があればこそ
楠木真次監事
学校の話が尽きませんが、われわれ日本人は明治に大改革を断行しました。これは、江戸時代の寺小屋教育の発達が要因。寺小屋が明治という時代を生み出したといいます。
教育は大切ですね。
ところで、メコン総合研究所の岩城事務局長は、見た目も日本人だが、ミャンマー出身。4年前に帰化された経歴をお持ちです。今まで、日本人の言い分を聞かれてきて、どんなことを思っておられるのでしょうか。
子どもたちが学ぶ環境を作ってあげたい
岩城良生事務局長
私はミャンマー人だったからミャンマーの支援をしていたこともありますが、今は日本人として、メコン総合研究所としてメコン川流域全体にかかわる活動をしています。
関口先生のおっしゃったとおり、教育は力です。
私の場合はミャンマーで教育を受けられなかったからこそ、日本に来ました。1988年に大学が閉鎖され、小学校から大学まで、すべての教育機関が閉鎖されたので日本に来ました。ミャンマーでは教育が犠牲になっています。国民の勉強をサポートしているのが寺小屋であり、その寺小屋をサポートしているのが私たちだという関係です。
私たちは、運よく勉強できて、こんな活動をしていられますが、国から出られない子どもたち、授業を受けられない子どもたちが学校に行けるような環境を作ってあげたいです。
楠木真次監事
岩城さんがいた20年前よりも教育に関する環境は悪化しているといいますが、それはどのような感じですか。
教育は時代の波に飲み込まれ…
岩城良生事務局長
88年の民主化運動は学生運動から始まり、小学校から大学院までの教育機関が3年近く閉鎖されました。当時の政府は2年半から3年にわたって、大学をはじめ、すべての高等教育機関をヤンゴン市内から市街の僻地に移築しました。学校が再開した時には戻れなくなった学生も大勢いました。
これが「88年世代」で、今40歳前後、ちょうど私たちの世代に当たり、その多くは海外に移住しました。
再開した公的な学校では、適切な教育を受けられなくなっていたので、1990年以降は寺小屋がたくさん誕生しました。
楠木真次監事
本日のテーマは「ミャンマーの子どもたちが教えてくれたこと」です。皆さんの子どもたちへの支援の内容を教えてください。
私は何も知らなかったが、何かしたかった
安倍昭恵顧問
ミャンマーには学校を作りたかったのですが、私ははじめ、ミャンマーに関する人をまったく知りませんでした。学校というものはどうやって作ればよいのかも知りませんでした。どこかの団体にお金を渡して建設をお願いすることはできたのでしょうが、私は現地に行き、現場を知りたいと思いました。自分で見て、本当に必要とされている場所に建てたかった。とりあえずミャンマーに行こう。と、何のあてもなく、友人と行ってきました。
誰も知っている人がいないと困るので、今日も来てくださっている「日本ウズベキスタン協会」での知人に、ミャンマーに関係のある人がいないかと尋ねたら、すぐに、岩城さんを紹介してくださったのです。関口先生とはもともとはワインの飲み友達で、たまたまワインの席でミャンマーの話をしたら、先生もミャンマーに行ったことがあるので協力するよと言ってくれたのです。私がミャンマー、ミャンマーと言っているうちに人が集まってきてくださって何人かでの訪問が実現したのです。岩城さんもメコン総合研究所の前身団体で寺小屋を建設されていましたし、浄土宗の先生方もすでに建設されていました。
力をもらったのは、私の方だった
私は、紹介された候補地を2カ所回ってきました。
関口先生の写真もありましたが、屋根だけで壁がない小屋を学校にしていたり、子供の人数がとても多く、小中学校が併設されている場所に建設することにしました。
日本に帰り、様々な方面に呼びかけ、学校を建設できました。私はその学校の開校式には行けませんでしたが、昨年は現地を訪問できました。子どもたちの勉強する姿を見てやって良かったのだと思いました。
最初に行ったときには、子どもたちは本当に粗末な服装だったし、モノもない。しかし、皆、目を輝かして元気だった。そのエネルギーをたくさんもらって、「私はこの子たちに何かしてあげたい」という力をたくさんもらって帰国したのです。
教育支援は無条件で良いことなのか
実は、関口先生の写真を見ながら思っていたことがあります。
日本は欧米の価値観を受け入れて社会を作っていますが、私たちははたしてしあわせなのでしょうか。経済は発展したけれどしあわせなのか。と、根本的なところで疑問を持っています。
ブータンから始まったGNH(グロス・ナショナル・ハピネス)という基準があります。しあわせの点数をつけると日本は経済的発展にくらべて多くの人がしあわせだとは思っていないこともわかっています。
そうすると、子どもたちにとって教育とは何なのか。
教育の機会を平等に与えてあげるということは必要だが、私たちの価値観が正しいのか?
年間3万人が自殺しているが平均寿命は延びている。
平均寿命は延びているが痴呆症の方々が増えている。
長年働いて稼いだお金も医療費に消える…。
私たちがそういう結果をもたらす教育を押し付ける。
学校を作って教育を広めることが正しいのかと、考えているのです。
さきほどは少数民族の写真がたくさんありました。皆素晴らしい笑顔で個性的な恰好をしています。でも、少数民族の子どもが教育を受けて標準化されていくと、耳に穴をあけることについて宜しくないだとかそういう西洋的な標準化された価値観を学んでいくかもしれない。
関口先生は、ビーズで装飾した民族衣装を買い取ったとおっしゃったが、彼女たちが教育を受けて賃金の高い職業に就きたいと思うようになったら、あのような伝統的な衣装がすたれていくのではないか。そう思うと、何が良いことなのかと悩んでしまうのです。
楠木真次監事
私も安倍さんが作った寺小屋の開校式に出席しました。子どもたちが割れんばかりの大声で音読しながら勉強していました。日本人が忘れたことがあの学校にはありました。今日のタイトル通り「子どもたちに教えられたこと」を実感しました。
スタディツアーで日本人はショックを受ける
袖山榮眞理事長
いろいろと言いたいことはあります。今年8月に2度目のスタディツアーを実施します。私は東海学園大学の学長もしていますので、ここの先生方にも参加するように呼びかけています。1度目のツアーは評判がよかったのです。
われわれが当初に狙ったこととは違う結果でしたが、現代の日本人にショックを与えるという意味で価値があった。
最初は、寺小屋をもっと作る。ということを目的にしていました。
私は長野県の出身で、同和問題について考える宗教者の団体でも役員をしていました。
その時に、「これは気付かなかった」と思わされたのが、当時、不当な扱いを受けていた方々が「自分たちは学校で教育を受ける機会がなかったので、自分たちで地道に識字教育を重ねてきた」とおっしゃった。英語でリテラシーと言うが、読書の能力を人から奪うのは基本的人権を侵していることです。
われわれが、お金を集めてミャンマーに学校を建てるというと、軍事政権がいる国じゃないかという答えが返ってくるが、そうではなくて、文字を読むことができる人を一人でも増やしていくことが、国の力になる。と私は考えています。
私は政権の在り方について議論しているのではなく、読み書きの力を発展、成長させていきたいのだと訴えているのです。皆さんにはこの観点から協力をお願いしたいのです。
楠木真次監事
メコン総合研究所では様々な立場の方々からご寄付を頂いて現地とのハシゴの役目をしています。岩城さんからその活動を紹介してください。
子どもたちが寺小屋に来る理由。食事の確保
岩城良生事務局長
メコン総合研究所は、法人化してからの4年間で10校の学校を建設しました。そのうちの5校は浄土宗の先生方の御力によるものです。
ただし、私たちの前身団体時代にも2校、建設していますので、浄土宗報恩明照会としては7校になります。ほかに、安倍さんやほかの方々と建設した学校があります。
関口先生のお話しにありましたが、「なぜ、寺小屋に子どもが来るのか」という問題です。
子どもは弁当を持参できない。ミャンマーの学校には給食がない。弁当を持参するのが基本です。しかし、寺小屋に来る子供には、弁当を持参する子はいない。
これはなぜかと言いますと、父母が日雇い労働者で朝4時には働きに出て、9時頃に日当をもらって帰ってきます。それから、その日の食事を作る。という生活です。だから、子どもたちは昼ご飯を食べに帰宅します。そうすると、午後の授業には帰ってこない子どもも珍しくないのです。
公的な学校ですと、出席率など厳しく、家庭の事情と学業が並立しません。寺小屋の場合は午後に学校に戻れない子どもでも面倒を見てくれます。小学校の中高学年になると、弟や妹を連れてくる子が増えます。兄、姉として、下の子の面倒を見ているのです。これも寺小屋の特長です。
先ほども識字率の話が出ましたが、ミャンマーの識字率は89・9%。これほど高いのは寺小屋があるおかげです。ミャンマーは昔から寺小屋があって、公的な学校に行けない子が来ています。
1食でも給食を提供できれば、子どもは学校に通える
ここで、皆さんに知って頂きたいことがあります。
一食でもこの子どもたちに与えることができたら、もっと学校に来ることができるようになります。
できるだけ、子どもたちに給食を上げたいのです。
メコン総合研究所として、これからの活動の柱としていきます。今までに開設した学校で、給食の問題に取り組みたいと考えています。
日本円で100円あれば、5人の子供に一食与えることができます。今まではハードだけでしたが、これからはソフト面でも活動していきたいのです。
楠木真次監事
給食は単に、ご飯を上げるのではなく、通学しやすい環境を整えてあげるという意味があるのですね。
教育支援はデリケートな問題でもある
関口照生顧問
寺小屋というセイフティーネットを支援することで落ちこぼれていく子どもを拾い上げることができる。寺小屋支援はこういうことだと思う。ただ、どうしても、支援は、実行しやすい地域に集中するものです。
先ほどお見せした少数民族は、実は、政府関係者にお聞きしても、あの人たちがどのような生活をしているのかよく分かっていない。支援をする側としてはなるだけ、そういう場所にまで届くように努力したいものです。それから、「箱モノ行政」から脱却して、ソフトの充実に注力するべきだと思います。
地域ごとに、大切なものの順位が変わる。地域によっては給食が一番大事だとか、学習が最優先だとか、変わるわけです。そういう問題。しかし、教育に外国人がかかわるのは難しい。もし、日本ならば、外国人が教育支援をしてきたら怒るでしょう。そういうことも勘案しながら、ソフトの充実を図っていくのがこれからの支援の在り方だと思います。
私は、こういうことを考えると同時に、ミャンマー人の人柄の良さを痛感しています。
こういう人々から、将来、今度は私たちが彼らからの支援を受ける未来もあるのだということを頭に入れておくことも重要です。われわれがミャンマー人介護スタッフから、介護を受ける。ということです。こういう人々が働ける場所を日本に作っておくのも重要です。これは双方にとって励みになるでしょう。
また、ミャンマーというと寄付が集まりにくい。ということもあります。お金がなければ支援できない。ということも事実です。
楠木真次監事
私は経験がないのですが、たとえば、ミャンマーで財布を落とす。パスポートを落とす。そうすると、ほぼ間違いなく返却される。という話を聞きます。ほかの国、日本でさえも難しいでしょう。なかなかできることではないです。そんな人柄の良さがあります。
編集注 パネルデスカッションが終了し、ここで聴講者からの質問を受け付けました。
今泉記念ビルマ奨学会の今泉清詞会長が次のようにお話しされ、大きな話題を提供されました。
われわれに命を与えてくれた恩返し
今泉清詞会長
私は、大東亜戦争の時に従軍しました。
今、一般的には支援の在り方について、人道的な感覚として、相手が貧しい国だから、支援してやろうじゃないかという認識だと思います。しかし、私たちからすれば、「恩返し」なのです。
戦時中、32万人が進駐して19万人が戦死した。13万人が帰国した。19万人の遺骨はほとんど帰っていません。現地の人々に埋葬してもらっています。よく、19万の英霊に対して、「安らかに眠れ」と言いますが、やはりミャンマーの大地で安らかに眠るには、その国が繁栄していないと彼ら英霊も安らかに眠れないのです。そのために、ミャンマーが平和であってほしい。繁栄してほしい。
復員した13万人は、皆、同じことを言います。
「もし、ミャンマーでなかったら、私たちは帰国できなかった」ということです。
皆さんご存知の通り、ビルマ戦線の悲惨さは筆舌に尽くしがたいものがあります。
食べるモノがない。それを現地の人々が、自分の食べ物を分けて与えてくれた。
このことを思うと、「相手が貧しいから支援してやろう」なんて、とんでもない傲慢ですよ。
若い人にも、われわれに命を与えてくれた恩返しだという気持ちを持って、ミャンマーを見てほしい。気持ちが逆なんです。与えてやっているのではない。恩返しなんです。われわれの世代は、皆、そう考えているのです。
袖山榮眞理事長
私が最初にお話ししたことですが、ミャンマー人僧侶が子どもたちに対して、われわれ寺小屋に来た日本人を指して、「前世で君たちに世話になった人たちが、今度は君たちの世話をしに来たよ」という説明をしました。その目線、その発想で活動をするのが大切です。良いお話しを頂きました。ありがとうございました。
私たちは、もっと素晴らしいものを受け取っている
安倍昭恵顧問
今泉先生に、恩返しという言葉をもらって、そういう気持ちが私の中にもあることが分かりました。
ミャンマーがほかの国と違うのは、この気持ちがあるかないかですね。
私が岩城さんに最初に会った時、彼は、「自分はミャンマーで戦死した19万人の日本人のなかのひとりだ」と言いました。大変感動したのを覚えています。ミャンマーに関係した日本人がなくなり、今度はミャンマー人として生まれた。それが自分だと。
子どもはどこに生まれても夢を持つ権利があります。
ミャンマー語には「夢」という言葉がないそうです。将来何になりたいという夢を聞かれると多くの子どもは教師や軍人になると答えます。
日本で使う、目標やあこがれを意味する「夢」という言葉はないそうですが、私は、ミャンマーの子どもにも「夢」を持ってほしいと思っています。
私がミャンマーに行くと言うと、怖い国だと言われるのですが、とんでもない。やさしい人々の国ですよ。我慢強く、明るい人々の国です。
今日、皆さんは写真を見て、ミャンマーに対して共感を持ってもらえたと思います。ぜひ、多くの人に今日のことを話してあげてください。
相手が貧しいからしてあげるのではなく、もちろん、その側面があるのは事実ですが、それだけではないのです。
今日も、愛知県から来てくださった先生がおられます。この先生はミャンマーでの遺骨収集に携わっておられる。日本の小学校で、この先生と私で講演をしました。ミャンマーの話をして、最後に子どもたちが感想文を書いてくれました。涙が出るような文章ばかりでした。ミャンマーに行っていない子どもも、私たちの話を聞いて、共感してくれたのです。
私たちは、与えるだけではない。もっと素晴らしいものを受け取っているということも知ってほしいと思います。
今の日本人がなくしたモノが何だったのか、ミャンマーから教えてもらってほしいと思います。
ここで、第2部は終了。懇親会へと移り、私は今泉会長のもとへ行きこんな話をしました。
――私は、今泉先生のおっしゃった、恩返しは、行動のきっかけにすぎないと思っています。なぜかと言いますと、先生たちの恩返しを、私の恩返しとして共有するにはすこし無理があるからです。ですから、壇上で皆さんが口々におっしゃった「ああ、恩返しだ。素晴らしい発想だ」という賛同には、抵抗があります。恩返しが結論になってしまうと、そこから先に進めなくなってしまう。でも、恩返しだと思っていたけれど、その先には、いのちの共感があった。ということだろうと思っています。自分の存在が相手の存在と共感し合う。そうでなければ、支援なんてできないです。私は自分の支援活動については、それ以外の想いや願い、理想などは持ち合わせていないのです。
恩を受けてあなたが今を生きていることは、それだけで大切なことなのです
今泉清詞会長
その通りですよ。私たちの恩返しがそこに到達するきっかけだと観ていただいて結構ですよ。私たち戦争を体験した者は、恩返しという気持ちから離れることはできないのです。
恩返しについて、こんなことがありました。奨学金を用立てて、ミャンマー人青年を育てる。この私のやっていることについて、昔、近しい人がこんなことを言いました。
「あなたは自分の資産を投げうってそんなことをやっているが、だれか一人でも、ミャンマー人がありがとうと言いに来たことがありますか?誰も感謝を示さないじゃないですか。そんな活動はやめてしまえばよいのです」ということです。
一隅を照らす、これ国宝なり
ですから、私はその人に言いました。
「では、君は、君を育ててくれた両親や祖父母、その先の先祖たちに、今までありがとうと言ったことがありますか?一度も言ったことがないでしょう。責めているのではなく、それはそれで構わないのです。ありがとうが出てこなくても、その恩を受けてあなたが今を生きていることは、それだけで大切なことなのです」と言いましたら、それ以降、その話は出なくなりました。
伝教大師の「一隅を照らす、これ国宝なり」じゃないですが、心はそう思ってやっていることです。
Fin.
本原稿は、仏法僧Buddhist On Stage からの転載です。










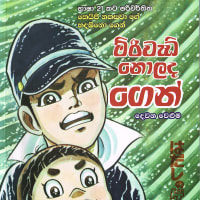









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます