
【サロメ】フランツ・フォン・シュトゥック
イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にもはいった。人々は、「パプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから、あんな力が、彼のうちに働いているのだ」と言っていた。
別の人々は、「彼はエリヤだ」と言い、さらに別の人々は、「昔の預言者の中のひとりのような預言者だ」と言っていた。
しかし、ヘロデはうわさを聞いて、「私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ」と言っていた。
実は、このヘロデが、自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤのことで、――ヘロデはこの女を妻としていた――人をやってヨハネを捕え、牢につないだのであった。
これは、ヨハネがヘロデに、「あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法です」と言い張ったからである。
ところが、ヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら、果たせないでいた。
それはヘロデが、ヨハネを聖なる正しい人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。また、ヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。
ところが、よい機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に、重臣や、千人隊長や、ガリラヤのおもだった人などを招いて、祝宴を設けたとき、ヘロデヤの娘がはいって来て、踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王は、この少女に、「何でもほしい物を言いなさい。与えよう」と言った。
また、「おまえの望む物なら、私の国の半分でも、与えよう」と言って、誓った。
そこで少女は出て行って、「何を願いましょうか」とその母親に言った。すると母親は、「バプテスマのヨハネの首」と言った。
そこで少女はすぐに、大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。
「今すぐに、パプテスマのヨハネの首を盆に載せていただきとうございます」
王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。
そこで王は、すぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持って来るように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に載せて持って来て、少女に渡した。少女は、それを母親に渡した。
ヨハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やって来て、遺体を引き取り、墓に納めたのであった。
(マルコの福音書、第6章14節~29節)
イエスさまは「律法と預言者はヨハネまでです」、「女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人はいない」とおっしゃっておられるわけですけど……旧約聖書の代表的な預言者であるイザヤといいエレミヤといい、大抵ろくな目に遭ってなかったり、ろくな死に方をしてませんよね(^^;)
伝承によれば、イザヤは首をノコギリ引きにされて殉教、エレミヤは労多く報いの少ない人生を終えて、エジプトという異郷の地で亡くなったといいます
他にも神さまから遣わされた預言者が旧約聖書には何人も出てくるのですが、全体として不幸な印象がすごく強いんですよね。
もちろん中には、預言者として高い地位を得、人々から尊ばれて生涯を終えた方もいらっしゃると思うのですが、正しいこと、神さまに語られたことをそのまま言っただけなのに、それが時の王の逆鱗に触れ、大変な目にあったり……いや~、そんなんだったらそもそも、「神さまのおっしゃる正しいこと」になんか関わらないほうがいいんじゃね?とすらちらっと思ってしまいます(^^;)
でも、十二弟子がちょうどそうであるように、こうしたことはすべて、後世の信者ひとりびとりに必要なこととして起こった……そうした見方も出来ると思うんですよね。
十二弟子は、パトモスに島流しにされたヨハネ以外、全員殉教しましたし、旧約時代の偉大な預言者たちも、その多くが苦労の多い大変な生涯だったように見えます。
このことは、「神さまに従うのって、それだけ大変なんだよ 」というのちの信者の模範であると同時に――「イザヤやエレミヤだってあれだけ大変だったんだから、ましてや小さな信仰者であるわたしが苦労するのは当然だ」、「いやいや、あれほど迫害されて苦労した彼らに比べたら、わたしの人生の苦悩などは小さなことだ」……といった、精神的な支えにもなることだと思います。
」というのちの信者の模範であると同時に――「イザヤやエレミヤだってあれだけ大変だったんだから、ましてや小さな信仰者であるわたしが苦労するのは当然だ」、「いやいや、あれほど迫害されて苦労した彼らに比べたら、わたしの人生の苦悩などは小さなことだ」……といった、精神的な支えにもなることだと思います。
逆にいったとすれば、イザヤもエレミヤもそう大した苦労もなく、大預言者先生としての生涯を幸福に過ごしていたとしたら、もしかしたら彼らの名前というのは後世にそんなに轟かなかった可能性もあるのではないでしょうか。
けれど、特にエレミヤなどは、彼の哀歌の中だけでなく、エレミヤ書の中でも時々神さまに愚痴ってますよね(^^;)
「わたしの一生は恥の内に終わるのか」とか「何故わたしは母の胎から出てきたのか」などなど、「こんなことなら生まれなきゃ良かった 」とすら嘆いているエレミヤ。
」とすら嘆いているエレミヤ。
私の生まれた日は、のろわれよ。
母が私を産んだその日は、祝福されるな。
私の父に、「あなたに男の子が生まれた」と言って伝え、
彼を大いに喜ばせた人は、のろわれよ。
その人は、主がくつがえして悔いのない町々のようになれ。
朝には彼に叫びを聞かせ、
真昼にはときの声を聞かせよ。
彼は、私が胎内にいるとき、私を殺さず、
私の母を私の墓とせず、
彼女の胎を、永久にみごもったままにしておかなかったのだから。
なぜ、私は労苦と苦悩に会うために胎を出たのか。
私の一生は恥のうちに終わるのか。
(エレミヤ書、第20章14~18節)
この彼の気持ちって、めちゃめちゃよくわかりますよね。いくら神さまから語られた言葉を語っても、王もその取り巻きも民衆ですらも、誰も彼の言葉にはまともに耳を傾けてくれない……普通、それが<神さまから真実語られた言葉>であったとすれば、もっと多くの人々が真剣に耳を傾けてよさそうなものです。
でもほとんどの人々が「自分にとってそれが都合のいい言葉なら聞こう」という霊的姿勢であり、エレミヤがいくら神さまから語られた真実の御言葉を語ろうとも、彼らの霊的姿勢が真っ直ぐになることはなかったのでした。
そして新約聖書は、ヨハネの荒野で叫ぶ声――「神の通られる道を真っ直ぐにせよ」というメッセージからはじまるのです。
また、ペンテコステ後、ペテロは使徒行伝の中でこう言っていますね。「この曲がった時代から救われなさい」と。
今から二千年前ですらすでに<時代が曲がっていた>のだとすれば、今という現代はもう、相当曲がり曲がって曲がりくねっている……そう感じるのはおそらく、わたしだけではないのでないでしょうか。
そしてその曲がりというか、歪みみたいなものを人が矯正される時には、相当な痛みを伴います。ようするに、エレミヤやヨハネの語ったような神さまの真実の御言葉に接した時、その曲がりや歪みを矯正しなくてはいけないと直感した人々は、そんな自分にとって都合の悪い言葉は聞きたくなかったんですよね。そのままただダラダラと惰性に従って、「明日も今日と同じくきっと平和さ」、「だって我々は神に選ばれた選民なんだし、他の民族どもとは訳が違う」……といったように思い、日々を生きていたのかもしれません。
ところが、エレミヤの時代、エレミヤが神さまより受けて語っていたとおりの破滅が彼らユダヤ民族を襲います。
「あ~あ、だから言ったのに」とか「ほ~ら、言わんこっちゃない」などと、エレミヤはこれっぽっちも思わなかったに違いありません。そのくらい、当時の南ユダ王国、ユダヤ人たちを襲った状況は悲劇的でした。王は捕えられ、民たちは捕囚の憂き目にあい、国は崩壊し、他国の支配下に置かれるということになったのです。
このことは、現代のわたしたちにも当てはまることのような気がします。「明日も今日と同じく平和だろう」などと思っていると、不意に破滅が襲ってくる……という点において。
ノアの箱舟のノアの話はあまりに有名ですが、まわりにいた人々はみな、彼が大きな箱舟を作るのを見て、馬鹿にさえしていたことでしょう。けれど、この時代の人々がノアが前もって語っても耳を傾けなかったように、今という現代も、実際はまったく同じなのではないでしょうか。
そして二千年前にイエスさまが語ったことも、「聞く耳のある者」のみが聞いて、信じたのです。
聖書の中には終わりの日のことについても言及がありますが、実際に<その日>が訪れるまで、いかに神さまの福音の御言葉に忠実に生きることが出来るか――わたし自身、日々なんとなくぼんやり過ごしつつも、心の片隅ではそんなことを思っていたりします(^^;)
それではまた~!!
イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にもはいった。人々は、「パプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから、あんな力が、彼のうちに働いているのだ」と言っていた。
別の人々は、「彼はエリヤだ」と言い、さらに別の人々は、「昔の預言者の中のひとりのような預言者だ」と言っていた。
しかし、ヘロデはうわさを聞いて、「私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ」と言っていた。
実は、このヘロデが、自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤのことで、――ヘロデはこの女を妻としていた――人をやってヨハネを捕え、牢につないだのであった。
これは、ヨハネがヘロデに、「あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法です」と言い張ったからである。
ところが、ヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら、果たせないでいた。
それはヘロデが、ヨハネを聖なる正しい人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。また、ヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。
ところが、よい機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に、重臣や、千人隊長や、ガリラヤのおもだった人などを招いて、祝宴を設けたとき、ヘロデヤの娘がはいって来て、踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王は、この少女に、「何でもほしい物を言いなさい。与えよう」と言った。
また、「おまえの望む物なら、私の国の半分でも、与えよう」と言って、誓った。
そこで少女は出て行って、「何を願いましょうか」とその母親に言った。すると母親は、「バプテスマのヨハネの首」と言った。
そこで少女はすぐに、大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。
「今すぐに、パプテスマのヨハネの首を盆に載せていただきとうございます」
王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。
そこで王は、すぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持って来るように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に載せて持って来て、少女に渡した。少女は、それを母親に渡した。
ヨハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やって来て、遺体を引き取り、墓に納めたのであった。
(マルコの福音書、第6章14節~29節)
イエスさまは「律法と預言者はヨハネまでです」、「女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人はいない」とおっしゃっておられるわけですけど……旧約聖書の代表的な預言者であるイザヤといいエレミヤといい、大抵ろくな目に遭ってなかったり、ろくな死に方をしてませんよね(^^;)
伝承によれば、イザヤは首をノコギリ引きにされて殉教、エレミヤは労多く報いの少ない人生を終えて、エジプトという異郷の地で亡くなったといいます

他にも神さまから遣わされた預言者が旧約聖書には何人も出てくるのですが、全体として不幸な印象がすごく強いんですよね。
もちろん中には、預言者として高い地位を得、人々から尊ばれて生涯を終えた方もいらっしゃると思うのですが、正しいこと、神さまに語られたことをそのまま言っただけなのに、それが時の王の逆鱗に触れ、大変な目にあったり……いや~、そんなんだったらそもそも、「神さまのおっしゃる正しいこと」になんか関わらないほうがいいんじゃね?とすらちらっと思ってしまいます(^^;)
でも、十二弟子がちょうどそうであるように、こうしたことはすべて、後世の信者ひとりびとりに必要なこととして起こった……そうした見方も出来ると思うんですよね。
十二弟子は、パトモスに島流しにされたヨハネ以外、全員殉教しましたし、旧約時代の偉大な預言者たちも、その多くが苦労の多い大変な生涯だったように見えます。
このことは、「神さまに従うのって、それだけ大変なんだよ
 」というのちの信者の模範であると同時に――「イザヤやエレミヤだってあれだけ大変だったんだから、ましてや小さな信仰者であるわたしが苦労するのは当然だ」、「いやいや、あれほど迫害されて苦労した彼らに比べたら、わたしの人生の苦悩などは小さなことだ」……といった、精神的な支えにもなることだと思います。
」というのちの信者の模範であると同時に――「イザヤやエレミヤだってあれだけ大変だったんだから、ましてや小さな信仰者であるわたしが苦労するのは当然だ」、「いやいや、あれほど迫害されて苦労した彼らに比べたら、わたしの人生の苦悩などは小さなことだ」……といった、精神的な支えにもなることだと思います。逆にいったとすれば、イザヤもエレミヤもそう大した苦労もなく、大預言者先生としての生涯を幸福に過ごしていたとしたら、もしかしたら彼らの名前というのは後世にそんなに轟かなかった可能性もあるのではないでしょうか。
けれど、特にエレミヤなどは、彼の哀歌の中だけでなく、エレミヤ書の中でも時々神さまに愚痴ってますよね(^^;)
「わたしの一生は恥の内に終わるのか」とか「何故わたしは母の胎から出てきたのか」などなど、「こんなことなら生まれなきゃ良かった
 」とすら嘆いているエレミヤ。
」とすら嘆いているエレミヤ。私の生まれた日は、のろわれよ。
母が私を産んだその日は、祝福されるな。
私の父に、「あなたに男の子が生まれた」と言って伝え、
彼を大いに喜ばせた人は、のろわれよ。
その人は、主がくつがえして悔いのない町々のようになれ。
朝には彼に叫びを聞かせ、
真昼にはときの声を聞かせよ。
彼は、私が胎内にいるとき、私を殺さず、
私の母を私の墓とせず、
彼女の胎を、永久にみごもったままにしておかなかったのだから。
なぜ、私は労苦と苦悩に会うために胎を出たのか。
私の一生は恥のうちに終わるのか。
(エレミヤ書、第20章14~18節)
この彼の気持ちって、めちゃめちゃよくわかりますよね。いくら神さまから語られた言葉を語っても、王もその取り巻きも民衆ですらも、誰も彼の言葉にはまともに耳を傾けてくれない……普通、それが<神さまから真実語られた言葉>であったとすれば、もっと多くの人々が真剣に耳を傾けてよさそうなものです。
でもほとんどの人々が「自分にとってそれが都合のいい言葉なら聞こう」という霊的姿勢であり、エレミヤがいくら神さまから語られた真実の御言葉を語ろうとも、彼らの霊的姿勢が真っ直ぐになることはなかったのでした。
そして新約聖書は、ヨハネの荒野で叫ぶ声――「神の通られる道を真っ直ぐにせよ」というメッセージからはじまるのです。
また、ペンテコステ後、ペテロは使徒行伝の中でこう言っていますね。「この曲がった時代から救われなさい」と。
今から二千年前ですらすでに<時代が曲がっていた>のだとすれば、今という現代はもう、相当曲がり曲がって曲がりくねっている……そう感じるのはおそらく、わたしだけではないのでないでしょうか。
そしてその曲がりというか、歪みみたいなものを人が矯正される時には、相当な痛みを伴います。ようするに、エレミヤやヨハネの語ったような神さまの真実の御言葉に接した時、その曲がりや歪みを矯正しなくてはいけないと直感した人々は、そんな自分にとって都合の悪い言葉は聞きたくなかったんですよね。そのままただダラダラと惰性に従って、「明日も今日と同じくきっと平和さ」、「だって我々は神に選ばれた選民なんだし、他の民族どもとは訳が違う」……といったように思い、日々を生きていたのかもしれません。
ところが、エレミヤの時代、エレミヤが神さまより受けて語っていたとおりの破滅が彼らユダヤ民族を襲います。
「あ~あ、だから言ったのに」とか「ほ~ら、言わんこっちゃない」などと、エレミヤはこれっぽっちも思わなかったに違いありません。そのくらい、当時の南ユダ王国、ユダヤ人たちを襲った状況は悲劇的でした。王は捕えられ、民たちは捕囚の憂き目にあい、国は崩壊し、他国の支配下に置かれるということになったのです。
このことは、現代のわたしたちにも当てはまることのような気がします。「明日も今日と同じく平和だろう」などと思っていると、不意に破滅が襲ってくる……という点において。
ノアの箱舟のノアの話はあまりに有名ですが、まわりにいた人々はみな、彼が大きな箱舟を作るのを見て、馬鹿にさえしていたことでしょう。けれど、この時代の人々がノアが前もって語っても耳を傾けなかったように、今という現代も、実際はまったく同じなのではないでしょうか。
そして二千年前にイエスさまが語ったことも、「聞く耳のある者」のみが聞いて、信じたのです。
聖書の中には終わりの日のことについても言及がありますが、実際に<その日>が訪れるまで、いかに神さまの福音の御言葉に忠実に生きることが出来るか――わたし自身、日々なんとなくぼんやり過ごしつつも、心の片隅ではそんなことを思っていたりします(^^;)
それではまた~!!











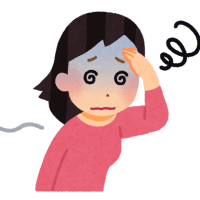
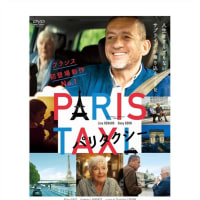












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます