
【大工の聖ヨセフ】ジョルジュ・ド・ラ・トゥール
たぶん、どんな確固たる無神論者の方でも、おそらく否定できないこととして――わたしたちの脳、心のどこかには必ず「神サマ助ケテ」機構的な何かがあるということです(^^;)
つまり、普段は無神論で生活している方でも、究極的に困ると心の奥底から「神さま、助けて~!! 」と叫びたくなるでしょうし、これはもうほとんど本能的なものなので、理性的に考えて「神なぞいないのだから無意味
」と叫びたくなるでしょうし、これはもうほとんど本能的なものなので、理性的に考えて「神なぞいないのだから無意味 」ということすら超えて、もういるのかいないのかなんてどうでもいいから助けて、というくらい追い込まれているということです。
」ということすら超えて、もういるのかいないのかなんてどうでもいいから助けて、というくらい追い込まれているということです。
これはわたしが個人的に思っていることですけれども、「あの人は神を呪う権利があると感じるほど不幸な人生を生きているのに、信仰熱心だ 」という方というのは、キリスト教徒でなくてもイスラム教徒の方や、あるいは仏教徒、ヒンズー教徒、その他の宗教を信じておられる方の中にもたくさんいらっしゃると思います。
」という方というのは、キリスト教徒でなくてもイスラム教徒の方や、あるいは仏教徒、ヒンズー教徒、その他の宗教を信じておられる方の中にもたくさんいらっしゃると思います。
自分の不幸な人生のどこかで、「だから神なぞいはしないんだ」と思う瞬間がもし仮にあったにせよ、貧しかったり病気だったり、その他なんらかの困窮に喘いでいると、神さまってもうほとんど隣人にも近い存在になってくると思います。何故かというと、「神を信じようが信じまいが、すでに失うものは何もない」というくらいだと、せめても神さまを信じていられたほうが……それが藁のように頼りないものでも、「何もない」よりは精神的に遥かに豊かだからです。
>> 彼はいたんだ葦を折ることもなく、くすぶる燈⼼を消すこともなく、まことをもって公義をもたらす。
(イザヤ書、第42章3節)
「彼はいたんだ葦を折ることもなく、くすぶる燈⼼を消すこともなく、まことをもって公義をもたらす。」 このみことばを、私たちはしばしば「葦」のように弱い私たちを慰めることばとして、今にも消えてしまいそうな「くすぶる燈⼼」を再び回復してくださることばとして理解しています。
>>いたんだ葦を折ることもなく……水辺や野原などに、葦がたくさん生えているのを見たことのある方は、たくさんいらっしゃると思います。簡単に折れてしまうことから、弱い存在の象徴と言えるでしょうが、しかもそれが痛んでいる。つまり、傷んだ葦とは、いたんでいなくてもそもそも「いつどうなるかわからない」弱い存在であり、しかもそれが傷んでいたりしたら……もうほとんど無用の存在にすら近いかもしれません。でもイエスさまは、そのような無用になったように見える存在ですら折ることもなく大切にしてくださり、さらには「くすぶる燈心」を消すこともない。
>>ランプは休みなくみずから燃える
奴隷が油を与えるけれど
そんなことに構わない
燐光にはげんでいる激しい芯は
奴隷は満たすのを忘れ
ランプは盛んに燃えつづける
奴隷が立ち去って
油の絶えたことも気づかずに
(「ディキンスン詩集」新倉俊一先生・編訳/思潮社より)
よく、蝋燭の灯火といったものは、人の寿命にたとえられることがあると思います。それまでもし仮に安全な部屋の中で光り輝いていたとしても、誰かがドアを開ければ、突然風が吹きこんできて不意に消えてしまうかもしれません。人間というのはそのくらい頼りない、次の瞬間、あるいは三十分後にですらどうなってるかわからない、脆弱な存在といっていいと思います。
ディキンスンの詩の解釈のほうは、蝋燭は奴隷がいなくなり、油を絶やしているとも気づかず、傲慢に赤々と輝いているけれども、暫くすればこの蝋燭はどうなるか……そうした人間存在の儚さを間接的に描いているといっていいと思います。
つまり、「くすぶる燈心」とは……わたしたちも「自分は一体いつまで燃えていられるのだろう」と、不安になることがよくあると思います。何分、「いつまで油をつぎ足してもらえ続けるのか」、「蝋燭が尽きようとする時、せめても別の蝋燭に火を灯してもらい、生き続けられるのか」――まるでわからないわけですよね、人間の側には。
けれど、イエスさまは「いたんだ葦」ですら大切にしてくださる方なので、わたしたちがあらゆることで不安と恐怖に見舞われる時にも手で覆って風から守ってくださり、さらには「もうそろそろ蝋燭自体なくなって、消えていきそうなんですけど~。これってどうにかしていただけるんでしょうか 」という、蝋燭の蝋の部分が残り少なくなるそのずっと以前から、「我が子よ。心配することない。わたしの名を信じている者は、次の世ではもっと明るく輝く存在となれるのだから」と、そのようにおっしゃってくださると思います。
」という、蝋燭の蝋の部分が残り少なくなるそのずっと以前から、「我が子よ。心配することない。わたしの名を信じている者は、次の世ではもっと明るく輝く存在となれるのだから」と、そのようにおっしゃってくださると思います。
蝋燭の蝋がまだ半分以上も残っているのに、突然火が消えてしまっても――本当はどうということもないのです。わたしたちがあんなにも「これが消えたらどうしよう 」とか、「あれがなくなったらどうしよう
」とか、「あれがなくなったらどうしよう 」と恐れ、不安になっていたことというのは……実際、炎が消えても、神さまのことさえ信じていたら何も問題のないことでした。
」と恐れ、不安になっていたことというのは……実際、炎が消えても、神さまのことさえ信じていたら何も問題のないことでした。
そもそも、「まだ半分以上も蝋燭が残っていたのだから、もっと燃えていたかった」などとは、天国へ行ってしまえば「いつ消えてしまうのかと恐れ怯えつつ不安になりながらギリギリまで燃えていたかった」とは、おそらく思わないものなのではないでしょうか。
けれど、人が神を畏れねばならない理由のひとつとして……同じ葦の出てくるたとえでも、
>>今、おまえは、あのいたんだ葦の杖、エジプトに拠り頼んでいるが、これは、それに寄りかかる者の手を刺し通すだけだ。エジプトの王、パロは、すべて彼に拠り頼む者にそうするのだ。
(列王記第二、第18章21節)
とあるように、真実の神以外の持つ力を信じる者は、むしろ逆にその葦に刺し通されると書き記されているわけです。簡単にいうと、「自分には今これだけ力があるから、お金があるから、自信を持って人生の歩みを確かなものにしているから」、神など信じなくても十分やっていけるんだ、頼ることの出来る大きな力や権力があるんだ……といったような場合、案外気づいてないかもしれないわけですよね。実は自分が「いたんだ葦の杖」を支えとしており、ところがそれを頑丈な永久に持つ鉄の杖か何かだと思い込んでいるということに。
でもある瞬間、ハッと気づくわけです。「自分にはこの鉄の杖があるから、大丈夫なんだ。他の人が受けるような禍いは決して自分に降りかかってくることはないだろう。いや、降りかかってきても自分には財力や権力があるから何事も穏便に済むだろう」……と内心思っていたとすれば、神さまにとっては葦の弱さも鉄の強さも同じようなものなので、もろともに滅ぼす力がある――といったようなことが大体、聖書の行間には書いてあると思うんですよね(^^;)
そして、葦の杖を持つ者を鉄の杖を持っている強者とすることも出来れば、鉄の杖を持つ者を腐った葦の杖とともに倒れるようにも出来る……「だから人は神を畏れなければならない」とも言えると思うのですが、わたしたちの現実の見方として、「葦の杖を持つ弱い者はそのまま倒れ、鉄の杖を持つ者はさらにその鉄によって葦のように弱い者を打ち据える」といった時、どうしてもそうした場合が多いとしか思えない時――信仰を持っていて、神を信じていてなんになるのか、何かになるのかという部分があるかもしれません。
でも、「人を恐れて神を畏れない」というよりは、「神を畏れて人を恐れない」ことのほうが、人生において遥かに有益な道と思います。イエスさまは、権力ある強い人の鉄の杖を粉々にし、葦のように弱い人々を守ってくださる方だからです。
>>恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強め、あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。
(イザヤ書、第41章10節)
ポイントはたぶん、「あなたがあれあれの良いことをしたから、その代わりにわたしはこれこれのことをしてあなたを守ろう 」といったように神さまはおっしゃっているわけではなく、罪に汚れて呪われたように忌まわしく、腐った匂いをそこら中に放っているような存在であっても、イエスさまを信じて悔い改めるなら、祈りによって神さまが喜ばれるような芳香を放つ存在として、イエスさまは喜んでわたしたちを変えてくださるということだと思います。
」といったように神さまはおっしゃっているわけではなく、罪に汚れて呪われたように忌まわしく、腐った匂いをそこら中に放っているような存在であっても、イエスさまを信じて悔い改めるなら、祈りによって神さまが喜ばれるような芳香を放つ存在として、イエスさまは喜んでわたしたちを変えてくださるということだと思います。
聖書には365回「恐れるな」という言葉が出てくるそうなのですが、それだけ人間は何かのことで恐れて不安になりやすい存在なのだと思います。そして、そのような存在に人間を創ったのだから、神はその責任を取って我々を守り、幸福にすべきなのだ……と、わたしもクリスチャンになる前は考えていた気がします(=現状そうなっていないということは、神なぞ存在しないのだという思考回路)。でも、365回ですからね!なんだかまるで、一年365日、イエスさまは毎日のように聖霊さまを通して「わたしがいるから恐れることはない」とおっしゃってくださっているのかもしれません。
まあ、「うるう年は? 」と聞かれると、「四年にいっぺん一日くらい、神に頼らず自分でなんとかせんかーい!
」と聞かれると、「四年にいっぺん一日くらい、神に頼らず自分でなんとかせんかーい! 」ということではなく、そんな人間の細かい暦には関係なくイエスさまは守ってくださると思います。「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」と聖書にあるように、イエスさまはコンビニのように365(366日)24時間休みなしで働いておられます。今の世の中、日本では大体コンビニってあちこちにたくさん見受けられる珍しくもない建物かもしれません。でも神さまはそれ以上に、どこにでもそこいら中にいらっしゃると、わかる方にはそう意識せずとも自然に聖霊さまを通してそのことが当たり前にわかるというか(笑)。
」ということではなく、そんな人間の細かい暦には関係なくイエスさまは守ってくださると思います。「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」と聖書にあるように、イエスさまはコンビニのように365(366日)24時間休みなしで働いておられます。今の世の中、日本では大体コンビニってあちこちにたくさん見受けられる珍しくもない建物かもしれません。でも神さまはそれ以上に、どこにでもそこいら中にいらっしゃると、わかる方にはそう意識せずとも自然に聖霊さまを通してそのことが当たり前にわかるというか(笑)。
それではまた~!!

















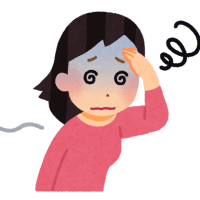
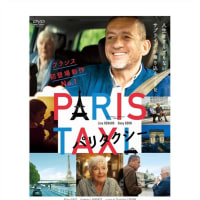





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます