
【神秘の子羊(ヘントの祭壇画)】ヤン・ファン・エイク
>>こうして、彼らは、神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真中に安置した。それから、彼らは神の前に、全焼のいけにえと和解のいけにえをささげた。
ダビデは、全焼のいけにえと和解のいけにえをささげ終えてから、主の名によって民を祝福した。
主に感謝せよ。
主はまことにいつくしみ深い。
その恵みはとこしえまで。
言え。
「私たちの救いの神よ。
私たちをお救いください。
国々から私たちを集め、
私たちを救い出してください。
あなたの聖なる御名に感謝し、
あなたの誉れを誇るために」
ほむべきかな。イスラエルの神、主。
とこしえから、とこしえまで。
それから、すべての民はアーメンと言い、主をほめたたえた。
(歴代誌第一、第16章1~36節)
この間、歴代誌第一の第16章あたりを読んでいると、聖書の欄外の解説のところに、
・全焼のいけにえ=神になだめの香りをささげるため、牛または羊の全部を焼くささげ物。献身のしるし。
・和解のいけにえ=犠牲の動物の一部を祭壇で焼き、一部は祭司に、一部は供えた者に分け与えられた。感謝のしるし。
とあって、「ああ、本当にそうだなあ 」と思わされました。
」と思わされました。
なんというか、イエスさまが神の子としてこの世に来てくださったことにより、イエスさま御自身が旧約聖書の預言のとおり、十字架上でこの父なる神への「生贄」、究極の犠牲を払ってくださったことにより……その御父に捧げられた「なだめの供え物」、贖罪によって、イエスさまを神の子と信じる者には罪の赦しと永遠のいのちが与えられるということになりました。
牛や羊などを神さまに「焼いて捧げる」といった行為というのは、一般的には「大昔の人の、神さまに対する儀式的行為」といったイメージが強いわけですが、このあたり、旧約聖書から新約聖書へとどんなふうに思想が続いていくのか――がわかると、クリスチャンとしては「主こそ神です、主こそ神です! 」と畏れ尊ぶ気持ちがますます深まり、そのあたりの深さが信者以外には秘蹟のひとつとして隠されていることに対しても、恐れの気持ちがますます強まるような気がします。。。
」と畏れ尊ぶ気持ちがますます深まり、そのあたりの深さが信者以外には秘蹟のひとつとして隠されていることに対しても、恐れの気持ちがますます強まるような気がします。。。
>>雄牛とやぎの血は、罪を除くことができません。
ですから、キリストは、この世界に来て、こう言われるのです。
「あなたは、いけにえやささげ物を望まないで、わたしのために、からだを造ってくださいました。
あなたは全焼のいけにえと罪のためのいけにえとで満足されませんでした。
そこでわたしは言いました。
『さあ、わたしは来ました。
聖書のある巻に、わたしについてしるされているとおり、
神よ、あなたのみこころを行うために』」
すなわち、初めには、「あなたは、いけにえとささげ物、全焼のいけにえと罪のためのいけにえ(すなわち、律法に従ってささげられる、いろいろの物)を望まず、またそれらで満足されませんでした」と言い、また、「さあ、わたしはあなたのみこころを行なうために来ました」と言われたのです。後者が立てられるために、前者が廃止されるのです。
このみこころに従って、イエス・キリストのからだが、ただ一度だけささげられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。
また、すべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じいけにえをくり返しささげますが、それらは決して罪を除き去ることができません。
しかし、キリストは、罪のために一つの永遠のいけにえをささげて後、神の右の座に着き、それからは、その敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。
キリストは聖なるものとされる人々を、一つのささげ物によって、永遠にまっとうされたのです。
聖霊も私たちに次のように言って、あかしされます。
「それらの日の後、わたしが、彼らと結ぼうとしている契約は、これであると、主は言われる。
わたしは、わたしの律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける」
またこう言われます。
「わたしは、もはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない」
これらのことが赦されるところでは、罪のためのささげ物はもはや無用です。
(へブル書、第10章4~18節)
もちろん、イエスさまが十字架上で御自身を完全に御父に捧げられたように、そうした完全な献身行為についても大切と感じつつ、そこまで信仰的に完全燃焼まで出来ない弱い身としては――「和解のいけにえ」、感謝して分けあう、ということに、何故かより強い語りかけを感じた気がしました。
♰和解=神に対して罪を犯し反抗している人間が、キリストの十字架の死によって罪を赦され、神との交わりの関係を回復すること。これによって神との平和が与えられ、神の怒りと、罪に対する刑罰は取り除かれ、義と認められる。神が和解の主体であって、人間の側から神に和解を求めることはできない。
もしわたしがキリスト教徒じゃなかったとすれば、ここの「和解」という言葉の意味について読んでも「??? 」といったところであり、むしろ、「神が和解の主体であって、人間の側から神に和解を求めることはできない」というところを読んで、「やっぱりキリスト教の神っておかしーんじゃない?
」といったところであり、むしろ、「神が和解の主体であって、人間の側から神に和解を求めることはできない」というところを読んで、「やっぱりキリスト教の神っておかしーんじゃない? 」と思ったりしたんじゃないかという気がします。
」と思ったりしたんじゃないかという気がします。
でも、わたしたち人間の側から御父に直接何かを申し上げる清さのようなものは何もないのですが、御父との間にイエスさまが仲保者として入ってくださることにより……神さまと人間の間に「和解」が成立するという、このことがとても大切なことなわけです。
>>キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しいひとりの人に造り上げて、平和を実現するためであり、また、両者を一つのからだとして、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。
それからキリストは来られて、遠くにいたあなたがたに平和を宣べ、近くにいた人たちにも、平和を宣べられました。
私たちは、このキリストによって、両者ともに一つの御霊において、父のみもとに近づくことができるのです。
(エペソ人への手紙、第2章14~18節)
イエスさまがわたしたち人間と父なる神さまとの間で「とりなし」をしてくださり、さらにイエスさまが送ってくださった聖霊さまにより、この聖霊はわたしたちとイエスさまとの間のとりなしをしてくださる方であります。
>>御霊(聖霊)も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、どのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、私たちのためにとりなしてくださいます。
人間の心を探り窮める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は、神のみこころに従って、聖徒のためにとりなしをしてくださるからです。
(ローマ書、第8章26~27節)
世の中で戦争や争いが絶えない昨今、ニュースを聞いたりする時にこの「和解」ということが何度となく心を掠めることがありました。世界中の多くの人々が「なんとか和解できないものか」という願いを持っていると思うのですが、個人的に思うに、キリスト教でいう「和解」というのは、もっと深いものだと思うんですよね。
つまり、国同士だけでなく、人対人の小さなグループ同士であれ、人間的に「わかりあうことは不可能」というくらいの対立がある時……解決するということはほとんどありえないとしか思えない。何故といって、イエスさまの語っている「和解」というのは、唯一「互いに譲りあいの精神を持つ時だけ」成立するものでしょうし、片方が譲った分より多く分捕ろうというのでは、絶対に和平というのは成立しないものだからです。
ただ、国同士の大きなことについては祈ることしか出来ないかもしれませんが、せめても身近なところで「和解」の精神を少しでも持てるよう意識して努力すること、それですらも自分には難しいなあと感じる時、やっぱりマーリン・キャロザース先生の「いいことも悪いことも神さまに感謝し賛美する」精神というのは一番強いなあと思わされるものであります
それではまた~!!

















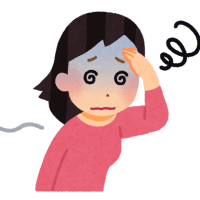
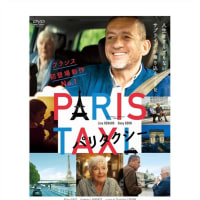





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます