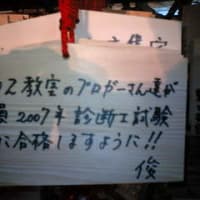なぜか目が冴えてしまったので続きを書きました。
2次試験の勉強方法です。
何でもそうだと思うのですが、何のためにやるのかという目的が大事だと思います。診断士の勉強もそうだと思います。
一度、なぜその勉強をやるのかは振り返って考えた方がいいと思います。
例えば、
過去問を何度も繰り返し解く
過去問の与件文を写経する
などなど。
過去問や演習は、何度も繰り返しやるうちに、解答の方向性は覚えてしまったり、与件文の根拠も分かってしまいます。
それでも、何度もやる意味(意義)は何だろう?
例えば、過去問の特徴を整理する、解答する際の深さを確認する、過去に問われた切り口を整理する、解答でよく使われるキーワードをまとめる、などなど、目的は色々あると思います。
その目的をしっかり明確にして、勉強するべきと思います。
で、その勉強の成果をしっかり確認していくことです。
最終的には、自分の解答プロセスを固め、判断基準(知識や切り口など)を充実させるために、勉強しているわけですので、予備校の演習などで、それが定着できたかを、都度確認するべきです。
演習などで間違えたところは、なぜ間違えたのかを深堀りして(なぜ、なぜ、なぜと繰り返し問うて、真因を掴んで)、それを解答プロセスに盛り込んだり、判断基準の強化を図ったりして、そして次の演習で試す。
PDCAサイクルをしっかり回すことが、大切なのだろうと思います。
次からは、全体を通して振り返ってみます。
2次試験の勉強方法です。
何でもそうだと思うのですが、何のためにやるのかという目的が大事だと思います。診断士の勉強もそうだと思います。
一度、なぜその勉強をやるのかは振り返って考えた方がいいと思います。
例えば、
過去問を何度も繰り返し解く
過去問の与件文を写経する
などなど。
過去問や演習は、何度も繰り返しやるうちに、解答の方向性は覚えてしまったり、与件文の根拠も分かってしまいます。
それでも、何度もやる意味(意義)は何だろう?
例えば、過去問の特徴を整理する、解答する際の深さを確認する、過去に問われた切り口を整理する、解答でよく使われるキーワードをまとめる、などなど、目的は色々あると思います。
その目的をしっかり明確にして、勉強するべきと思います。
で、その勉強の成果をしっかり確認していくことです。
最終的には、自分の解答プロセスを固め、判断基準(知識や切り口など)を充実させるために、勉強しているわけですので、予備校の演習などで、それが定着できたかを、都度確認するべきです。
演習などで間違えたところは、なぜ間違えたのかを深堀りして(なぜ、なぜ、なぜと繰り返し問うて、真因を掴んで)、それを解答プロセスに盛り込んだり、判断基準の強化を図ったりして、そして次の演習で試す。
PDCAサイクルをしっかり回すことが、大切なのだろうと思います。
次からは、全体を通して振り返ってみます。