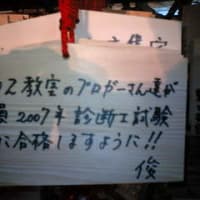2次に最初に取り組んだのは、1次に合格した年(H18)の1次終了後、翌日からでした。
1次終了後に参加した502の飲み会で、予備校の先生から翌週の授業までに、過去問を全て解いてくることと言われて始めて取り組みました。もちろん1週間では解けるはずもなく、その年の盆休み1週間は図書館に閉じこもり、毎日事例を朝から晩まで解いている状態でした。
結論から言えば、遅すぎました。
今、思えば、早い段階で2次の問題に触れて、どういう内容、どういうレベルを聞かれるかを知っておく必要がありました。企業経営理論を終わった時に、事例Ⅰと事例Ⅱをせめて1事例ほど解いてみて、どういうレベルのものか、どういう知識が必要とされているかを感覚的にでも掴んでおいた方がいいと思います。
一昨年、結局約2ヶ月半で本試を迎えましたが、あと半月あればという感触でした。もちろん、2ヶ月半は毎日平日でも3~4時間勉強していましたから、勉強時間が足りないという事はないのですが。
結果は、AAAC-B。
2次では、1次の知識をそのまま使うのではないと、よく言われますが、僕は少し違うかな、と思います。
例えば、生産で、ロット生産って何?だけでなく、ロット生産が必要とされる背景(外部要因)や、ロット生産をせざるをえない中で必要となる対応(例えば段取り改善)などの関連を把握しておく必要があります。 1次はどちらかと言えば、抽象論や概要を学ぶと思うのですが、2次では、それを実際の企業でどういう形で現れるかを結びつける力が必要になるのかなと思うのです
その訓練をするのには、早い段階から(1次を勉強している段階から)意識的にやるのが効果的なのではと思います。
で、次は2次で大事だと思ったことを書いてみようと思います
1次終了後に参加した502の飲み会で、予備校の先生から翌週の授業までに、過去問を全て解いてくることと言われて始めて取り組みました。もちろん1週間では解けるはずもなく、その年の盆休み1週間は図書館に閉じこもり、毎日事例を朝から晩まで解いている状態でした。
結論から言えば、遅すぎました。
今、思えば、早い段階で2次の問題に触れて、どういう内容、どういうレベルを聞かれるかを知っておく必要がありました。企業経営理論を終わった時に、事例Ⅰと事例Ⅱをせめて1事例ほど解いてみて、どういうレベルのものか、どういう知識が必要とされているかを感覚的にでも掴んでおいた方がいいと思います。
一昨年、結局約2ヶ月半で本試を迎えましたが、あと半月あればという感触でした。もちろん、2ヶ月半は毎日平日でも3~4時間勉強していましたから、勉強時間が足りないという事はないのですが。
結果は、AAAC-B。
2次では、1次の知識をそのまま使うのではないと、よく言われますが、僕は少し違うかな、と思います。
例えば、生産で、ロット生産って何?だけでなく、ロット生産が必要とされる背景(外部要因)や、ロット生産をせざるをえない中で必要となる対応(例えば段取り改善)などの関連を把握しておく必要があります。 1次はどちらかと言えば、抽象論や概要を学ぶと思うのですが、2次では、それを実際の企業でどういう形で現れるかを結びつける力が必要になるのかなと思うのです
その訓練をするのには、早い段階から(1次を勉強している段階から)意識的にやるのが効果的なのではと思います。
で、次は2次で大事だと思ったことを書いてみようと思います