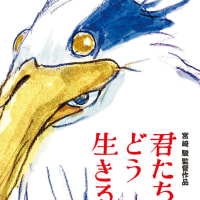結婚式のあと、ウィンザー公爵家の若夫妻となったリチャードとシャーロットは、しばらく領地で過ごしてから王都のタウンハウスに戻った。この地で、この家で、これから二人の新たな日常が始まるのだ——。
「数日したら非番だから、そのときは二人で街に遊びに行こう」
結婚休暇を終え、久しぶりに騎士団の仕事に出かけようというところで、リチャードは見送りのシャーロットにそう言った。唐突だったせいか、彼女はすこし驚いたように目をぱちくりとさせる。
「お仕事のほうはよろしいのですか?」
「ああ……」
タウンハウスに戻ってからの三日間は、不在時にたまった書類などを処理するのに必死で、とても遊びに行くどころではなかった。だが、もうあらかた片付いたので一日くらいなら問題ない。
「急ぎの面倒な案件さえ来なければな」
「ふふっ、では祈っておきますね」
シャーロットの顔にふわりと笑みが浮かぶ。
クッ——あまりの愛らしさにリチャードは心を射抜かれた。もう騎士団になんか行きたくない。いますぐ一緒に街で遊びたい。もしくは部屋にこもって戯れたい。けれど、そうはいかないことくらいわかっている。
「……行ってくる」
「行ってらっしゃいませ」
にっこりとするシャーロットにつられるように微笑み返し、そのままじっと見つめていると、彼女の後ろに控えていた執事がわざとらしく咳払いした。
「わかってるよ」
リチャードは彼女の頬に口づけ、ひどく名残惜しく思いながらも家をあとにした。
約束の日、王都の空は穏やかに晴れわたっていた。
幸いにも急ぎの仕事が来なかったため、何の問題もなく予定どおりシャーロットと街に出かけることになった。よほどのことがなければ行くつもりでいたこともあり、事前準備は万端である。
まずは馬車で劇場に向かう。シャーロットは結婚前にカーディフの街で見た大衆演劇を気に入っていたが、今日は古典的な歌劇だ。娯楽というより芸術としての側面が強いためにいささかとっつきにくい。
「歌劇も見てみたいと思っていたんです」
「あー……君の好みに合うかはわからないぞ?」
「それを知ることも楽しみです」
屈託なく答えるシャーロットはとても眩しかった。
深いブルーグリーンを基調とした大人びたドレスを着ているのに、時に子供のように無邪気になる。そんな彼女が愛おしくて、このときは何の憂いもなくただ心をはずませていたのだが——。
「で、そちらが噂の奥方ですかな?」
「ええ……妻のシャーロットです」
「はじめまして」
シャーロットが軽く膝を曲げて挨拶すると、声をかけてきたレディング侯爵の顔がほころぶ。ただしまなざしだけは鋭く隙のないままで。
「これはかわいらしい。グレイ伯爵が過剰なくらいに大事にしていたのも頷けますな。あまり蔑ろにしては彼の不興を買ってしまいますぞ」
「ご心配には及びません」
苛立ちを隠し、笑みさえ浮かべながらリチャードはさらりとそう返した。
「開演時間ギリギリに来るべきだったな」
予約した席に座るなり、リチャードはぐったりとして溜息まじりにぼやく。
浮かれて早く来たのが間違いだった。劇場に着くなり、たいしてというかまったく親しくない貴族たちが次々に声をかけてくるのだ。ここが社交の場のひとつであることをすっかり失念していた。
めったに姿を見せない公爵家の嫡男が現れれば、そうもなるだろう。
ただ、今回はリチャードというより妻が目当てだったのかもしれない。ずっと領地にいて社交デビューもしていない彼女にみんな興味があったようで、値踏みするように不躾に観察していた。
「すまなかった、こんなことになるなんて思ってなくて」
「いえ、これも妻の役目だと心得ています」
隣のシャーロットはにっこりとしてそう応じるが、ふと思い出したように真面目な顔になると、口元に手を添えてささやく。
「それより……やはりみなさん例の誤解をしているようですけど、きちんと訂正しておかなくてよろしかったのですか?」
「あー……」
例の誤解というのは、リチャードがアーサーに懸想しているということだ。
少なくないひとが挨拶を交わしながら暗に揶揄していた。アーサーの身代わりとして娘を娶ったと信じているのだろう。自分はともかく、シャーロットにまで好奇の目を向けられるのは腹立たしい。
しかしながら訂正するのも簡単ではない。いまになって急に事実無根と訴えたところで信じてもらえない可能性が高い。何かしら不都合があって火消しをしていると思われるのが関の山である。
「いずれ何か上手い方法を考えるよ。君には嫌な思いをさせてしまうかもしれないが、もうしばらく我慢してもらえるとありがたい」
「わたしは気にしていませんので」
本当に気にしていないかのようにさらりと答える。
可憐な見目にもかかわらず意外と肝が据わっているのだ。だからといって何も感じないわけではないだろう。申し訳なく思いつつも、いまはただ素直に感謝して微笑み返すしかなかった。
公演が始まると、シャーロットは舞台に釘付けになった。
今回は舞台正面のロイヤルボックスなのでとても見やすいし、音響も悪くない。そしてまわりを囲われているので視線を気にせず落ち着ける。彼女にもきっと満足してもらえているのではないかと思う。
歌劇はとある国の王子が東国の姫に一目惚れして求婚する話である。姫と結婚するために提示された三つの難題を解き、命を懸けて試練に立ち向かい、最後には頑なだった姫の心をとかして結ばれるのだ。
まだ若いころ——シャーロットと出会うまえだが、リチャードは教養の一環としてこの歌劇を観たことがあった。当時はそこまでして姫を求める王子を愚かしいと思ったが、いまはその気持ちがわかる。
俺だって——。
ちらりとシャーロットの横顔を窺う。
直接的に命を懸けたわけではないが、彼女を得るために騎士団長になろうと危険も厭わず仕事をしてきた。十年が過ぎても彼女を得たいという気持ちは薄れなかった。理屈ではないのだ。
そして、それは間違いではなかったと確信している。
「楽しめたか?」
幕が下りたあと、まだ余韻にひたっているシャーロットに声をかけると、彼女はハッと我にかえったように振り向いて大きく頷く。
「すごかったです。歌が……人間にこんな力強く豊かな声が出せるなんて……体や心の奥底にまで響いてきて感情を揺さぶられました。カーディフの街で見た演劇も面白かったのですけど、こちらには本当に圧倒されて……」
ほんのりと頬を火照らせながら興奮ぎみに声をはずませ、目もかがやかせ、心からそう思っているのだということが伝わってくる。これほど感動してもらえるのなら連れてきた甲斐があった。
「気に入ったのならまた一緒に来よう。今度は他の演目で」
「はい!」
シャーロットが元気よく満面の笑みで応じる。そんな彼女をたまらなく愛おしく思いながら、リチャードは甘く微笑み返した。
「あっ……このあたり、何となくですけど覚えています」
劇場を出て、次の目的地のほうに足を進めていたところ、シャーロットがふいにそう声を上げた。ゆるやかな下りの坂道を指差しながら言葉を継ぐ。
「確か、こちらを行くと青空市場がありましたよね?」
十年前、王都で暮らしていたときのことを言っているのだろう。例の誘拐事件のせいで一、二週間ほどしかいなかったが、市場が気に入っていたようだとアーサーから聞いたことがある。
「行ってみるか?」
「えっ、でもこのあと予定があるのではないですか?」
「すこしくらい寄り道しても構わないよ」
そう言うと、まだ迷っている彼女の手をとって横道へ足を向ける。彼女は一瞬だけ驚いたように目を見開いたものの、すぐに笑顔になり、ストロベリーブロンドの髪をなびかせながら隣に並んだ。
「わたしたち、もしかしてだいぶ浮いてません?」
青空市場につくと、シャーロットはちらちらと周囲に視線を走らせて、隣のリチャードにだけ聞こえる声でそうささやいた。場所柄、盛装をした自分たちが浮いているのは確かだが——リチャードはふっと微笑む。
「何も悪いことはしてないんだから堂々としてればいい。まあ興味本位のまなざしは向けられるだろうが、これくらいで眉をひそめるようなひとはいないよ」
「わかりました」
シャーロットは気を取りなおしたようにそう答えてニッコリとした。もう他人からどう思われるかは構わないことにしたのだろう。歩きながら目をかがやかせてあちらこちらの露店を眺める。
「雰囲気は十年前とそんなに変わってないだろう?」
「はい……こんなふうに果物や野菜が山盛りになっているのを見るのが好きで、よく買い出しについていってました。みなさん優しくて、幼いわたしにもよくしてくださったことを覚えています」
懐かしむようにシャーロットの顔がやわらぐ。
それだけでここに寄り道してよかったと思えた。ひときわ目をひく果物の山のまえで足を止め、せっかくなので何か買っていこうかと考えていると。
「誰かと思ったらリチャードじゃないか!」
驚いたようにそう言われて顔を上げる。
そこにいた店員は、以前、ちょっとした事件で顔見知りになった女性だった。数年前まで騎士団員として街を見回っていたこともあり、住人たちとはけっこう面識があるのだ。
「お久しぶりです」
「随分とめかし込んでるねぇ」
「観劇の帰りなんですよ」
そんな立ち話をしていたところ、女性店員が一歩後ろにいるシャーロットに気付いたようだ。目が合ったらしくシャーロットが会釈する。いい機会なので彼女を紹介しておこうかと思ったそのとき。
「その子、まさかあんたの?」
女性店員がこっそりと小指を立てながら声をひそめた。
確か、小指を立てるしぐさは親密な女性を意味していたはずだ。彼女の態度をいささか怪訝に思いつつも「そうですが」と返事をする。すると彼女はひどく非難がましいまなざしになり溜息をついた。
「成熟した女に興味が持てないのかもしれないけどね、子供に手を出すのはやめな。いい大人なんだから無責任なことはするんじゃないよ」
「いや、ちょっと待ってください!」
そこまで言われて、ようやくあらぬ誤解をされていることに気がついた。あわてて一歩後ろにいたシャーロットを抱き寄せると、真面目な顔で言う。
「こちらは妻のシャーロットです」
「……つま……妻ぁ?!」
目を丸くした女性店員がすっとんきょうな声を上げた。そのせいで一気にまわりの注目を浴びてしまうが、リチャードはいっさい動じることなく言葉を継ぐ。
「もう十六歳なので子供ではありませんよ」
「それは、勘違いして悪かったね」
彼女は素直に謝罪の言葉を述べたものの、再び溜息をつく。
「だけど十六ってのもね……あんたからすりゃ十六なんて子供みたいなものだろう。まあ成人ではあるし、合法的に結婚したのならとやかくは言えないんだけどさ。金や権力にものを言わせて強引に娶ったんじゃないのかい?」
「ご想像におまかせします」
言っていることがそこそこ当たっているだけに耳が痛い。だからといっていまさら懊悩も後悔もしない。さらりと笑顔でかわしてその場を離れようとしたが。
「あの……」
それまで黙っていたシャーロットが遠慮がちに口を開いた。
一斉に周囲の人たちが振り向き、その視線に彼女はすこし気圧されていたようだが、すぐに仕切りなおして女性店員のほうに目を向ける。
「わたしはリチャード様を心よりお慕いしております。確かに世間一般の夫婦より年齢差はあるのかもしれませんが、こうして夫婦になれてよかったと思っていますし、とても幸せです」
そう告げると、ふわりと花が咲くように微笑んだ。
瞬間、わぁっと大きな歓声や拍手がまわりから沸き起こる。女性店員もあははと豪快に笑っていた。そして思い立ったようにオレンジをいくつか紙袋に入れると、シャーロットに押しつける。
「わたしからの結婚祝いだよ、持っていきな!」
「わあっ、ありがとうございます」
シャーロットがはしゃいだ声を上げた。
「うちからもどうぞ」
「これも持っていって」
「わたしも」
別のところの店員や居合わせた客などが、こぞってシャーロットの抱える紙袋にさまざまな果物を入れていく。やがて彼女ひとりでは抱えきれないほど山盛りになり、リチャードが代わりに持った。
「つらいことがあったらいつでも逃げておいで。守ってあげるからね!」
件の女性店員がドンと胸を叩くと、シャーロットはくすくすと笑いながら頷いた。
リチャードは苦笑するが、彼女が受け入れられたことについては喜ばしく思う。いざというときのために頼れるひとはいたほうがいい。もちろんそんなことがないよう心がけるつもりだけれど。
「二人ともまたいつでも顔を出しておくれ」
「はい、ありがとうございました」
居合わせたひとたちにもあらためて二人で礼を述べて、その場をあとにした。あかるく賑やかな見送りの声を背後に聞きながら——。
次の目的地は喫茶店である。
寄り道をしたため予約時間から少し遅れての到着となった。めったに満席にならないので本来なら予約の必要もないのだが、シャーロットのために最良の席を用意したくて、確保を頼んでおいたのだ。
「落ち着いた素敵なところですね」
案内されて席につくと、彼女はあたりを見まわしながら感嘆の声を上げた。
調度品や内装はどれも上質で、暖色の灯りとあいまって統一感のある優美な空間を作り出している。そのうえ奥まった席なので他の客の目を気にしなくていい。彼女も喜んでくれたようで一安心である。
「アーサーが王都にいるときはよく一緒に来てたんだ。あいつ、ここの茶葉をよく里帰りのおみやげにしてたみたいだから、君も飲んだことあるかもな」
「おみやげの紅茶はいつも楽しみにしていました。この店のだったんですね」
シャーロットはそう言って微笑む。
ここは基本的に喫茶のみだが、紅茶好きのアーサーはいつのまにかオーナーと懇意になり、おみやげにしたいからと稀少な茶葉も分けてもらっていたのだ。もちろん相応の代金を払って。
「失礼いたします」
会話が途切れたタイミングで声がかかる。
振り向くとオーナーがいた。リチャードよりも幾分か年上と思われる物腰のやわらかい男性で、いつもと同じく執事のような衣装を身にまとっている。彼はすっと進み出ると恭しく一礼した。
「リチャード様、シャーロット様、このたびはご結婚おめでとうございます」
そう述べて、後ろに控えていた店員から手提げ袋を受け取り、ソファに座っているリチャードのほうへそれを差し出す。
「心ばかりですが、よろしければお祝いとしてお納めください」
「ああ、ありがとう……喜んでいただくよ」
思いもよらないことにリチャードはすこし驚きつつも、にこやかに受け取った。
チラリと中を確認したところ茶葉とジャムのようだ。向かいでそわそわしているシャーロットもきっと喜んでくれるだろう。茶葉は言わずもがな、ジャムも果実感が強くてなかなか美味なのだ。
「わたしが結婚したことはどちらで?」
「先日、グレイ伯爵から伺いました」
「ああ……」
そういえばアーサーは結婚式のあとで王都に寄ると言っていた。そのときだろう。いったいどこまで話したのかは気になるところだが——ポーカーフェイスの得意なオーナーからは窺い知ることができなかった。
「今日は行く先々で声をかけられたな」
オーナーが下がると、リチャードはメニューを開きながら思わずそうぼやいた。
何せこれがふたりの初めての正式なデートなのだ。できるなら誰にも邪魔されることなく一日を過ごしたかった。ふたりだけの世界にひたっていたかった。それが偽らざる正直な気持ちである。
「わたしは祝っていただけてうれしかったです」
「まあ、それならよかったけど……」
確かにシャーロットは青空市場での祝福に無邪気な笑顔を見せていたし、喫茶店のオーナーからもらった結婚祝いにも興味を示していた。ただ——。
「さすがに貴族連中にはうんざりしただろう」
「そうですね……お祝いの言葉にも何か含みのある方が多そうでしたから。でも、みなさんからリチャードや父の話を聞けたことはうれしかったです」
あのときは嫌な顔ひとつ見せることなく応対していたものの、やはり思うところはあったのだ。しかし後半のうれしかったという件についてはよくわからず、小首を傾げながら腕を組む。
「話なんてどれもたいしたものじゃなかったと思うが」
「おふたりがとっても仲良しだってことはわかりました」
「……あくまで友人としてだからな?」
「もちろん承知しています」
そう応じてシャーロットはくすくすと笑い出した。
どうやら例の男色疑惑が再燃したわけではないらしい。ほっと安堵しつつ、いまだに面白がっている彼女に恨めしげな視線を向ける。だが、目が合うと思わずというかつられるように苦笑してしまった。
「そろそろ注文を決めようか。喉も渇いたし」
「はい」
ようやくシャーロットも自分のメニューに手を伸ばした。わくわくとした様子だったのに、中を見るなり驚いたように大きく目をぱちくりとさせる。
「紅茶だけでこんなにたくさん種類があるんですね」
「オーナーが好きでな。紅茶にはこだわりがあるらしい」
「父がこの喫茶店に来ていた理由がよくわかりました」
「だろ?」
その言葉に彼女はくすりと笑った。
「ですがわたしは父と違って詳しくありませんし、どう選んだらいいのか……」
メニューには品種と産地とフレーバーが記されているのだが、知識がなければわからないだろう。リチャードも昔はわからなかった。だがここで紅茶を楽しむうちにわかるようになってきたのだ。
「どういうものが好きだとか嫌いだとかあるか?」
「そうですね……スパイシーなものはすこし苦手です」
「ああ、あれは好みが分かれるよな」
軽く笑いながら手元のメニューに目を落とす。
アーサーの影響で彼女もいろいろな紅茶を飲んでいるようだが、すべて自宅だろう。それならばこの店で飲むからこその価値があるものを勧めたい。たとえばオーナーが丹念に淹れるからこそ格段においしくなるもの、淹れるのに一手間がかかり自宅ではなかなか難しいもの、もしくは——。
「これなんかどうだ?」
ふと口元を上げ、手を伸ばして彼女のメニューのひとつを指さす。
それはシャーロットだから勧める意味があるもの——この店に初めてアーサーを連れてきたときに勧めた、そして彼がたいそう気に入って絶賛したあの紅茶、ベルガモットのフレーバードティーだった。
「数日したら非番だから、そのときは二人で街に遊びに行こう」
結婚休暇を終え、久しぶりに騎士団の仕事に出かけようというところで、リチャードは見送りのシャーロットにそう言った。唐突だったせいか、彼女はすこし驚いたように目をぱちくりとさせる。
「お仕事のほうはよろしいのですか?」
「ああ……」
タウンハウスに戻ってからの三日間は、不在時にたまった書類などを処理するのに必死で、とても遊びに行くどころではなかった。だが、もうあらかた片付いたので一日くらいなら問題ない。
「急ぎの面倒な案件さえ来なければな」
「ふふっ、では祈っておきますね」
シャーロットの顔にふわりと笑みが浮かぶ。
クッ——あまりの愛らしさにリチャードは心を射抜かれた。もう騎士団になんか行きたくない。いますぐ一緒に街で遊びたい。もしくは部屋にこもって戯れたい。けれど、そうはいかないことくらいわかっている。
「……行ってくる」
「行ってらっしゃいませ」
にっこりとするシャーロットにつられるように微笑み返し、そのままじっと見つめていると、彼女の後ろに控えていた執事がわざとらしく咳払いした。
「わかってるよ」
リチャードは彼女の頬に口づけ、ひどく名残惜しく思いながらも家をあとにした。
約束の日、王都の空は穏やかに晴れわたっていた。
幸いにも急ぎの仕事が来なかったため、何の問題もなく予定どおりシャーロットと街に出かけることになった。よほどのことがなければ行くつもりでいたこともあり、事前準備は万端である。
まずは馬車で劇場に向かう。シャーロットは結婚前にカーディフの街で見た大衆演劇を気に入っていたが、今日は古典的な歌劇だ。娯楽というより芸術としての側面が強いためにいささかとっつきにくい。
「歌劇も見てみたいと思っていたんです」
「あー……君の好みに合うかはわからないぞ?」
「それを知ることも楽しみです」
屈託なく答えるシャーロットはとても眩しかった。
深いブルーグリーンを基調とした大人びたドレスを着ているのに、時に子供のように無邪気になる。そんな彼女が愛おしくて、このときは何の憂いもなくただ心をはずませていたのだが——。
「で、そちらが噂の奥方ですかな?」
「ええ……妻のシャーロットです」
「はじめまして」
シャーロットが軽く膝を曲げて挨拶すると、声をかけてきたレディング侯爵の顔がほころぶ。ただしまなざしだけは鋭く隙のないままで。
「これはかわいらしい。グレイ伯爵が過剰なくらいに大事にしていたのも頷けますな。あまり蔑ろにしては彼の不興を買ってしまいますぞ」
「ご心配には及びません」
苛立ちを隠し、笑みさえ浮かべながらリチャードはさらりとそう返した。
「開演時間ギリギリに来るべきだったな」
予約した席に座るなり、リチャードはぐったりとして溜息まじりにぼやく。
浮かれて早く来たのが間違いだった。劇場に着くなり、たいしてというかまったく親しくない貴族たちが次々に声をかけてくるのだ。ここが社交の場のひとつであることをすっかり失念していた。
めったに姿を見せない公爵家の嫡男が現れれば、そうもなるだろう。
ただ、今回はリチャードというより妻が目当てだったのかもしれない。ずっと領地にいて社交デビューもしていない彼女にみんな興味があったようで、値踏みするように不躾に観察していた。
「すまなかった、こんなことになるなんて思ってなくて」
「いえ、これも妻の役目だと心得ています」
隣のシャーロットはにっこりとしてそう応じるが、ふと思い出したように真面目な顔になると、口元に手を添えてささやく。
「それより……やはりみなさん例の誤解をしているようですけど、きちんと訂正しておかなくてよろしかったのですか?」
「あー……」
例の誤解というのは、リチャードがアーサーに懸想しているということだ。
少なくないひとが挨拶を交わしながら暗に揶揄していた。アーサーの身代わりとして娘を娶ったと信じているのだろう。自分はともかく、シャーロットにまで好奇の目を向けられるのは腹立たしい。
しかしながら訂正するのも簡単ではない。いまになって急に事実無根と訴えたところで信じてもらえない可能性が高い。何かしら不都合があって火消しをしていると思われるのが関の山である。
「いずれ何か上手い方法を考えるよ。君には嫌な思いをさせてしまうかもしれないが、もうしばらく我慢してもらえるとありがたい」
「わたしは気にしていませんので」
本当に気にしていないかのようにさらりと答える。
可憐な見目にもかかわらず意外と肝が据わっているのだ。だからといって何も感じないわけではないだろう。申し訳なく思いつつも、いまはただ素直に感謝して微笑み返すしかなかった。
公演が始まると、シャーロットは舞台に釘付けになった。
今回は舞台正面のロイヤルボックスなのでとても見やすいし、音響も悪くない。そしてまわりを囲われているので視線を気にせず落ち着ける。彼女にもきっと満足してもらえているのではないかと思う。
歌劇はとある国の王子が東国の姫に一目惚れして求婚する話である。姫と結婚するために提示された三つの難題を解き、命を懸けて試練に立ち向かい、最後には頑なだった姫の心をとかして結ばれるのだ。
まだ若いころ——シャーロットと出会うまえだが、リチャードは教養の一環としてこの歌劇を観たことがあった。当時はそこまでして姫を求める王子を愚かしいと思ったが、いまはその気持ちがわかる。
俺だって——。
ちらりとシャーロットの横顔を窺う。
直接的に命を懸けたわけではないが、彼女を得るために騎士団長になろうと危険も厭わず仕事をしてきた。十年が過ぎても彼女を得たいという気持ちは薄れなかった。理屈ではないのだ。
そして、それは間違いではなかったと確信している。
「楽しめたか?」
幕が下りたあと、まだ余韻にひたっているシャーロットに声をかけると、彼女はハッと我にかえったように振り向いて大きく頷く。
「すごかったです。歌が……人間にこんな力強く豊かな声が出せるなんて……体や心の奥底にまで響いてきて感情を揺さぶられました。カーディフの街で見た演劇も面白かったのですけど、こちらには本当に圧倒されて……」
ほんのりと頬を火照らせながら興奮ぎみに声をはずませ、目もかがやかせ、心からそう思っているのだということが伝わってくる。これほど感動してもらえるのなら連れてきた甲斐があった。
「気に入ったのならまた一緒に来よう。今度は他の演目で」
「はい!」
シャーロットが元気よく満面の笑みで応じる。そんな彼女をたまらなく愛おしく思いながら、リチャードは甘く微笑み返した。
「あっ……このあたり、何となくですけど覚えています」
劇場を出て、次の目的地のほうに足を進めていたところ、シャーロットがふいにそう声を上げた。ゆるやかな下りの坂道を指差しながら言葉を継ぐ。
「確か、こちらを行くと青空市場がありましたよね?」
十年前、王都で暮らしていたときのことを言っているのだろう。例の誘拐事件のせいで一、二週間ほどしかいなかったが、市場が気に入っていたようだとアーサーから聞いたことがある。
「行ってみるか?」
「えっ、でもこのあと予定があるのではないですか?」
「すこしくらい寄り道しても構わないよ」
そう言うと、まだ迷っている彼女の手をとって横道へ足を向ける。彼女は一瞬だけ驚いたように目を見開いたものの、すぐに笑顔になり、ストロベリーブロンドの髪をなびかせながら隣に並んだ。
「わたしたち、もしかしてだいぶ浮いてません?」
青空市場につくと、シャーロットはちらちらと周囲に視線を走らせて、隣のリチャードにだけ聞こえる声でそうささやいた。場所柄、盛装をした自分たちが浮いているのは確かだが——リチャードはふっと微笑む。
「何も悪いことはしてないんだから堂々としてればいい。まあ興味本位のまなざしは向けられるだろうが、これくらいで眉をひそめるようなひとはいないよ」
「わかりました」
シャーロットは気を取りなおしたようにそう答えてニッコリとした。もう他人からどう思われるかは構わないことにしたのだろう。歩きながら目をかがやかせてあちらこちらの露店を眺める。
「雰囲気は十年前とそんなに変わってないだろう?」
「はい……こんなふうに果物や野菜が山盛りになっているのを見るのが好きで、よく買い出しについていってました。みなさん優しくて、幼いわたしにもよくしてくださったことを覚えています」
懐かしむようにシャーロットの顔がやわらぐ。
それだけでここに寄り道してよかったと思えた。ひときわ目をひく果物の山のまえで足を止め、せっかくなので何か買っていこうかと考えていると。
「誰かと思ったらリチャードじゃないか!」
驚いたようにそう言われて顔を上げる。
そこにいた店員は、以前、ちょっとした事件で顔見知りになった女性だった。数年前まで騎士団員として街を見回っていたこともあり、住人たちとはけっこう面識があるのだ。
「お久しぶりです」
「随分とめかし込んでるねぇ」
「観劇の帰りなんですよ」
そんな立ち話をしていたところ、女性店員が一歩後ろにいるシャーロットに気付いたようだ。目が合ったらしくシャーロットが会釈する。いい機会なので彼女を紹介しておこうかと思ったそのとき。
「その子、まさかあんたの?」
女性店員がこっそりと小指を立てながら声をひそめた。
確か、小指を立てるしぐさは親密な女性を意味していたはずだ。彼女の態度をいささか怪訝に思いつつも「そうですが」と返事をする。すると彼女はひどく非難がましいまなざしになり溜息をついた。
「成熟した女に興味が持てないのかもしれないけどね、子供に手を出すのはやめな。いい大人なんだから無責任なことはするんじゃないよ」
「いや、ちょっと待ってください!」
そこまで言われて、ようやくあらぬ誤解をされていることに気がついた。あわてて一歩後ろにいたシャーロットを抱き寄せると、真面目な顔で言う。
「こちらは妻のシャーロットです」
「……つま……妻ぁ?!」
目を丸くした女性店員がすっとんきょうな声を上げた。そのせいで一気にまわりの注目を浴びてしまうが、リチャードはいっさい動じることなく言葉を継ぐ。
「もう十六歳なので子供ではありませんよ」
「それは、勘違いして悪かったね」
彼女は素直に謝罪の言葉を述べたものの、再び溜息をつく。
「だけど十六ってのもね……あんたからすりゃ十六なんて子供みたいなものだろう。まあ成人ではあるし、合法的に結婚したのならとやかくは言えないんだけどさ。金や権力にものを言わせて強引に娶ったんじゃないのかい?」
「ご想像におまかせします」
言っていることがそこそこ当たっているだけに耳が痛い。だからといっていまさら懊悩も後悔もしない。さらりと笑顔でかわしてその場を離れようとしたが。
「あの……」
それまで黙っていたシャーロットが遠慮がちに口を開いた。
一斉に周囲の人たちが振り向き、その視線に彼女はすこし気圧されていたようだが、すぐに仕切りなおして女性店員のほうに目を向ける。
「わたしはリチャード様を心よりお慕いしております。確かに世間一般の夫婦より年齢差はあるのかもしれませんが、こうして夫婦になれてよかったと思っていますし、とても幸せです」
そう告げると、ふわりと花が咲くように微笑んだ。
瞬間、わぁっと大きな歓声や拍手がまわりから沸き起こる。女性店員もあははと豪快に笑っていた。そして思い立ったようにオレンジをいくつか紙袋に入れると、シャーロットに押しつける。
「わたしからの結婚祝いだよ、持っていきな!」
「わあっ、ありがとうございます」
シャーロットがはしゃいだ声を上げた。
「うちからもどうぞ」
「これも持っていって」
「わたしも」
別のところの店員や居合わせた客などが、こぞってシャーロットの抱える紙袋にさまざまな果物を入れていく。やがて彼女ひとりでは抱えきれないほど山盛りになり、リチャードが代わりに持った。
「つらいことがあったらいつでも逃げておいで。守ってあげるからね!」
件の女性店員がドンと胸を叩くと、シャーロットはくすくすと笑いながら頷いた。
リチャードは苦笑するが、彼女が受け入れられたことについては喜ばしく思う。いざというときのために頼れるひとはいたほうがいい。もちろんそんなことがないよう心がけるつもりだけれど。
「二人ともまたいつでも顔を出しておくれ」
「はい、ありがとうございました」
居合わせたひとたちにもあらためて二人で礼を述べて、その場をあとにした。あかるく賑やかな見送りの声を背後に聞きながら——。
次の目的地は喫茶店である。
寄り道をしたため予約時間から少し遅れての到着となった。めったに満席にならないので本来なら予約の必要もないのだが、シャーロットのために最良の席を用意したくて、確保を頼んでおいたのだ。
「落ち着いた素敵なところですね」
案内されて席につくと、彼女はあたりを見まわしながら感嘆の声を上げた。
調度品や内装はどれも上質で、暖色の灯りとあいまって統一感のある優美な空間を作り出している。そのうえ奥まった席なので他の客の目を気にしなくていい。彼女も喜んでくれたようで一安心である。
「アーサーが王都にいるときはよく一緒に来てたんだ。あいつ、ここの茶葉をよく里帰りのおみやげにしてたみたいだから、君も飲んだことあるかもな」
「おみやげの紅茶はいつも楽しみにしていました。この店のだったんですね」
シャーロットはそう言って微笑む。
ここは基本的に喫茶のみだが、紅茶好きのアーサーはいつのまにかオーナーと懇意になり、おみやげにしたいからと稀少な茶葉も分けてもらっていたのだ。もちろん相応の代金を払って。
「失礼いたします」
会話が途切れたタイミングで声がかかる。
振り向くとオーナーがいた。リチャードよりも幾分か年上と思われる物腰のやわらかい男性で、いつもと同じく執事のような衣装を身にまとっている。彼はすっと進み出ると恭しく一礼した。
「リチャード様、シャーロット様、このたびはご結婚おめでとうございます」
そう述べて、後ろに控えていた店員から手提げ袋を受け取り、ソファに座っているリチャードのほうへそれを差し出す。
「心ばかりですが、よろしければお祝いとしてお納めください」
「ああ、ありがとう……喜んでいただくよ」
思いもよらないことにリチャードはすこし驚きつつも、にこやかに受け取った。
チラリと中を確認したところ茶葉とジャムのようだ。向かいでそわそわしているシャーロットもきっと喜んでくれるだろう。茶葉は言わずもがな、ジャムも果実感が強くてなかなか美味なのだ。
「わたしが結婚したことはどちらで?」
「先日、グレイ伯爵から伺いました」
「ああ……」
そういえばアーサーは結婚式のあとで王都に寄ると言っていた。そのときだろう。いったいどこまで話したのかは気になるところだが——ポーカーフェイスの得意なオーナーからは窺い知ることができなかった。
「今日は行く先々で声をかけられたな」
オーナーが下がると、リチャードはメニューを開きながら思わずそうぼやいた。
何せこれがふたりの初めての正式なデートなのだ。できるなら誰にも邪魔されることなく一日を過ごしたかった。ふたりだけの世界にひたっていたかった。それが偽らざる正直な気持ちである。
「わたしは祝っていただけてうれしかったです」
「まあ、それならよかったけど……」
確かにシャーロットは青空市場での祝福に無邪気な笑顔を見せていたし、喫茶店のオーナーからもらった結婚祝いにも興味を示していた。ただ——。
「さすがに貴族連中にはうんざりしただろう」
「そうですね……お祝いの言葉にも何か含みのある方が多そうでしたから。でも、みなさんからリチャードや父の話を聞けたことはうれしかったです」
あのときは嫌な顔ひとつ見せることなく応対していたものの、やはり思うところはあったのだ。しかし後半のうれしかったという件についてはよくわからず、小首を傾げながら腕を組む。
「話なんてどれもたいしたものじゃなかったと思うが」
「おふたりがとっても仲良しだってことはわかりました」
「……あくまで友人としてだからな?」
「もちろん承知しています」
そう応じてシャーロットはくすくすと笑い出した。
どうやら例の男色疑惑が再燃したわけではないらしい。ほっと安堵しつつ、いまだに面白がっている彼女に恨めしげな視線を向ける。だが、目が合うと思わずというかつられるように苦笑してしまった。
「そろそろ注文を決めようか。喉も渇いたし」
「はい」
ようやくシャーロットも自分のメニューに手を伸ばした。わくわくとした様子だったのに、中を見るなり驚いたように大きく目をぱちくりとさせる。
「紅茶だけでこんなにたくさん種類があるんですね」
「オーナーが好きでな。紅茶にはこだわりがあるらしい」
「父がこの喫茶店に来ていた理由がよくわかりました」
「だろ?」
その言葉に彼女はくすりと笑った。
「ですがわたしは父と違って詳しくありませんし、どう選んだらいいのか……」
メニューには品種と産地とフレーバーが記されているのだが、知識がなければわからないだろう。リチャードも昔はわからなかった。だがここで紅茶を楽しむうちにわかるようになってきたのだ。
「どういうものが好きだとか嫌いだとかあるか?」
「そうですね……スパイシーなものはすこし苦手です」
「ああ、あれは好みが分かれるよな」
軽く笑いながら手元のメニューに目を落とす。
アーサーの影響で彼女もいろいろな紅茶を飲んでいるようだが、すべて自宅だろう。それならばこの店で飲むからこその価値があるものを勧めたい。たとえばオーナーが丹念に淹れるからこそ格段においしくなるもの、淹れるのに一手間がかかり自宅ではなかなか難しいもの、もしくは——。
「これなんかどうだ?」
ふと口元を上げ、手を伸ばして彼女のメニューのひとつを指さす。
それはシャーロットだから勧める意味があるもの——この店に初めてアーサーを連れてきたときに勧めた、そして彼がたいそう気に入って絶賛したあの紅茶、ベルガモットのフレーバードティーだった。