short story:
きょうも、また、一日が終わった。 長い一日が。
おれは、ひとり、カウンターに凭(もた)れかかりながら、客にはぜったいに出さない とっておきのヴァイスを飲(や)っていた。
重い腰を上げて、ふう、と ひと息をつきながらカウンターに入ると、かけっぱなしになっていたレコード ―― 客からリクエストされた Led Zeppelin のライヴ・アルバム、『狂熱のライヴ』 ―― を仕舞って、「いつものやつ」 に針をのせた。
 Tom Waits “Closing Time” (1973年)
Tom Waits “Closing Time” (1973年)
一曲目 ‘Ol' 55’ の軽やかなピアノのイントロにひきずられるように、一日の疲れが どっと身体にのしかかってきて、おれは、カウンターによろめきこんだ。
そして、カウンターに顔をうずめながら、だれもいやしないのに、弁解めいたことをつぶやいた。 いや、ね、Led Zeppelin が だめだってわけじゃあないんだ。 Zeppelin も好きだよ。 ただ、いまは、「狂熱」 よりも、Tom の声がほしいんだ。 と。
Tom の歌声は、おれの身に、そっと沁み込んでくる。 おれのまわりを囲んで、おれをすっぽりと包んで、やさしく撫でさすって呉れるような、そんな気がするのだ。
午前三時。 だれもいない、閉店後の室内の薄明かりに ひとりまどろむおれは、Tom の歌声に守られていた。
こわいものはなにもない。 なんの心配もない。 ―― そんなふうに思うと、のどの奥から、ふいに、涸れたつぶやきがあふれ出てきた。
おれは しがない、バーのマスター。
金もなければ、女もいない。
おれは しがない、バーのマスター。
この店だけが、おれの持ち物。
それでいいのさ。
それでいいのさ。
あまりにもくだらなくて、自嘲すらも もったいない気がした。 どうやら酒が足りないようだ。 ―― おれは、二本目のヴァイスを取り出した。
そこへ、店の戸を、コツ、コツ、コツ、と叩く音がした。 いったい、だれだろう? こんな時間に。
見ると、ほんの少し開いた戸の隙間から、女の白い顔が出てきた。 店の客だ。 数時間まえまで カウンターで呑んでいた、ちょっとかわいい、女の子。 ちょっと? いいや、ホントは、すごく、かわいいのだ。
「あれ? どうしたの?」 とたずねると、その子は、
「辻さん! ごめんね、わたし、ケイタイ、置いてっちゃったみたいなんだけど。 なかった?!」 と、泣きそうな顔で訊いてきた。
見渡してみると、カウンターの下に、メタリック・ブルーのカタマリが転がっているのが、すぐにわかった。
「ああ、あった! 良かったあ」
彼女は、ほっとした様子で携帯電話を拾いあげると、コートの袖で、さすってみせた。 あたたかそうな、見るからに仕立ての良さそうなコート。 彼女の白い顔がくっきりと浮くような、深くて上品な、黒。
そんなにいとおしいケイタイなのかね。 ―― なんて思いながら、おれは、その様子を見ていた。
しかし、女の子のくせに、メタリック・ブルーってのも、変わってるよな。 まあ、こんなさびれたバーにひとりで呑みに来ている時点で、カワッタ女の子なのかもな。
だいたい、彼女みたいな女の子が、なぜ、おれのところに来るのか。 彼女ならば、きっと、どこぞのこじゃれたバーのほうが似合っているような気がするけれど。 ―― そんなことを考えながら、じっと彼女を見つめていたせいか、彼女は、ちょっと照れたように、
「なに呑んでるの?」 と、おれのヴァイスのグラスに目を遣った。
はっとして、おれは、眼差しをほどいた。 「ン? これ? ドイツの白ビール」
「ふうん、そんなの、お店のメニューにあった?」 なんて、すかさず彼女が訊いてくるので、おれは、ちょっと笑ってみせた。 彼女が、さぐるようにおれの眼をのぞき込むので、しょうがなくおれは、カウンターに入り、とっておきのヴァイスを取り出して、彼女に投げた。
彼女は、しっかり受け取ると、「わあい」 と無邪気によろこんで栓を開けた。 そして、ぐいっとのどに押し込むと、「おいしい! 冬に合う感じ」 と声を上げた。 彼女は、かわいい顔をして、いい呑みっぷりをするのだ。
あーあ、ホントは、グラスに入れたほうが うまいのに。 ―― なんて思いながらも、グラスを渡すタイミングを計れず、
「だろ?」 と、調子を合わせてみた。
「お店に置けばいいのに」
「おれは、ホントに好きなもンは、人には教えてやンないんだ」
彼女は笑った。 彼女の、憂いを含んだようなソプラノ ―― Laura Nyro みたいな ―― が、薄暗い店のなかで心地よく転がった。 むかし、おれの家で飼っていた ねこの首輪の鈴音みたいだ、と思った。
外の空気が冷たかったせいなのか、頬が染まっていて、彼女は、いつもより幼く見えた。 彼女は、ヴァイスの瓶を握りしめて、ちょっと首をかしげた。 白い顔に浮かぶ思案の表情。 おれがいつもカウンター越しに胸をときめかせる、あの、つややかな貌(かお)。
考えてみると、こうしてゆっくり彼女と向かい合うのは、はじめてだった。 ひとりで呑みに来ていても、彼女は人気があって、野郎の客たちの絶好の話し相手になっていたから。
思わぬ幸福なひととき。 たまには、いいこともあるもんだ。
彼女は、すぐに帰ろうと思っていたのだけど、せっかくビールをもらったから、もう少しゆっくりしていくわ ―― とでも言いたいかのように、変な勢いをつけて、カウンターに腰を下ろした。
“Closing Time” の A 面が終わったので、おれは、レコードをひっくり返した。
「これ、だあれ?」 ―― 彼女は、おもむろに、音楽のことを訊いてきた。
「トム・ウェイツっていうオヤジ。 このころはまだオヤジじゃないけどな」
「なんていうタイトル?」
「『クロージング・タイム』」
「『閉じている時間』?」
「ウーン、『閉店時間』ってことじゃネエカ? バーの閉店時間。 ジャケット見てみな。 そんな感じするだろ?」
「うん、そうね。 すてきね」 と言って、レコード・ジャケットにたたずむ Tom の姿 ―― 薄明かりのなかで、ピアノに凭れかかり、煙草を燻(くゆ)らす ―― に見入った。
「ああ、なんだか、これ、ほんとうに落ち着くね」
彼女は、沈黙を避けるように ことばをつないだ。 酒のことを言っているのか、音楽のことを言っているのか、わからないけれど、きっと、音楽のことを言っているのだろう、と思った。 そんな彼女が、なんとなく、かわいらしく思えた。
彼女は、ほんとうは、こんな時間に、こんなところに、いるような子じゃないんだ ―― そう思うと、おれの のどの奥から、一日の疲れを溜め込んだ しわがれた声がしぼり出てきた。 ―― ああ、彼女の声と、なんて ちがいなんだ。 美女と野獣か。
「だろ? アルバムのタイトルどおり、こうして店が終わったあとに聴きたくなるンだよね」
「お店が終わったあとにしか、聴かないの?」
「言ったろう? おれは、ホントに好きなもンは、人にゃ教えてやらないって。 みんながいるときには、かけないよ」
「いじわるね」
「ウン。 いや、ホントはさ、じぶんがものすごく好きなレコードって、つい聴き入っちゃうから、ひとりのときに聴きたいンだよね」
「ああ、そうね。 わたしもそうかも知れない。 ほんとうに好きな曲は、ひとりでじっくり聴きたくなるな」
「そうだろう?」 ―― こんなおれのたわ言に同調してくれる彼女のやさしさがうれしくて、おれはつづけた。
「おれはさ、『いやし系』 なんてことば、大嫌いだけど、この世のなかに、もし、人のココロをいやせる音楽ってもンがあるなら、このアルバムがそうかも知れない、なんて思っててさ。 一曲目のイントロ聴いただけで、ホロリとくるよ。 それくらい大好きだから、もう、客なんかほったらかしで聴き入っちまう」 ―― 調子に乗って、さらに音楽おたくぶりを発揮してしまう有り様だった。
彼女を見遣ると、彼女は退屈そうな様子も見せずに、
「そんなに好きなのね。 ごめんなさいね、邪魔しちゃって」 と、あのブルージーなソプラノで包んで呉れた。 それは、古いピアノの、高いほうの音が さざなみを打つときのように、おれのむねを揺らした。
「いや、いいンだよ。 ナッチャンだから、特別」 ―― われ知らず本音が出てしまい、あわてて それをゴマ化すように、音楽の話に引き戻した。
「ナッチャンさ、イーグルスって知ってる? そう、『ホテル・カリフォルニア』 の。 あいつらがさ、トム・ウェイツの曲、カヴァーしてるンだよ。 このアルバムの一曲目。 ホント、いい曲だよ。 いや、ほかにも、いい曲いっぱいあるけどさ。 ナッチャンも、きっと好きだと思うよ。 酒呑みなら、きっと、沁みるよ。 トム・ウェイツ自身がのんべえだから。 のんべえのキモチを歌わせたら、ホントにすごいよ。 ナッチャンも のんべえだろ?」
「いやだ、わたし、そんなにのんべえじゃないもの」
彼女は、クチビルを尖らせた。 ―― なんてかわいい口なのだろう!
「いいや、のんべえだね」 わざと、からかうように意地悪く言ってみた。 小学生か、おれは?
「もう、ひどい」
「もっと呑むかい? ヴァイス」
「ヴァイスなら、もらう!」
「やっぱり、のんべだ」
「のんべえじゃないもん」
こんな真夜中にキャッキャとふざけて。 おれたちゃ、いったい、なんなんだ? まるで、すごく、イイ感じみたいじゃないか。 ―― ふいに我に返って、気恥ずかしくなった。 彼女は、こんな時間に、こんなところで、こんなおれと、ふざけ合うような、そんな女の子じゃないんだ。
このままこうして、彼女と、朝まで語り合えたら、どんなにかステキだろう。 けれども、それは、ほんのひとときの、夢でしかありえない。 たのしい時間は、もう終わりだ。
おれは、顔を引きしめて、「あのサア、やっぱり、もう、帰ンなよ」 と、歯をきしませながら、ゆっくり、言った。 言いたくもないことばを言わなきゃならないってのは、なんてみじめなのだろう。
急におれがそんなことを言うものだから、彼女は、ほんの少し まゆを寄せてみせた。
おれが、弁解するようにあわてて、「いや、もう遅いし。 明日も仕事だろ?」 と言うと、彼女は、そうね、と言って、立ち上がった。
むねがズキン、と痛んだ。
「送っていこか?」 ―― 彼女のうしろ姿に問いかけた。
彼女は、ちょっと振り返って、しずかに微笑んでみせた。 「辻さんって、やさしいのね。 でも、だいじょうぶ。 ひとりで帰れるから」
そう言って、しずかにドアのほうへと吸い込まれていった。
ああ、そうだ。 彼女は、おれなんかが、家まで送っていいような子じゃないんだ。 彼女は、ひとりで、戻らなくちゃいけないんだ、彼女自身の世界に。 サヨナラ。 オヤスミ。 また今度。 キミのうしろ姿を、ずっと見送るよ。
ドアのところでふいに、彼女は、つと振り返った。 そして、
「辻さんは」 ―― いったんことばを切って、「辻さんは、わたしに、ヒミツを教えてくれたでしょう? 辻さんの、ほんとうに好きなもの。 だから、わたしも、わたしのヒミツを教えてあげる」 と、言い出した。 のどに詰まった小骨をするりと取り出すみたいに。
まるで、蒼い花がひらくときのような、一瞬を感じた。 一瞬? 永遠?
「ええ? いいヨ! そんな、たいしたもンじゃないから!」 おれは、あわてて じぶんのむねのふるえを隠した。
けれど、のどから小骨を取り出してしまった彼女は、引き下がらなかった。 「だって、人のヒミツを知るのって、重いでしょ? ヒミツをひとつ知るには、ヒミツがひとつ必要だ、なあんていう詩もあるんだから。 だから、わたしのヒミツを教えて、ひとつ、軽くならなきゃ」
―― おれは、うなづくしかなかった。
蒼い花は、ゆっくりと頭をもたげた。 やっぱり、ほんの少しためらっているらしい。 けれども、一度ひらいてしまった花は、もう、引き返せないのだ。
彼女は、にらむように、ぎゅっとおれを見つめた。
いったい、なんだ? もう、この店には来ない、とか、結婚するの、とか? アタシ、ホントは、オトコなの、とか? ―― どうしよう。 どうしようもねえか。
ああ。 このまま、なあんにも知らずにいたほうが、しあわせなのかもナア。 時間よ、止まれ。 時間よ、止まれ。
彼女は、そんなおれのこころなぞ、知ってか知らずか、容赦なくつづけた。 まったく、女ってやつは。
「ほんとうはね」
―― ああ、やっぱり、オトコなのか? ばかなことを。 思いっきり眼を閉じて、その瞬間を待った。
「ほんとうは、わたし、ケイタイ、忘れていったんじゃないの」
―― 想像していたようなことばからあまりにもかけ離れていたせいか、意識を遠くにやっていたからか、なにを言っているのか、よくわからなかった。 でも、オトコじゃなきゃ、なんだっていい。 彼女が、彼女であるなら、それだけで、いいのだ。
「ほんとうはね、わざと、置いていったの」
へえ。 わざとねえ。 で? ―― おれは、なにも言えず、ただ笑ってみせた。
「だから、わざとなの。 で、わざと、いま、取りに来たの。 お客さんがだれもいなくなってから。 だって、お店にいるときは、辻さんとゆっくり話ができないでしょう?」
ふうん。 そっか、そっか。 よかった、よかった。 オトコじゃないんだ、女なんだ。 ホントによかった。
「なに、ニコニコしてるの? ちゃんと意味、わかってる?」 ―― 彼女は、もう、蒼い花ではなかった。 ついさっきまでのように頬を赤くして、無邪気な、怒ったような顔をしてみせた。
そりゃあ、そうだ! こんなにかわいい子が、オトコのわけがない。
「ウーン、イミ? わかンない。 でも、よかった、よかった」
「なにがいいの? んもう、辻さんって、ほんとうに鈍感なのね」 と、彼女は、また、クチビルを尖らせたが、おれがへらへらしていたので、あきらめたようにため息をついた。
「わたしが今度お店に来るときまでに、意味、ちゃんと考えておいてよ、ね」
そう言って、彼女は、ふわりと去っていった。
おれは、彼女の残していった、なんともいえない、あたたかな余韻にひたりながら、ひとり佇んだ。
意味? いったい、どんなイミがあるっていうんだ? 女ってのは、なんでああやって、妙な謎かけをするんだろう。 おれが鈍感すぎるだけなのか? ―― Tom Waits の歌声にまみれながら、ウンウンうなってみたけれど。
ようやく意味がわかり、〈そうだったのか、こんなおれを?〉 という うれしい気持ちと、〈いやそんな馬鹿な、こんなおれだもの〉 とじぶんを制する気持ちで、むねがいっぱいになったのは、ちょうど、レコードが “Closing Time” の最後の曲を奏でるときだった。
“Closing Time” ―― 不思議な、四十五分 五十五秒 の物語。
おれは、カウンターに残されたヴァイスの瓶を見遣って、大きく伸びをした。 そのまま、バンザイをしたくなった。
おれは、店の戸を締め、階段を一気に駆け下りた。 三段飛び、四段飛びして降りたい気持ちを抑えつつ。
そうして、いつもの帰り途を足早に歩きながら、考えたのは、幸福などというものは、待っているときには、来やしない、ということだった。
幸福は、思ってもみないときに、すぐそこのドアから、やって来るものなのかも知れない、と。
待って、待って、待ちくたびれて、もう、いいやって、あきらめたころに、ふいに。
そうしていつも、おれたちを、あっと言わせるのだ。
幸福を知らせるノックが、三回、鳴って。
BGM:
Tony Orlando & Dawn ‘ノックは三回 / Knock Three Times’
(「なつメロ」 として括られている、トニー・オーランド & ドーンの 1971 年のヒット曲。 私は、まだ生まれていないときのものだけれど。 どことなく、なつかしさに、こころをくすぐられる曲である)
(※ 裏 BGM としては、小沢健二さんの 「ドアをノックするのは誰だ」 をおすすめいたします :) )
きょうも、また、一日が終わった。 長い一日が。
おれは、ひとり、カウンターに凭(もた)れかかりながら、客にはぜったいに出さない とっておきのヴァイスを飲(や)っていた。
重い腰を上げて、ふう、と ひと息をつきながらカウンターに入ると、かけっぱなしになっていたレコード ―― 客からリクエストされた Led Zeppelin のライヴ・アルバム、『狂熱のライヴ』 ―― を仕舞って、「いつものやつ」 に針をのせた。
 Tom Waits “Closing Time” (1973年)
Tom Waits “Closing Time” (1973年)一曲目 ‘Ol' 55’ の軽やかなピアノのイントロにひきずられるように、一日の疲れが どっと身体にのしかかってきて、おれは、カウンターによろめきこんだ。
そして、カウンターに顔をうずめながら、だれもいやしないのに、弁解めいたことをつぶやいた。 いや、ね、Led Zeppelin が だめだってわけじゃあないんだ。 Zeppelin も好きだよ。 ただ、いまは、「狂熱」 よりも、Tom の声がほしいんだ。 と。
Tom の歌声は、おれの身に、そっと沁み込んでくる。 おれのまわりを囲んで、おれをすっぽりと包んで、やさしく撫でさすって呉れるような、そんな気がするのだ。
午前三時。 だれもいない、閉店後の室内の薄明かりに ひとりまどろむおれは、Tom の歌声に守られていた。
こわいものはなにもない。 なんの心配もない。 ―― そんなふうに思うと、のどの奥から、ふいに、涸れたつぶやきがあふれ出てきた。
おれは しがない、バーのマスター。
金もなければ、女もいない。
おれは しがない、バーのマスター。
この店だけが、おれの持ち物。
それでいいのさ。
それでいいのさ。
あまりにもくだらなくて、自嘲すらも もったいない気がした。 どうやら酒が足りないようだ。 ―― おれは、二本目のヴァイスを取り出した。
そこへ、店の戸を、コツ、コツ、コツ、と叩く音がした。 いったい、だれだろう? こんな時間に。
見ると、ほんの少し開いた戸の隙間から、女の白い顔が出てきた。 店の客だ。 数時間まえまで カウンターで呑んでいた、ちょっとかわいい、女の子。 ちょっと? いいや、ホントは、すごく、かわいいのだ。
「あれ? どうしたの?」 とたずねると、その子は、
「辻さん! ごめんね、わたし、ケイタイ、置いてっちゃったみたいなんだけど。 なかった?!」 と、泣きそうな顔で訊いてきた。
見渡してみると、カウンターの下に、メタリック・ブルーのカタマリが転がっているのが、すぐにわかった。
「ああ、あった! 良かったあ」
彼女は、ほっとした様子で携帯電話を拾いあげると、コートの袖で、さすってみせた。 あたたかそうな、見るからに仕立ての良さそうなコート。 彼女の白い顔がくっきりと浮くような、深くて上品な、黒。
そんなにいとおしいケイタイなのかね。 ―― なんて思いながら、おれは、その様子を見ていた。
しかし、女の子のくせに、メタリック・ブルーってのも、変わってるよな。 まあ、こんなさびれたバーにひとりで呑みに来ている時点で、カワッタ女の子なのかもな。
だいたい、彼女みたいな女の子が、なぜ、おれのところに来るのか。 彼女ならば、きっと、どこぞのこじゃれたバーのほうが似合っているような気がするけれど。 ―― そんなことを考えながら、じっと彼女を見つめていたせいか、彼女は、ちょっと照れたように、
「なに呑んでるの?」 と、おれのヴァイスのグラスに目を遣った。
はっとして、おれは、眼差しをほどいた。 「ン? これ? ドイツの白ビール」
「ふうん、そんなの、お店のメニューにあった?」 なんて、すかさず彼女が訊いてくるので、おれは、ちょっと笑ってみせた。 彼女が、さぐるようにおれの眼をのぞき込むので、しょうがなくおれは、カウンターに入り、とっておきのヴァイスを取り出して、彼女に投げた。
彼女は、しっかり受け取ると、「わあい」 と無邪気によろこんで栓を開けた。 そして、ぐいっとのどに押し込むと、「おいしい! 冬に合う感じ」 と声を上げた。 彼女は、かわいい顔をして、いい呑みっぷりをするのだ。
あーあ、ホントは、グラスに入れたほうが うまいのに。 ―― なんて思いながらも、グラスを渡すタイミングを計れず、
「だろ?」 と、調子を合わせてみた。
「お店に置けばいいのに」
「おれは、ホントに好きなもンは、人には教えてやンないんだ」
彼女は笑った。 彼女の、憂いを含んだようなソプラノ ―― Laura Nyro みたいな ―― が、薄暗い店のなかで心地よく転がった。 むかし、おれの家で飼っていた ねこの首輪の鈴音みたいだ、と思った。
外の空気が冷たかったせいなのか、頬が染まっていて、彼女は、いつもより幼く見えた。 彼女は、ヴァイスの瓶を握りしめて、ちょっと首をかしげた。 白い顔に浮かぶ思案の表情。 おれがいつもカウンター越しに胸をときめかせる、あの、つややかな貌(かお)。
考えてみると、こうしてゆっくり彼女と向かい合うのは、はじめてだった。 ひとりで呑みに来ていても、彼女は人気があって、野郎の客たちの絶好の話し相手になっていたから。
思わぬ幸福なひととき。 たまには、いいこともあるもんだ。
彼女は、すぐに帰ろうと思っていたのだけど、せっかくビールをもらったから、もう少しゆっくりしていくわ ―― とでも言いたいかのように、変な勢いをつけて、カウンターに腰を下ろした。
“Closing Time” の A 面が終わったので、おれは、レコードをひっくり返した。
「これ、だあれ?」 ―― 彼女は、おもむろに、音楽のことを訊いてきた。
「トム・ウェイツっていうオヤジ。 このころはまだオヤジじゃないけどな」
「なんていうタイトル?」
「『クロージング・タイム』」
「『閉じている時間』?」
「ウーン、『閉店時間』ってことじゃネエカ? バーの閉店時間。 ジャケット見てみな。 そんな感じするだろ?」
「うん、そうね。 すてきね」 と言って、レコード・ジャケットにたたずむ Tom の姿 ―― 薄明かりのなかで、ピアノに凭れかかり、煙草を燻(くゆ)らす ―― に見入った。
「ああ、なんだか、これ、ほんとうに落ち着くね」
彼女は、沈黙を避けるように ことばをつないだ。 酒のことを言っているのか、音楽のことを言っているのか、わからないけれど、きっと、音楽のことを言っているのだろう、と思った。 そんな彼女が、なんとなく、かわいらしく思えた。
彼女は、ほんとうは、こんな時間に、こんなところに、いるような子じゃないんだ ―― そう思うと、おれの のどの奥から、一日の疲れを溜め込んだ しわがれた声がしぼり出てきた。 ―― ああ、彼女の声と、なんて ちがいなんだ。 美女と野獣か。
「だろ? アルバムのタイトルどおり、こうして店が終わったあとに聴きたくなるンだよね」
「お店が終わったあとにしか、聴かないの?」
「言ったろう? おれは、ホントに好きなもンは、人にゃ教えてやらないって。 みんながいるときには、かけないよ」
「いじわるね」
「ウン。 いや、ホントはさ、じぶんがものすごく好きなレコードって、つい聴き入っちゃうから、ひとりのときに聴きたいンだよね」
「ああ、そうね。 わたしもそうかも知れない。 ほんとうに好きな曲は、ひとりでじっくり聴きたくなるな」
「そうだろう?」 ―― こんなおれのたわ言に同調してくれる彼女のやさしさがうれしくて、おれはつづけた。
「おれはさ、『いやし系』 なんてことば、大嫌いだけど、この世のなかに、もし、人のココロをいやせる音楽ってもンがあるなら、このアルバムがそうかも知れない、なんて思っててさ。 一曲目のイントロ聴いただけで、ホロリとくるよ。 それくらい大好きだから、もう、客なんかほったらかしで聴き入っちまう」 ―― 調子に乗って、さらに音楽おたくぶりを発揮してしまう有り様だった。
彼女を見遣ると、彼女は退屈そうな様子も見せずに、
「そんなに好きなのね。 ごめんなさいね、邪魔しちゃって」 と、あのブルージーなソプラノで包んで呉れた。 それは、古いピアノの、高いほうの音が さざなみを打つときのように、おれのむねを揺らした。
「いや、いいンだよ。 ナッチャンだから、特別」 ―― われ知らず本音が出てしまい、あわてて それをゴマ化すように、音楽の話に引き戻した。
「ナッチャンさ、イーグルスって知ってる? そう、『ホテル・カリフォルニア』 の。 あいつらがさ、トム・ウェイツの曲、カヴァーしてるンだよ。 このアルバムの一曲目。 ホント、いい曲だよ。 いや、ほかにも、いい曲いっぱいあるけどさ。 ナッチャンも、きっと好きだと思うよ。 酒呑みなら、きっと、沁みるよ。 トム・ウェイツ自身がのんべえだから。 のんべえのキモチを歌わせたら、ホントにすごいよ。 ナッチャンも のんべえだろ?」
「いやだ、わたし、そんなにのんべえじゃないもの」
彼女は、クチビルを尖らせた。 ―― なんてかわいい口なのだろう!
「いいや、のんべえだね」 わざと、からかうように意地悪く言ってみた。 小学生か、おれは?
「もう、ひどい」
「もっと呑むかい? ヴァイス」
「ヴァイスなら、もらう!」
「やっぱり、のんべだ」
「のんべえじゃないもん」
こんな真夜中にキャッキャとふざけて。 おれたちゃ、いったい、なんなんだ? まるで、すごく、イイ感じみたいじゃないか。 ―― ふいに我に返って、気恥ずかしくなった。 彼女は、こんな時間に、こんなところで、こんなおれと、ふざけ合うような、そんな女の子じゃないんだ。
このままこうして、彼女と、朝まで語り合えたら、どんなにかステキだろう。 けれども、それは、ほんのひとときの、夢でしかありえない。 たのしい時間は、もう終わりだ。
おれは、顔を引きしめて、「あのサア、やっぱり、もう、帰ンなよ」 と、歯をきしませながら、ゆっくり、言った。 言いたくもないことばを言わなきゃならないってのは、なんてみじめなのだろう。
急におれがそんなことを言うものだから、彼女は、ほんの少し まゆを寄せてみせた。
おれが、弁解するようにあわてて、「いや、もう遅いし。 明日も仕事だろ?」 と言うと、彼女は、そうね、と言って、立ち上がった。
むねがズキン、と痛んだ。
「送っていこか?」 ―― 彼女のうしろ姿に問いかけた。
彼女は、ちょっと振り返って、しずかに微笑んでみせた。 「辻さんって、やさしいのね。 でも、だいじょうぶ。 ひとりで帰れるから」
そう言って、しずかにドアのほうへと吸い込まれていった。
ああ、そうだ。 彼女は、おれなんかが、家まで送っていいような子じゃないんだ。 彼女は、ひとりで、戻らなくちゃいけないんだ、彼女自身の世界に。 サヨナラ。 オヤスミ。 また今度。 キミのうしろ姿を、ずっと見送るよ。
ドアのところでふいに、彼女は、つと振り返った。 そして、
「辻さんは」 ―― いったんことばを切って、「辻さんは、わたしに、ヒミツを教えてくれたでしょう? 辻さんの、ほんとうに好きなもの。 だから、わたしも、わたしのヒミツを教えてあげる」 と、言い出した。 のどに詰まった小骨をするりと取り出すみたいに。
まるで、蒼い花がひらくときのような、一瞬を感じた。 一瞬? 永遠?
「ええ? いいヨ! そんな、たいしたもンじゃないから!」 おれは、あわてて じぶんのむねのふるえを隠した。
けれど、のどから小骨を取り出してしまった彼女は、引き下がらなかった。 「だって、人のヒミツを知るのって、重いでしょ? ヒミツをひとつ知るには、ヒミツがひとつ必要だ、なあんていう詩もあるんだから。 だから、わたしのヒミツを教えて、ひとつ、軽くならなきゃ」
―― おれは、うなづくしかなかった。
蒼い花は、ゆっくりと頭をもたげた。 やっぱり、ほんの少しためらっているらしい。 けれども、一度ひらいてしまった花は、もう、引き返せないのだ。
彼女は、にらむように、ぎゅっとおれを見つめた。
いったい、なんだ? もう、この店には来ない、とか、結婚するの、とか? アタシ、ホントは、オトコなの、とか? ―― どうしよう。 どうしようもねえか。
ああ。 このまま、なあんにも知らずにいたほうが、しあわせなのかもナア。 時間よ、止まれ。 時間よ、止まれ。
彼女は、そんなおれのこころなぞ、知ってか知らずか、容赦なくつづけた。 まったく、女ってやつは。
「ほんとうはね」
―― ああ、やっぱり、オトコなのか? ばかなことを。 思いっきり眼を閉じて、その瞬間を待った。
「ほんとうは、わたし、ケイタイ、忘れていったんじゃないの」
―― 想像していたようなことばからあまりにもかけ離れていたせいか、意識を遠くにやっていたからか、なにを言っているのか、よくわからなかった。 でも、オトコじゃなきゃ、なんだっていい。 彼女が、彼女であるなら、それだけで、いいのだ。
「ほんとうはね、わざと、置いていったの」
へえ。 わざとねえ。 で? ―― おれは、なにも言えず、ただ笑ってみせた。
「だから、わざとなの。 で、わざと、いま、取りに来たの。 お客さんがだれもいなくなってから。 だって、お店にいるときは、辻さんとゆっくり話ができないでしょう?」
ふうん。 そっか、そっか。 よかった、よかった。 オトコじゃないんだ、女なんだ。 ホントによかった。
「なに、ニコニコしてるの? ちゃんと意味、わかってる?」 ―― 彼女は、もう、蒼い花ではなかった。 ついさっきまでのように頬を赤くして、無邪気な、怒ったような顔をしてみせた。
そりゃあ、そうだ! こんなにかわいい子が、オトコのわけがない。
「ウーン、イミ? わかンない。 でも、よかった、よかった」
「なにがいいの? んもう、辻さんって、ほんとうに鈍感なのね」 と、彼女は、また、クチビルを尖らせたが、おれがへらへらしていたので、あきらめたようにため息をついた。
「わたしが今度お店に来るときまでに、意味、ちゃんと考えておいてよ、ね」
そう言って、彼女は、ふわりと去っていった。
おれは、彼女の残していった、なんともいえない、あたたかな余韻にひたりながら、ひとり佇んだ。
意味? いったい、どんなイミがあるっていうんだ? 女ってのは、なんでああやって、妙な謎かけをするんだろう。 おれが鈍感すぎるだけなのか? ―― Tom Waits の歌声にまみれながら、ウンウンうなってみたけれど。
ようやく意味がわかり、〈そうだったのか、こんなおれを?〉 という うれしい気持ちと、〈いやそんな馬鹿な、こんなおれだもの〉 とじぶんを制する気持ちで、むねがいっぱいになったのは、ちょうど、レコードが “Closing Time” の最後の曲を奏でるときだった。
“Closing Time” ―― 不思議な、四十五分 五十五秒 の物語。
おれは、カウンターに残されたヴァイスの瓶を見遣って、大きく伸びをした。 そのまま、バンザイをしたくなった。
おれは、店の戸を締め、階段を一気に駆け下りた。 三段飛び、四段飛びして降りたい気持ちを抑えつつ。
そうして、いつもの帰り途を足早に歩きながら、考えたのは、幸福などというものは、待っているときには、来やしない、ということだった。
幸福は、思ってもみないときに、すぐそこのドアから、やって来るものなのかも知れない、と。
待って、待って、待ちくたびれて、もう、いいやって、あきらめたころに、ふいに。
そうしていつも、おれたちを、あっと言わせるのだ。
幸福を知らせるノックが、三回、鳴って。
―― TO THE WAITING FEW.
BGM:
Tony Orlando & Dawn ‘ノックは三回 / Knock Three Times’
(「なつメロ」 として括られている、トニー・オーランド & ドーンの 1971 年のヒット曲。 私は、まだ生まれていないときのものだけれど。 どことなく、なつかしさに、こころをくすぐられる曲である)
(※ 裏 BGM としては、小沢健二さんの 「ドアをノックするのは誰だ」 をおすすめいたします :) )










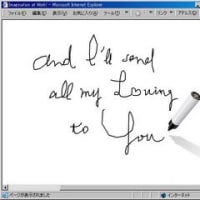



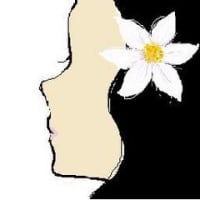









読んでくださって、ありがとうございます!
ええと、モデルは両人とも実在しているのですが、ストーリーは完全な創作なんですヨ。
本当にあった話かと思われたなんて、そんなそんな ... 。
照れますが、うれしいです!
本当にあった話かとおもいましたよ!
それぐらい、男心&女の描写がうまいですねぇ~
John Doe さん、こんばんは。
Tom Waits,お好きですか?!
Tom Waits が好きだというかたに出逢えると、とてもうれしいです。
(『Down by Low』での役柄、なかなかにおもしろかったです)
ああ、そうですね。
Tom Waits は、熟成されたモルト・ウィスキーのようですね。
グラスのなかで氷を、ゆっくりじっくり溶かしていくウィスキー。
琥珀色の、焼きつくような、ガソリンのような、皇かな液体。
それを一口呑みこむと、じわりじわりと、酔いが私を包み込む ... 。
# Tom Waits さんの自伝(?)、たしか、本の帯に、「おれに酔うなよ」とか書いてあった気がします ... 。
# もう、酔っちゃっているので、やめられないです ... 。
Down by Lowはびっくりしましたが。
何十年も樽で寝かせたシングルモルト。
濁ったオイルが浮かぶ道端の水溜り。
ヤニの浮いた酒場に置かれた、古い楽器。
彼のその声はまるで琥珀。
口当たりは重く、鈍く、喉を焼く。
その中に時間を閉じ込め、
扉を開ければ、いつも変わらぬ塊を包み込む。
その包みを開きたい。
それを味わいたい。
それが溶けてその塊をほぐすまで、
時間をかけ、足を運び、温める。
その頃にはその味に囚われて、
もうやめられなくなっている。
はじめまして!
(asoko20cm さんから trackback && コメントをいただけるなんて ... ! )
記事、拝読して、小説の一場面を思い起こしました。
まるで日本ではないような、どこか異国の出来事のような感じも。
(アメリカの短編小説の出だしのような感じが ... 。 どこかなつかしさの香りのような)
こういった情景に、トム・ウェイツはよく合いますね。
同じトムウェイツを聞きながらバーで飲む話でここまで違うのかと青ざめております。
私のやつは日記なのでかっこ悪すぎで当たり前なのですが・・・
復活おめでとう御座います。
読んでくださって、ありがとうございます!
うれしいです。
そんなそんな、お洒落ですかね~。
モデルが良かったんですかね~。
創作文はひさしぶりで、書くのにものすごく時間がかかってしまいました ... 。
えと、Eagles さん、お聴きになられたことあるかも、ですか??
Hotel California は、むかしカラオケなどに行ったときには歌ったりしました。
けっこう受けが良かったりします :)
お洒落な物語だと感じました!
格好いいなぁ~…。
イーグルスは、聞いたことある、かも。
待っていてくださったんですか?!
ありがとうございます。
読んでくださって、ありがとうございます。
また、書きます (気が向いたら?!)
最初は、「羽音」さんのつもりではなかったのですが、書いている途中で、「羽音」さんぽいかな??なんて思ったのでした。
another side of Haon として、応募期限切れ後に trackback 送ってしまおうかしら、なんて、一瞬考えたのですよん。
でも、なんとなく、やめておきました。
※ちなみに、意味のわからないかたのために ... 。
「羽音」とは、goo blogger による同人誌 『BLOG FRIENDS #2』 のマスコット・キャラクターの名まえです。
羽音に関する創作文は、こちらで募集されていました。
http://blog.goo.ne.jp/daiskekun/e/f1bd032452959ecfd7d355abeca19edb
応募作品一覧
http://blog.goo.ne.jp/daiskekun/e/52c3470b3acebe7e9069edcf9ba3eaea
受賞者発表
http://blog.goo.ne.jp/daiskekun/e/b7db78b60e1c2de4e677d5861682acb4
ありがとう
短いくせに、おれのよりずっと名作になったうじゃん、このままじゃっ! おれの努力はどこ? ってな感じで(ズルッ…)。
ほんっと応募の期限が切れていて、よかったよかった(笑)。
読んでくださって、ありがとうございます。
ええと、アップするまで時間をあけたので、推敲する時間はたっぷりあったのですけれど ... 。
あれれれれん。
それにしても、記事を書くのって、パワーがいりますね ... 。
# 「彼女」に「羽音」という名をつけてみようかなあ ... なんて、一瞬、考えたんですよ。
しびれちゃったよw。
以下、参考にしなくてもいい参考。
文中、不要な「彼女」を二個見つけたんだ。
記事中に、Tom Waits の “Closing Time” のジャケットを貼りたいがために、Amazon Associate と、goo ブログ アドヴァンスに申し込んでしまいました ... 。
(決して、完全復活するとか、やる気マンマンというわけではありません ... )
この物語は、ある特定の少数の人のために書きました。
(TO THE WAITING FEW)
少数の待ち人へ、ということですが、この blog (のようなもの) の更新を待っている人へ ... というような、そんな大それた意味ではなく、あらゆる待ち人を意味しています。
愛する人を待つ人、幸福を待つ人、かなしみの果てを待つ人。
そのうちのほんの少数の人のこころに届けば、とてもうれしく思います。
また、この記事を書くきっかけを与えてくださったかたに感謝いたします。