HK G3はローラーロッキング・ディレイドブローバックと呼ばれる独特の排莢機構を採用している――G3軍用アサルト・ライフルの機構をそっくり流用して設計されたMP5も、当然この機構を採用している。
ローラーロッキング・ディレイドブローバックは読んで字のごとく、ローラーロッキングでブローバックを遅延 させるものだ――ブローバックというのは排莢の際、撃発によって生じた燃焼ガスのガス圧を利用してボルトを後退させ薬莢を排出する機構なのだが、通常この作動は撃発と同時に起こる。
面に対する圧力の作用にかかわる定理や法則の中に、パスカルの定理というものがある――簡単に言うと『密閉容器中の流体はその容器の形に関係なく、ある一点に受けた単位面積当たりの圧力をそのままの強さで、流体の他のすべての部分に伝える』という流体静力学における基本原理だ。
無論中学生になるころには誰でも習っているだろうが、要するに逃げ場のない空間に発生した圧力はすべての面に均等にかかるのだ。
これを銃身とその内部に装填された弾薬に置き換えると、撃発直後、薬莢内部に発生した圧力に押し出されて銃身内部に弾頭が移動した状態は、筒状の空間が弾頭と薬莢で閉じられている状態になる。
この状態であれば、発射ガスの圧力は薬莢の内部のすべての面と銃身、それに弾頭の底部に均等にかかっていることになる――頑丈な銃身が圧力で破裂することは無いが、代わりに弾頭は銃口方向へ押し出されて発射され、同時に薬莢もそれを保持するボルトごと後方へと押されるのだ。
話は変わるが、現代的なライフルの大半は閉鎖 ボルト式――弾薬を保持するボルトと呼ばれる部品が前進し、薬室に弾薬が装填されて排莢口が閉じた 状態で保持される構造になっている。
HK G3アサルトライフルの構造をそのままダウンサイジングしたMP5も同様で、現在はともかくMP5が発表された当時はクローズド・ボルト構造はサブマシンガンとしてはかなり珍しかった。対して同じ時期に主流だったアメリカ製のイングラムMAC10や、イスラエル製のUZIサブマシンガンは開放 ボルトと呼ばれる方式を採用している。
クローズド・ボルトとオープン・ボルトの違いはその動作機構にある。オープン・ボルトはボルトが常時後退し、排莢口が開いた 状態で保持されている――オープン・ボルトに価値を見出したい人間はその状態を風通しがよく冷却 効果が高いと評する。
だがアルカードに言わせれば、狙ったところに当たらない銃など鉄屑同然だった。そもそもひたすらフルオートで撃っているだけのハリウッド映画ならともかく、実銃で過熱 を気にするほど連射しなければならない程度の腕しか無いのなら、サブマシンガンなど持ち歩いたところで弾薬がいくらあっても足りない。
オープン・ボルトはその構造上、トリガーを引くとボルトが前進し、弾薬が薬室に装填されて排莢口が閉鎖され、撃針が雷管を叩いて装薬を撃発する様になっている。重いボルトがスプリングの力で前進することで、機関部の内部で大きな重心位置の移動が起こるのだ――それによって銃口位置の上下動が起こり、照準線の角度も変わってしまう。結果、オープン・ボルトの銃は比較的安定させやすいセミオート撃発でも、照準が狂ってしまいやすい。
熟練した射手がセミオートで使ってもそうなるのだ、フルオートで撃ったときの精度などなにをか況やというところだろう。
イングラムやUZIの様なサブマシンガンを評してプリンカー と評する人間がいるが、その評価は正しい――誤解されがちだがフルオート射撃というのは、遠距離ではまったく役に立たないものだ(※)。
現代の近接距離戦闘 の様に細かく区切って銃を撃つという発想が無く、AGEミニ・ガンの様な電動ガトリングバルカンやブラウニングM2の様な機関銃が全盛だった時代には、標的を文字通り蜂の巣にする勢いで派手に撃ちまくっていたものだが――それがいかに盛大な浪費なのかは、アメリカ兵が敵兵ひとりを斃すのに一万発の弾薬を必要としたというヴェトナム戦争時の記録からも明らかだ(※2)。
フルオートというのは、逃げ場の無い狭い場所でしか役に立たない――それはこちらが敵に向けて撃つ場合だけでなく、敵がこちらに撃つ場合にも言えることだが。
改めてディレイド・ブローバックに話を戻すが、クローズド・ボルトはオープン・ボルトに対して桁違いの照準精度を確保している――トリガーが引かれた時点ですでにボルトが前進しているために重いボルトの移動による重心移動が起こらないからで、照準線が狂いにくい。
だが、それでもやはり照準線の移動は起こる――自動装填 を行う銃にはボルトやスライドの後退に伴う重心移動があり、それが弾頭が銃口から出るより早く起こってしまうため、ここでやはり弾頭の軌道は射手の意図したものとは異なるものになる。
そのどうしようもない問題を解決するため、ヘッケラー・アンド・コッホ社はローラーロッキング機構によってボルトの後退 を遅延 させる、遅延 ブローバック構造を採用した。
装薬の燃焼によって銃身内部の圧力が高まると、ガス圧に押されて薬莢がボルトを後退させる。G3系のボルト機構は薬莢後部のリムを銜え込むロッキング・ピースの後方にローラーがふたつ配置されており、ボルトが後退する前にまずローラーが動く様に出来ている。
ローラーは後方ではなく、内側に向かって斜めに動く様に出来ている――ローラーがボルトヘッド・キャリアーの側面から突き出してバレル・エクステンションに嵌まりこんだ構造になっているため、発射ガスによって押されたボルトの後退が始まるためにはまずローラーがボルトの内部に押し戻されなければならない。この構造のため、ボルトの後退が一瞬だけ遅れるのだ――これが重心移動を遅らせて、結果セミオート時の極めて高い命中精度とマイルドな反動によるフルオート時の扱いやすさを両立した。
クローズド・ボルト構造のメリットが周知され普及してきた現在はともかく、当時は百メートル離れたところからアイアンサイトで敵の頭部を狙えるサブマシンガンなどほかに無かったのだ――高い精度と扱いやすさは、人質救出作戦の様に標的を選ばなければならない状況では非常に有用なものだ。
唯一問題があるとすれば――これはG3系列の銃すべてに言えることだが、野戦向きではないことくらいだろう。その問題が致命的だが。
MP5も含めたG3系の銃はすべてそうだが――ローラーロッキングによる部品点数の多い複雑な構造を取っているため、塵埃や部品の摩耗に極めて弱い。砂漠にでも持ち込もうものなら、数日で使い物にならなくなるだろう。実際、ヘッケラー・アンド・コッホ社は新型軍用銃にはローラーロッキングを採用せず、別の機構を採用している――これはM16など西側諸国の軍用銃全般に言えることだが部品点数の多い複雑な構造をしたものが多く、頻繁で綿密な整備が不可欠となる。
また重要なのは、工作精度に対する依存度が極めて高いことだ――ビルマなどの工業技術的に未熟な国で生産されたHK G3のコピー品は、故障が多くて使い物にならなかったという話をよく耳にする。
MP5が登場した当時は過剰性能 だのと揶揄され、価格の高さも相俟ってほとんど売れなかったが、それでも人質救出チームや対テロリスト部隊には極めて高い評価を受けていた。そういった人質救出部隊は平時は訓練に時間を費やしているし、作戦行動中以外に銃のメンテナンスにいくらでも時間を取れるからだ――雨はともかくとして、砂嵐の中で作戦行動を行う様な状況になることもない。
アルカードにとっても、別に問題にならない――彼は別にイラクの奥地で監視所を設けて、何週間も潜伏してイスラム系過激派の拠点を監視するために武装しているわけではない。
そんなことを考えながら、アルカードはレシーヴァーを取り上げて上下をひっくり返し、銃腔を覗き込んだ。
G3系列のライフルやサブマシンガンの薬室部分には、フルートと呼ばれる溝が切られている――G3やG33、PSG-1といった先細りの形状をした薬莢を持つ弾薬を使うライフルの場合は後方へ向かって広がる放射状だが、MP5の様なサブマシンガンの場合は銃身と平行になる。
フルートは読んで字のごとく溝という意味で、発射ガスの一部を薬莢の外側に廻り込ませる働きをしている――薬莢は撃発の際の発射ガスの膨張で多かれ少なかれ膨らむものだが、ボルトの後退を意図的に遅らせる構造になっているHK G3シリーズの場合、撃発から排莢までに十分な時間があるために薬莢の膨張率が大きい。そのため薬莢が薬室の内側に張りついてボルトの後退が始まっても剥がれず、そのままボルト・ヘッドが薬莢の一部を引きちぎってしまうことがあるのだ――空気を入れていない=内外で気圧差の無いゴム風船がしぼんでいる様に、また空気を入れた風船が周囲の気圧が上がって内外の気圧が均等に近づくと再びしぼむ様に、フルートは発射ガスの一部を薬莢の外側に流入させることで薬莢の内外の圧力を均等に近づけて薬莢が薬室に張りつくのを防ぎ、また溝に流れ込んだガスが潤滑剤の様な役割を果たすことでボルト・ヘッドが薬莢を抜き取りやすくしているのだ(※3)。
だが、代わりにフルートの内部に発射ガスの残存物が残りやすく、スラッジをきちんと取り除かないと動作不良の原因になる――最悪薬莢がちぎれて戦闘を継続出来なくなる恐れもあるので、クリーニングは徹底しておかなければならない。
唯一の救いは薬莢が小さいことと薬莢の形状が先細りでないぶん、まだ掃除が楽なことくらいか。GSG-9の狙撃チームにいたときに狙撃訓練後のPSG-1のクリーニング作業であまりの面倒臭さに無性に死にたくなったことを思い出しながら、アルカードは溜め息をついた。
幸いなことに、今はスラッジを分解する洗浄液という便利なものがある――これはこれで、つけたまま放っておくと錆の原因になるが。
洗浄スプレーを薬室の内側から吹きつけて、スラッジを拭き取っていく――純正の清掃用具の中にはクリーニング・ロッドに取りつけて使う棒ブラシの様な代物もあるのだが、アルカードはそれがあまり好きではなかった。
クリーニング・ロッドに布切れを巻きつけて銃身に差し込んでは引き抜き、布を取り換えて再び差し込んでは引き抜きを繰り返しながら、アルカードはやがて布に汚れが附着しなくなったことに満足してクリーニング・ロッドを置いた。
洗浄液がある程度乾燥するまでは錆止めの油も塗れないので、そのまま放っておく――とりあえずの暇潰しに、アルカードは手袋をはずしてから机の端に置いてあったパソコンに手を伸ばした。
パソコンの手前に無造作に置かれた二挺のX-FIVE自動拳銃も視界に入ってくるが、そちらにはとりあえず手をつけない――物事はいっぺんにやろうとするとしくじるものだ。
開きっぱなしになっているパソコンの電源ボタンに手を触れる――BIOSの画面が表示されたところで、アルカードはディスプレイから視線をはずした。
肘掛けに両肘をついて、椅子の背凭れに体重を預ける。少し瞼が重くなっているのがわかった――昨日は夜通し行動していたうえに、昼間は少しでも眠ろうと思っていたらマークツーにじゃれつかれて寝るに寝られなかったのだ。
まあ、そのマークツーと遊んでやるのがだんだん面白くなってきたので、昼間は眠気を忘れていられたが。
一般的な吸血鬼に対する認識には誤解が多い――噛まれ者 は本能的に太陽の光を嫌う。光が帯びた大量の性質の異なる魔力によって魔力構造を破壊され、さらに肉体の代謝機能が暴走して肉体が崩壊し消滅してしまうからだ。だがそれも下位の吸血鬼のみのことで、真祖や『剣』は白昼出歩いても特に支障は無い。
真祖の特性を色濃く受け継いだ『剣』は、太陽のもとで出歩いても死ぬことは無い。体は重くなり能力も制限されるものの、それだけだ。下位の吸血鬼の様に、鏡の反射光にさえ苦痛を感じる様なことは無い。
特に棺桶で眠る様なことも無いし、ついでに言うならいきなり夜型生活になったりもしない――普段のアルカードは典型的な昼型生活を送っているし、棺桶とも縁が無い。
大蒜と十字架が苦手、というのも吸血鬼に対する極めて一般的な誤解のひとつだろう――大蒜を見ただけでおびえる吸血鬼などというのは存在しないし、別に触れたからどうだというものでもない。嗅覚が利くので人間だったときより臭く感じて苦手になるというのはあるかもしれないが、まあ少なくともアルカードは大蒜は普通に食べられる。
十字架に関しても似た様なものだ――今アルカードがこうして平気で教会の敷地内にいる様に、十字架などの宗教的器物も弱点にはなり得ない。
教会によって祝福儀礼を施された器物なら、堕性を帯びた魔力を持つ吸血鬼にとっては確かに危険ではあるのだが――ただのアクセサリー的な十字架や十字の模様、十字路などを目にしておびえ狂ったりはしない。
アルカードに至っては、聖性を帯びた十字架や聖遺物に普通に触ることが出来る――あえて言うなら、聖水や聖餅はまずかった。
そこらの有象無象ならともかくアルカードにとっては、一般的に言われる吸血鬼の弱点などというのはその程度のものだ。
ついでに言うなら、水が苦手というのも――
※……
二〇〇七年ごろに自衛隊用に開発された九ミリ機関けん銃は外観構造ともにUZIに酷似しており、作動もオープン・ボルトです。戦場に持っていく火器に異物の入り込みやすいオープン・ボルト構造を採用しているあたり、さすが実戦経験ゼロの人間が現場を考慮せずに開発してる代物だけあるなあと思わざるをえません。
また墜落した航空機のパイロットが友軍の救助部隊が来るまでの間自分の身を守るためのいわゆるPDW、個人防衛用小火器 としての要素も開発コンセプトに含まれているはずなのですが、墜落した機体ごと敵の支配地域内に放り出されて補給が断絶し、弾数に限りのある状況で使うことを想定した火器に無駄弾の出やすいオープン・ボルト構造を採用するという点も、個人的には理解に苦しむところです。
※2……
別にM60やらM134やらで敵兵ひとりひとりに対して一万発ずつ撃ちまくったという意味ではありません。敵兵の殺害数に対して弾薬の消費量を計算するとひとり当たり一万発ということで、それだけ無駄弾が多かったということです。
※3……
発射済みの空薬莢 はこの構造のために大きく膨張してフルートに喰い込み、フルートにめり込んで変形し、発射ガスのスラッジで汚れます。
本編の遠い遠い過去の記憶 の作中においてアルカードがPSG-1狙撃銃によるキメラ研究者の暗殺を行っていたシーンがあり、その文中に薬莢に残ったフルートの痕跡でメーカーが簡単に特定されるという趣旨のことを書きましたが、主な原因がこれです。
URLを貼るのは避けておきますが、WikipediaのHK P7自動拳銃の項目に発射後の空薬莢の写真が掲載されています。
ローラーロッキング・ディレイドブローバックは読んで字のごとく、ローラーロッキングでブローバックを
面に対する圧力の作用にかかわる定理や法則の中に、パスカルの定理というものがある――簡単に言うと『密閉容器中の流体はその容器の形に関係なく、ある一点に受けた単位面積当たりの圧力をそのままの強さで、流体の他のすべての部分に伝える』という流体静力学における基本原理だ。
無論中学生になるころには誰でも習っているだろうが、要するに逃げ場のない空間に発生した圧力はすべての面に均等にかかるのだ。
これを銃身とその内部に装填された弾薬に置き換えると、撃発直後、薬莢内部に発生した圧力に押し出されて銃身内部に弾頭が移動した状態は、筒状の空間が弾頭と薬莢で閉じられている状態になる。
この状態であれば、発射ガスの圧力は薬莢の内部のすべての面と銃身、それに弾頭の底部に均等にかかっていることになる――頑丈な銃身が圧力で破裂することは無いが、代わりに弾頭は銃口方向へ押し出されて発射され、同時に薬莢もそれを保持するボルトごと後方へと押されるのだ。
話は変わるが、現代的なライフルの大半は
HK G3アサルトライフルの構造をそのままダウンサイジングしたMP5も同様で、現在はともかくMP5が発表された当時はクローズド・ボルト構造はサブマシンガンとしてはかなり珍しかった。対して同じ時期に主流だったアメリカ製のイングラムMAC10や、イスラエル製のUZIサブマシンガンは
クローズド・ボルトとオープン・ボルトの違いはその動作機構にある。オープン・ボルトはボルトが常時後退し、排莢口が
だがアルカードに言わせれば、狙ったところに当たらない銃など鉄屑同然だった。そもそもひたすらフルオートで撃っているだけのハリウッド映画ならともかく、実銃で
オープン・ボルトはその構造上、トリガーを引くとボルトが前進し、弾薬が薬室に装填されて排莢口が閉鎖され、撃針が雷管を叩いて装薬を撃発する様になっている。重いボルトがスプリングの力で前進することで、機関部の内部で大きな重心位置の移動が起こるのだ――それによって銃口位置の上下動が起こり、照準線の角度も変わってしまう。結果、オープン・ボルトの銃は比較的安定させやすいセミオート撃発でも、照準が狂ってしまいやすい。
熟練した射手がセミオートで使ってもそうなるのだ、フルオートで撃ったときの精度などなにをか況やというところだろう。
イングラムやUZIの様なサブマシンガンを評して
現代の
フルオートというのは、逃げ場の無い狭い場所でしか役に立たない――それはこちらが敵に向けて撃つ場合だけでなく、敵がこちらに撃つ場合にも言えることだが。
改めてディレイド・ブローバックに話を戻すが、クローズド・ボルトはオープン・ボルトに対して桁違いの照準精度を確保している――トリガーが引かれた時点ですでにボルトが前進しているために重いボルトの移動による重心移動が起こらないからで、照準線が狂いにくい。
だが、それでもやはり照準線の移動は起こる――
そのどうしようもない問題を解決するため、ヘッケラー・アンド・コッホ社はローラーロッキング機構によってボルトの
装薬の燃焼によって銃身内部の圧力が高まると、ガス圧に押されて薬莢がボルトを後退させる。G3系のボルト機構は薬莢後部のリムを銜え込むロッキング・ピースの後方にローラーがふたつ配置されており、ボルトが後退する前にまずローラーが動く様に出来ている。
ローラーは後方ではなく、内側に向かって斜めに動く様に出来ている――ローラーがボルトヘッド・キャリアーの側面から突き出してバレル・エクステンションに嵌まりこんだ構造になっているため、発射ガスによって押されたボルトの後退が始まるためにはまずローラーがボルトの内部に押し戻されなければならない。この構造のため、ボルトの後退が一瞬だけ遅れるのだ――これが重心移動を遅らせて、結果セミオート時の極めて高い命中精度とマイルドな反動によるフルオート時の扱いやすさを両立した。
クローズド・ボルト構造のメリットが周知され普及してきた現在はともかく、当時は百メートル離れたところからアイアンサイトで敵の頭部を狙えるサブマシンガンなどほかに無かったのだ――高い精度と扱いやすさは、人質救出作戦の様に標的を選ばなければならない状況では非常に有用なものだ。
唯一問題があるとすれば――これはG3系列の銃すべてに言えることだが、野戦向きではないことくらいだろう。その問題が致命的だが。
MP5も含めたG3系の銃はすべてそうだが――ローラーロッキングによる部品点数の多い複雑な構造を取っているため、塵埃や部品の摩耗に極めて弱い。砂漠にでも持ち込もうものなら、数日で使い物にならなくなるだろう。実際、ヘッケラー・アンド・コッホ社は新型軍用銃にはローラーロッキングを採用せず、別の機構を採用している――これはM16など西側諸国の軍用銃全般に言えることだが部品点数の多い複雑な構造をしたものが多く、頻繁で綿密な整備が不可欠となる。
また重要なのは、工作精度に対する依存度が極めて高いことだ――ビルマなどの工業技術的に未熟な国で生産されたHK G3のコピー品は、故障が多くて使い物にならなかったという話をよく耳にする。
MP5が登場した当時は
アルカードにとっても、別に問題にならない――彼は別にイラクの奥地で監視所を設けて、何週間も潜伏してイスラム系過激派の拠点を監視するために武装しているわけではない。
そんなことを考えながら、アルカードはレシーヴァーを取り上げて上下をひっくり返し、銃腔を覗き込んだ。
G3系列のライフルやサブマシンガンの薬室部分には、フルートと呼ばれる溝が切られている――G3やG33、PSG-1といった先細りの形状をした薬莢を持つ弾薬を使うライフルの場合は後方へ向かって広がる放射状だが、MP5の様なサブマシンガンの場合は銃身と平行になる。
フルートは読んで字のごとく溝という意味で、発射ガスの一部を薬莢の外側に廻り込ませる働きをしている――薬莢は撃発の際の発射ガスの膨張で多かれ少なかれ膨らむものだが、ボルトの後退を意図的に遅らせる構造になっているHK G3シリーズの場合、撃発から排莢までに十分な時間があるために薬莢の膨張率が大きい。そのため薬莢が薬室の内側に張りついてボルトの後退が始まっても剥がれず、そのままボルト・ヘッドが薬莢の一部を引きちぎってしまうことがあるのだ――空気を入れていない=内外で気圧差の無いゴム風船がしぼんでいる様に、また空気を入れた風船が周囲の気圧が上がって内外の気圧が均等に近づくと再びしぼむ様に、フルートは発射ガスの一部を薬莢の外側に流入させることで薬莢の内外の圧力を均等に近づけて薬莢が薬室に張りつくのを防ぎ、また溝に流れ込んだガスが潤滑剤の様な役割を果たすことでボルト・ヘッドが薬莢を抜き取りやすくしているのだ(※3)。
だが、代わりにフルートの内部に発射ガスの残存物が残りやすく、スラッジをきちんと取り除かないと動作不良の原因になる――最悪薬莢がちぎれて戦闘を継続出来なくなる恐れもあるので、クリーニングは徹底しておかなければならない。
唯一の救いは薬莢が小さいことと薬莢の形状が先細りでないぶん、まだ掃除が楽なことくらいか。GSG-9の狙撃チームにいたときに狙撃訓練後のPSG-1のクリーニング作業であまりの面倒臭さに無性に死にたくなったことを思い出しながら、アルカードは溜め息をついた。
幸いなことに、今はスラッジを分解する洗浄液という便利なものがある――これはこれで、つけたまま放っておくと錆の原因になるが。
洗浄スプレーを薬室の内側から吹きつけて、スラッジを拭き取っていく――純正の清掃用具の中にはクリーニング・ロッドに取りつけて使う棒ブラシの様な代物もあるのだが、アルカードはそれがあまり好きではなかった。
クリーニング・ロッドに布切れを巻きつけて銃身に差し込んでは引き抜き、布を取り換えて再び差し込んでは引き抜きを繰り返しながら、アルカードはやがて布に汚れが附着しなくなったことに満足してクリーニング・ロッドを置いた。
洗浄液がある程度乾燥するまでは錆止めの油も塗れないので、そのまま放っておく――とりあえずの暇潰しに、アルカードは手袋をはずしてから机の端に置いてあったパソコンに手を伸ばした。
パソコンの手前に無造作に置かれた二挺のX-FIVE自動拳銃も視界に入ってくるが、そちらにはとりあえず手をつけない――物事はいっぺんにやろうとするとしくじるものだ。
開きっぱなしになっているパソコンの電源ボタンに手を触れる――BIOSの画面が表示されたところで、アルカードはディスプレイから視線をはずした。
肘掛けに両肘をついて、椅子の背凭れに体重を預ける。少し瞼が重くなっているのがわかった――昨日は夜通し行動していたうえに、昼間は少しでも眠ろうと思っていたらマークツーにじゃれつかれて寝るに寝られなかったのだ。
まあ、そのマークツーと遊んでやるのがだんだん面白くなってきたので、昼間は眠気を忘れていられたが。
一般的な吸血鬼に対する認識には誤解が多い――
真祖の特性を色濃く受け継いだ『剣』は、太陽のもとで出歩いても死ぬことは無い。体は重くなり能力も制限されるものの、それだけだ。下位の吸血鬼の様に、鏡の反射光にさえ苦痛を感じる様なことは無い。
特に棺桶で眠る様なことも無いし、ついでに言うならいきなり夜型生活になったりもしない――普段のアルカードは典型的な昼型生活を送っているし、棺桶とも縁が無い。
大蒜と十字架が苦手、というのも吸血鬼に対する極めて一般的な誤解のひとつだろう――大蒜を見ただけでおびえる吸血鬼などというのは存在しないし、別に触れたからどうだというものでもない。嗅覚が利くので人間だったときより臭く感じて苦手になるというのはあるかもしれないが、まあ少なくともアルカードは大蒜は普通に食べられる。
十字架に関しても似た様なものだ――今アルカードがこうして平気で教会の敷地内にいる様に、十字架などの宗教的器物も弱点にはなり得ない。
教会によって祝福儀礼を施された器物なら、堕性を帯びた魔力を持つ吸血鬼にとっては確かに危険ではあるのだが――ただのアクセサリー的な十字架や十字の模様、十字路などを目にしておびえ狂ったりはしない。
アルカードに至っては、聖性を帯びた十字架や聖遺物に普通に触ることが出来る――あえて言うなら、聖水や聖餅はまずかった。
そこらの有象無象ならともかくアルカードにとっては、一般的に言われる吸血鬼の弱点などというのはその程度のものだ。
ついでに言うなら、水が苦手というのも――
※……
二〇〇七年ごろに自衛隊用に開発された九ミリ機関けん銃は外観構造ともにUZIに酷似しており、作動もオープン・ボルトです。戦場に持っていく火器に異物の入り込みやすいオープン・ボルト構造を採用しているあたり、さすが実戦経験ゼロの人間が現場を考慮せずに開発してる代物だけあるなあと思わざるをえません。
また墜落した航空機のパイロットが友軍の救助部隊が来るまでの間自分の身を守るためのいわゆるPDW、
※2……
別にM60やらM134やらで敵兵ひとりひとりに対して一万発ずつ撃ちまくったという意味ではありません。敵兵の殺害数に対して弾薬の消費量を計算するとひとり当たり一万発ということで、それだけ無駄弾が多かったということです。
※3……
発射済みの
本編の
URLを貼るのは避けておきますが、WikipediaのHK P7自動拳銃の項目に発射後の空薬莢の写真が掲載されています。










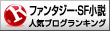







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます