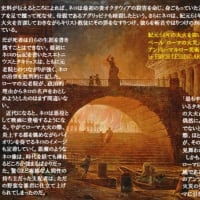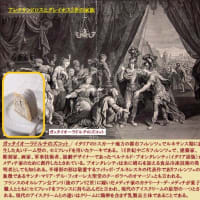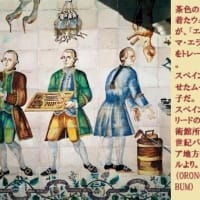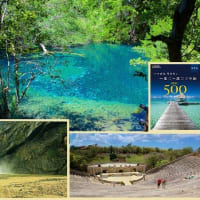〇◎ “私が知りたいのは、地球の生命の限界です” ◎〇
= 海洋研究開発機構(JAMSTEC)及びナショナルジオグラフィック記載文より転載・補講 =
☠ 青春を深海に掛けて=高井研= ☠

ᴂ 特別番外編 「しんかい6500」、震源域に潜る ᴂ
◇◆ その1 ワタクシの中に「断固たる決意」ができたのです(2/3) ◆◇
東北地方太平洋沖地震直後の一瞬は訳も分からずパニックハイな状態でしたが、その後は一週間ぐらい、まるで何も手につかないような状態でした。 「この国はどうなるんだろう」と強烈な不安と落ち込みに襲われていました。「こんな状況で研究なんてバカくさくてやってられるか」とも思いました。
しかし時間が経つにつれ、落ち込みと同時に、「今、日本海溝の海底や深海はどうなっているんだろうか、もしかしてアンナ事やコンナ事になっているんじゃないだろうか」というような科学的な想像や研究イメージ、そして妄想が徐々に湧いてきました。
もちろん「この非常時に・・・、オマエ、アホけ?」と言われたら返す言葉はない、と思っていました。
ただ、純粋に科学者の観点から東北地方太平洋沖地震を捉えた場合、あの超巨大地震は、1000年に1度の自然現象であり、その影響も近代科学が誕生してから調査されたことがない空前のスケールであることは想像に難くありません。この現象を明らかにすることは「科学の義務」と言えるのではないだろうかと、フツフツと思いはじめたのです。
そして、ワタクシを含めたJAMSTECの研究者は、日本を代表する地球と海洋の最先端研究機関の研究者なのです。日本が経験した超巨大地震の全貌を「我々JAMSTECの研究者が明らかにしないで誰がするんだ」と思っていたに違いありません。
ワタクシを含めたJAMSTECの研究者は、日本を代表する地球と海洋の最先端研究機関の研究者なのです。日本が経験した超巨大地震の全貌を「我々JAMSTECの研究者が明らかにしないで誰がするんだ」と思っていたに違いありません。
「科学の義務」や「研究者の大義」というような書き方をしましたが、もちろんあくまでワタクシが勝手にそう思ったことです。JAMSTECに限らず、大学や公的研究機関で働く科学者の中にも違う考えを持つ人も多いでしょう。「科学」は、何よりもまず「人と社会のためにあるべき」、つまり「健康や安全」、「被害の拡散防止や低減」、「生活や産業や経済の復興」あるいは「人と社会の安寧のための正しい情報提供」、のためにあるべきであると。
全くその通りだと思います。国の財政から研究資金を支援され研究を行っている以上、人と社会のために何ができるかを第一義に考えることは当然のことです。

都合がいいように聞こえるかもしれませんが、そのような観点から考えても、「同じ社会に生きる個人として」のワタクシのできることはいろいろ思いついても、「プロの科学者として」のワタクシの研究やその成果や技術が「人と社会のために為されるべき」ことは、「自分にしかできない1000年に1度の自然現象を多面的な地球―生命の繋がりとして解き明かすこと」しかないと思ったのです。
もちろん「科学の義務」や「研究者の大義」というような、いくぶん取り澄ました考え方だけではなく、もっと個人的な思いとして、ただ単純に「超巨大地震が暗黒の生態系に与えた影響」にすごく興味があったことは否定しません。それを知りたいという思いが日に日に大きくなっていました。
実はノーテンキに見えるワタクシの青春にも、「生きていることが苦しい」と思った時があります。そんな時、目の前にある現実の世界で苦しむワタクシのココロを何度も救ってくれたのが、人智を超えた数学の論理的美しさ、宇宙や地球の時空間的壮大さや生命の営みの不思議さ、の一端に触れている時間であり、それに挑む人間の情熱にシンクロしている時間だったのです。
「本当に苦しい時こそ現実を超越したナニモノカにココロを救われる」。それはある意味「信仰」にも繋がる真実だと思います。アニメの「フランダースの犬」のネロにとって、それはルーベンスであり、ルーベンスの「キリストの昇架」だったのではないでしょうか。地震直後の不安と落ち込みで苦しんでいたワタクシの場合、それが「地震を通じた地球と生命の営み」に思いを馳せることだったのかもしれません。

=光の届かぬ海底世界に、」人類が求める宝が眠る=
生物の起源は深海にある
水圧が高く、太陽光が届かない低温の環境下は、深海生物の餌も少ない。そんな過酷な環境下でも、数百度の熱水が噴出する海底の「熱水噴出孔」に含まれる化学物質の酸化・還元エネルギーから生成された栄養分を摂取している生物がいる。渡部さんが研究するのは、そうした「化学合成生態系」の基礎的な研究だ。
――海洋生物といってもさまざまな種類が存在しますが、わざわざ深い海の生物を研究対象とする意味は?
渡部 ひとことで海洋生物といっても、どれくらいの種類がいるのか私たち研究者でさえ正確には把握できていません。まだまだ未知な部分が多いのですが、深海生物は、生命の起源を探るという意味で重要な研究対象です。オゾン層のない太古の地球では、紫外線が直接降り注ぐ陸地には生物が存在していなかったと考えられています。そのため、太陽光が届かない深海に、生命の起源があったと考えられています。生命の起源に「水」はとても重要な要素で、地球以外の惑星に目を向けても、必ず「水」の存在から生命の存在を推測しています。
生命は恐らく、太陽の光を必要とせず、地球内部から出てくるエネルギーを使って生命活動を維持する生物から始まりました。彼らが地球上で最初に生まれ、それが多様化していくことで現在、地球上にあるような生態系の構築につながっていきました。
深海世界に生物の多様性の手がかりが隠されている(1/2)
――「生命の起源を探る」という点で、どんな研究をされていますか?
渡部 私自身は、生物が種分化によって多様化していく過程を研究しています。熱水噴出孔の周りには「化学合成生態系」が構築されていて、他の深海とは異なる生物群が生息しています。海底にすむ貝やカニなどの生物も、卵から孵化(ふか)する子ども(いわゆる幼生)はプランクトンとして過ごします。
化学合成生態系は深海底に島のように分布しています。私はプランクトン幼生が海の中をどのように旅をし、新しい集団を構築し、さらに新しい種が構築されていくかを調べています。最初にターゲットとして選んだ研究対象は「フジツボ」です。陸上での飼育が容易という点で選びました。
フジツボは圧力耐性が高く、浅い海だけでなく深海にも生息しています。実際、深海にすむフジツボの幼生を陸上で飼育することもできますし、浅い海にすむフジツボの幼生を加圧下で飼育することもできます。しかし、子ども時代に表層と深海の双方で生きることのできる生物が、何を決め手に親として生息する海域を選んでいるのかは、まだまだ解明されていません。それでも、研究を通じて、深海生物でも表層の海流に乗って遠くまで分散し、すむ場所を探して旅をしている生態がわかってきました。

・・・・・・・・つづく・・・・・・・
動画 :しんかい6500
=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
前節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/fa9f08387d22d3f55d85ae755f6a95e4
後節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/6da510b0eef73806357f9c527df0d897
----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい-------------- 【壺公夢想;如水総覧】 :http://thubokou.wordpress.com 【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/ 【疑心暗鬼;如水創作】 :http://bogoda.jugem.jp/ 下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行 ================================================ ・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・ 森のなかえ ================================================