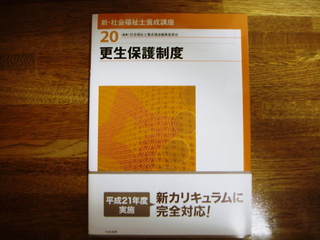
昨日(6月22日)、第2997号で書きましたが、
毎週・月曜・4時間目、定例的に勉強会を持つこととしました。
メンバーは、修士1年のSさんとNさん、それに私。
Sさんは、第21回試験で合格。Nさんは僅差で不合格。
ですから、この特別勉強会は、Nさんを励ます場でもあります。
今日のこの記事は、私の次回(6月29日)に備えた準備。
【新しい科目への備えで合否が左右される】
2010年1月に実施される第22回社会福祉士国家試験は、出題数や合格基準などは従来の試験を踏襲されるが、試験科目が13科目から19科目へ、科目の中では、科目名の変更はあっても内容的には大きな変動が無い科目から、まったく新しい科目まで色々あります。
短い期間に勉強するわけなので、勉強の方法というか、要領が重要ですね。
今回のこのブログでは、ことし合格したSさんのアイデアの紹介などもしていきます。
新しい科目の代表が、「更生保護制度」です。
【基礎的な情報の確認】
まず、科目ごとの出題基準が公表されているので、その19番めにある「更生保護制度」の内容をよく理解する。
社会福祉士国家試験試験科目別出題基準 このブログ第2991号(2009.06.19)で紹介済みです。
大項目
中項目
小項目
と対比した表になっています。専門的な用語が羅列されていて、それだけで内容を理解することは無理があります。
【教科書】
そこで、標準的な教科書を探しました。(写真)
新・社会福祉士養成講座 第20巻 更生保護制度
には、章立てがかかれてあります。
教科書の章立てと上記の出題基準はほとんど一致しています。
【法務省のサイト】
更生保護の仕事は、法務省保護局というところで所管しています。上記教科書で見ても、14名の執筆者のうち、実に11名が法務省保護局や各管区の地方更生保護委員会の専門家です。
法務省HPに、
「更生保護」とは
という解説があります。(9ページ)
最初は、この解説から始めるのもいいかな、と考えています。
*法務省保護局のサイトには、さらに詳しい解説が続いています。
*国家試験の勉強に有効な過去問ですが、たしかこれまでの「法学」などでも出題は無かったと思います。受験者にはすべて、白紙ということになります。
毎週・月曜・4時間目、定例的に勉強会を持つこととしました。
メンバーは、修士1年のSさんとNさん、それに私。
Sさんは、第21回試験で合格。Nさんは僅差で不合格。
ですから、この特別勉強会は、Nさんを励ます場でもあります。
今日のこの記事は、私の次回(6月29日)に備えた準備。
【新しい科目への備えで合否が左右される】
2010年1月に実施される第22回社会福祉士国家試験は、出題数や合格基準などは従来の試験を踏襲されるが、試験科目が13科目から19科目へ、科目の中では、科目名の変更はあっても内容的には大きな変動が無い科目から、まったく新しい科目まで色々あります。
短い期間に勉強するわけなので、勉強の方法というか、要領が重要ですね。
今回のこのブログでは、ことし合格したSさんのアイデアの紹介などもしていきます。
新しい科目の代表が、「更生保護制度」です。
【基礎的な情報の確認】
まず、科目ごとの出題基準が公表されているので、その19番めにある「更生保護制度」の内容をよく理解する。
社会福祉士国家試験試験科目別出題基準 このブログ第2991号(2009.06.19)で紹介済みです。
大項目
中項目
小項目
と対比した表になっています。専門的な用語が羅列されていて、それだけで内容を理解することは無理があります。
【教科書】
そこで、標準的な教科書を探しました。(写真)
新・社会福祉士養成講座 第20巻 更生保護制度
には、章立てがかかれてあります。
教科書の章立てと上記の出題基準はほとんど一致しています。
【法務省のサイト】
更生保護の仕事は、法務省保護局というところで所管しています。上記教科書で見ても、14名の執筆者のうち、実に11名が法務省保護局や各管区の地方更生保護委員会の専門家です。
法務省HPに、
「更生保護」とは
という解説があります。(9ページ)
最初は、この解説から始めるのもいいかな、と考えています。
*法務省保護局のサイトには、さらに詳しい解説が続いています。
*国家試験の勉強に有効な過去問ですが、たしかこれまでの「法学」などでも出題は無かったと思います。受験者にはすべて、白紙ということになります。


























レポートの関係で同じ出版社のテキスト、4と13を少し、14を少し読んだところです。
法務省のサイト、という目の付けどころに、「なるほど!」です。
先生がまとめられていたので、さすが
先生の資料を参考にし次回に備えます。
元ゼミ生Qさん、こちらこそ よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
これで
メンバーが4人ということに・・
たまに「スクーリング」もやりましょう。
この間は、Sさんから各科目の年表串刺し論が披露されました。これで自前の年表を軸に各科目の年代ものを覚えるという方法です。
聞いてみると、「なるほど」が多いです。
コメントありがとうございます。
Qさんも遠隔参加ということで
楽しくなりました。
料金無料(笑)。
法務省サイトは穴場ですね。
修士1年のカテゴリは
全員のコメント参加が無い状態では維持がきついですねぇ。最後の2回では「日中比較」で少し掘り下げてみたいです。