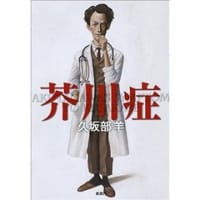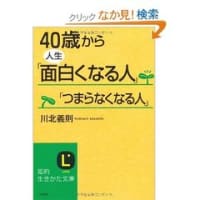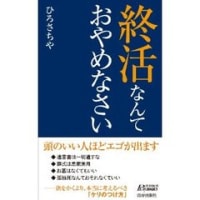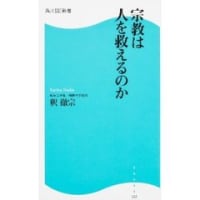「お番」の晩は雪のころ、
雪はなくても暗のころ。
くらい夜みちをお寺へつけば、
とても大きな蝋燭と、
とても大きな火鉢で、
明るい、明るい、あたたかい。
大人はしつとりお話で、
子供は騒いぢや叱られる。
だけど、明るくにぎやかで、
友だちやみんなよつてゐて、
なにかしないぢやゐられない。
更けてお家へかへつても、
なにかうれしい、ねられない。
「お番」の晩は夜なかでも、
からころ足駄の音がする。
(報恩講:金子みすゞ)
きのうときょうの二日間、自坊での「御正忌報恩講」の
法座を勤めさせていただきました。
本来なら、ご命日の16日にしなければならないのですが、
ご講師の都合で、どうしても16日の前後になります。
上の詩は、金子みすゞさんが子どものころの、“報恩講”の
様子を描いたものです。
本当に、ゆったりとした、人々の生活ぶりが手に取るようです。
そんな時代とはちがって、今の時代はなんと性急なことか。
アルジェリアでは、大変な事態になっています。
アルジェリア軍隊が人質の安全に十分配慮せずに作戦を強行した
ことに対して、人質となった当該国からの批判が強まっています。
国内では、橋下市長が、桜宮高校の体育科の入試を中止しろとか、
教員全員を配置転換させるめどをつけろとか、肝心の生徒たちの
思いをそっちのけで、行政の独断専行が進んでいるようです。
「歩」という漢字を調べてみました。
「止(とめへん)」の下に「少ない」と書いて、「歩む」と読みます。
「止」とは“とどまる”とか“たちどまる”の意味です。
戦後の民主主義教育の「歩み」が、今のことだとしたら、
一時しのぎに、臭いものにはフタみたいなことでは、
将来のものは、なかなか見えようもありません。
「歩歩」というような熟語もあります。
ゆっくり、立ち止まりながら、一歩ずつ、まわりをしっかりと
見渡しながら、
そんなにあわてず、少しずつ、行きましょうよ。

きょうも来てくださって、ありがとうございます
このブログの“タイトル”「君はまだ、抱いていたのか!!」の意味は、
こちらです!