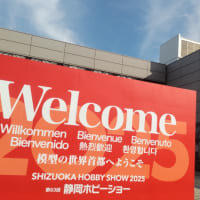日本最古のコンクリート電柱
北海道函館市末広町
私達の暮らしに欠かすことのできない電気。
その電気を家屋等の建物に送り届けるのに必要なものが、変圧器を備えたり電線を引き込むための電柱ですね。
電柱は、街の景観に浸透していることもあり、とくに珍しくもありませんが、誰もが思い描く形は、丸くて垂直に伸びる大木の様な形でしょうね。
今から100年前の1923年(大正12年)、北海道の玄関口として栄えた函館にコンクリート製の電柱がお目見えしました。
これは〜
電気が人々の生活に徐々に導入され始めた明治時代初期の頃は、全て木製の電柱が用いられていましたが、火災が多く、大火も起きている函館という街は、耐火、防火に力を入れていました。


1923年、大正12年、函館市末広町に新築されたモダン建築の銀行(北海道拓殖銀行函館支店)に電気を引き込む電柱が木製では、不釣り合いとされたことから、コンクリート製の電柱が作られることとなります。
これは、函館水電( 現在の北海道電力)が立てたもので、形状は四角に近い角錐型(かくすいがた)で、同時代に増え始めた耐火建築の建造物に合わせてコンクリート製の電柱も徐々に作られていきました。
コンクリート電柱が丸い形の円柱型に変わるのはまだ後のことです。
写真の電柱から、かつて市道を挟んだ向かい側に同じ角錐型の電柱があり、夫婦電柱として親しまれましたが、昭和46年に向い側の角錐型電柱は撤去されてしまいました。
現在、一本だけ残る角錐型コンクリート電柱は今も現役で役割を果たしています。