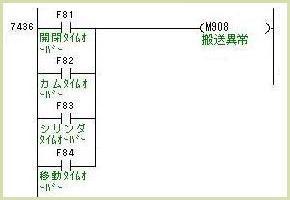ラダーのちょこっとしたこだわりが以下のブログに記載されていました。
ラダーのちょこっとしたこだわりが以下のブログに記載されていました。http://d.hatena.ne.jp/ladderman/20080311/p1
比較は全て「<」こっち向きに揃えるとの事
私も同じ事をしています。
例えばD0の値が1~100の範囲かと言った比較回路は
---[<= K1 D0]-[>= K100 D0]----
と書くのでなく
---[<= K1 D0]-[<= D0 K100]----
と書きます。この方が瞬間に判断がし易いからです。
[K1 <= D0 <= K100] と言った感じです。
考えたら、比較命令が上記のように引数3つにも対応してくれてればいいのですが。
(メーカによっては対応しているかもしれません?)
考えたら、ラダーのコマンドの作りが
①、人間側よりの作りなのか
②、CPUよりの作りなのか と考えられます。
もっと言えば、CPUの命令の作り方が上記の①なのか②なのかに行き着くような気もします...
ハードの能力が弱かった時代ならいざ知らず、現在は十分あるはずです。
ものの作り方は(設計思想)、人間側から攻めて貰わないとと考える私です。