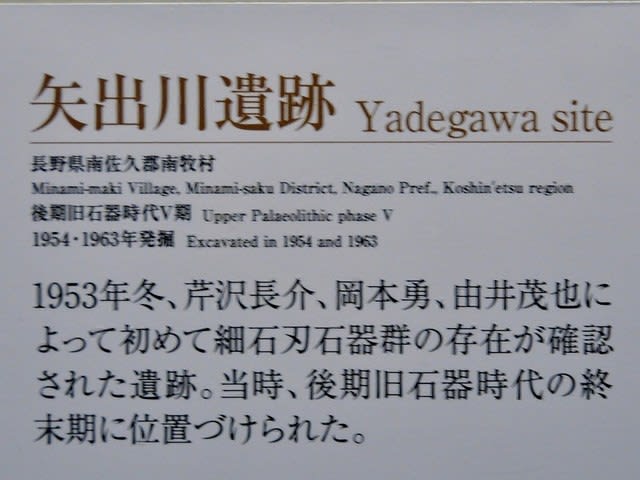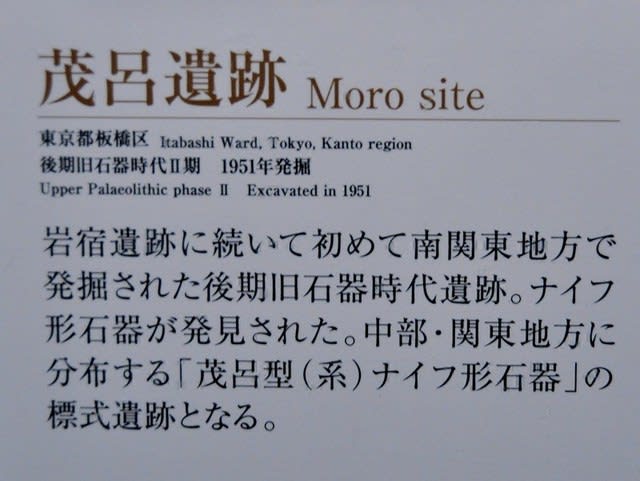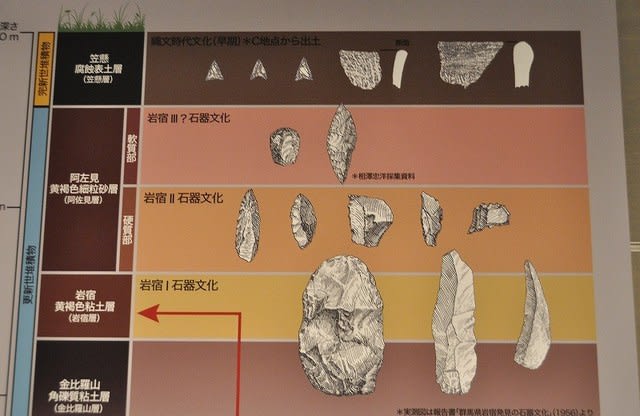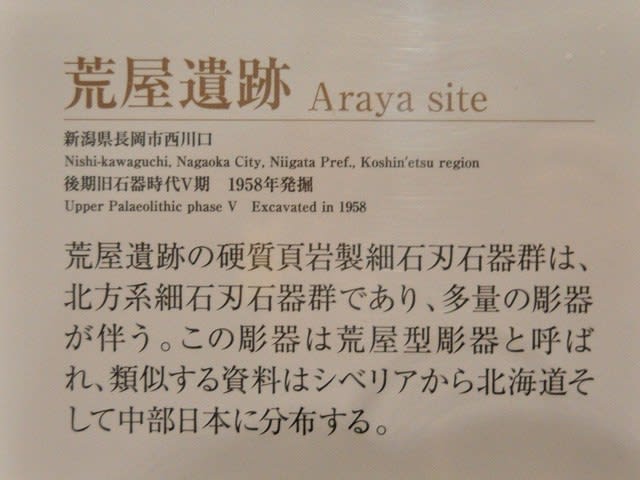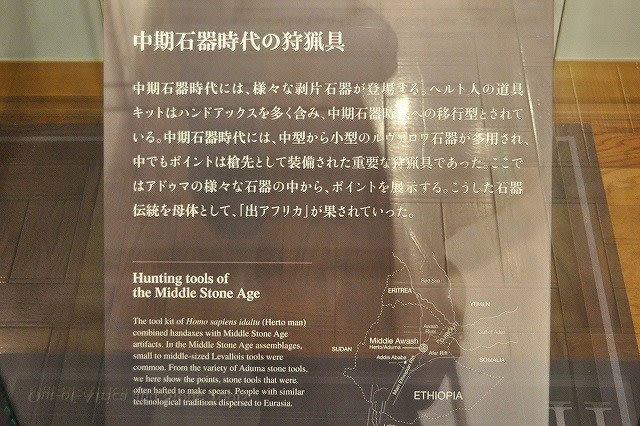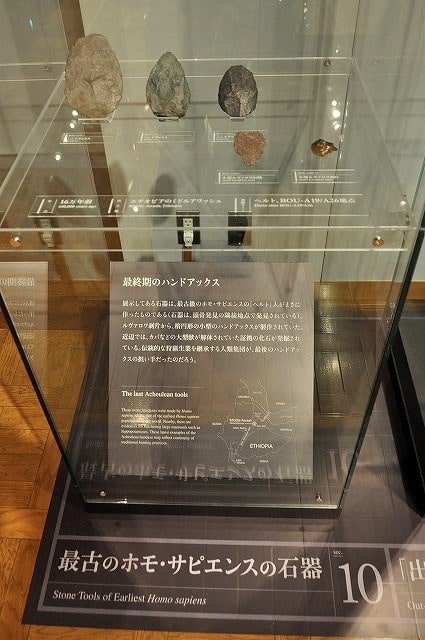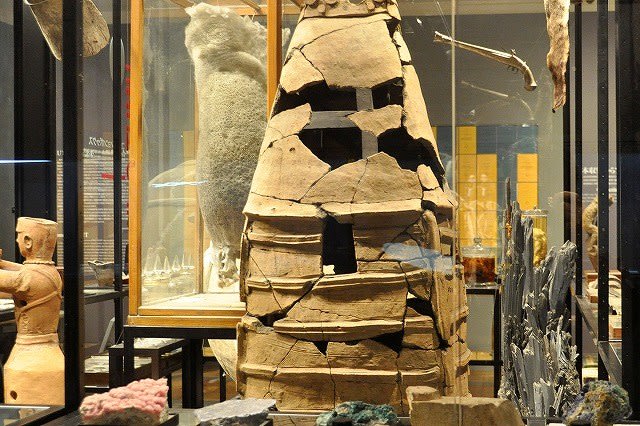「遠軽文化財埋蔵センター」へ(1/3)~旭川➡道の駅しらたき➡遠軽町・白滝
9/29、予想最高気温20℃!、快晴の絶好のバイク日和で
す。今季最後のツーリング!と、この日を待っていました。
目的は、私の近年の関心ごとである旧石器時代の遺物が
展示されている「遠軽文化財埋蔵センター」の見学です。
実は、9月上旬からの予定でしたが、天気と都合が悪くタ
イミングがつかめないでいました。それに北海道は10月に
入ると寒くなり、バイクに乗れなくなるといった事情も。
また、折しも、大型の台風24号が日本列島を縦断した後北
上し、10/1には北海道近くを通過する予報がでています。
10:00、バイク友と「道の駅 とうま」で待ち合わせです。
すぐ、ツーリング開始!です。
北見峠(標高;857m)を越え、「道の駅しらたき」で休息。
目的地の白滝ICまで後10.6Kmのところですがー。

 「道の駅 しらたき」は、気温;15℃(標高547m)でした。
「道の駅 しらたき」は、気温;15℃(標高547m)でした。

 木々が紅葉してきましたがー。
木々が紅葉してきましたがー。

 まだ、霜は降りていないのでないかな?
まだ、霜は降りていないのでないかな?
遠軽文化財埋蔵センターに着きました

 ここが遠軽文化財埋蔵センターです。
ここが遠軽文化財埋蔵センターです。
「白滝ジオサイトマップ」で白滝の概要を!

~以下は、「白滝ジオサイトマップ」の拡大写真~


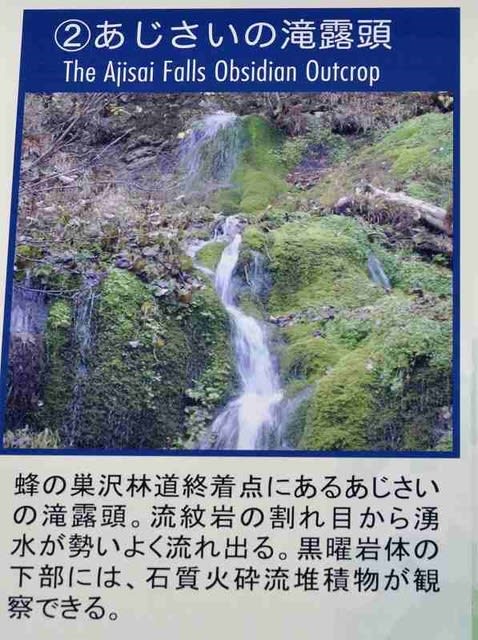





 遠軽文化財埋蔵センターは、8年前OPENしたまだ新し
遠軽文化財埋蔵センターは、8年前OPENしたまだ新し
い建物です。まずは、駐車場に設置されていた「ジオサイ
トマップ」で黒曜石の露頭のある場所、白滝遺跡が発掘され
た場所などの概要を確認することからスタートしました。
バイク友の彼は、近年団体で赤石山の黒曜石の露頭の見学
をしているという。さて、展示会場の様子はいかにー。👀
遠軽町埋蔵文化財センターへ(2/3)~後期旧石器時代の遺物
9/29、遠軽町埋蔵文化財センターの見学開始です。
現在、遠軽町内で確認されている埋蔵文化財包蔵地
(遺跡が発見されている場所)が217か所あるという。
これらの遺跡は、後期旧石器時代(30,000~12,000
年前)からアイヌ文化期までの長い期間にわたってい
ます。この地で、黒曜石の露頭があったり、小型剥片
石器や尖頭状石器、細石刃石器などが発掘調査されて
いましたが、埋蔵文化財包蔵地が飛躍的に増えたのは
高規格道路(旭川ー紋別間)の建設がきっかけです。


当センター展示室では、この発掘で出土した遺物を
中心に、わかりやすく工夫し展示しています。


 黒曜石原産地の特徴の中に、旭川も、「?」ですが記載!
黒曜石原産地の特徴の中に、旭川も、「?」ですが記載!






































 ナウマンゾウの臼歯
ナウマンゾウの臼歯









 時代的にはかけ離れていますが、寄贈されたアンモナイトもー。
時代的にはかけ離れていますが、寄贈されたアンモナイトもー。
 ここ遠軽町白滝は、日本最大級の黒曜石の産地です。
ここ遠軽町白滝は、日本最大級の黒曜石の産地です。
その埋蔵量は2億から5億トンといわれ、市街地北側の赤石
山を中心に露頭がいくつも広がっています。この黒曜石の
産地のふもとの標高300mほどの河岸段丘の上では、約百
か所もの旧石器時代の遺跡が発見され、22か所で発掘調査
が行われ、700万点の遺物が出土したとのことです。
遠軽町埋蔵文化財センターへ(3/3)~センター➡白滝遺跡群➡当麻ダム➡旭川
遠軽町埋蔵文化財センターで旧石器時代の遺物をたっぷり
見た後、「遠軽町郷土館」や「丸瀬布郷土資料館」も見学した
い気持ちもありましたが、旭川に戻ることにしました。
途中、国指定史跡の「白滝遺跡群」を見ることにしました。
恐らく発掘調査の終わった後は、ある程度復元し放置され
るので、ブュシュ等が繁茂していることが予期されます。


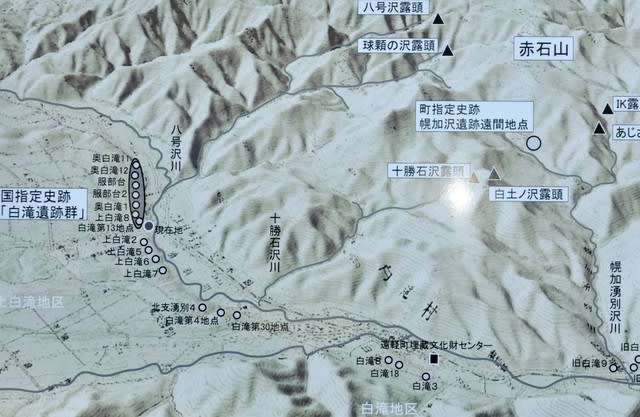
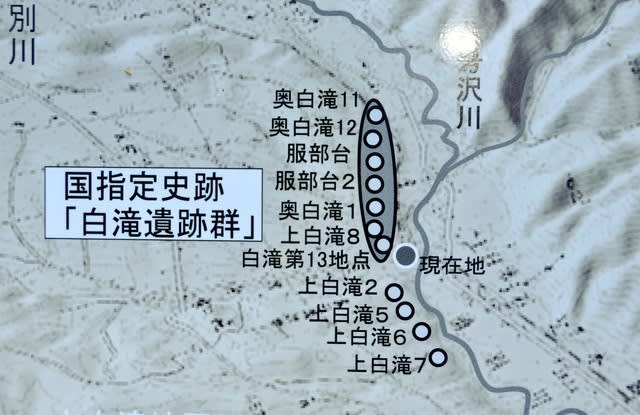
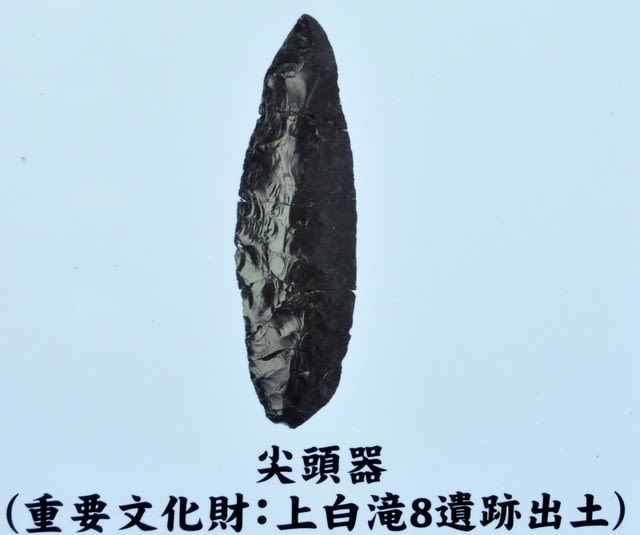
 国道沿いの白滝遺跡群№C-011という場所に行きましたが
国道沿いの白滝遺跡群№C-011という場所に行きましたが
立派な看板があり、親切ていねいに説明されていました。
13:30ごろ「道の駅 しらたき」で遅い昼食。
その後ー
9月末にもなると、日没が早いのと夕方になると気温もグンと
下がるので、早めに旭川に戻ることにしました。バイクには適
温(最高気温は20.8℃)で、風もなく抜けるような青空です。
愛別で高速をおり、私の場合、当麻町を経由して帰ると少し
近道になることもあり、ここでバイク友とお別れです。 
その途中、灌漑用の「当麻ダム」に立ち寄ることにしました。
「永山新川」にハクチョウやカモが飛来しなくなってからし
ばらく行っていませんが、5月に遭った当麻の友人から当麻
ダムでハクチョウを見たとの情報がありました。ですから、
当麻ダムは機会があれば行ってみよう!と思っていました。
当麻ダムの様子

 これが当麻ダムです。ダムのふもとまで水田があります。
これが当麻ダムです。ダムのふもとまで水田があります。

 今の時季は放水されており、カラッポ!です。
今の時季は放水されており、カラッポ!です。

 これではハクチョウやカモは来ないな!
これではハクチョウやカモは来ないな!

 春であればダムの水が満タンなので飛来する可能性あり!ーと納得。
春であればダムの水が満タンなので飛来する可能性あり!ーと納得。

 ここには魚がいないのかな?
ここには魚がいないのかな?
色付いてきた山々




 当麻市街・旭川方面
当麻市街・旭川方面
 今年最後のツーリングか、と思い大事に走ってきました。
今年最後のツーリングか、と思い大事に走ってきました。
走行距離180km、帰宅16:00は心にも体にもやさしいツー
リングでした。今年も元気で、無事故・無違反で終えたこと
にヨロズの神様に感謝!です。合わせて、向学心に燃え、生
涯学習を実践している自分を自分でホメながらー(^^♪
 。
。


 この建物が「第二展示室」入口です。
この建物が「第二展示室」入口です。
 クマの親子が冬眠している様子。
クマの親子が冬眠している様子。









 昔の人、よく考えたものですね。
昔の人、よく考えたものですね。














 忍路環状列石の模型。
忍路環状列石の模型。






















 忍路遺跡は、縄文時代後期ということで、私の興味関心の「後期石器
忍路遺跡は、縄文時代後期ということで、私の興味関心の「後期石器


















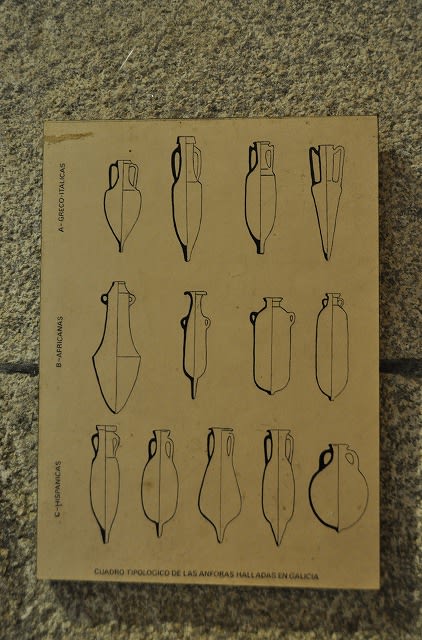



















































































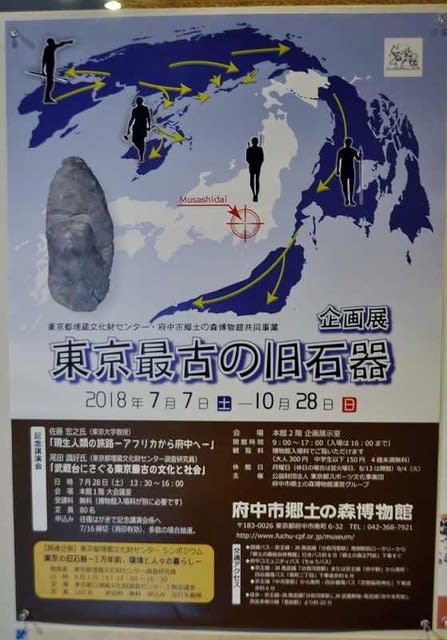































































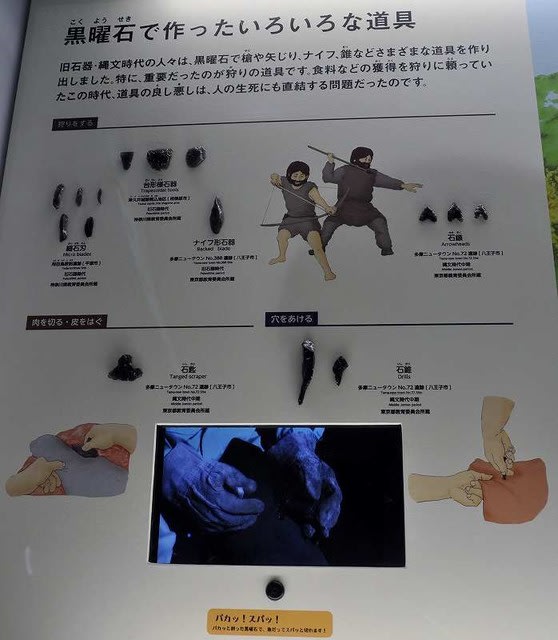





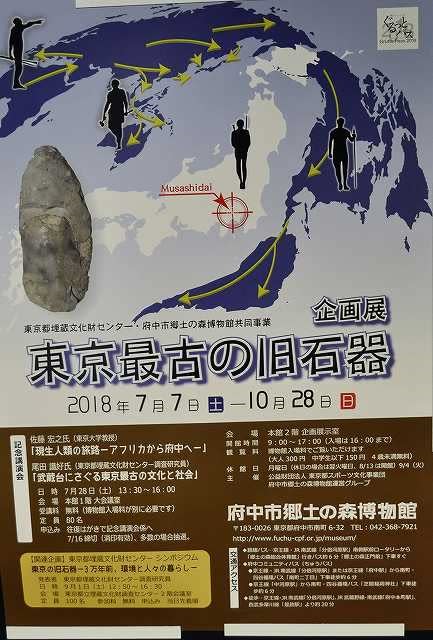









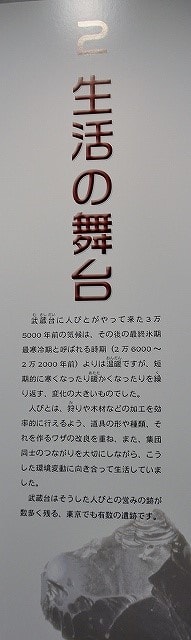






























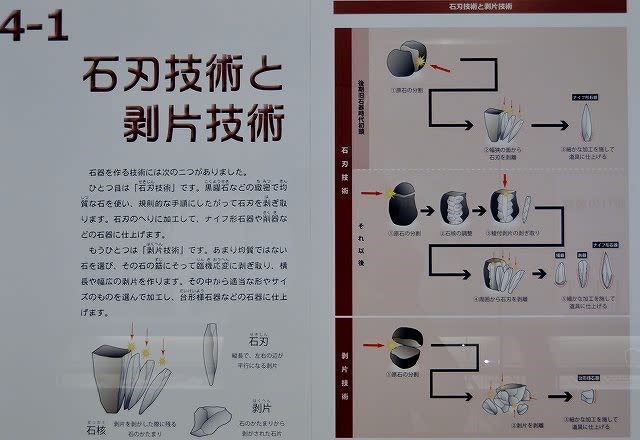









































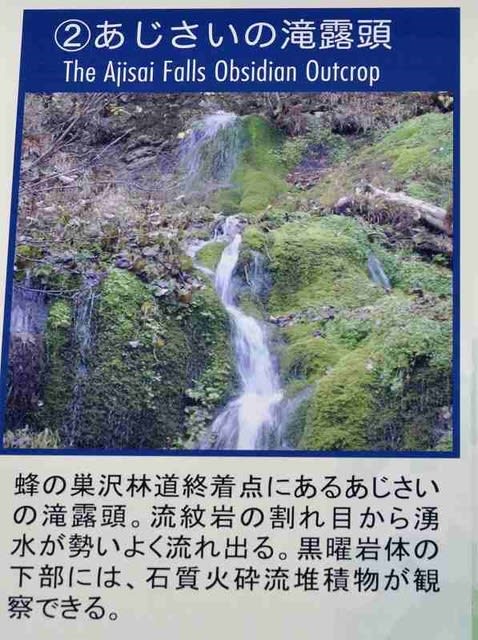


























































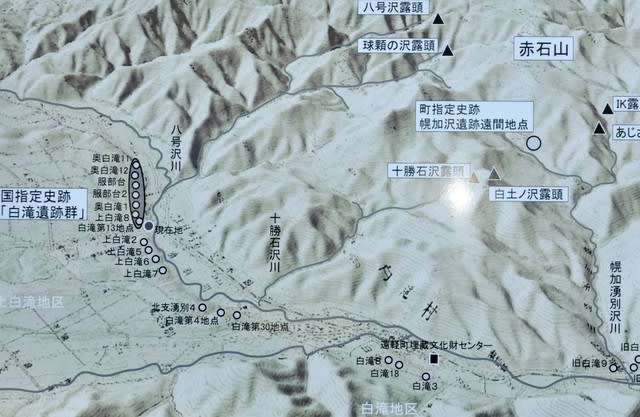
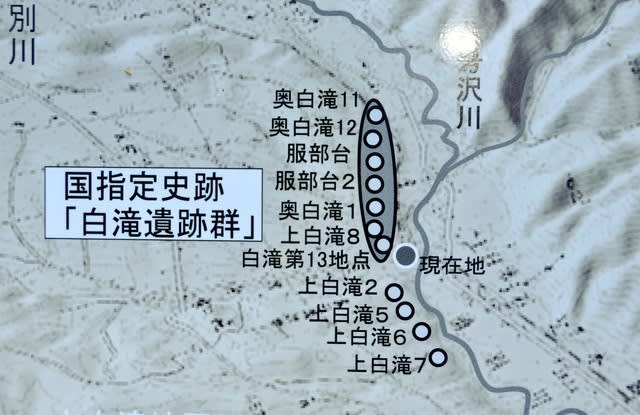
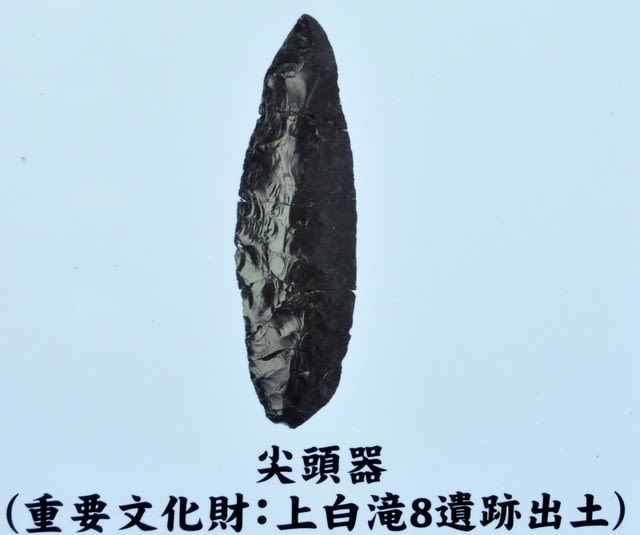






















 何度も現地に行っているうちに、石斧以外に新たなものがあることがー。
何度も現地に行っているうちに、石斧以外に新たなものがあることがー。