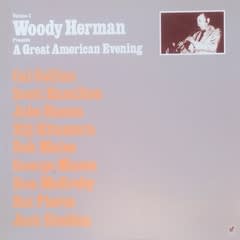Jazz Prose / The Fraser Macferson Quintet
今から30年近く前、全国各地でジャズフェスティバルが開かれた。大手企業が冠スポンサーになって、日本の有名グループだけでなく海外からも多くのミュージシャンが集まり、夏の風物詩のひとつとなっていた。最近ではこのようなフェスティバルもすっかり影を潜め、代わりに町興しの一環として、街を挙げてのジャズイベントが開かれるようになった。
東京では、新宿のトラッドジャズフェスティバルを始めとして、身近な所では阿佐ヶ谷ジャズストリート、練馬、そして我が家のある小金井でも規模は小さいが毎年開催されている。これらの、プロだけでなく地元のアマチュアも交えて楽しいお祭りは、東京だけでなく全国各地で数多く開かれているようだ。それだけ、身近にジャズを聴く機会は増えているのだが・・・。
昨年、ゴルフ帰りに宇都宮ジャズクルージングに寄ってみた。渡辺貞夫の出身地である宇都宮はジャズファンが多いのか、このイベントは年3回も開かれている。同時に10か所以上でセッションが行われ、地元のミュージシャンが多く、名前も演奏内容も分からないので初めて行くと、まずどこに行くかで迷った。
プログラムの中に、テナーの岡田嘉満と知った名前が見つかった。村田浩のビバップバンドの一員として、東京だけでなく全国を廻っているが彼の地元は栃木。普段は北関東を中心に活動をしているようで、東京ではなかなか聞く機会が無い。彼のように地方を拠点としているミュージシャンのライブ演奏を聴く機会は、たまたまその地を訪れた時以外ないものだ。
ローカルミュージシャンの演奏に出会う機会が少ないのは日本だけでなく万国共通。アメリカはともかく、ミュージシャンの絶対数の少ないカナダとなると尚更だ。
バンクーバーを拠点としていたフレイザーマクファーソンの演奏に惚れ込んだのは、コンコルドのカールジェファーソン。彼が自費出版で出したアルバムをコンコルドのカタログに載せ、新たにアルバムを作るためにバンクーバーにも乗り込んだ。その成果が前作のIndian Summerだ。そして、そのマクファーソンを今度はコンコルドジャズフェスティバルの舞台に引っ張り出した。ロンカーターとジムホールが出演した1984年のフェスティバルであった。
マクファーソンは単身バンクーバーからコンコルドへ。他のメンバーもギターのエドビケットとベースのスティーブウォレスはトロントから。コンコルドのホスト役でもあるデイブマケンナとジェイクハナはボストンからと、一緒に共演するメンバーは共に東海岸から集まった。
メンバーはかって一緒に共演した経験があり、演奏スタイルはジェファーソンが最も好むスタイルとなると、大舞台での演奏であってもほとんど打ち合わせやリハをすることなくプレーは始まった。テナーのスタイルはレスター派。日本で言えば、尾田悟といった感じのリラックスした演奏が続く。
メジャーな世界では無名であったマクファーソンも、地元バンクーバーのスタジオではファーストコールの存在。カナダでも賞を受賞する腕前であったが、レコーディングの機会には決して恵まれていなかった。そんな、ローカルの実力者にもレコーディングやフェスティバルの舞台に上がる機会を与えたのがコンコルドであった。商売っ気抜きで、好きなミュージシャンを追いかけるのがジェファーソンの道楽であったとも言えよう。
スタイルはフレイザーより多少バップスタイルだが、岡田嘉満のテナーも実によく歌うテナーだ。彼も自費制作のアルバムはあるようだが、今の時代なかなかメジャープレーヤーのアルバムでさえ制作できるレコード会社は無くなった。ローカルで活躍する隠れた名手のアルバムを作ろうというジェファーソンのようなマニアックなスポンサーはいないものかと思う。
1. You'd Be So Nice to Come Home To
2. All Alone
3. On a Slow Boat to China
4. Darn That Dream
5. Happy Man
6. I'll Never Be the Same
7. It Could Happen to You
8. There Is No Greater Love
Fraser Macfherson (ts)
Ed Bicket (g)
Dave Mckenna (p)
Steve Wallace (b)
Jake Hanna (ds)
Produced by Carl Jefferson
Recording Engineer : Phil Edward
Recorded live at The Concord Pavillion, Concord, California August 1984
Originally released on Concord CJ-269
今から30年近く前、全国各地でジャズフェスティバルが開かれた。大手企業が冠スポンサーになって、日本の有名グループだけでなく海外からも多くのミュージシャンが集まり、夏の風物詩のひとつとなっていた。最近ではこのようなフェスティバルもすっかり影を潜め、代わりに町興しの一環として、街を挙げてのジャズイベントが開かれるようになった。
東京では、新宿のトラッドジャズフェスティバルを始めとして、身近な所では阿佐ヶ谷ジャズストリート、練馬、そして我が家のある小金井でも規模は小さいが毎年開催されている。これらの、プロだけでなく地元のアマチュアも交えて楽しいお祭りは、東京だけでなく全国各地で数多く開かれているようだ。それだけ、身近にジャズを聴く機会は増えているのだが・・・。
昨年、ゴルフ帰りに宇都宮ジャズクルージングに寄ってみた。渡辺貞夫の出身地である宇都宮はジャズファンが多いのか、このイベントは年3回も開かれている。同時に10か所以上でセッションが行われ、地元のミュージシャンが多く、名前も演奏内容も分からないので初めて行くと、まずどこに行くかで迷った。
プログラムの中に、テナーの岡田嘉満と知った名前が見つかった。村田浩のビバップバンドの一員として、東京だけでなく全国を廻っているが彼の地元は栃木。普段は北関東を中心に活動をしているようで、東京ではなかなか聞く機会が無い。彼のように地方を拠点としているミュージシャンのライブ演奏を聴く機会は、たまたまその地を訪れた時以外ないものだ。
ローカルミュージシャンの演奏に出会う機会が少ないのは日本だけでなく万国共通。アメリカはともかく、ミュージシャンの絶対数の少ないカナダとなると尚更だ。
バンクーバーを拠点としていたフレイザーマクファーソンの演奏に惚れ込んだのは、コンコルドのカールジェファーソン。彼が自費出版で出したアルバムをコンコルドのカタログに載せ、新たにアルバムを作るためにバンクーバーにも乗り込んだ。その成果が前作のIndian Summerだ。そして、そのマクファーソンを今度はコンコルドジャズフェスティバルの舞台に引っ張り出した。ロンカーターとジムホールが出演した1984年のフェスティバルであった。
マクファーソンは単身バンクーバーからコンコルドへ。他のメンバーもギターのエドビケットとベースのスティーブウォレスはトロントから。コンコルドのホスト役でもあるデイブマケンナとジェイクハナはボストンからと、一緒に共演するメンバーは共に東海岸から集まった。
メンバーはかって一緒に共演した経験があり、演奏スタイルはジェファーソンが最も好むスタイルとなると、大舞台での演奏であってもほとんど打ち合わせやリハをすることなくプレーは始まった。テナーのスタイルはレスター派。日本で言えば、尾田悟といった感じのリラックスした演奏が続く。
メジャーな世界では無名であったマクファーソンも、地元バンクーバーのスタジオではファーストコールの存在。カナダでも賞を受賞する腕前であったが、レコーディングの機会には決して恵まれていなかった。そんな、ローカルの実力者にもレコーディングやフェスティバルの舞台に上がる機会を与えたのがコンコルドであった。商売っ気抜きで、好きなミュージシャンを追いかけるのがジェファーソンの道楽であったとも言えよう。
スタイルはフレイザーより多少バップスタイルだが、岡田嘉満のテナーも実によく歌うテナーだ。彼も自費制作のアルバムはあるようだが、今の時代なかなかメジャープレーヤーのアルバムでさえ制作できるレコード会社は無くなった。ローカルで活躍する隠れた名手のアルバムを作ろうというジェファーソンのようなマニアックなスポンサーはいないものかと思う。
1. You'd Be So Nice to Come Home To
2. All Alone
3. On a Slow Boat to China
4. Darn That Dream
5. Happy Man
6. I'll Never Be the Same
7. It Could Happen to You
8. There Is No Greater Love
Fraser Macfherson (ts)
Ed Bicket (g)
Dave Mckenna (p)
Steve Wallace (b)
Jake Hanna (ds)
Produced by Carl Jefferson
Recording Engineer : Phil Edward
Recorded live at The Concord Pavillion, Concord, California August 1984
Originally released on Concord CJ-269