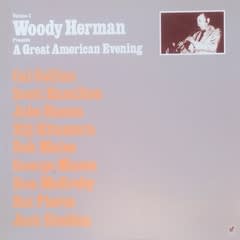Stand By For The Jack Sheldon Quartet
昔、スイングジャーナルの読者人気投票のランキングを見ると、ギターに植木等、トロンボーンに谷啓といった名前が並んでいた。コメディアンとして有名になったクレージーキャッツの面々であるが、以前はジャズを演奏していたミュージシャン達であった。コミックバンドを経て、それぞれの道へ進んだが、谷啓は、最後までテレビ番組でもトロンボーンのプレーを披露していた。
ジャックシェルドン、元々は‘50年代西海岸で活躍していたトランぺッター。50年代のウェストコーストで作られたアルバムには、コンボでもオーケストラでも彼の名前は数多く見かける。
しかし、60年代に入ると、テレビや映画に俳優、コメディアンとして登場し、活躍の場はすっかりテレビ中心に変った。テレビに出ている時もトランペットとボーカルを忘れることは無かったが、ストレートのジャズというよりは、ポピュラーな曲を演奏したり、子供番組の主題歌を歌ったり、その活動はジャズからはどんどん離れていった。
しかし、70年代に入ると、再びトランぺッターとしてスタジオワークを中心に活動を再開する。そして、ストレートなジャズの演奏も。ビルベイリーのビッグバンドに参加し、コンコルドのアルバムにもシェルドンの名前が見られるようになった。
そんな彼を、カールジェファーソンが放っておくことは無かった。
Concordレーベルは、ベテランの復帰の機会を提供する、ある種のリハビリの場のような存在であった。無理に今風の演奏を強い得ることなく、本人の意向を一番尊重し、ベストなプレーができる環境を常に用意していたので、ミュージシャンにとっては気負うことなく久々のプレーでも気楽に演奏できたかもしれない。
今回もコンコルドのハウストリオとでもいえる、トンプキンス、ブラウン、ジェイクハナがバックを務める。このトリオをバックに、シェルドンに「お好みのトランペットと歌をご自由にどうぞ」といった感じのセッションである。
ジャケットのテレビ画面を模したデザインも、シェルドンのキャリアを知っている人にとっては、意味が良く分かると思う。テレビではプレーヤーとしてよりも、長年Merv Griffin Showのミュージカルディレクターとして有名になってしまったシェルドンだが、今度のプログラムは「いつもお馴染みのシェルドンではなく、ジャックシェルドンカルテットがスタンバイしています」ということだろう。
そして、このカルテットの演奏は、ジェファーソンの思惑どおり、シェルドンのジャズプレーヤーとしての側面を再び全面的にアピールした内容となった。
トランペットを吹くボーカルといえばチェットベイカーが有名だが、タイプは異なってもこのシェルドンも両刀使いだ。このアルバムでも、トランペットとボーカルの曲を交互に配し、楽器も歌もどちらもメインとアピールしたかったのだろう。
基本的にはモダンスイング系のスインギーなトランペットであるが、曲に合わせてプレースタイルは微妙に変えている。バイバイブラックバードのトランペットというとマイルスを思い出してしまうが、ここでもミュートプレーで軽快に(もちろんマイルスのような鋭さはないが)、そしてシャドウオブユアスマイルでは、低音域でストレートなメロディーの美しさを訴える。バラードもスインギーな曲もご機嫌である。
歌の方も、余興で歌うといった感じではなく、最後の曲、The Very Thought of Youでは7分にも及んでじっくり歌い込んでいる。
この録音がきっかけだと思うが、翌月行われたウディーハーマン仕切りのジャムセッションにも参加している。
その後も、プレーや歌を継続して行くが、エンターテイナーとしてステージの楽しさも、演奏や歌に加えて人気を博した要因であろう。いずれにしても、才能豊かな人は、何かを極めるにしても他の分野での才能が助けになって大きく育つのは間違いない。
どんなに上手く演奏しても、ただ黙々と演奏するライブが楽しくないのは、そのようなキャラクターが影響するのかもしれない。
その当時のライブの様子↓
1. I Love you
2. Daydream
3. Cherry
4. Don’t Get Around Much Anymore
5. Bye Bye Blackbird
6. I’m Getting Sentimental Over You
7. Shadow of Your Smile
8. Get Out Of Town / Ours
9. Poor Butterfly
10. The Very Thought Of You
Jack Sheldon (tp)
Ross Tompkins (p)
Ray Brown (b)
Jake Hanna (ds)
Produced by Carl Jefferson
Recording Engineer : Phil Edwards
Recorded at Ocean Way Recording, Hollywood, California, March 1983
Originally released on Concord CJ-229
昔、スイングジャーナルの読者人気投票のランキングを見ると、ギターに植木等、トロンボーンに谷啓といった名前が並んでいた。コメディアンとして有名になったクレージーキャッツの面々であるが、以前はジャズを演奏していたミュージシャン達であった。コミックバンドを経て、それぞれの道へ進んだが、谷啓は、最後までテレビ番組でもトロンボーンのプレーを披露していた。
ジャックシェルドン、元々は‘50年代西海岸で活躍していたトランぺッター。50年代のウェストコーストで作られたアルバムには、コンボでもオーケストラでも彼の名前は数多く見かける。
しかし、60年代に入ると、テレビや映画に俳優、コメディアンとして登場し、活躍の場はすっかりテレビ中心に変った。テレビに出ている時もトランペットとボーカルを忘れることは無かったが、ストレートのジャズというよりは、ポピュラーな曲を演奏したり、子供番組の主題歌を歌ったり、その活動はジャズからはどんどん離れていった。
しかし、70年代に入ると、再びトランぺッターとしてスタジオワークを中心に活動を再開する。そして、ストレートなジャズの演奏も。ビルベイリーのビッグバンドに参加し、コンコルドのアルバムにもシェルドンの名前が見られるようになった。
そんな彼を、カールジェファーソンが放っておくことは無かった。
Concordレーベルは、ベテランの復帰の機会を提供する、ある種のリハビリの場のような存在であった。無理に今風の演奏を強い得ることなく、本人の意向を一番尊重し、ベストなプレーができる環境を常に用意していたので、ミュージシャンにとっては気負うことなく久々のプレーでも気楽に演奏できたかもしれない。
今回もコンコルドのハウストリオとでもいえる、トンプキンス、ブラウン、ジェイクハナがバックを務める。このトリオをバックに、シェルドンに「お好みのトランペットと歌をご自由にどうぞ」といった感じのセッションである。
ジャケットのテレビ画面を模したデザインも、シェルドンのキャリアを知っている人にとっては、意味が良く分かると思う。テレビではプレーヤーとしてよりも、長年Merv Griffin Showのミュージカルディレクターとして有名になってしまったシェルドンだが、今度のプログラムは「いつもお馴染みのシェルドンではなく、ジャックシェルドンカルテットがスタンバイしています」ということだろう。
そして、このカルテットの演奏は、ジェファーソンの思惑どおり、シェルドンのジャズプレーヤーとしての側面を再び全面的にアピールした内容となった。
トランペットを吹くボーカルといえばチェットベイカーが有名だが、タイプは異なってもこのシェルドンも両刀使いだ。このアルバムでも、トランペットとボーカルの曲を交互に配し、楽器も歌もどちらもメインとアピールしたかったのだろう。
基本的にはモダンスイング系のスインギーなトランペットであるが、曲に合わせてプレースタイルは微妙に変えている。バイバイブラックバードのトランペットというとマイルスを思い出してしまうが、ここでもミュートプレーで軽快に(もちろんマイルスのような鋭さはないが)、そしてシャドウオブユアスマイルでは、低音域でストレートなメロディーの美しさを訴える。バラードもスインギーな曲もご機嫌である。
歌の方も、余興で歌うといった感じではなく、最後の曲、The Very Thought of Youでは7分にも及んでじっくり歌い込んでいる。
この録音がきっかけだと思うが、翌月行われたウディーハーマン仕切りのジャムセッションにも参加している。
その後も、プレーや歌を継続して行くが、エンターテイナーとしてステージの楽しさも、演奏や歌に加えて人気を博した要因であろう。いずれにしても、才能豊かな人は、何かを極めるにしても他の分野での才能が助けになって大きく育つのは間違いない。
どんなに上手く演奏しても、ただ黙々と演奏するライブが楽しくないのは、そのようなキャラクターが影響するのかもしれない。
その当時のライブの様子↓
1. I Love you
2. Daydream
3. Cherry
4. Don’t Get Around Much Anymore
5. Bye Bye Blackbird
6. I’m Getting Sentimental Over You
7. Shadow of Your Smile
8. Get Out Of Town / Ours
9. Poor Butterfly
10. The Very Thought Of You
Jack Sheldon (tp)
Ross Tompkins (p)
Ray Brown (b)
Jake Hanna (ds)
Produced by Carl Jefferson
Recording Engineer : Phil Edwards
Recorded at Ocean Way Recording, Hollywood, California, March 1983
Originally released on Concord CJ-229