「astah*を使って、開発の要求仕様から、プログラム作成までを、トレーサビリティを保って、どのように開発するかを書いてみる」という、このシリーズ、以下の手順で説明する予定ですが、
(1)作るべきもののユースケースを書く
(2)ユースケースシナリオを書く
(3)ロバストネス分析
(4)バウンダリ(画面)、エンティティ(テーブル等)の属性を埋めていく
(5)バウンダリの項目を元に、画面構成を考える。
(6)(必要があれば)エンティティを正規化して、ER図にする
(7)フレームワークを決定する
(8)画面クラスをソースコードに書き直す
(9)エンティティをDBのテーブルと、DAOに書き直す
(10)コントローラーを書き直す
前回、(2)をやったので、今回は、「(3)ロバストネス分析」について。
■ロバストネス分析とは
ロバストネス分析の説明は、ここにあるとおり。
つまり、MVCみたいに、システムを
バウンダリ:ユーザーとの入出力
コントロール:バウンダリとエンティティをつなぎ処理する
エンティティ:保存すべきデータを管理しておく
の3つにわけます。
このバウンダリ、コントロール、エンティティは、3つの層と考えられ、
・同じ層の間
・お隣さんとの層の間
とは、やりとりできますが、
・間を離れた層の間
では、やりとり「できません」
つまり、バウンダリから、エンティティには、アクセス「できません」
これを、コミュニケーション図という形にまとめるのが、バウンダリ分析です。かんたんにいっちゃうと・・・
■本日のミッション
したがって、今日やるべき、ミッションは、前に書いたユースケース
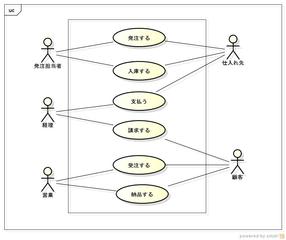
とユースケースシナリオをもとに、バウンダリ分析をして、

なコミュニケーション図を作ることです(上記例は受注のみ)。
■作り方
(1)ユースケース図は、コンピューターに「処理させたいこと」を書いているはずです。
ってことは、これは、処理=コントロールになります。
ってことで、各ユースケースを「~処理」という形にして、
迷わずコントロールにしましょう。
例:ユースケース:受注する→受注処理(コントロール)
(2)ユースケースシナリオを見てください。それに、画面入力・画面出力はありますか?
あれば、「~画面」として、バウンダリを書きましょう(~はユースケース名)
帳票も出力するのであれば、帳票のバウンダリも作ります。
例:ユースケース:受注する→受注画面(バウンダリ)
(3)引き続き、ユースケースシナリオを見てください。
画面から入力されたもの+保存されているデータを元に、
何らかの処理をして、
画面、帳票、保存すべきデータに出力
しているはずです。このとき、保存されている、すべきデータがエンティティとなります。
エンティティはたいてい名詞ですが、名詞が全てではなく、
ひとつひとつが区別して、管理できるものです。
なにかと、一緒になっていているようなものは、属性です
(「なにか」が、エンティティかも?)
ってことで、ユースケースシナリオの名詞に着目し、
・保存すべきデータで
・ひとつひとつ区別でき、管理すべきもの
をエンティティとしてあげて、記述します
なお、処理をしたり、保存しなくてよいデータを作成している場合、
それはコントロールです
他のユースケース名でなく(コントロールになることなく)、
重要で、かつ独立したものは、コントロールとして挙げておいていいです。
→挙げなくてもいいです。当コントロールクラスのメソッドにしますから・・・
(4)今書いた、コントロール、バウンダリ、エンティティに線を引きます。
バウンダリ - コントロール - エンティティ1
- エンティティ2
:
のような感じで、線が引かれると思います。
(5)メッセージを記入します。
ユースケースシナリオが、ここに書くことを意識している場合は、
たぶん、ユースケース1つ1つをぺたぺた貼ればいい感じだと思います
(Enterprise Architectのシナリオなどの場合)
こんでできあがり。
受注画面とか、めちゃくちゃ大雑把!と思うかもしれないけど、
とりあえず、これでいい。次回、詳しく書きます。

























