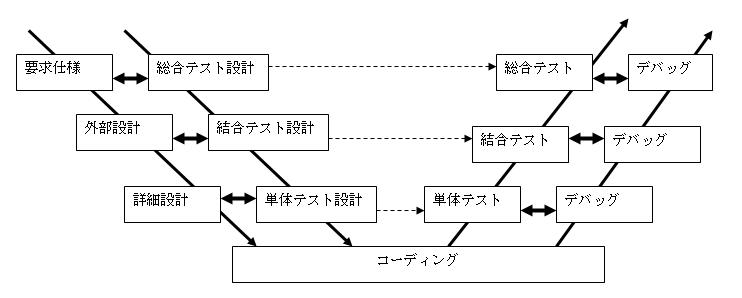午前中に、Flex SDK(Flexの無償の開発環境)のインストールをして、デバッグ環境ではみれるようになったけど、ブラウザごしに見たいので、
(1)Flash Playerをインストールしました。
(2)ダウンロードしたflexを解凍したフォルダの下にある、
runtimes\player\10.1\win\InstallPlugin.exe
をダブルクリックして、実行しました。
(3)再起動しました
再起動しないと、アイコンが変わらなかった。
そうしたら、サンプルで作ったswfが、ちゃんと、swf用のアイコンになって、ダブルクリックできた。
でも、もうひとつのInstallAX.exeのほうは、

なダイアログがでて、インストールできなかったけど、よかったのかな?
ま、いっか。
ちなみに、

ってこと。


















 「関連先」と「関連元」を選ぶ。このとき、タイプをかならず、「多」対「多」にしておくこと。
「関連先」と「関連元」を選ぶ。このとき、タイプをかならず、「多」対「多」にしておくこと。