20年位前、1980年代終わりごろから、最近まで、ソフト業界とかその周辺の変遷について、特にソフト開発の立場を中心に見て行く、土日シリーズ「失われた20年-ソフト業界は変わったのか?」その第4回目。
今、第三次オンが終わったころ(1980年代後半)について書いていて、今回は、そのころの開発方法論について書きたいと思います。
■要求分析、システム設計、詳細仕様化
当時の設計方法論は、「別冊インターフェース 実践ソフトウェア作法」(CQ出版社 1998)
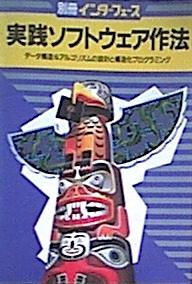
の18ページ(の図)によると、
要求分析→システム設計→詳細仕様化
と進むように書いてあります。
で、このシステム設計なのですが、これを、基本設計といったり、概要設計といったり、さまざまになっている。(さらに紛らわしいことに概念設計という言葉もありました)。
実際、上記、実践ソフトウエア作法の19ページの図に書かれているドキュメントの流れをまとめると、
1.基本要求書、システム提案書
2.基本仕様書
3.機能仕様書、構造仕様書、データ構造仕様書、操作仕様書
4.論理仕様書
と流れるかたちになっているのですが、基本仕様書の説明がこの段階では要求分析で明確になった問題を基本仕様という形で文書化するとありますので、基本仕様は、要求分析内ということになります。
一方、「南條優のSEパワーアップ システム速習読本」(学研 1992)
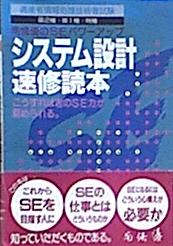
の39ページ、「システム設計の3段階」では、
第一段階 基本設計(概念設計とも呼ばれることあり)
第二段階 概要設計(外部設計ともいう)
第三設計 詳細設計
としています。
ただ、今も基本仕様=要求仕様といわれると、びみょーなところはあると思います。基本と概要の区別がいまより、明確ではないのよね。
そして、いまだと、「この要求文は、こう分析されるので、こうなり・・」という流れがはっきりしていたけど、むかしは、こういうドキュメントを作れば、まあ、かいはつできるんじゃねーかー?っていう流れだった(いまでも、そういう人は一部いるけど)気がします。
■当時は詳細設計があったのよね。。
当時は、詳細設計があって、さらには、コーディングも紙に書いていたのよね(世の中には、コーディング用紙というのも、売っていた)。
そして、そういう詳細設計を書く図があるのよね。。
各社でいろんなのがあった。富士通はたしかYAC?
■具体的な手順は
具体的な手順については、「情報システムの開発と設計」(株)東和コンピューターマネジメント著 1987
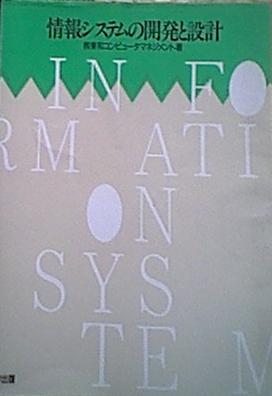
の目次に、おおまかにのっているので、その目次を出してきます
(2章から。6章まで。実際には、節の下に、さらに見出しがあります)
第二章 システム開発計画
第一節 システムの構想立案
第二節 現状の調査分析(機能調査)
第三節 新システムの期待効果について
第四節 データ中心設計
第五節 計画のまとめ
第六節 プロジェクト管理
第三章 概要設計(ロジカル設計)
第一節 システム機能の展開
第二節 出力設計
第三節 処理方式の選定
第四節 入力設計
第五節 コード設計
第六節 データ設計
第七節 システムの実効性を高めるために
第八節 システム概要のまとめ
第四節 詳細設計(フィジカル設計)
第一節 プログラム構造設計
第二節 出力詳細設計
第三節 入力詳細設計
第四節 物理データ設計
第五節 詳細設計のまとめ
第五節 システムの構築
第一節 モジュールの内部論理設計
第二節 コーディング
第三節 テスト・デバッグ
第六節 システムの運用
第一節 移行の実施
第二節 システムの評価
第三節 システムの保守
いまでも、基本設計、概要設計という言葉を使う人もいます。
この当時の流れをそのまま使っている人たちです。
ってことで、次回は、ちょっと時代を下げて、91年ころの様子を欠いていきたいと思います。



























