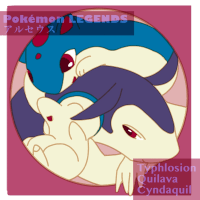ジョルジュ=クロード、クロード伯爵家の三男として生まれて17年。
今人生最大の危機的状況に陥っている。
普段なら声をかけることさえも憚られるほどの格上の人物から、これまた目を合わせることも大罪とされるような人物へのナイフ投げの指南役を任され、全身から滝のように流れ出た汗が、おそらく足元で水溜りを作っているに違いない。
(いっそそのナイフがこの僕の眉間を貫いてくれたら!)
そうだ。
自分が指南役に指されたのは、ナイフ投げの技術が優れているからでも教える技術に優れているからでもない。しがない伯爵家の三男。かたや、侯爵家の正統後継者。この権力関係において、何かの手違いがあっても(侯爵家の後継者の手元が狂って大惨事になっても)容易に処分することができる人物である、というただその一点のみだ。
それを分からないほど子供ではない。だが、指名に浮かれることも、竦むことも、ままならない責を背負うジョルジュに、後継者ミカヅキは淡々と接する。
「お前、かなり教えるのが上手いな」
と言われ、その言葉の真意が分からず、ひたすら恐縮するしかないジョルジュをどう思っているのか。ミカヅキは、「ダーツが得意なのか?」と尋ねてくる。
「い、いえ、得意、という、か」
得意ではないと言えば、そんな人物に指南役を任せたリオルドの立場がないだろう。
得意だと言えば、これまでこの倶楽部内で下の存在であることで居場所を確保してきた己の立場が危うくなるかもしれない。
(教えるより難しい)
と頭を抱える羽目になるとは。
実際、ダーツをするのはこれが初めてだ、というミカヅキに欠点を指摘する事は、それほど恐ろしいことではなかったと知る。
ミカヅキという人物は、そのやり方に難があることを指摘しても機嫌を損ねることは一切なく、素直にジョルジュの言葉に倣い、やってみせる。さらに今のはどうだったか?と自ら教えを乞うてくるのだ。そのやりとりを2、3繰り返して、ミカヅキは自分が劣っていることに拘らないようだと分かれば、教えること事態は容易かったものだ。
そのやりとりに対する言葉が、先のあれ。
「得意かどうかは、良くわかりません。ただ、初めてのあなた様より少しだけ経験がある分、お教えすることができる、というだけ、だと思います」
格上の人物に決して礼を失しない様、言葉を選んで選んで接する。これを間違えば、自分だけでなく、家にまで咎めは及ぶ。それだけの格の違いがある。まさに、雲の上の人、なのだ。同じ学校に通っていたとして、自分では声をかけるどころか、側に寄ることも考えられなかっただろう。
そんな人物が、ジョルジュの事を称えてくるのにはどうするのが正解なのか。
縋りたい存在はどこにもいない。皆、遠巻きに様子を伺っているようだ。
(誰か)
二年前、兄に連れられて「弟をよろしく」と紹介されたのは、ただここに出入りさせてやって欲しいというそれだけ。この場所の扉を開けて、次の一歩目から先はジョルジュ自身が己の裁量でのし上がっていかなければならなかった。
(僕には向かない)
序列に従い、大人しく下に控え、ただ家のためにリオルドという人物との繋がりを維持するだけが精一杯。そんな気弱な年少者を排除するでもなく、「ここでは何かをしないといけない、なんて決まりはないよ。ただここに居ることで周囲を理解していけば良いんだよ」と気にかけてくれていたサリスは今、リオルドの機嫌を取るのに必死な様。
(ただ居るだけで良いなら、と、思っていたのに)
この一連の事態を引き起こしているミカヅキはそれをどう考えているのか。
ジョルジュの精一杯取り繕った返答に、じゃあ何が楽しいんだ?と問うてくる。
楽しい遊戯だ。1日の仕事を終えて、学業を終えて、夜に集まって皆で騒ぐ。それぞれに趣味のあう仲間と、そこここで語らいながら。
「それは、やっぱり、点数を競い合ったりして」
勝った負けた、と陽気な声をあげて、もう一戦!と逸る。
それが楽しい遊戯だ、とジョルジュには思えない。ここに居たからこそわかる。それこそ、サリスが言ったように、周囲を理解したのだ。
競い合って。
上下関係を築いて。
力のあること、力のないことを体に叩き込む。遊戯ではない。社会だ。
「じゃあ、俺とやるか?」
というミカヅキは、この店の中に置いて頂点に立つ。その場所からジョルジュを相手に選ぶ。
「とんでもない!僕なんかじゃ、とてもお相手は務まりませんよ!」
「務まるかどうかなんて気にするな。俺なんかやっと前に飛ぶ様になった程度だぞ」
お前が下手だというなら丁度良いくらいだろ、というのにも必死で無理です、と返す。
誰も助けてはくれない。
的に当てる感覚を掴ませるためにミカヅキと二人、ダーツの的まで近づいた場所にいることでさらに孤立を深めていることに気づく。
もっと揉めていることがわかるくらい拒絶すれば、誰かが、…サリスが気づいてくれるだろうか。それとも、ミカヅキに恥をかかせた、と言って咎められるのだろうか。
(あの日)
まだここに出入りするようになって日も浅い頃、ダーツ勝負を促され、周囲の言葉に乗せられて相手より遥かに良い点数を叩き出してしまった恐怖が蘇る。ジョルジュよりも格上の、年長者だ。明らかに空気が変わる、一瞬で周囲が敵になる、それを肌で感じた恐怖。それを救い上げたのは、サリスの「おいおい君たちビギナーズラックを知らんか?」という明るい言葉と、その手から差し出されたグラス。誰しも経験があるだろう?と周囲を見回しながら、ジョルジュにおめでとう、と言ったサリスは。
「見事、ビギナーズラックを引き出したジョルジュと、その場を与えたグランドンに喝采を!」と周囲を囃し立て、「おめでとうジョルジュ、これで君も俺たちの真の仲間入りだな」と、祝福のグラスを空けろ、と促し、その場の空気を一変させた。
新参者にしてやられた倶楽部の常連たち、から、新参者を歓迎する年長者たちの余裕を引き出した。サリスに目配せされ震える手でグラスの中身を飲み干せば、皆が口々に何かを称えていた。あの苦さと、白々しさは一生忘れられない。
「なるほど、ビギナーズラックか」と言った相手は、揶揄するようにジュルジュに絡み、次もまたやろう、と言った。次もまた同じ様に点数を競い合うことができたら本物だよな、と暴力的なほど威圧を込めて。
それが全て。
あの日から自分は、生きる術を誤ることはしなかった。
それを、この人は分からないだろう。頂点から、その景色から、ジョルジュの様な小さな存在を視認することもないような場所にいる人には。
「分からないでもないが」
不意にそう聞こえて、過去の記憶に沈んでいたジョルジュは顔をあげる。
「俺とお前の立場から、同列に何かを成す、というのは壁があるのだろう、とは分からないでもない」
ミカヅキはそう言って、ジョルジュが捧げているナイフを手に取る。
「昔からそうだったからな。あ、気にするなよ、お前の何かを責めてるわけじゃない」
その言葉は何の感情も含まないように、静かだ。静かに、ジョルジュに何かを聞かせたいのだとわかるほど。
遊戯を嗜み人と関わることを目的とする場所には不似合いなほど静かにミカヅキは語る。
「お前は、手本でさえも投げなかった。ああ、先のアルフリートもそうだな。やり方を教えるなら、まずやって見せるのが手っ取り早い。それでも、それを選択しないくらい、お前たちと俺の間に壁があるのは、良くわかった」
昔からわかっていたと思っていたが、やはりわかっているのと実感するのとは違うな、とダーツの的を見る。
「俺はそれをぶっ壊したい」
「え?」
ジョルジュではなく的を向いての言葉だったので、聞き違えただろうか。粗野な言葉、それはどこに向かっているのか。
ジョルジュが不用意に上げた声に、ミカヅキが振り返る。
「俺は昔から一人だった。壁があることをわかっていて、壁ごと付き合うなんて器用なことはできなかった。やりたいとも思わなかったけどな。だから、やり方が分からない。この通り、お前と、ナイフ一つ投げ合うこともできない」
「あ」
相手を。
遊びの相手を希望されて。
それに答えられないのは自分だというのに。それを責めることなく続けられた言葉。
「けれど、サリスがそれで良いというから来たんだ」
サリスの名前を発した一瞬だけ、ミカヅキの視線はジョルジュの背後に振れた。
チラリと振れた視界に、おそらくサリスの姿を認めたのだろう。だがジョルジュはそれを共有できない。視線をミカヅキから離せなかったのは。
「初めてのことにやり方が分からないのは当たり前だから。ただ、居るだけで良い。それだけで違う。自分をそこに存在させるだけで、ずいぶん、違う。そう言うから来た」
サリスが、ジョルジュに言ってくれたことを、同じように言っていたと知って感じたのは親近感か。まさか、そんなはずは、と思っても目の前の人物から目を離せない。互いの関係は何も変わらない。変わったのは、意識か。
「俺としてはそんな面倒な人間が居るだけで周囲には迷惑なだけだろうと思うんだがな。…お前は、どう思う?ジョルジュ」
初めて自分と同世代の人なのだ、と意識し始めた人からそう問いかけられて答えられるはずもない。それもわかっているように、ミカヅキは笑ってみせた。
初めて、笑ってくれた。
何かを責めているのではなく、ただ自分の発言に失笑したように。
「いや、すまない。弄んだわけじゃない。お前の意見を聞いてみたいと思ったのは本当だ」
ただ今は早い、ともわかっている、と言って。
「だから、考えたことがないなら考えてみてくれ。また次の機会に、聞かせてくれたら嬉しい」
(嬉しい)
それは、次がまたあるということだ。
また、自分を指名して、交流を持ちたいという言外の約束。
(どうして)
遥か格上の存在が、名を呼ぶ事にも許しを乞うほどの存在である君が自分の意見を意識するのは。
「どうして」
「投げられるようになったから、せっかくなら教えてくれたお前と投げ合ってみたい」
礼だ、と言う。
礼なんて。
受け取れるほどの身の上じゃない。
「僕は、僕はただ言われるままに」
「それでも相手をしてくれたじゃないか」
リオルドが多くの者の中からお前を指名したのは意味がある、とミカヅキに言われ、言葉が出ない。
それは、何か事故が起きた時の保険で。
そんなことを口にできるはずもないジョルジュを、まじまじと見てミカヅキは断言する。
「厄介なこの俺の相手を務めるに相応しい、という評価だ」
(馬鹿な!)
頭を殴られたかのような衝撃に声も出ない。
「自信を持て」
(そんなこと)
わずかも逸らされないミカヅキの眼光に震えているのか。その威光に慄いているのか。ジョルジュは膝が震えるのを自覚した。
「周囲の評判が最悪の俺を、誰にでも預けるほどリオルドは愚かではない」
(この僕が、あのリオルド様に認識されているはずがない)
ミカヅキからすれば遥か格下のリオルドではあるが、彼もまた侯爵家の後継に名を連ねる人物なのだ。ただ家の名があってジョルジュは扉を開かれただけの繋がりでしかない。
それを知るはずもないミカヅキは断言する。
「これだけの人数を集めて、一つの倶楽部を長年維持する人物だぞ。俺は一目置いてる。それだけの人物に指名された、お前もだ」
こんなにも傲慢な物言いで、人を傅かせることのできる位格が、ジョルジュを認めている。あまりにも酷い現実感だ。震える声が、何かを吐き出している。
「僕は、あなたの相手もできなかった」
「ああ、気にするな。それだけ、俺の格は桁違いだ。滅多にお目にかかれないほどの高みだぞ。この店の誰とも次元がちがう、規格外だってことなら嫌と言うほどわかっている」
自分の位格を奢っているのか、揶揄しているのか。初めて言葉をかわしたジョルジュでは、到底理解も及ばない。
それでも。
「僕があなたに大差で勝利していたら、どうしましたか」
ミカヅキの戯言に付き合わされたように、滑りでた言葉はナイフよりタチが悪い。
ああいっそそのナイフが僕の眉間を貫いていてくれたら。
何度思ったかしれない。それに迷いなく重なる言葉。
「引き抜いていたな」
「え?」
「俺の元に引き抜いていた」
真っ直ぐな言葉。真っ直ぐな態度。それは一人を選んできた生き様が故の、真っ直ぐな軌跡。
ブレることなく、相手に向かう美しさは恐ろしさと紙一重。ナイフの様に、鋭い切先が光を放つ。
「次はなんとかお前に勝負してもらえる策を練ってくる。…ああ、もう少し当てられる様にもなってるはずだが」
と言ったミカヅキは不敵に笑ってみせた。
「このままリオルドの元に仕えたいというなら手を抜けば良い」
失望してやる、と言い。俺に引き抜かれても良いなら勝って見せろ、と言う。
そこにやっと掛けられた、外部からの干渉。
「ミカヅキ様、ダーツはお気に召しませんでしたか?」
と、ジョルジュの背後から現れたのはサリスだ。
「サリスさん」
「ああ、そうだな、一人で練習するなら家でもできるしな」
「そうですね、せっかくですし、もう少し人数を交えてできる遊びをしましょうか」
「そうするか」
とサリスの提案に乗ったミカヅキは手にしていたナイフを、差し出されたトレイに戻す。もう、ジョルジュへの関心は薄れたのか、こちらを見向きもしない。
そんなミカヅキの無情な態度にジョルジュを案じたように、サリスは慌ててジョルジュの肩を撫でた。
「よくやった、ジョルジュ。立派だったぞ」
その手のひらの重さ。
言葉の温かみ。
張り詰めていた何かが切れ、涙がこぼれ落ちた。
やり遂げたことへの安堵か、この先に待ち受けることに対する不安か。
ただここに居るだけで良い、とサリスに言われた同士。
方や、居るだけで何も起こさない生き方を選択した。
方や、居るだけで何かが起こってしまう生き方しかできなかった。
その存在を強烈に見せつけ、周囲を混乱させる。そんな面倒な人間が居るだけで、迷惑なだけだろうと思うんだが。
どう思う?ジョルジュ。
(分からない)
今のこの感情をどう持っていけば良いのか、自分には分からない。
(だけど、答えたい)
不甲斐ない自分の指南に、礼だと言ったあの人の問いかけに答えたい。
意見を聞かせてもらえたら嬉しい。そう言わせただけの熱量が自分にあると信じて、全力で応えたいという願い。
生きる術を見誤らないことよりずっと、大事なことだと思った。
次がいつくるとも知れないほど、住む世界がちがう。それでも言葉は通じ合う。
自信を持てと言われて希望を知る。
今はまだ、自分の栄誉のためにこのナイフを的に投げることはできないけれど。
(あの人に失望されない為になら、投げられるはずだ)
その意思が貫いた先に何が待ち受けているのか、今は分からない。遥か高みから延べられた手に縋りたいのかどうか。縋ったことで、あるいは跳ね除けたことで、今以上に恐ろしい事態に身を置くのかどうかも、知れはしない。
ただわかっていることは、一つ。
自分の力で投げたナイフの先に、未来はある。