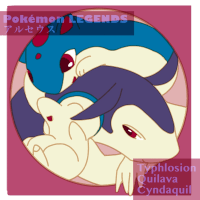(よし!!2分45秒!)
45秒になりたてでなく、46秒になる直前でもなく、真の45秒。
そんなものがあるとすれば…だが、今日の45秒は確かに45秒の真っ只中と言える…という冴えた確信があった。
モエギは極限まで意識を集中して、2分45秒でポットを取り上げ、紅茶をカップへと注ぐ。
主人の為に淹れるこの紅茶は2分47秒蒸らす、と教わっていたからポットを取り上げてからカップへと注ぐまでの2秒も考慮して45秒で蒸らし時間を切り上げてみたのだ。
(これなら文句はないだろう)
まさに完璧!という高揚感で給湯室を出たモエギは主人の待つ書斎へと向かった。
いつもどこかしらの家に招かれて接待を受けている主人には珍しく、午後はゆったりとした時間を書斎で過ごしている。
いつもなら主人に午後の紅茶を提供するのは執事のフローネストだが今日は不在だ。城下町にある医者の元へ定期検診の日なのだ。
こういった場合だけでなく、老い先短い自分がいつ不自由になっても主人には今まで通りの紅茶を、というフローネストの鉄の意志の元、モエギがそれを習うようになって1年ほど。
指導に従って主人好みの紅茶を淹れられるよう研鑽を積んできたつもりだが、いまだにフローネストから合格点をもらったことはない。
(何が違うんだか?)
何かが違うのだろうことは、わかる。
実際、主人はフローネストの淹れた紅茶と、モエギの淹れた紅茶を間違えたことはなかった。
(飲めりゃそれで良いんだけどな)
とモエギは思っているのだが、やはりこの家の養子に入っておいて紅茶の一つも満足に提供できないのはまずいだろう。
自分は、この家にあって実の息子ではない。
公に養子という対場ではあるが、それは主人との関係性においては、主従であると分かっている。
「伯爵様、入りますよ」
開け放された書斎に立ち入る直前に断り、トレイを持って中に入れば、窓際の長机にいたルガナ伯爵が手にしていた本を閉じ、「ではそちらへ行こう」と立ち上がる。
部屋の中央にある応接のローテーブルを示されて、モエギもそちらへと紅茶の用意をする。
午後の日差しが傾き始める頃、城から戻ったモエギが顔を出した時に、「紅茶を淹れて欲しいのだが」と言われてからさほど時間はかけなかったつもりだ。
それは主人であるクルートにも分かったようで。
「ずいぶん、手際よく動けるようになったな」
と言葉少なに褒めてくれるのは、素直に嬉しい。
「それはもう。フローネストさんの教育の賜物ですからね」
主人の身の回りの世話をすることに関しては厳しいフローネスト老に師事してきたのだ。
モエギが主人に褒められるという事は、すなわち、フローネストの手腕に他ならない。
それを弁えているのも、フローネストの教えだ。
決して驕ってはならない。貴族社会において主人の寵愛を一身に受ける事は身を滅ぼす。これはお前のためだ、と二人きりの時にいつも言い聞かせてくる厳格な老爺の言葉を、モエギはとても信頼していた。
「今日の紅茶は、ぜひともフローネストさんにも感想をもらいたいところなんですけど」
そう言いながら、テーブルに差し出した紅茶を勧めると、クルートは、「ほう」と興味深そうに微笑んでみせた。
「なるほど、今までになく香りがいい」
そう言ってクルートが茶葉の香りを楽しむ様子をただ待つ。
フローネストなら長年主人に仕えてきた経験から、茶の時間を所望する主人の気分に適切な茶葉を選ぶこともできるだろうが、モエギにはまだそこまでの技量はない。無難な茶葉を選んだのはやや逃げに走ったかな、とも自省するだけに、クルートが香りを気に入ったというなら、まずは合格点だろうか。
そう考えていると、「お前も確かめてみなさい」とクルートが向かいの席を勧めてきて、モエギは素直にそれに従った。
主人用と、自分用と。
自分のカップを取り上げて香りを確かめる。正直なところ、茶葉を蒸らす時間で変わるほどの香りの繊細さが分かるわけではない。
だからモエギはなるべく正確に、「これが主人の好みだ」と淹れられた紅茶の全てを数値化して、ギリギリまでその数字を追求しているだけのこと。あとは日によっての誤差。それもほんのわずかな。
…そう、今日の45秒のように。
だから、どうだね?とクルートに尋ねられても、何かしら自分の感想があるわけではない。
「…可もなく不可もなく、って感じですね」
とびきり良いとも、とびきり悪いとも思わない。
そう答えれば、クルートが笑う。
お前は正直だね、と言われて、モエギはカップをソーサーに戻した。
「伯爵様は?どうです?何か、違うってわかります?」
ここにフローネストがいれば即座に叱られているような事を聞いている自覚はあったが、今彼はいない。
そしてクルートは大概、自分で従者を叱りつけたりはしない。
少なくともモエギが彼の養子になって今まで、そんなところを見た事はなかった。
「そうだな。初めの頃と比べると、随分と良くなった」
「ええー、そんな…、茶葉も見分けられない昔と比べられてもな…」
そこは当たり前というか。いや、今でも大雑把にしか見分けがつかないが。少なくとも昔よりは銘柄も産地も頭に入っている。
「フローネストに感想をもらいたいほどの自信があるんだろう?」
「それはそうですけど。ただの自己満足かどうかを知りたいっていうか」
「明日も同じに淹れられるかい?」
「え、それは、…ちょっと無理、かな」
「ではそれが答えだ」
うーん。掴み所がないな、とモエギはクルートの言葉に不満を感じたが。
「あ、そうだ。点数。点数をください。フローネストさんの淹れたお茶が100点として」
モエギの淹れた紅茶を手に、ゆったりと背もたれに身を任せているクルートが可笑しそうに笑う。モエギの言葉を、そうやって軽くいなして、不遜を楽しんでいる。
彼が機嫌の悪い所を見せるのはモエギにではない。
「そうだな。では、80点、というところか」
「80、点」
掴み所のない主人の満足度を、わかりやすく数値化して、ますますわからなくなった。
80がいい点数か、悪い点数か。それはモエギの側とクルートの側と、見る方によっていくらでも評価を変えるだろう。
そう困惑する自分を持て余しているようなモエギの反応に、クルートが身を起こして、カップをソーサーに戻した。
「お前の現時点での最高点が80点。後の20点は、フローネストが今までこの屋敷に仕えてきた時間が積み上げた20点だ」
どうあってもモエギには太刀打ちできないものだ、とでも言うように。
おそらくフローネストも同じように言うだろう、と続けられて、モエギはがっかりする。
「はあ、そうですか」
「おや。最高点だと言ってあげたのに、不満かい?」
何が不満かと尋ねられて、モエギは自分の中にある正体不明の感情を探る。
努力している。フローネストにも、クルートにも、満足な自分を提供できるように、それはもう毎日努力しているつもりではあるが。
紅茶一つで、その努力を可視化しようとした自分の真意はどこにあったか。
点数で己の努力を計り、それが一つの区切りになると期待したのに、芳しくない結果に失望する。
結局。
「結局、褒められたいだけだったかな、って」
子供のような単純な欲望が見えただけで、期待したものは得られなかった。
そんな胸の内を晒せば、クルートは静かに微笑む。
「欲深いのは良い事だ」
私は嫌いではないよ、と言われてモエギが目をあげると同時に、お前のそう言うところがね、とクルートが続けた。
「そうでなくては、養子になどしなかっただろう」
それはいつもクルートがモエギにかける価値。
その価値があるからモエギはここに居られるという現実。
「その現実を守り抜くために、常に努力を怠らず、すべてに対して貪欲であれ。いつもお前に言ってきた事だ」
「はい」
「努力に終わりが欲しいかい?」
率直にそう尋ねられて、心はすぐさま反発を見せる。
「いえ、そういうのじゃなくて」
今の生活に疲れたとか、努力は無駄らしいとか、そういった感情はない。
なぜなら、クルートに迎え入れられて今日まで、モエギの努力に対する褒賞は常に十分すぎるほどに与えられてきた。
これ以上何を望むのかと問われても、すぐに答えを導き出すことは難しいだろうほどに。
「良いね。さらに努力を重ねられる何かが満ち足りないとでも?」
「さらに?」
「努力に終わりなどこない」
そう言い切ったクルートは正面からモエギを見据える。
「私はね、モエギ。お前と、レネーゼの後継者が手を組み、この家を乗っ取ろうとしているのだとしても一向に構わない」
「……」
静かな。しかし、確かな。
突然の衝撃。
クルートが何を言い出したのか、咄嗟にはわからなかったほどの。
「ええっ?!」
「そう驚くことかい?」
「驚きますよ!そんなこと、考えたこともない」
これは。
先日に、城でミカヅキと会っていたモエギの身辺を疑われているのか。
あの一件ならば、確かに、クルートに対してやましいことはあるのだ。
何らかの事故で幼馴染が、レネーゼの後継者の姿に成り代わった。その事を、モエギはクルートに秘めている。
これが他の人間なら即座に利用し、その利用価値をクルートに報告しているところだが、自分はどうにもあの幼馴染に弱い。
あの呑気な幼馴染が陰謀だの秘計だのに巻き込まれているのを見るのはあまり良い気がしないものだ。
たったそれだけのつまらない感情から、主人に対して秘め事を一つ抱える羽目になるとは。幼馴染の存在も、その秘め事を軽く扱えるだろうと考えた自分も、こうなっては呪わしい。
身の潔白を示せ、と主人に刃を突き立てられて身動きが取れなくなるほど、自分は甘かった。
それをどう覆せば良いか、と思考するモエギを押しとどめたもの。
それもまた、クルートの言葉。
「お前はまだ私を解っていないね」
そう言ったクルートの声音は、いつになく、優しかった。
それに困惑する。
いつもだいたい本心など悟らせないような完璧な微笑みを面に貼り付け、はるか高みから人々の動向を見下ろしては全くの無関心でいるのが、クルート・ルガナという貴族の有様ではなかったか。
「…伯爵様のことはあんまり解ったと思ったことはないですけど」
そんな困惑がこぼれたモエギの素直な言葉に、クルートが失笑する。
「おや、そうだったか。それは失礼」
楽しそうにひとしきり笑って見せてから、クルートは背もたれに身を預けた。
そこにはもう、モエギの知らない彼は姿を隠し、いつも通りの表情を見せる。
「私は、お前以上に貪欲なのだよ」
それは、知っている。
知っていると、思っていた。
「生きていく上で、努力の終わりは来ない。常に、全力で生きることに努める、それが人の宿命だ。野生を捨て、文明を選んだ人間の、生きるか死ぬかの戦いなのだと思っている」
野に放たれた命が常に死に脅かされるように、人もまた他者に、社会に、制度に、その命の行く末を脅かされている。
「それに安穏と身を任せているなど愚の骨頂。生きるための努力を怠るなど、醜悪の極み。」
お前もそれを知っているだろう、とクルートの言葉はモエギを脅迫する。
貧しい村で育ち、その日の暮らしも危うくして親を亡くし、親戚を頼り一人見知らぬ世界へ飛び出した。頼れるのは己だけ、その日の運命を左右するのは自分自身、そんな覚悟で生き繋いできた日々を知っている。この人は知っているのだ。だからこそモエギを拾い上げた。
「だからこそ、どんな事態も歓迎する。お前がミカヅキと手を組もうと、他の貴族に私を売ろうと、どんな手を使ってでも牙を剥くならそれを受けて立つ。それを裏切りだのと罵る気は一切ないね。お前もまた、生きるための戦いに身を投じたのだと、喝采をあげたいほどだ」
そのためにお前を育てている、とまで言われているようでモエギはその言葉にクルートの芯を見せつけられたことに気づいた。
「それではまるで」
まるで。
その先の答えを期待するようなクルートの視線。
言葉に出して良いのだ、と促す無言。
モエギは一呼吸ごとにクルートの思惑に吸収されるように身を乗り出していた。
「俺に殺されたがっているみたいに」
満足の笑みをたたえて。
「聞こえますけど」
モエギの言葉を受け止めたクルートが、狂喜に満ちたように見えた瞬間。
「まだまだ、お前程度にやられるとは思っていないがね」
と、穏やかに言葉を吐き出した。
その穏やかさは、確かにそれまでの場の空気にそぐわないものではあった。
知らず、呼吸さえも支配されていたかのような一時。
「だがそれに見合うほどに成長して欲しいと願っていることは確かだよ」
モエギは大きく息を吐き出す。
クルートの、何事もなかったかのような穏やかな様子に、一瞬の狂気は跡形もなく。
「それほどの覚悟無くして、この貴族社会で爵位を守っていられるものかね」
それほどに動じない。モエギ程度の小さな秘め事一つ、家を守る当主にとっては取るに足りないものなのだろう。
「だから、お前が誰と何を謀ろうと構わない。ミカヅキのあの変わり身も、お前の関わりがあろうとなかろうと、ただ私はそれを迎える用意がある、と言うだけだ」
「そんなに期待してもらっても、別に何もないですよ」
「ある方が良い、と言っているのに。つまらないことをいうものじゃないよ」
「…何らかの関わりは、持ちたいと思いますけど」
「まあお前は、謙虚なふりをして相当な野心家だと信じているよ」
と、紅茶のカップを手にし、「フローネストの教育の賜物とやらをね」などとからかわれては、まだまだ甘いと言われているようなものだ。
何をしても構わない、というクルートの本心は、モエギを育てるためのものでありながら、80点には到底満たないことを表している。
この家に仕える時間の積み重ねが20点。80点は最低条件。
「つまり、可もなく、不可もなく、ってことですね」
先ほどの同じセリフを、紅茶の入れ方ではなく、モエギ自身に対してのセリフとして言ってみる。
それも謙虚なふりだと思いたいね、と返され。
モエギもカップを取り上げた。
澄んだ美しい紅の色に、自身の顔が映り込み。
「だが、覚えておくんだね」
と、クルートの言葉が静かに紅に放たれる。
「主導の軸は常にお前自身が握っている事だ」
それが、何をしても構わない条件である、と言い含める。
モエギという一人の人間を手元で育て、主人にさえも牙を剥けと望むほどの執着は。
いっそ生への絶望のようにも感じられて、モエギは、紅に染まらざるを得なかった主人の境涯へと引きずり込まれていくのを感じていた。
「他人と手を組み敵対しようとも、お前が主導であるならば、それを招いたのは私自身の責任だと受け止めることもできるが」
他人にそそのかされ、己を見失い、命の主導を自ら手放すなどという最低な行為には侮蔑さえも生温い。
「お前が主導の軸を手放したと見做すその暁には、いっそ殺してくれと懇願するほどの報復措置をとる」
裏切りより、敵対より、はるかに許し難いという真意。冷酷にモエギを見据える彼に、親子の情はない。そんなものは必要ない。あるのはただ主従の絆し。
引きずり込まれた意識のそこで触れた主人の真意は、それでも、わずかもモエギを怯ませるものではなかった。
ずっと、以前より自分はそれを知っている。
生きるということは、自分以外の他者との戦いだ。
「殺してくれと懇願するくらいなら、自分でなんとかする方が楽ですね」
何を気負うでもなく、自然にそんな言葉が口をついて出ていた。
気づけば、クルートはいつも通りの微笑みを見せている。
それだからお前のことが嫌いではないよ、とつい先ほどにも聞いた言葉をあえてモエギに聞かせ。
「では、お茶をもう一杯、所望しようか」
「あ」
唐突に、この部屋の空気を現実にひきもどすクルートの言葉に、否応なく従いかけたモエギだったが。
「今度は100点の方を」と、主人の言葉は書斎の入り口の方へ向けて放たれた事に、モエギもそちらを見る。
この家を取り仕切る老執事が、ただ黙って一礼し、速やかにその場から姿を消した。