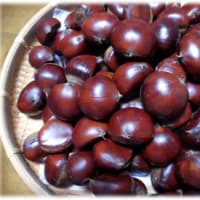今日はしろあと歴史館夏季企画展「たかつき古地図散歩ー描かれた村・山・川の風景ー」のお手伝いで『真上村絵図』を持って、学芸員とスタッフの会メンバー4名で、現在の真上地区を探訪して来ました。
先日も歩いたのですが、嬉しいことに古地図で古い道や水路、集落を歩けるのです。
今日の1枚の写真は、現在の住所は天神になっているのですが、絵図に載っている曹洞宗の黄牛山霊松寺(れいしょうじ)への参道「ねがひ坂」「かなへ坂」です。
黄牛山霊松寺(れいしょうじ)は、寺伝によれば、8世紀中頃行基菩薩が開創し、牛飼山地蔵院と称したが、応永19年(1412)、無月妙応禅師が老松(黄牛松)の下から現れた黄金仏を本尊の胎内に納め、堂宇を再興して霊松寺と改めました。
永禄元年(1558)正親町天皇の勅願所となり綸旨、勅額をご下賜されました。
天正年間(1573~1593年)に当時の高槻藩の藩主でキリシタン大名としても有名な高山氏の兵火に罹り諸堂宇を焼失しました。(この事については異論もあります)
江戸時代の寛永・享保年間に本堂や庫裏、鐘楼、山門などの堂宇を再建しました。現在の堂宇は平成3年に再建されたものです。
寺内に三好長慶の嫡男で、芥川城城主であった三好義興の自然石の墓「三好のカンカン石」や、江戸時代の高槻城主土岐定義公の墓が、境外には入江春正公の墓が現存し、高槻にとって縁が深く、昔の名残をとどめています。
その霊松寺の正面の坂は、往路は「ねがひ坂」、復路は「かなへ坂」と名付けられていて、これには「何か願い事を持って手を合わせに来られた方々がお帰りの際にはその願い事が叶いますように」との願いが込められているそうです。
JR高槻駅から10分ほどの所にありますので、ぜひお参り、お願いに来て下さい。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日5月25日(丙戌ひのえいぬ 友引)はこんな日です。
●「広辞苑記念日」
1955(昭和30)年のこの日、多くの人が頼りにしている岩波書店の国語辞典新村出編の『広辞苑』の初版が発行されました。
初版の編集には7年をかけており、登録語数は20万語で定価は2000円でした。
ちなみに、当時のコーヒーは1杯50円でした。
その後、50年以上にわたり発行され続けている『広辞苑』は約1000万部以上の大ロングセラーとなっています。
●「食堂車の日」
1899(明治32)年、山陽鉄道・京都~三田尻(現在の防府)で日本初の食堂車が走りました。
一等・二等の乗客専用で、メニューは洋食のみでした。
●「別所線の日」
長野県上田市の上田駅と別所温泉駅を結ぶ上田電鉄の別所線。その存続を目的に結成された「別所線の将来を考える会」が制定しました。
日付は別所線のシンボルとも言える丸窓電車の車輌ナンバー「モハ5250」の525からです。
電車内でのコンサートなど、さまざまなトレイン・パフォーマンスを行い、別所線の魅力を伝えていく日です。
●「主婦休みの日」
年中無休で家事や育児にがんばる主婦が、ほっと一息ついて自分磨きやリフレッシュするための休日が「主婦休みの日」で、1月25日、5月25日、9月25日が記念日です。
女性のための生活情報紙を発行する株式会社サンケイリビング新聞社が中心となり制定しました。
日付は年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みなどの主婦が忙しい時期のあとの年3日を設定したもので、日頃は家事や育児を主婦に任せがちなパパや子供たちが家事に取り組み、その価値を再認識する日との提唱も行っています。
●「有無の日」
第62代天皇・村上天皇の967(康保4)年の忌日です。
村上天皇は、急な事件のほかは政治を行わなかったからとのこと…。
村上天皇の在位した21年間の天皇親政により理想の政治が行われた時代として、醍醐天皇(第60代天皇)の治世と併せて、延喜・天暦の治と呼ばれています。
●毎月25日は、「天神の縁日」です。
![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は2029話です。「よかった!」と思われたら「季節・四季」ボタンをポチッとして下さい。