外れていたチューニング糸を元通りに取り付けので、次に筐体,シャーシ,,そして真空管などを掃除しました。まずは、先日トラクターや耕運機のタイヤに空気を入れたエアーコンプレッサーを利用して、積年溜まったゴミをエアーで吹き飛ばしました。
その後、エアーでは取れない汚れを濡れティッシュや雑巾を使って拭き取りました。真空管も規格番号が分かるようにガラス表面の汚れを拭きとりました。その結果、電源を入れるとほんわりとカソードが赤熱するのが分かるようになりました。
エアーコンプレッサーのエアーで積年のゴミを吹き飛ばす 
私が中学生の頃まで真空管が全盛期でした。産業的にはトランジスタがすでに普及し始めていましたが、私のような素人にはまだまだトランジスタは高根の花でした。私が初めて手に入れた半導体はセレン整流器でした。トランスにその整流器を繋いで直流の電源を作っていました。
そもそもトランス自体が新品はとても高価でした。そこで、毎日のようにゴミ捨て場に通いました。運が良いと、捨ててある壊れた真空管ラジオを発見します。思わず歓声を上げていました。タダでトランスや真空管が手に入るのです。こうして部品を手に入れていました。ゴミ捨て場は宝の山だったのです。
拭きとり前の汚れた真空管 拭き取り後の真空管12VA6

トランジスタを初めて購入したのは中学二年生の頃でした。通信販売で二個(2SB111)購入しました。そして、そのトランジスタで夏休みの課題として金属探知機を製作しました。しかし、どうしても動作しないのです。後で誤りに気が付きました。購入したトランジスタは低周波用だったのです。金属探知機として動作させるためには、455KHzの高周波で発信してビート音を出さなければなりません。つまり高周波用トランジスタを使わなければならなかったのです。当時、高周波や低周波などの知識が足りませんでした。
真空管のガラス部を掃除 ほんのりと赤熱するカソード

最新の画像[もっと見る]
-
 今年度も始まった放課後学習 成器塾
15時間前
今年度も始まった放課後学習 成器塾
15時間前
-
 インド藍の苗を畑に植え付け
2日前
インド藍の苗を畑に植え付け
2日前
-
 真夏に備えてハンマーナイフモアで草刈り
3日前
真夏に備えてハンマーナイフモアで草刈り
3日前
-
 野生のミツバチが我家にお引越し
4日前
野生のミツバチが我家にお引越し
4日前
-
 ジャンボニンニクを収穫し、軒下で乾燥
5日前
ジャンボニンニクを収穫し、軒下で乾燥
5日前
-
 藍畑の草刈り。ごめんなさいキジさん
6日前
藍畑の草刈り。ごめんなさいキジさん
6日前
-
 ほぼろを編むための駒を新たに作る(2/2)
7日前
ほぼろを編むための駒を新たに作る(2/2)
7日前
-
 育苗中のカボチャとマクワウリの苗を植える畑を耕運
1週間前
育苗中のカボチャとマクワウリの苗を植える畑を耕運
1週間前
-
 藍染めに備え、藍の苗を植え替え (3/3)
1週間前
藍染めに備え、藍の苗を植え替え (3/3)
1週間前
-
 ほぼろを編むための駒を新たに作る(1/2)
1週間前
ほぼろを編むための駒を新たに作る(1/2)
1週間前
「古ラジオ修理工房」カテゴリの最新記事
 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4)
昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4)
昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4)
昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4) 古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2)
古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2) 古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x)
古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x)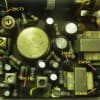 SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x)
SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(6/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(6/x)















