最後に電源周りの回路を調べてみました。整流管は懐かしい12Fです。この真空管は、私が中学生の時にスタンダードな半波整流管でした。直熱管で、電源が入るとほのかにヒーターが赤熱します。10分程度経つと真空管は暖かくなります。昭和30年代、火鉢しかない私にとって密かに手を温める暖房でした。そこが、真空管が好きな理由の一つです。
さて、整流周りの回路で特徴的なのは、巨大な箱型平滑電解コンデンサです。四端子の電解コンデンサでした。子供の頃、この箱型電解コンデンサを分解し、巻かれた茶色の油紙に挟まれたアルミ箔を取り出して遊んでいました。
懐かしい半波整流管12F、直熱管のほのかな赤熱が暖かい
このラジオの平滑回路は極めて平凡でした。整流時の波形を平滑するために、チョークではなく抵抗が使われていました。配線を調べていると、人が手を加えられたことが分かりました。その一つが、平滑用電界コンデンサです。端子の一つが切断されていました。ショートしたか容量低下したのではないかと思われます。箱型の平滑コンデンサの容量は、初段が6μFで平滑抵抗後の2段目が4μFでした。容量が低いのでハム音が大きかったのではないかと思います。この平滑コンデンサは廃棄します。新しく購入して、かつ容量の大きいもの(10~30μF 耐圧350V)にしようと思います。
平滑回路部の配線 切断された平滑コンデンサ端子

回路図を調べていますが、私が中学生の頃に作った並三ラジオより古いようです。そのため、特にコンデンサ類は容量が低いにも関わらず大きいのです。容量も減っているかも知れないため、すべてのコンデンサは新しいものに交換します。なかでも困ったのは、大きな箱のような形をしている四端子平滑用電界コンデンサです。箱型の電解コンデンサはもう売っていないと思います。そのため、円柱型の電解コンデンサに取り替えます。
これで、回路図を調べ終わりました。シャーシ内の素子をいったん全て取り払って綺麗に掃除します。そして、あらためて抵抗やコンデンサ類を取り付けようと思います。仕事の合間の気が向いた時に、のんびり作業しようと思います。
電源部の回路、真空管12Fによる半波整流と平滑回路
最新の画像[もっと見る]
-
 今年度も始まった放課後学習 成器塾
3時間前
今年度も始まった放課後学習 成器塾
3時間前
-
 インド藍の苗を畑に植え付け
1日前
インド藍の苗を畑に植え付け
1日前
-
 真夏に備えてハンマーナイフモアで草刈り
2日前
真夏に備えてハンマーナイフモアで草刈り
2日前
-
 野生のミツバチが我家にお引越し
3日前
野生のミツバチが我家にお引越し
3日前
-
 ジャンボニンニクを収穫し、軒下で乾燥
4日前
ジャンボニンニクを収穫し、軒下で乾燥
4日前
-
 藍畑の草刈り。ごめんなさいキジさん
5日前
藍畑の草刈り。ごめんなさいキジさん
5日前
-
 ほぼろを編むための駒を新たに作る(2/2)
6日前
ほぼろを編むための駒を新たに作る(2/2)
6日前
-
 育苗中のカボチャとマクワウリの苗を植える畑を耕運
1週間前
育苗中のカボチャとマクワウリの苗を植える畑を耕運
1週間前
-
 藍染めに備え、藍の苗を植え替え (3/3)
1週間前
藍染めに備え、藍の苗を植え替え (3/3)
1週間前
-
 ほぼろを編むための駒を新たに作る(1/2)
1週間前
ほぼろを編むための駒を新たに作る(1/2)
1週間前
「古ラジオ修理工房」カテゴリの最新記事
 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4)
昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4)
昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4)
昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4) 古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2)
古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2) 古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x)
古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x)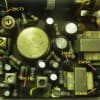 SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x)
SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(6/x)
真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(6/x)
















以前ラジオの修理の件でお伺いした者ですが、恐縮ながら現在見ていただくことは可能でしょうか。
引き続き情勢を見守りたいと思います。