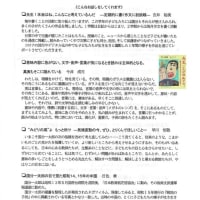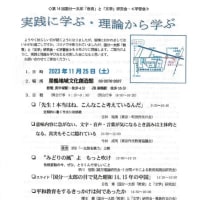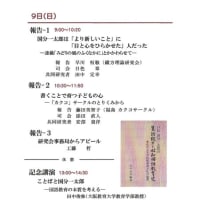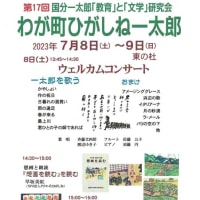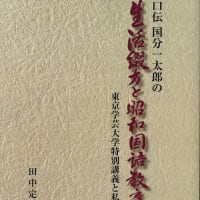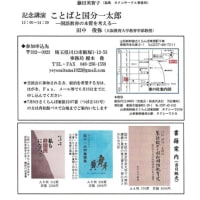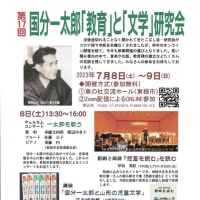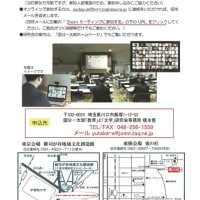北に住むひとのこころ―(4)
七
「蕎麦切」の文章は、ある日、ある時の出来事をつづったものではない。田中定幸の近著『作文指導のコツ』〈全三巻〉の分類では「いつも型」にはいる。くりかえしあったこと・たび重なる経験を、国分一太郎が書いた文章にあたる。
したがって書き出しは「奥羽線楯岡駅から西へ最上川をわたってすこし行く大久保の…」とはじまり、「そばきり」名人の芦野勘三郎じいさん、あとつぎの又三・能子夫妻と親しくしてもらっていること。また、そこへ足繁く通うきっかけについてもふれて、それをまとめて書いている。
つぎの段落では、話を勘三郎じいさんにすすめている。勘三郎じいさんと、書き手国分一太郎との関係をあらわす象徴的なことばである「お前のあたま、カッパのようにまんなかだけはげたなあ」という会話を、くりかえし交わされたこととして書いている。あわせて、勘三郎じいさんにたいする思いを、しっかりと書いている。
「ここに来て、…」というところで、話が、核心にふれていく。「私がまなぶのは、あとつぎの又三氏の守旧のこころである」と書いていく。ここから「日本経済新聞」に掲載したときには、題にしていることが分かる。テーマを示してもいる。「守旧のこころ」を国分一太郎がどんなことから感じたかを、書いている。
つぎの段落は、「…よりいっそうほめる」をうけて、「それ以上に」とさらに強調して、そのよさをあげている。朝早く起きてつめなければならない「おがくずがま」のことをとりあげている。「おがくずがま」をつかうことこそ、守旧のこころであり、このかまでゆでた「そば」だからこそうまいのだとほめる。
最後の段落では、「つゆ」についてもふれている。「あらきそば」の「そばつゆ」が日本のどこの「そばつゆ」よりおとっているとはけっしておもえないと書いている。
子どもたちと読むときには、段落ごとに番号をふっておいてやる。そして、今、読みすすめてきたように、ていねいに段落ごとに書かれている内容にふれながら読んでいく。
そして、国分一太郎のかいた「蕎麦切」は、日ごろから、親しくしてもらっている又三・能子夫妻が、守旧のこころを持ち続けていることのすばらしさを、ところどころに自分の体験をもりこんで書いたものであることをつかませる。だからこそ、おいしい「そば」ができるのだと、この作品のテーマをつかませる。「三段法」の作品読みの、①の部分が、これにあたる。
つぎに、「表現の方法・技術」というところに目をむけていく。「目のつけどころ(1)」である。ここには〈○組みたてかた〉〈●こまかい書きつづりかた〉の二つの観点があった。
〈○組みたてかた〉については、テーマをつかむための、読みが生きる。したがって、「書き出し」の部分では、「そばきり」の名人のいるそばやについて、2段落目では、名人、勘三郎じいさんのこと、三段落では、又三氏の守旧のこころ、四段落では「それ以上に」と、さらにこころをうたれること、を書いている。…というように、その段落の下に、要点をまとめていくようにする。
もう一つの〈●こまかい書きつづりかた〉については、つぎのようなことに着目するように期待する。三段落であったら、
・「ここに来て、私がまなぶのは、‥‥である。」と、はっきり書いている。
・「又三氏はおごらない。」と、短く書いている。
・「ここのそばがどんな(・・・)に(・)有名になっても」の「使い方がよい。
・「このならわしをそのまま守っている」と書いて、守旧のことばをおぎなっている。
・守旧のこころであることがらを、短い文で、たたみかけるように書いている。…この段落で伝えたいことを、的確 にえらんでいる。
・「板そば」だけの「だけ」が生きている。…「板そば」が強調されるし、ほかのそばは扱ってないことがわかる。
・「なかみが、おじいさん以来の秘訣のままなのを私はよりいそうほめる」と、書いている。
…の部分は、その理由である。よい、といってとりあげたときには、その理由をみんなに伝えてもらうようにしている。
着目する点をあげればきりがないので、この段落の、上段にはどんなことを思いうかべて読んだかを書いてみる。
*おそばやさんに来てもまなんでいるのですね。
*「守旧のこころ」―だれも気づかないようなところに、いつも目をむけている。
*「いつ行っても」とそのときだけでなく、ふだんから又三氏や店の様子をよくみている。
*「外便所だけが…」と、変わったところも見ている。
*「それといっしょに」と考えたのがおもしろい。
*蕎麦屋さんだから、そばのなかみのことをしっかりととらえて、評価している。
と、こんなふうになる。「外便所だけがきれいにできている」「その便所を私はほめる」子どもだったら、なぜ、ここに便所がでてくるのか疑問をもつかもしれない。
けれども、「守旧のこころ」の奥には、お店に来るお客さんによろこんでもらうこころがかくされている。便所のことで「不便」をかけては申し訳ないと又三氏は思っている。だから、ここは新しくする。そのこころがわかっているから国分一太郎は、「その便所を私はほめるとかく。この目のつけどころがすごい。そして、「それといっしょに」、便所といっしょに、そばやにとっては一番だいじな「なかみ」にふれている。ここが、おもしろい。
次の「それ以上に、」とつづく、つぎの段落の書きぶりはどうだろう。
・「それ以上に」と書いている。前の段落を意識して、つないでいる。
・「おがくずがま」のことを書いている。
・「朝早く起きて、まずやることが…」、そのたいへんさにふれるように書いている。
・能子さんのことばとして書いている。
・つきかために使う、昔の餅つききねのことを書いている。その変化を書いている。
・この家に行く(・・)たび(・・)に(・)私は見せてもらう。と書いている。くりかえす、行動として書いている。
・「もらった」と書かないで「もらう」と書いている。現在・未来形をつかって、これからも見ることをあらわして いる。
・「そして」が、生きている。
・「いまさらのように」と書いている
・うまさを…あじわう、とくり返しする「行動」として書いている。
・「守旧のこころ」を一番かんじる、「おがくずがま」にかかわることを、くわしく書いている。
こういったことに目をむける。なぜよいかは、ここではふれない。
では、上段には、どんなことばが結果としてはいったのだろう。
*ひとがあまり気にかけないような、「おがくずがま」にも、いつも目をむけている。
*くりかえし言う、能子さんの話を大事な事としてきいている。
*訪ねていくたびに、「見せてもらう」と考えている。
*そばのうまい理由を、しっかりととらえている。
ここでは、くりかえし経験したことを書いた文章であるので、国分一太郎の「へいぜいの=つねひごろの・ふだんの」見方、考え方のよさ、するどさ、変化や経過をとらえる姿勢・態度のすばらしさを感じる。
後半は、しばらくたって訪ねた「あらきそば」でのことーーある日、あるときの出来事、すなわち「ある日型」の文章――がつづられている。前半で、「おまけにこのごろその中身も弱ったようす」と書いていた勘三郎じいさんがなくなったことが記され、法号のことにもふれながら書きすすめている。「この小文をかいてしばらくたったあと」と書いて、白居易の詩を入れながら書いているが、「はじめ」「なか」「おわり」と「ひとまとまりの文章」を書く指導を大切にしてきた国分一太郎にいわせれば、この部分は、「やがて息子の又三さんは」につなぐ、前置きでもあるし、守旧のこころを又三さんが、勘三郎じいさんからひきつがれていることを思っているから、こう書いたにちがいない。
子どもには、「あらきそば」を訪ねたことから書きはじめていますねと、「はじめ」を意識させるとともに、じっくり読んだあとでは、「法号」「白居易の詩」「あのじいさん」「藁屋根の家」、こういた単語を一つひとつおさえさせて、「はじめ」を、こう書いた国分一太郎のおもいについても、想像させたい。
「やがて息子又三さんは、あらためて、いずまいを…」と書かれている。この文章は「ある日型」の文章であり、「時系列」で書かれている。内容と「組たてかた」は、このくらいにして、「こまかい書きづづりかた」を見ていく。それをあげるならば、
・「あらためて、いずまいをなおすようにし」と、中止めをつかい、さらに、「そばで寄りそってすわった能子夫人 と」、ふたりの行動を書いて、夫妻が同じ気持ちでいることを表している。
・「そばに寄りそうようにすわった」と書くことで、よりいっそう感じる。
・「いずまいをなおすように」と、状況にあったことばを選んで書いている。
・話すときの様子について書いている。
・カギ括弧をつかって、会話をうつしている。このことばは、どちらがいったかはわからないが、前の文にふたりの 行動を書いたことと、「能子夫人とこもごもに」ということから、ふたりの気持ちを伝えている大切なことばであ ることがわかる。
・「おどおどするおももちで」としたときの、表情を書いている。
・「つぎのようであった」と、つぎの段落へのつながりを説明している。
・「せっかく書いてくださったけれども」や「あれは」という表現で、前に書いてあることを思い浮かべさせ、短 く、適切に表現している。
・語る内容をまとめて書く一方で、もっとも重要な、そのひとたちの思いを、そのままの会話表現で書いている。
・「もったいないことである。」と、話をうけとめて思った気持ちをすなおに書き表している。
・「おふたりの純粋きわまりない心根に感動し」と、つぎの「いいえ、いいえ」につなぐように書いている。
と、少し理由をつけたすかたちで、その表現のよさをとりあげるとこうなる。
上段にあたる、目のつけどころ(2)の「生活態度・姿勢」「認識・操作の方法」は、こうなった。
●又三さん、だけでなく能子さんの様子にも目と心をむけていたのですね。
●ふたりのしぐさを、よく見ていましたね。
●はなしはじめたことばに、よく注意しましたね。
○「…、こうである」と、前おきをして、まとめてあらわすこともできるのですね。
●長いことばを、一言ひとこと、よくきいていたのですね。
○人のはなしを、ふだんからよく聞くことができるのですね。よい性質が身についていますね。
○ここまでのはなしはこうなのだと、まとめることができるようになったのですね。
●そのおわびは、「もったいないこと」と感じたのですね。
○ふだんから、感動する、素直な心をもっているのですね。
ふだんからの習慣で、子どもむけのことばになってしまったが、こうである。また、それを、「○つねへいぜいの生活ぶり」と「●その時々のからだの動かしかた・行動」に分けて示した。
さらに、国分一太郎は、この「三段法」においては、目のつけどころ(1)と(2)を結合させて読むことこそが「つづりかた教育の独自性」だとして大事にする。
はじめは、どう書かれているか、文そのものに目を向ける。「先生、どうか、ゆるしてけらっしゃい。そのかわり、プロパンガスの火のもやしかたに注意して、いままでと、けっして変わらない、そばのゆでかたをするつもりだからっす」と、会話を書いていることに目をつける。カギ括弧をつかって会話を書いたこと。その会話を書いたことによって、話し手が、どんなことに対して、どう思っているか。これからどうしようとしているか、会話のもっている意味を理解させる。それによって、この日の出来事、書き手の伝えたいことが生き生きと伝わってくることをおさえる。
そして、こういう会話が書けたのはなぜかと、子どもたちに考えさせる。読んでいるうちに、気づかせたりもする。
☆長い会話を、よく思い出して書けたのは、そのとき、その場所で、よく聞いていたからだ。
☆その時の様子をよく思い出して書けたのは、よく目をはたらかせて、見ていたからだ。
☆「おふたりの純粋きわまりのない心根に感動し」と、書けたのは、ふだんから、すなおなやさしい気持ちで接する ようにこころがけてきたからだ。
こう考えさせたり、気づかせたりすることで、文章表現力も、こころの成長もはかることができる。そのためにも、「三段法」による文章のみかたを、実際に作品をよむことを通じてできなければならないと、国分一太郎はいうのである。 (つづく)
七
「蕎麦切」の文章は、ある日、ある時の出来事をつづったものではない。田中定幸の近著『作文指導のコツ』〈全三巻〉の分類では「いつも型」にはいる。くりかえしあったこと・たび重なる経験を、国分一太郎が書いた文章にあたる。
したがって書き出しは「奥羽線楯岡駅から西へ最上川をわたってすこし行く大久保の…」とはじまり、「そばきり」名人の芦野勘三郎じいさん、あとつぎの又三・能子夫妻と親しくしてもらっていること。また、そこへ足繁く通うきっかけについてもふれて、それをまとめて書いている。
つぎの段落では、話を勘三郎じいさんにすすめている。勘三郎じいさんと、書き手国分一太郎との関係をあらわす象徴的なことばである「お前のあたま、カッパのようにまんなかだけはげたなあ」という会話を、くりかえし交わされたこととして書いている。あわせて、勘三郎じいさんにたいする思いを、しっかりと書いている。
「ここに来て、…」というところで、話が、核心にふれていく。「私がまなぶのは、あとつぎの又三氏の守旧のこころである」と書いていく。ここから「日本経済新聞」に掲載したときには、題にしていることが分かる。テーマを示してもいる。「守旧のこころ」を国分一太郎がどんなことから感じたかを、書いている。
つぎの段落は、「…よりいっそうほめる」をうけて、「それ以上に」とさらに強調して、そのよさをあげている。朝早く起きてつめなければならない「おがくずがま」のことをとりあげている。「おがくずがま」をつかうことこそ、守旧のこころであり、このかまでゆでた「そば」だからこそうまいのだとほめる。
最後の段落では、「つゆ」についてもふれている。「あらきそば」の「そばつゆ」が日本のどこの「そばつゆ」よりおとっているとはけっしておもえないと書いている。
子どもたちと読むときには、段落ごとに番号をふっておいてやる。そして、今、読みすすめてきたように、ていねいに段落ごとに書かれている内容にふれながら読んでいく。
そして、国分一太郎のかいた「蕎麦切」は、日ごろから、親しくしてもらっている又三・能子夫妻が、守旧のこころを持ち続けていることのすばらしさを、ところどころに自分の体験をもりこんで書いたものであることをつかませる。だからこそ、おいしい「そば」ができるのだと、この作品のテーマをつかませる。「三段法」の作品読みの、①の部分が、これにあたる。
つぎに、「表現の方法・技術」というところに目をむけていく。「目のつけどころ(1)」である。ここには〈○組みたてかた〉〈●こまかい書きつづりかた〉の二つの観点があった。
〈○組みたてかた〉については、テーマをつかむための、読みが生きる。したがって、「書き出し」の部分では、「そばきり」の名人のいるそばやについて、2段落目では、名人、勘三郎じいさんのこと、三段落では、又三氏の守旧のこころ、四段落では「それ以上に」と、さらにこころをうたれること、を書いている。…というように、その段落の下に、要点をまとめていくようにする。
もう一つの〈●こまかい書きつづりかた〉については、つぎのようなことに着目するように期待する。三段落であったら、
・「ここに来て、私がまなぶのは、‥‥である。」と、はっきり書いている。
・「又三氏はおごらない。」と、短く書いている。
・「ここのそばがどんな(・・・)に(・)有名になっても」の「使い方がよい。
・「このならわしをそのまま守っている」と書いて、守旧のことばをおぎなっている。
・守旧のこころであることがらを、短い文で、たたみかけるように書いている。…この段落で伝えたいことを、的確 にえらんでいる。
・「板そば」だけの「だけ」が生きている。…「板そば」が強調されるし、ほかのそばは扱ってないことがわかる。
・「なかみが、おじいさん以来の秘訣のままなのを私はよりいそうほめる」と、書いている。
…の部分は、その理由である。よい、といってとりあげたときには、その理由をみんなに伝えてもらうようにしている。
着目する点をあげればきりがないので、この段落の、上段にはどんなことを思いうかべて読んだかを書いてみる。
*おそばやさんに来てもまなんでいるのですね。
*「守旧のこころ」―だれも気づかないようなところに、いつも目をむけている。
*「いつ行っても」とそのときだけでなく、ふだんから又三氏や店の様子をよくみている。
*「外便所だけが…」と、変わったところも見ている。
*「それといっしょに」と考えたのがおもしろい。
*蕎麦屋さんだから、そばのなかみのことをしっかりととらえて、評価している。
と、こんなふうになる。「外便所だけがきれいにできている」「その便所を私はほめる」子どもだったら、なぜ、ここに便所がでてくるのか疑問をもつかもしれない。
けれども、「守旧のこころ」の奥には、お店に来るお客さんによろこんでもらうこころがかくされている。便所のことで「不便」をかけては申し訳ないと又三氏は思っている。だから、ここは新しくする。そのこころがわかっているから国分一太郎は、「その便所を私はほめるとかく。この目のつけどころがすごい。そして、「それといっしょに」、便所といっしょに、そばやにとっては一番だいじな「なかみ」にふれている。ここが、おもしろい。
次の「それ以上に、」とつづく、つぎの段落の書きぶりはどうだろう。
・「それ以上に」と書いている。前の段落を意識して、つないでいる。
・「おがくずがま」のことを書いている。
・「朝早く起きて、まずやることが…」、そのたいへんさにふれるように書いている。
・能子さんのことばとして書いている。
・つきかために使う、昔の餅つききねのことを書いている。その変化を書いている。
・この家に行く(・・)たび(・・)に(・)私は見せてもらう。と書いている。くりかえす、行動として書いている。
・「もらった」と書かないで「もらう」と書いている。現在・未来形をつかって、これからも見ることをあらわして いる。
・「そして」が、生きている。
・「いまさらのように」と書いている
・うまさを…あじわう、とくり返しする「行動」として書いている。
・「守旧のこころ」を一番かんじる、「おがくずがま」にかかわることを、くわしく書いている。
こういったことに目をむける。なぜよいかは、ここではふれない。
では、上段には、どんなことばが結果としてはいったのだろう。
*ひとがあまり気にかけないような、「おがくずがま」にも、いつも目をむけている。
*くりかえし言う、能子さんの話を大事な事としてきいている。
*訪ねていくたびに、「見せてもらう」と考えている。
*そばのうまい理由を、しっかりととらえている。
ここでは、くりかえし経験したことを書いた文章であるので、国分一太郎の「へいぜいの=つねひごろの・ふだんの」見方、考え方のよさ、するどさ、変化や経過をとらえる姿勢・態度のすばらしさを感じる。
後半は、しばらくたって訪ねた「あらきそば」でのことーーある日、あるときの出来事、すなわち「ある日型」の文章――がつづられている。前半で、「おまけにこのごろその中身も弱ったようす」と書いていた勘三郎じいさんがなくなったことが記され、法号のことにもふれながら書きすすめている。「この小文をかいてしばらくたったあと」と書いて、白居易の詩を入れながら書いているが、「はじめ」「なか」「おわり」と「ひとまとまりの文章」を書く指導を大切にしてきた国分一太郎にいわせれば、この部分は、「やがて息子の又三さんは」につなぐ、前置きでもあるし、守旧のこころを又三さんが、勘三郎じいさんからひきつがれていることを思っているから、こう書いたにちがいない。
子どもには、「あらきそば」を訪ねたことから書きはじめていますねと、「はじめ」を意識させるとともに、じっくり読んだあとでは、「法号」「白居易の詩」「あのじいさん」「藁屋根の家」、こういた単語を一つひとつおさえさせて、「はじめ」を、こう書いた国分一太郎のおもいについても、想像させたい。
「やがて息子又三さんは、あらためて、いずまいを…」と書かれている。この文章は「ある日型」の文章であり、「時系列」で書かれている。内容と「組たてかた」は、このくらいにして、「こまかい書きづづりかた」を見ていく。それをあげるならば、
・「あらためて、いずまいをなおすようにし」と、中止めをつかい、さらに、「そばで寄りそってすわった能子夫人 と」、ふたりの行動を書いて、夫妻が同じ気持ちでいることを表している。
・「そばに寄りそうようにすわった」と書くことで、よりいっそう感じる。
・「いずまいをなおすように」と、状況にあったことばを選んで書いている。
・話すときの様子について書いている。
・カギ括弧をつかって、会話をうつしている。このことばは、どちらがいったかはわからないが、前の文にふたりの 行動を書いたことと、「能子夫人とこもごもに」ということから、ふたりの気持ちを伝えている大切なことばであ ることがわかる。
・「おどおどするおももちで」としたときの、表情を書いている。
・「つぎのようであった」と、つぎの段落へのつながりを説明している。
・「せっかく書いてくださったけれども」や「あれは」という表現で、前に書いてあることを思い浮かべさせ、短 く、適切に表現している。
・語る内容をまとめて書く一方で、もっとも重要な、そのひとたちの思いを、そのままの会話表現で書いている。
・「もったいないことである。」と、話をうけとめて思った気持ちをすなおに書き表している。
・「おふたりの純粋きわまりない心根に感動し」と、つぎの「いいえ、いいえ」につなぐように書いている。
と、少し理由をつけたすかたちで、その表現のよさをとりあげるとこうなる。
上段にあたる、目のつけどころ(2)の「生活態度・姿勢」「認識・操作の方法」は、こうなった。
●又三さん、だけでなく能子さんの様子にも目と心をむけていたのですね。
●ふたりのしぐさを、よく見ていましたね。
●はなしはじめたことばに、よく注意しましたね。
○「…、こうである」と、前おきをして、まとめてあらわすこともできるのですね。
●長いことばを、一言ひとこと、よくきいていたのですね。
○人のはなしを、ふだんからよく聞くことができるのですね。よい性質が身についていますね。
○ここまでのはなしはこうなのだと、まとめることができるようになったのですね。
●そのおわびは、「もったいないこと」と感じたのですね。
○ふだんから、感動する、素直な心をもっているのですね。
ふだんからの習慣で、子どもむけのことばになってしまったが、こうである。また、それを、「○つねへいぜいの生活ぶり」と「●その時々のからだの動かしかた・行動」に分けて示した。
さらに、国分一太郎は、この「三段法」においては、目のつけどころ(1)と(2)を結合させて読むことこそが「つづりかた教育の独自性」だとして大事にする。
はじめは、どう書かれているか、文そのものに目を向ける。「先生、どうか、ゆるしてけらっしゃい。そのかわり、プロパンガスの火のもやしかたに注意して、いままでと、けっして変わらない、そばのゆでかたをするつもりだからっす」と、会話を書いていることに目をつける。カギ括弧をつかって会話を書いたこと。その会話を書いたことによって、話し手が、どんなことに対して、どう思っているか。これからどうしようとしているか、会話のもっている意味を理解させる。それによって、この日の出来事、書き手の伝えたいことが生き生きと伝わってくることをおさえる。
そして、こういう会話が書けたのはなぜかと、子どもたちに考えさせる。読んでいるうちに、気づかせたりもする。
☆長い会話を、よく思い出して書けたのは、そのとき、その場所で、よく聞いていたからだ。
☆その時の様子をよく思い出して書けたのは、よく目をはたらかせて、見ていたからだ。
☆「おふたりの純粋きわまりのない心根に感動し」と、書けたのは、ふだんから、すなおなやさしい気持ちで接する ようにこころがけてきたからだ。
こう考えさせたり、気づかせたりすることで、文章表現力も、こころの成長もはかることができる。そのためにも、「三段法」による文章のみかたを、実際に作品をよむことを通じてできなければならないと、国分一太郎はいうのである。 (つづく)