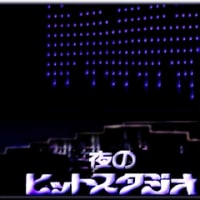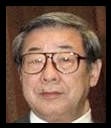
ここでは塚田さんの経歴を振り返りながら、在りし日の故人を追悼したいと思います。
塚田さんは1945年に東宝に入社。帝劇(帝国劇場)を経て、日劇(日本劇場)演劇部へ配属され、ここから演出家・構成作家としての人生をスタート。1955年に、NHK「ガラクタ狂想曲」でテレビ番組の構成を初めて担当して以降は主な活動の拠点を、まだまだ発展途上の段階にあったテレビ放送の世界に求め、「ロッテ歌のアルバム」(KRT→現・TBS)、「光子の窓」(日本テレビ)、「シャボン玉ホリデー」(日本テレビ)など、テレビ黎明期を彩った名番組の数々の立ち上げに参加。年末の「NHK紅白歌合戦」にもテレビ放送が始まり現行の大晦日、大劇場からの生中継スタイルに移行した第4回(1953年)に日劇スタッフの一員として関わって以来、第37回(1986年)まで30年近くに渡り構成・演出の中枢として活躍。毎年平均70%以上の視聴率を誇る「国民的番組」への発展に大きく寄与しました。
またこの頃から、自身の演出する番組や舞台に無名ながら有望な新人株を積極的に起用することでも知られ、獅子てんや・瀬戸わんや、脱線トリオ、そしてコント55号、てんぷくトリオらの人気沸騰の契機を作るなど、演芸界にも大きな足跡を残しています。
60年代後半には入ってからも「小川宏ショー」「新春かくし芸大会」(以上、フジテレビ)、「TBS歌謡曲ベストテン」「家族そろって歌合戦」(以上、TBS)など次々と人気番組の企画立案に参加し、放送作家としての名声を高めてゆくと共に、ザ・ピーナッツによる「銀色の道」(67年)、「涙のかわぐまで」(67年、歌:西田佐知子)などの歌謡曲の作詞の世界にも手を伸ばすなど、活動のジャンルを更に広げていきます。
そんな最中の68年秋、上記の「小川ショー」で旧知の仲であったフジテレビの伊藤昭プロデューサーとともに、長らく不振だった同局の月曜夜10時台のドラマ枠を休止させ、視聴率が確実に見込める新番組の企画が出来上がるまでの繋ぎの番組の企画案を出すように局の編成から要求され、ここから急ピッチでこの番組の企画を練る作業に取り掛かることとなります。その「繋ぎ番組」こそが、この「夜のヒットスタジオ」であったというわけです。
一般の企業や官公庁では仕事始まりの曜日に当たる月曜の夜10時。多くの一般家庭では既に寝床に就いているような夜深い時間帯での放送という点がネックとなり、ヒットスタジオの内容の骨格が出来上がるまでには相当な苦しみがあったようです。しかも、本放送開始前にパイロット版を1回製作することとなり、その製作の期日までほとんど時間がなく、塚田さんや伊藤プロデューサーほか主要製作陣3、4名が三日三晩、フジテレビの一室に缶詰の状態になってアイディアをひねった結果、ここは一つ「生放送の歌番組」ということで企画を通そう、ということでオチが付いたようです。
こうして何とか出来上がった企画案を元にパイロット版を1回製作したところ、編成担当者からも好感触を得たことから、同年11月から「夜のヒットスタジオ」というタイトルで本放送が開始される運びとなりました。
半ば「突貫工事」的、「見切り発車」的ともいえるような形での企画立案の下に始まった「繋ぎ」番組のヒットスタジオは、その後、生放送の長所ともいえるハプニング性を狙った演出を多用することによって瞬く間に世間の注目を一手に集める番組となり、いつの間にか当時低迷期にあったフジテレビの数少ない「ドル箱」へと成長、他方、他局にとっては「脅威」として恐れられる存在となっていきます。
ヒットスタジオの前期、「歌謡バラエティー」路線で人気を博していた頃は、塚田さん自身も、番組の裏方としてだけでなく、コメディリリーフとして自らも画面の前に積極的に登場し番組の盛り上げに一役買い、マエタケ命名による「どんどんクジラ」の愛称で、視聴者にも広くその顔が知れ渡るようになりました。「歌謡ドラマ」では毎回、指揮者の故・ダン池田さん、コーナー担当の小林大輔アナウンサー、レギュラーである東京ロマンチカのリーダー・鶴岡雅義、そして司会のマエタケと並び、重要なオチを付ける役割を任されることも度々ありましたし、オープニングメドレーのエンディング、出演歌手が総登場するときには大抵必ずといっていいほど、いちばん端に陣取り、珍妙な踊りを踊って笑いを取っていた画を覚えている人も現在40代より上の年代の人であればかなり多いはずです。
このヒットスタジオの好調ぶりにより、塚田さんは当然の如く、人気No.1の構成作家へと躍進。その後も「8時だョ!全員集合」(TBS)をはじめとして「オールスター家族対抗歌合戦」(フジテレビ)、「紅白歌のベストテン」(日本テレビ)、「ザ・ベストテン」(TBS)などの70年代~80年代のテレビ界を駆け抜けた人気番組の主要ブレーンに次々と起用され、1970年代後半~1980年代初めにかけては一番多い時期で週15本ものレギュラーを抱えるという、超多忙な日々を送ることとなります。
しかし、既にこの頃には塚田さんも50代半ばに差し掛かり、一人でこれだけの膨大な仕事量を満遍なく消化することも次第に難しくなり始めていました。そこで自らの不十分な点を補う意味合いも含め、広く有望な構成作家を育てるという名目の元に、1977年、構成作家集団「スタッフ東京」を立ち上げます。
この「スタッフ東京」には、後にビートたけしの番組の大半で主要ブレーンとして活躍する高田文夫や、「なるほど!ザ・ワールド」(フジテレビ)などで台頭することとなる玉井貴代志ら、若く、また非凡なセンスに溢れた才能の持ち主が次々と集い、80年代に入ってからは、彼ら弟子筋の作家陣たちに現場での細かい演出はまかせ、塚田さん自身はその演出方針に最終的な決断を下す、「総合監修」という放送の現場からは一歩離れた立場で担当番組に参加することが多くなってゆきました。
そして時は平成に代わり、高田ら自分が育てた作家陣が放送業界で一定のポジションをそれぞれ確立するようになると、それを見届けるかのように、塚田さんは放送界での仕事を完全にセーブ。以降は、八景島シーパラダイスなどの商業施設でのイベントや舞台演出の仕事を中心に活動するようになり、一時期はあれだけだ多くの番組でエンディングロールでお決まりの如く最後に登場していた「作・構成:塚田茂」という文字をテレビの画面で見かける機会はほとんどなくなりました。
ここ数年は脳梗塞で入退院を繰り返すなど体調を壊されておられたそうで、完全に演出家としての活動からも事実上はフェードアウトしておられたようです。ただ、まだまだ本当ならば今のテレビ界、とりわけ音楽番組に対する不満というのが塚田さんの心の中にはあったはずで、それを自由に発言できるような状態ではなかったというのは、「出たがり構成作家」として活躍をしていた塚田さんのこと、大変もどかしい思いであったのではないか・・・・とお気持をお察しするに余りあるところでもあります。
今年初頭のバンマスであったダン池田さんの訃報からそれほど月日が経っていない中で、先ほどヒットスタジオの産みの親である塚田さんの訃報に触れ、私自身、大変驚いていると同時に、また一歩「夜のヒットスタジオ」が輝いていた時代が遠くなったような気がして淋しい限りです。とりわけ、司会の芳村真理と並んで、ヒットスタジオの屋台骨を放送期間のほぼ全期を通じて支えてきた方だけにその思いはかなり強いです・・・。
これでまた一人、「ヒットスタジオ」にいて当然だという人が天に召されてしまったわけですからね・・・。時の流れの早さは本当に残酷だ、ということをこういう訃報に触れる度に思い知らされます。
塚田さんが亡くなっても、ヒットスタジオを毎週楽しみに見てきた人々の心の中にはきっと彼が演出してきた数多くの名場面はいつまでも残り続けることであろうと、私はそう信じたいです。生前、塚田さんは「ヒットスタジオは、代表作として堂々と胸を張って言える番組」だと自負しておられました。塚田さんはそれだけ強い意志を以て番組の企画・監修を通じて、視聴者に少しでも良質の娯楽を提供しようとされていたということの現われでもあり、その思いは少なからず当時の視聴者の方々にもきっと届いているはずだろうと思います。
塚田さんがこの番組を通じて伝えたかったこと、それはやはり「歌手も一人の人間である」という点に尽きると思います。オープニングメドレーやご対面コーナー、そして初期 人気企画のコンピューター恋人選び・歌謡ドラマ、そしてそれまでの歌謡番組の司会者像を覆した同等の権限を持った男女1ペアコンビの気さくな掛け 合い、そして自らも放送作家という本来裏方ながら表に率先して出てきて、番組を盛り立てるべくひょうきんなキャラクターを演じていたというところも含め、これらは全て、塚田さんの伝えようとしていたことを引き出すために用意された"仕掛け"であったわけです。この「画期的」と評される演出手法の成功が、その後の音楽・バラエティー番組 全体を通じて、その製作手法に大きな変革をもたらしたわけですから、やはりそういう意味でもテレビが末永く続く限り、彼の放送界に残した功績、そして彼が残したこの「ヒットスタジオ」という偉大な財産は風化される べきではないと思う次第です。
私も「ヒットスタジオ」ブログを管理している者として、塚田さんが残してきたこの偉大な財産を伝承していく責務を、勝手ながら痛感しているところでございます・・・。
塚田さん、本当にテレビを通じて、多くの「夢」を与えて頂き、ありがとうございました。安らかに・・・・。合掌。