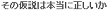いまどこ ―冒頭表示2
キーボードの2段めと3段目はなぜ互い違いになっていないの - 教えて!goo:
に答えてってな形で部分統合しようかナとも思う。
http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/c11db5b33d4a1d67900e568ab0dc6273ではちょっとスレ違うと思う。
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
http://www6.atpages.jp/~raycy/Q/ を http://www6.atpages.jp/raycy/blog2btron/door やらの作業経過を取り入れつつ、ふくらませるようなかんじで、、
There is quite a mythology about what exactly went on. For example, Beeching wrote:After many calculations and experiments, Sholes established the existing keyboard on which the first six letters are Q W E R T Y, and departed from all previous alphabetical arrangements. He then proceeded to sell this “QWERTY” arrangement of the keyboard. It was probably one of the biggest confidence tricks of all time―namely that idea that this arrangement was scientific and added speed and efficiency. This, of course, was true of his particular machine, but the idea that the so-called “scientific arrangement” of the keys was designed to give the minimum movement of the hands was, in fact, completely false! To write almost any word in the English language, a maximum distance has to be covered by the fingers.31
31 Wilfred A. Beeching, A Century of the Typewriter (London: Heinemann, 1974), p. 40.
In fact the QWERTY keyboard was faster in operation than an alphabetical keyboard (see later) so it is possible that there was an attempt to streamline operation, making some letters combinations slower, others faster.
Beechingのどこをmythologyとしているのかな?
this arrangement was scientific and added speed and efficiency.
This, of course, was true of his particular machine, but the idea that the so-called “scientific arrangement” of the keys was designed to give the minimum movement of the hands was, in fact, completely false!
To write almost any word in the English language, a maximum distance has to be covered by the fingers.
completely false!
a maximum distance
あたり、かな?
there was an attempt to streamline operation
some letters combinations slower, others faster.
→ Martin Campbell-Kelly The User-friendly Typewriter fast slow quick
typed in quick succession
commonly occurring letter pairs used the same finger would slow the operator down, and separating them widely would also improve matters.
Copyists worked quickly, but however neatly they wrote, reading Victorian copperplate was time consuming and required concentration.
While some early writing machines produced acceptable copy, they were much slower than the 25 words per minute of an experienced copyist.6
# User training―how people learned to type, and type faster;
So far as can be understood from the written accounts, in the prototype machine commonly occurring letter pairs in close proximity (such as D-E or S-T) would cause the type bars to clash and stick when the letters were typed in quick succession. The keys were accordingly rearranged to minimise the possibility of clashing. Because the typewriter was used in a two-finger, hunt-and-peck style at this time, ensuring that commonly occurring letter pairs used the same finger would slow the operator down, and separating them widely would also improve matters. There is quite a mythology about what exactly went on. For example, Beeching wrote:After many calculations and experiments, Sholes established the existing keyboard on which the first six letters are Q W E R T Y, and departed from all previous alphabetical arrangements. He then proceeded to sell this “QWERTY” arrangement of the keyboard. It was probably one of the biggest confidence tricks of all time―namely that idea that this arrangement was scientific and added speed and efficiency. This, of course, was true of his particular machine, but the idea that the so-called “scientific arrangement” of the keys was designed to give the minimum movement of the hands was, in fact, completely false! To write almost any word in the English language, a maximum distance has to be covered by the fingers.31In fact the QWERTY keyboard was faster in operation than an alphabetical keyboard (see later) so it is possible that there was an attempt to streamline operation, making some letters combinations slower, others faster.
typed in quick succession
commonly occurring letter pairs used the same finger would slow the operator down, and separating them widely would also improve matters.
It took weeks of practice for this to become fast and unconscious.
It was clear that a speed typist had to memorise the keyboard or else keep very quiet about saying that he could copy faster than McGurrin.56
The research for the Simplified keyboard was funded by the Carnegie Foundation and it was a highly systematic design, explicitly intended to fix the defects of the Universal―such as the need to type common digraphs with the same finger, the dominant use of the (usually slower) left hand, the presence of less common letters on the “home” row, and so on. He had little initial success in promoting the scheme, but on the outbreak of war he became a Lieutenant in the U.S. Navy and got the opportunity to undertake a modest trial.45
ハードSFと戦争と物理学と化学と医学 : QWERTYトンデモ説の発信源 in Japan 2007-08-08 12:57
my現象仮説には、
命題Pについては、my解釈(2007-07-28 23:15:18時点)←。
意図的にクイックに続けざまに打てないようにと、読めば、ショールズらの意図を表している可能性があると思っている。
クイックはダメよ的な解釈は、Martin Campbell-Kelly←にもみられる。
だが、Martin Campbell-Kellyは、他方、Beechingの言説の一部をmythologyとしている。だが、どの部分をさして、mythologyなのか、言説の切り分けが明確でないところがある。「completely false!」「a maximum distance」←あたりが、mythologyなのかな、とも思われる。
しかしながら、
my解釈では、初期タイプライターと、ワープロ以前までの、typebar式和名通称タイプアームタイプライターは、機構的な問題点の構図は何ら変わっていない。すなわち、一文字分のスペースを多数の印字棒が取りあう構図である。印字時間間隔の最小値最短値確保が必要。
絡むという語は、タイプライターの印字棒typebar和名通称タイプアームが接触して動かなくなったときの表現←であった。
速く打てないようにとは、クイックはダメよ的な、感覚が、手に残っている人が使えば、そういう感じは、感覚が同じく手に残っている人には伝わるのかなあと、、。
タイプアーム式のタイプライターでの打鍵感覚は、手に残っていれば、
衝突・接触して動かなくなる←
一定のペースでリズムよく打鍵←
印字の濃淡の抑制←
ピアノの鍵盤を奏でるようには、歌うように、しゃべるように、タイピングはしてはいけないものだったのだ、ということでしょう。
タイピングには、アイディアが沸いたようには打てないという制約があったのかも。まあ、そのぐらいは脳内バッファしとけよ、ってことなのか?
アイディア駆動で文がかけるようになることを、身体の脳へのよりいっそうの隷属と捉えてだろうか、粉川哲夫は、危惧を抱いているようだが、この件は、あとで折があれば、。
誰を信じるか。つまり 由(よ)るしかない、知るのはむずかしい←。推論の道筋を論理的に納得するのは難しい。だから、誰を信じるか、か。
自前の伝聞情報を付加して、ご自分が支持されている説の補強に入っていらっしゃるようだ。
「QWERTYはわざと速く打てないように」伝説の日本上陸 - yasuoka の日記
my現象仮説には、
命題P:「QWERTYはわざと速く打てないように」伝説の日本上陸としたときに、
命題Pの伝承過程というものが、観察されるであろう、といったことも含まれていたであろう。
命題Pについては、my解釈(2007-07-28 23:15:18時点)←。
意図的にクイックに続けざまに打てないようにと、読めば、ショールズらの意図を表している可能性があると思っている。
クイックはダメよ的な解釈は、Martin Campbell-Kelly←にもみられる。
だが、Martin Campbell-Kellyは、他方、Beechingの言説の一部をmythologyとしている。だが、どの部分をさして、mythologyなのか、言説の切り分けが明確でないところがある。「completely false!」「a maximum distance」←あたりが、mythologyなのかな、とも思われる。
しかしながら、
there was an attempt to streamline operationといったところは、クイックはダメよ的にも読めるのだが、、。
some letters combinations slower, others faster.
初期のタイプライタは機構が稚拙で,印字速度が速くなると印字棒がすぐ絡むという問題があった.これを解決するように試行錯誤で決められた――つまり速く打てないように決められたのが現在の配列である.この配列は,下から三段目の左から“Q” “W” “E” “R” “T” “Y”とキーが並んでいることからQWERTYキーボードと呼ばれている.
my解釈では、初期タイプライターと、ワープロ以前までの、typebar式和名通称タイプアームタイプライターは、機構的な問題点の構図は何ら変わっていない。すなわち、一文字分のスペースを多数の印字棒が取りあう構図である。印字時間間隔の最小値最短値確保が必要。
絡むという語は、タイプライターの印字棒typebar和名通称タイプアームが接触して動かなくなったときの表現←であった。
速く打てないようにとは、クイックはダメよ的な、感覚が、手に残っている人が使えば、そういう感じは、感覚が同じく手に残っている人には伝わるのかなあと、、。
タイプアーム式のタイプライターでの打鍵感覚は、手に残っていれば、
衝突・接触して動かなくなる←
一定のペースでリズムよく打鍵←
印字の濃淡の抑制←
ピアノの鍵盤を奏でるようには、歌うように、しゃべるように、タイピングはしてはいけないものだったのだ、ということでしょう。
タイピングには、アイディアが沸いたようには打てないという制約があったのかも。まあ、そのぐらいは脳内バッファしとけよ、ってことなのか?
アイディア駆動で文がかけるようになることを、身体の脳へのよりいっそうの隷属と捉えてだろうか、粉川哲夫は、危惧を抱いているようだが、この件は、あとで折があれば、。
安岡孝一氏は、坂村健87年説か、Alan Burkitt84年説かを議論しているのだが、坂村の名前が出てきたのには、少なからず驚いた。コンピュータの専門家じゃないか。
専門家だからといって技術史に詳しいわけじゃないのはよくあることなのだが、坂村が言うとなんとなく信じてしまう一般人は多いと思う。
誰を信じるか。つまり 由(よ)るしかない、知るのはむずかしい←。推論の道筋を論理的に納得するのは難しい。だから、誰を信じるか、か。
私の祖父は、郵便局で、モールス信号を送受信する技官だったが、QWERTYについては逆のことを言っていた。
「モールス信号は、アルファベットの頻度統計に基づいて、もっとも少ない打鍵数で送受信できるように設計されている。QWERTYも、もっとも速く打てるようにデザインされたんだ」
と。
自前の伝聞情報を付加して、ご自分が支持されている説の補強に入っていらっしゃるようだ。