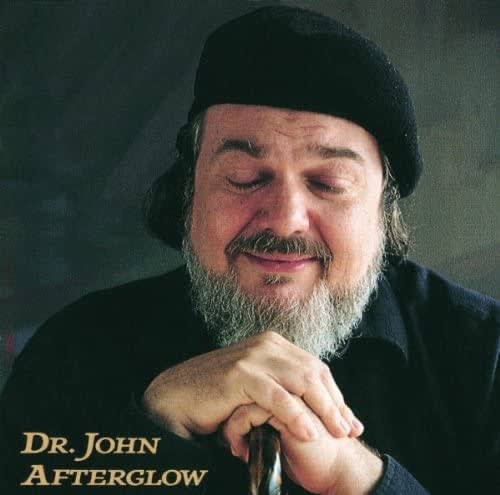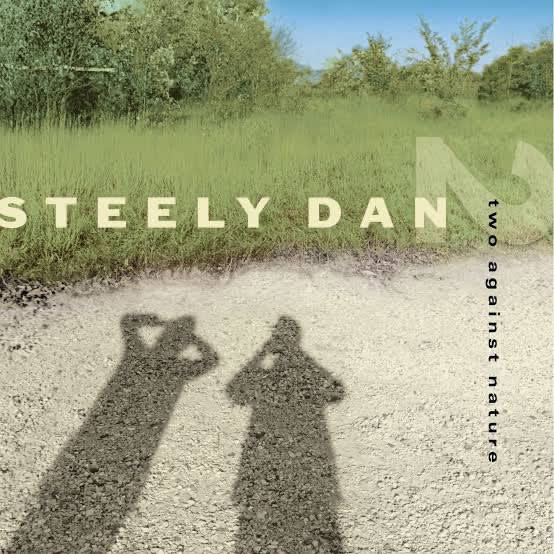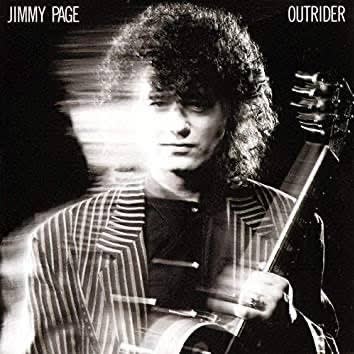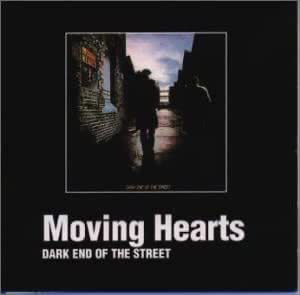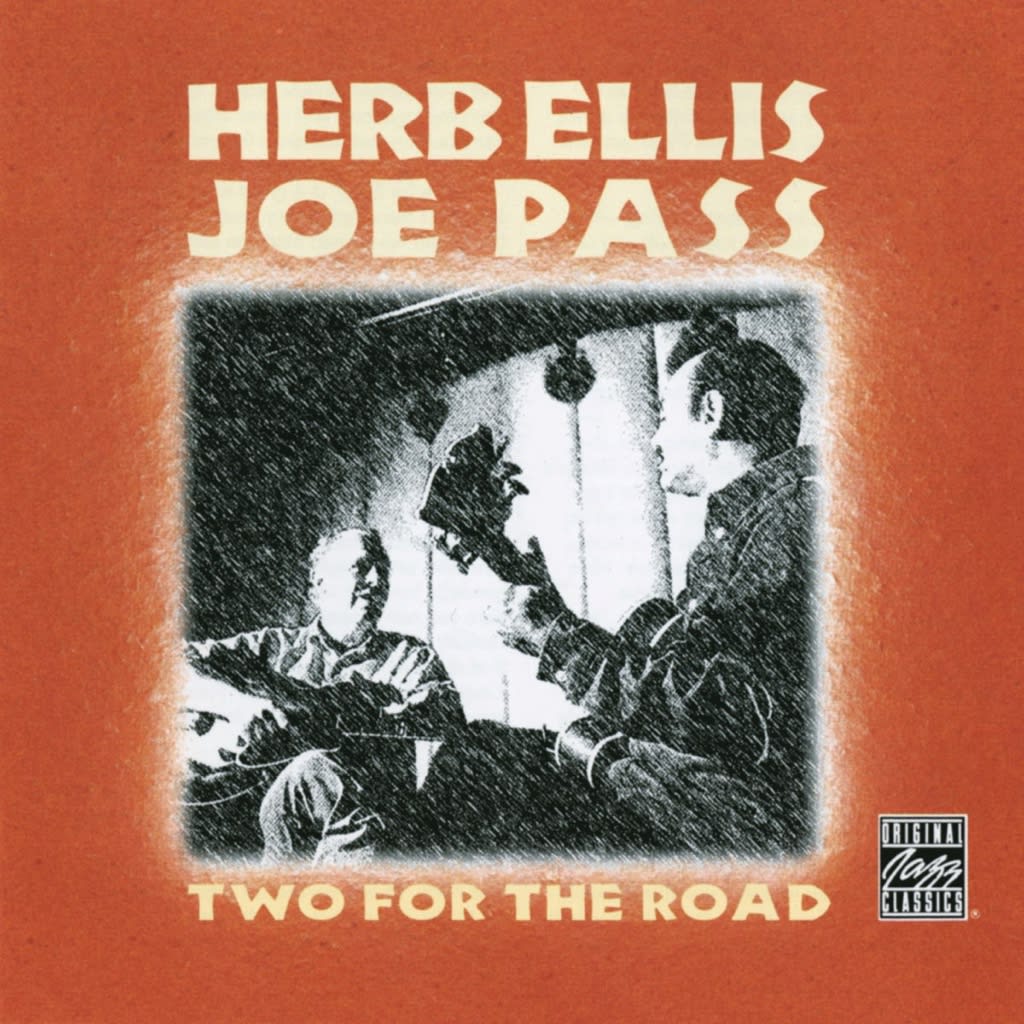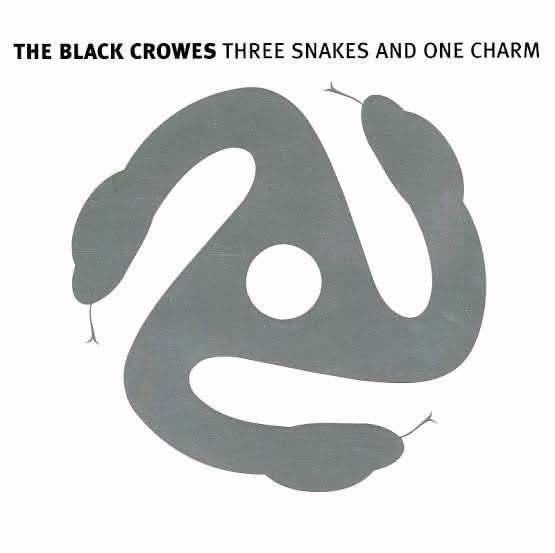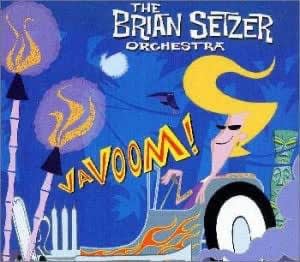2005年10月19日(水)

#290 エリック・クラプトン「PILGRIM」(REPRISE 9362-46577-2)
エリック・クラプトン、98年のアルバム。ロンドン録音。クラプトン、サイモン・クライミーの共同プロデュース。
正直いってよくわからないアルバム。聴いてて、クラプトンが何をやりたかったのか、まるでわからんのである。
ほとんどのトラックは、ドラムが打ち込み。ECバンドのドラマー、スティーヴ・ガッドは3曲で叩いているに過ぎない。
基本的に打ち込みサウンドを好まない筆者としては、まずこれでダメなのだ。ドラムは生に限る、そう思ってますから。
曲のほうも、どうもピンとこない。ひとことでいえば、冗長で起伏に乏しい、要するにぬるい感じの曲が多いのだ。「RIVER OF TEARS」「BROKEN HEARTED」「ONE CHANCE」みたいな。
ECのヴォーカル中心のアルバムを作ろうとしたと見えて、彼のギターはあまりというか、ほとんど活躍しない。いくつかの曲でソロはとっているが、とりたてて印象的なプレイは聴かれない。
代わりに、プロデューサーでもあるサイモン・クライミーのキーボードが主導権をとっている。そのため、ギター主体のガッツのある音はまるで聴けない。なんか、映画のサウンドトラックを延々と聴かされているような感じ。
これをECの音楽の「成熟」と見るべきかどうか。正直、よくわかりません。
ま、確実に過去のよりも「つまんない」音楽になってしまったのは、間違いないですな。
とはいえ、アラ捜しばかりしても仕方ないので、聴きどころも探してみようか。
うちのサイト的にはセントルイス・ジミーのカバー、「ゴーイング・ダウン・スロー」がまず目につきますな。
EC版は、ドラムが打ち込み、バックにストリングスが入った、いまどき風AORなサウンド。原曲のブルース臭は見事に消されて、ソフィスティケイトされたものになっている。
これはこれで面白いアレンジだとは思うが、なんか肩すかしを食らった感もいなめない。全然、ブルースじゃないんだもん。
あと、もう一曲、カバーをやっている。ボブ・ディランの「ボーン・イン・タイム」である。
これもディランにはできないようなことを特にやっているわけでもなく、フツーにソツなく歌っているだけなんで、あまり面白くない。
唯一ブルースっぽい曲といえば、ラウドなギター・サウンドを前面に押し出し、シャウトもきまっている「SICK & TIRED」。ここでようやく本来のクラプトンらしさを取り戻した感じ。できれば、ドラムスは生にして欲しかったが。
「SHE'S GONE」 もギター・サウンドを少し強調しているのだが、歌に入ると途端にギタ-が引っ込んでしまっているので、いまひとつだな。
結論。やっぱ、クラプトンはギターを持たせて、ガンガン弾かせないとダメ。歌だけ歌わせてちゃ、聴いててつまらない。そしてもちろん、ブルースを歌わせないと。
彼は、フツーのポップ・シンガーになる必要なんかないと思う。クラプトンは、ステージでブルースを歌ってりゃ、それだけで十分カッコいいんだから。
この一枚、「大人の音楽」を目指して、見事にコケたってとこかな。もちろん、彼のアルバムだから、一定水準はちゃんとキープしてるけど、「キック」がまるで感じられないのは残念であります。
余談でありますが、本盤にまつわる豆知識をひとつ。
これまでのECのジャケットとは明らかに趣の異なる、幻想的な雰囲気のジャケット・イラストを描いたのは、わが日本が誇るアニメーターにして漫画家、貞本義行。
「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラデザインを担当した、あの人である。
なんとECからの直々の希望により、このジャケットが生まれたという。
クラプトンも意外なところで日本のクリエイターに注目していたのだな。唯一感心したポイントてあります、ハイ。
<独断評価>★★☆