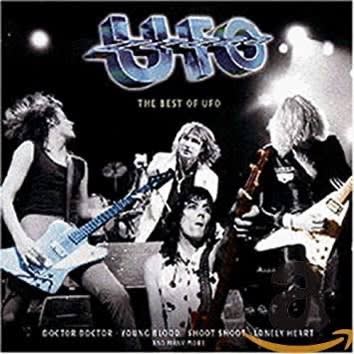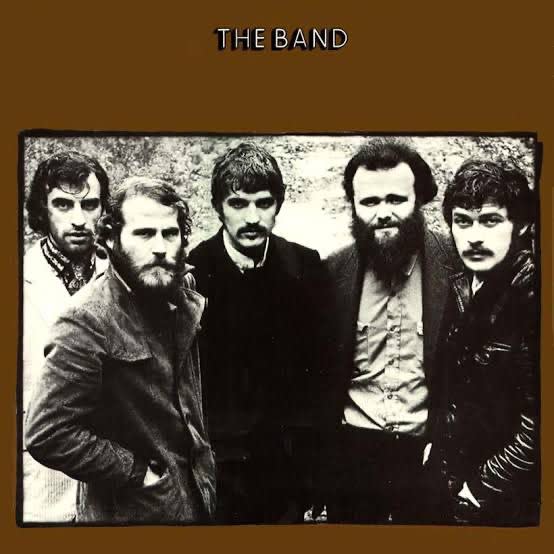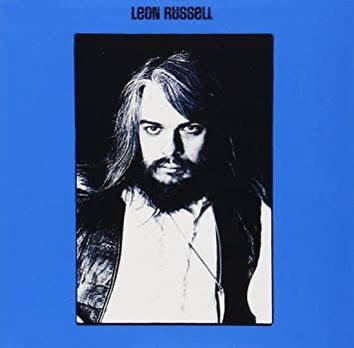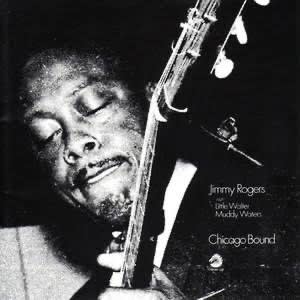2022年12月31日(土)

#412 HEART「バッド・アニマルズ」(東芝EMI/Capitol)
米国のロック・バンド、ハートの9枚目のスタジオ・アルバム。87年リリース。ロン・ネビスンによるプロデュース。
ハートは76年デビュー。アン(Vo)とナンシー(G)のウィルスン姉妹を中心とした6人編成でスタートした。
「マジック・マン」「クレイジー・フォー・ユー」などのヒットにより、人気バンドへ。以来、2度のブランクはあったものの、現在も活動を続けている長寿バンドである。
筆者は一度だけ、彼女たちのライブ・パフォーマンスに触れたことがある。79年8月に開催された、江ノ島ジャムにおいてである。
その時はファイアーフォール、ザ・ビーチボーイズ、日本のサザンオールスターズらと共に出演していたのだが、観客には横須賀あたりから来た海兵なのだろうか、多数のアメリカ人が詰めかけていて、彼らに一番人気があったのは、デビューして3年のハートだった。
「バラクーダ」とかで、とてつもなく聴衆がエキサイトしたのを、昨日のように覚えている。
大トリのビーチボーイズを上回る、その盛り上がりぶりにはビックリしたものだ。米国本国での人気は、さらにスゴかったに違いない。
当時、ポップ・シーンでは女性ふたりをフロントにしたバンドやグループがいくつもブレイクしていた。フリートウッド・マックしかり、ABBAしかり。
ルックス、そして歌唱力の高い女性を複数擁していると言うのは、最大の強みだったのだ。
ハートもまた、その例に漏れず強力な魅力を持ったバンドだった。アンの迫力満点の高音ボーカル、それを完璧にサポートする妹ナンシーのコーラスワーク、そして男性メンバーたちの高い演奏力という三拍子が揃っていた。
そんな最強な彼女たちではあったが、さすがにデビューして10年近くも経過すると、姉妹も30代半ばを迎え、世間のリアクションも落ち着いたものになって来る。
どんなに実力があってスーパーな存在でも、時間が経てば人には「慣れ」というものが生じてしまうからだ。
そんな中、テコ入れ策として85年よりロン・ネビスンという腕利きプロデューサーが招聘された。
ネビスンはシン・リジィ、UFO、ベイビーズ、マイケル・シェンカー・グループ、ジェファースン・スターシップ、サヴァイヴァーといったハード・ロック系のバンドのプロデュースで70年代より成果を出していた。
85年のアルバム「ハート」は、5枚のヒット・シングルを生み出し、グラミー賞も獲得した。
この成果をかわれたネビスンが再びプロデュースしたのが、本盤「バッド・アニマルズ」だ。
本盤からも、4枚のシングルがカットされている。まずはそちらから見ていこう。
「アローン」はトム・ケリー、ビリー・スタインバーグという外部作曲チームによる作品。「バラクーダ」のライブ・バージョンとのカップリングでリリースされ、全米2位の大ヒットとなる。
ピアノをフィーチャーしたバラード・ナンバーで、完全にヒット曲のテンプレ通りの作り。個性的とはいえないが、ソツのないメロディ、コード進行だ。
アンのハイトーン・ボイス、ナンシーとの強力なコーラスは生かされているものの、ナンシーのギターはほとんど聴こえない。
「フー・ウィル・ユー・ターン・トゥ」はソングライター、ダイアン・ウォーレンの作品。「マジック・マン」のライブ・バージョンがB面。
こちらはミディアム・テンポの力強いロック・ナンバー。ギター・サウンドは控えめのシンセ・サウンド。
ここでもウィルスン姉妹の勇ましいコーラスは健在だ。全米7位。
「ゼアズ・ザ・ガール」はアン(作詞)と女性シンガーソングライター、ホリー・ナイトの共作。全米12位。
この曲の特徴あるメロディ・ラインは明らかに80年代のニューウェーブのものだな。以前のハートからは、こういう曲は絶対生まれなかっただろう。
アンはその歌唱力で、難なくこの曲を歌いこなしているが、ハート本来の持つ良さはほとんど感じられない。「歌わされている」感が、強いのである。
そのB面は「バッド・アニマルズ」。こちらはアンとナンシー、そしてバンド・メンバーによる作品である。
重たいビートが印象的なハード・ロック。泣きのギター・ソロ。そして、野獣のように叫ぶアン。
「これぞハート!」と言いたくなるナンバーだ。
シングルA面にはなれなかったが、断然こちらの方が好みである。
「アイ・ウォント・ユー・ソー・バッド」は、再びケリー=スタインバーグによる作品。ゆったりとしたテンポのバラード・ナンバー。シンセ・サウンドに80年代っぽさを感じる。
たおやかなボーカルが、どことなくこそばゆい。この曲も、ハードらしさからだいぶんかけ離れている。
B面は「イージー・ターゲット」。アン、ナンシー、そしてハートの多くの曲で共作をしているソングライター、スー・エニスの作品。
ここではナンシーのアコースティック・ギターが、きちんと生かされたアレンジになっているのが、うれしい。外部ライターによる曲だと、そのあたりがどうしてもおざなりになっているからだ。
以上、4枚のシングルは、どれも外部コンポーザーの作曲によるものであった。
よりレコードを売るためとはいえ、これはちょっと残念なことだ。
ハート本来のバンド・サウンドを二の次にして、売れる曲作りを優先させてしまったのが、明らかだからだ。
全米2位という輝かしい記録も、手放しで喜べない気がする。
その他、アルバムには外部ライターの曲が、3曲収められている。
「ウェイト・フォー・アン・アンサー」「ユー・エイント・ソー・タフ」「ストレンジャーズ・オブ・ザ・ハート」だが、どれもポップで親しみやすいメロディではあるが、ハート本来の持ち味とは違うような気がする。
「これ、別にハートに歌わせないで、他のシンガーでもいいんじゃね?」と、あまのじゃくなことを考えてしまうのだ。
やはり、ハートのオリジナル曲、前出の2曲やアルバムラストの「RSVP」のような、アンのシャウト、ナンシーのギター、ふたりのコーラス、ハードなギター・ソロ、そういった要素がすべて揃ってこそ、ハートなのだ。
ウェル・メイドには違いないが、なんか好みじゃないアルバム。
ギターがメインの、かつての荒削りなハート・サウンドの方に、心惹かれてしまう筆者なのでありました。
<独断評価>★★★
※今年も「一日一枚」をご愛読いただき、ありがとうございました。
新年、三が日はお休みをいただきます。よろしくご了解ください。
では、来年もよろしくお願いいたします。
米国のロック・バンド、ハートの9枚目のスタジオ・アルバム。87年リリース。ロン・ネビスンによるプロデュース。
ハートは76年デビュー。アン(Vo)とナンシー(G)のウィルスン姉妹を中心とした6人編成でスタートした。
「マジック・マン」「クレイジー・フォー・ユー」などのヒットにより、人気バンドへ。以来、2度のブランクはあったものの、現在も活動を続けている長寿バンドである。
筆者は一度だけ、彼女たちのライブ・パフォーマンスに触れたことがある。79年8月に開催された、江ノ島ジャムにおいてである。
その時はファイアーフォール、ザ・ビーチボーイズ、日本のサザンオールスターズらと共に出演していたのだが、観客には横須賀あたりから来た海兵なのだろうか、多数のアメリカ人が詰めかけていて、彼らに一番人気があったのは、デビューして3年のハートだった。
「バラクーダ」とかで、とてつもなく聴衆がエキサイトしたのを、昨日のように覚えている。
大トリのビーチボーイズを上回る、その盛り上がりぶりにはビックリしたものだ。米国本国での人気は、さらにスゴかったに違いない。
当時、ポップ・シーンでは女性ふたりをフロントにしたバンドやグループがいくつもブレイクしていた。フリートウッド・マックしかり、ABBAしかり。
ルックス、そして歌唱力の高い女性を複数擁していると言うのは、最大の強みだったのだ。
ハートもまた、その例に漏れず強力な魅力を持ったバンドだった。アンの迫力満点の高音ボーカル、それを完璧にサポートする妹ナンシーのコーラスワーク、そして男性メンバーたちの高い演奏力という三拍子が揃っていた。
そんな最強な彼女たちではあったが、さすがにデビューして10年近くも経過すると、姉妹も30代半ばを迎え、世間のリアクションも落ち着いたものになって来る。
どんなに実力があってスーパーな存在でも、時間が経てば人には「慣れ」というものが生じてしまうからだ。
そんな中、テコ入れ策として85年よりロン・ネビスンという腕利きプロデューサーが招聘された。
ネビスンはシン・リジィ、UFO、ベイビーズ、マイケル・シェンカー・グループ、ジェファースン・スターシップ、サヴァイヴァーといったハード・ロック系のバンドのプロデュースで70年代より成果を出していた。
85年のアルバム「ハート」は、5枚のヒット・シングルを生み出し、グラミー賞も獲得した。
この成果をかわれたネビスンが再びプロデュースしたのが、本盤「バッド・アニマルズ」だ。
本盤からも、4枚のシングルがカットされている。まずはそちらから見ていこう。
「アローン」はトム・ケリー、ビリー・スタインバーグという外部作曲チームによる作品。「バラクーダ」のライブ・バージョンとのカップリングでリリースされ、全米2位の大ヒットとなる。
ピアノをフィーチャーしたバラード・ナンバーで、完全にヒット曲のテンプレ通りの作り。個性的とはいえないが、ソツのないメロディ、コード進行だ。
アンのハイトーン・ボイス、ナンシーとの強力なコーラスは生かされているものの、ナンシーのギターはほとんど聴こえない。
「フー・ウィル・ユー・ターン・トゥ」はソングライター、ダイアン・ウォーレンの作品。「マジック・マン」のライブ・バージョンがB面。
こちらはミディアム・テンポの力強いロック・ナンバー。ギター・サウンドは控えめのシンセ・サウンド。
ここでもウィルスン姉妹の勇ましいコーラスは健在だ。全米7位。
「ゼアズ・ザ・ガール」はアン(作詞)と女性シンガーソングライター、ホリー・ナイトの共作。全米12位。
この曲の特徴あるメロディ・ラインは明らかに80年代のニューウェーブのものだな。以前のハートからは、こういう曲は絶対生まれなかっただろう。
アンはその歌唱力で、難なくこの曲を歌いこなしているが、ハート本来の持つ良さはほとんど感じられない。「歌わされている」感が、強いのである。
そのB面は「バッド・アニマルズ」。こちらはアンとナンシー、そしてバンド・メンバーによる作品である。
重たいビートが印象的なハード・ロック。泣きのギター・ソロ。そして、野獣のように叫ぶアン。
「これぞハート!」と言いたくなるナンバーだ。
シングルA面にはなれなかったが、断然こちらの方が好みである。
「アイ・ウォント・ユー・ソー・バッド」は、再びケリー=スタインバーグによる作品。ゆったりとしたテンポのバラード・ナンバー。シンセ・サウンドに80年代っぽさを感じる。
たおやかなボーカルが、どことなくこそばゆい。この曲も、ハードらしさからだいぶんかけ離れている。
B面は「イージー・ターゲット」。アン、ナンシー、そしてハートの多くの曲で共作をしているソングライター、スー・エニスの作品。
ここではナンシーのアコースティック・ギターが、きちんと生かされたアレンジになっているのが、うれしい。外部ライターによる曲だと、そのあたりがどうしてもおざなりになっているからだ。
以上、4枚のシングルは、どれも外部コンポーザーの作曲によるものであった。
よりレコードを売るためとはいえ、これはちょっと残念なことだ。
ハート本来のバンド・サウンドを二の次にして、売れる曲作りを優先させてしまったのが、明らかだからだ。
全米2位という輝かしい記録も、手放しで喜べない気がする。
その他、アルバムには外部ライターの曲が、3曲収められている。
「ウェイト・フォー・アン・アンサー」「ユー・エイント・ソー・タフ」「ストレンジャーズ・オブ・ザ・ハート」だが、どれもポップで親しみやすいメロディではあるが、ハート本来の持ち味とは違うような気がする。
「これ、別にハートに歌わせないで、他のシンガーでもいいんじゃね?」と、あまのじゃくなことを考えてしまうのだ。
やはり、ハートのオリジナル曲、前出の2曲やアルバムラストの「RSVP」のような、アンのシャウト、ナンシーのギター、ふたりのコーラス、ハードなギター・ソロ、そういった要素がすべて揃ってこそ、ハートなのだ。
ウェル・メイドには違いないが、なんか好みじゃないアルバム。
ギターがメインの、かつての荒削りなハート・サウンドの方に、心惹かれてしまう筆者なのでありました。
<独断評価>★★★
※今年も「一日一枚」をご愛読いただき、ありがとうございました。
新年、三が日はお休みをいただきます。よろしくご了解ください。
では、来年もよろしくお願いいたします。