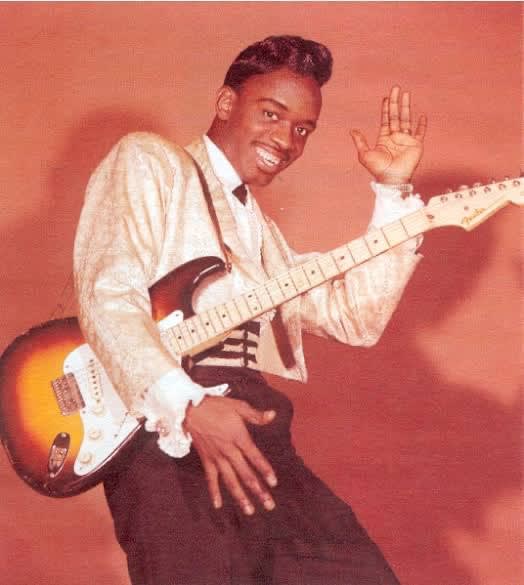2008年12月7日(日)
#60 ブリトニー・スピアーズ「(I Can't Get No)Satisfaction」(Ooos!...I Did It Again/Jive)

この2日で27才になったアメリカのトップ・シンガー、ブリトニー・スピアーズのセカンド・アルバム(2000)よりローリング・ストーンズのカバー曲を。ロドニー・ジャーキンスによるプロデュース。
リリース当時、ブリトニーは18才。すでにデビュー・シングル&アルバムで大ブレイク。10代半ばでポップ・スターとしての王座を獲得した彼女が、その地位をゆるぎないものにしたのが、このセカンド・アルバム、ということになる。
インナースリーブを見ると、彼女の素顔はまだまだあどけない。現在のセクシー路線(2001あたりから始まっている)に比べると、ホント、当時はアイドル歌手そのものだったのだ。
8才で芸能界デビュー、子役時代を経て、10代なかばで歌手デビュー。彼女が目標にし、後には共演も果たしたマドンナに比べると、まるまる10年早くポップ・クイーンの座に着いたわけだが、若すぎる成功というものは、子役出身の映画俳優に多いが、えてして本人の実生活に混乱をもたらすもの。ブリちゃんもご多分にもれずで、20代に入ってからの私生活における迷走ぶりは、皆さんご存知のとおりだ。パリス・ヒルトンあたりと並んで「お騒がせセレブ」の常連となってますな、ここ4、5年。
でもこのアルバムを出したころは、まだまだ清純路線のまっただなかで、なかには少々エロティックな雰囲気の曲もあるものの、おおむね健全なポップ・チューンでした。
で、この「(I Can't Get No)Satisfaction」でありますが、ロック=バンド・サウンドというよりはマドンナ・ライクなダンス・チューンに仕上がっとります。
基本的には「いい子路線」のブリトニー(なにせ、「結婚するまで処女でいる」なんてことを当時は公言していたからね)。しかし、いい子でばかりいると、シンガーとしての芸風にも限界がある。
そこで、あえて基本路線をふみはずし、あたしだって不良にだってなるかもしんないわよ、とチラリ本音を見せたのが、このストーンズ・カバーなんだと思う。
いつものさわやか路線というよりは、ちょっともの憂げでセクシーな歌い方は、マドンナをひき継いでポップ・クイーンとなった彼女にふさわしい貫禄さえ感じさせますな。日本の、あまたいる女性アイドル歌手たちとは、全然スケールが違うって感じ。
現在のやさぐれなブリちゃんの、原点ともいえる一曲。ひさしぶりに第一線に復活、デビュー以来のヒットとなった「Womanizer」なども合わせて聴いてみれば、ポップ・スターとしての彼女の底力がよくわかるのでは。ルックスだけじゃなく、歌声そのものにハンパじゃない魅力があるのですよ、ブリトニーには。