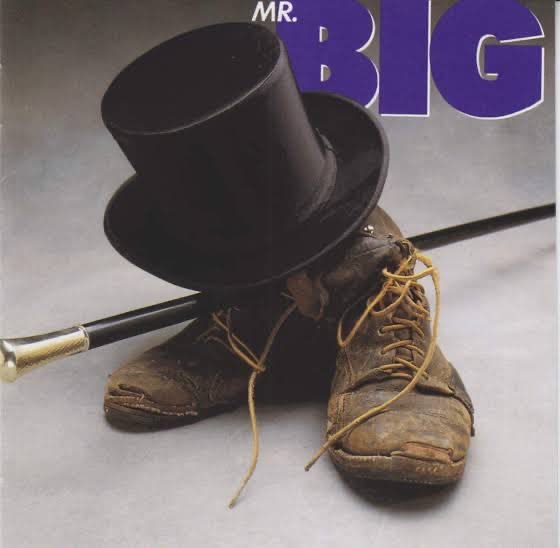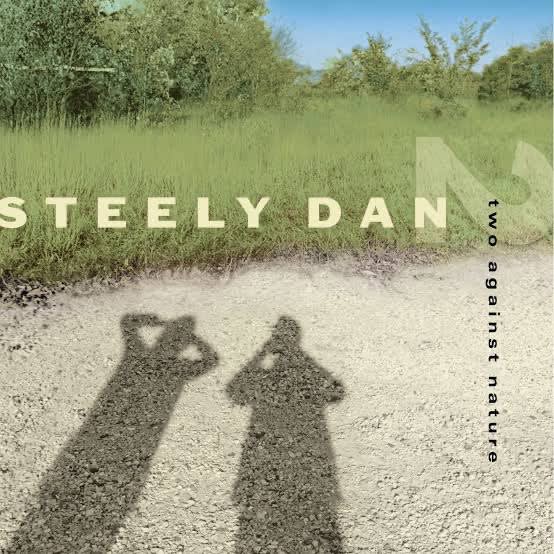2023年3月31日(金)

#499 JANIS JOPLIN「PEARL」(CBS/SONY CSCS 6051)
米国の女性シンガー、ジャニス・ジョプリンの4枚目のアルバム。71年リリース。ポール・A・ロスチャイルドによるプロデュース。
エピソードにこと欠かないジャニスのラスト・レコーディングであるが、それらについて触れているとキリがない。今回はテーマを収録曲に絞って、書いてみたい。
オープニングの「ジャニスの祈り」はジャニス自身の作品。原題は「Move Over」。
ジャニスの代表曲とも言えるナンバー。ヘビーなビート、ブルーズィなメロディを持つナンバー。
この曲はさまざまなアーティストがカバーしているが、筆者的には72年発表の英国バンド、スレイド版が一番ソウルを感じさせる歌唱なので気に入っている。
ノディ・ホルダーの激しいシャウトは、生前のジャニスを彷彿とさせるものがあるのだ。
聴くたびに、ジャニスの心からの叫びにノック・アウトされてしまう名唱、そしてアルバム随一「ロック」を感じさせる一曲。
「クライ・ベイビー」は、スロー・テンポのソウル・バラード。ジェリー・ラゴヴォイ、バート・バーンズ、サム・ベルの作品。
ラゴヴォイは「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」「心のかけら」などのヒット曲で知られる白人ソング・ライダー。
この曲は、男性R&Bシンガー、ガーネット・ミムズ63年のヒットのカバー。
71年春にシングル・カットされ、全米42位を獲得している。
バックのフル・ティルト・ブギ・バンドも、ピアノ、オルガンのダブル・キーボードというサザン・ソウル色濃厚なバッキングで、ジャニスを盛り立てている。
とにかく、ジャニスの骨太でエモーショナルな歌唱が圧倒的のひとことだ。
「寂しく待つ私」はダン・ペン、スプーナー・オールダムの作品。
以前一度取り上げたこともある、ペン=オールダムのコンビはソウル、カントリーを問わず多くのヒット曲を書いている。
これはカバーものでなく、彼らに依頼して作られたナンバーのようだ。
かなわぬ愛に耐える女心を歌う、オルガンをフィーチャーしたゴスペル色の強いバラード。
ジワジワと情感の高まっていく歌いぶりが、まことに素晴らしい。
のち1999年にペン&オールダム自身によっでセルフ・カバーもされているので、興味のある方はぜひそちらもチェックしてみて。
「ハーフ・ムーン」はジョン・ホール、ジョアンナ・ホールの作品。ジョン・ホールはのちにオーリアンズで活躍するミュージシャン。
ファンキーなビートが印象的なナンバー。「下北のジャニス」の異名を持つ日本のシンガー、金子マリもレパートリーにしていた。
ジャニスとしてはクールなボーカル・スタイルの一曲。ハイトーンのシャウトに、ソウルを感じる。
「生きながらブルースに葬られ」は唯一のインストゥルメンタル・ナンバー。歌入れ当日にジャニスが亡くなったことにより、歌抜きで収録された。ニック・グレイヴナイツの作品。
のちにポール・バターフィールド率いるベター・デイズによりレコーディングされているので、歌詞はそちらで確かめてほしい。
あまりにも、ジャニス本人の人生とかぶる歌内容。そんな因縁の一曲を、ハードでノイジーなギターで弾き倒す。
いってみれば、彼らバック・バンドによるジャニスへの葬送曲だ。
米国南部の葬式のように、しんみりと送り出すのではなく、思い切り騒がしくしてやることが、死者への一番のはなむけになるのかも。
「マイ・ベイビー」は再びジェリー・ラゴヴォイ、そしてモルト・シューマンの作品。
ガーネット・ミムズにより初録音されてヒット。後期のヤードバーズもカバーしてライブで披露している。
このアルバムではさらにもう一曲、ラゴヴォイをカバーしており、ジャニスが彼の作品をいかに気に入っていたことがよく分かる。
ビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニー時代には「心のかけら」をカバーしていたことも思い出す。
生きること、恋することをたたえる讃歌。ポジティブな歌詞内容が心に刺さります。
「ミー・アンド・ボビー・マギー」はシンガーソングライター、クリス・クリストファーソン、フレッド・フォスターの作品。
アルバムリリースと同時期にシングル・カットされて全米1位の大ヒットとなる。
ちょっとユーモラスな、カントリー・タッチの曲が意外とジャニスにマッチしている。
作曲者のひとり、クリストファーソンもジャニスのヒットにより一躍注目されて、オリジナル・バージョンも合わせてヒット。
曲のキャッチーさと、ジャニスという歌い手のキャラクターが相まって、多くの人々に愛されるナンバーとなったと言える。
「ベンツが欲しい」は、ジャニスとボブ・ニューワースの作品。
アカペラと靴のタップ音だけが収録されているのは、仮歌の録音のみの段階でジャニスが亡くなったことによる。
そんな荒削りな音源ではあるものの、生の歌声ゆえにむしろ、原曲の本質をそのまま剥き出しにしているようだ。
恋人にメルセデス・ベンツを買って欲しいという気持ち、それは破天荒なロックスターとしてではなく、平凡な一市民としての幸福を実は望んでいた、ジャニスの潜在意識のあらわれではないかなと、筆者は愚考している。
「トラスト・ミー」はボビー・ウーマック、マイケル・マクリュアの作品。
ゴスペル感覚あふれるソウル・バラード。ウーマックはアコースティック・ギターでも参加している。
ジャニスのパッショネイトにして、細やかな表現が光るナンバー。聴いているうちに、涙が滲んできそう。
ラストの「愛は生きているうちに」はラゴヴォイとシューマンの作品。
これもカバー曲だ。男性ソウル・シンガー、ハワード・テイト67年のヒット。
ダイナミックなサウンドに乗って、自由自在に感情を解き放つジャニス。
シンガーとしての最高の境地に達した一曲である。
9週連続で全米1位の大ヒットという、レコードホルダーのアルバム。
ジャニス・ジョプリンの追悼盤という、特別な一枚ゆえのベストセラーといえなくもないが、それ抜きでも曲の出来ばえは、どれをとっても本当に素晴らしい。
ロック色よりはソウル色が強めで、それもモロ、南部のサウンド。
ゴスペルの本質をここまで理解して、しかも肉体での表現ができた白人シンガーはかつていただろうか。
たぶん、いない。
ジャニスのマスターピースとは、文句なしにこの「パール」のことである。
<独断評価>★★★★
米国の女性シンガー、ジャニス・ジョプリンの4枚目のアルバム。71年リリース。ポール・A・ロスチャイルドによるプロデュース。
エピソードにこと欠かないジャニスのラスト・レコーディングであるが、それらについて触れているとキリがない。今回はテーマを収録曲に絞って、書いてみたい。
オープニングの「ジャニスの祈り」はジャニス自身の作品。原題は「Move Over」。
ジャニスの代表曲とも言えるナンバー。ヘビーなビート、ブルーズィなメロディを持つナンバー。
この曲はさまざまなアーティストがカバーしているが、筆者的には72年発表の英国バンド、スレイド版が一番ソウルを感じさせる歌唱なので気に入っている。
ノディ・ホルダーの激しいシャウトは、生前のジャニスを彷彿とさせるものがあるのだ。
聴くたびに、ジャニスの心からの叫びにノック・アウトされてしまう名唱、そしてアルバム随一「ロック」を感じさせる一曲。
「クライ・ベイビー」は、スロー・テンポのソウル・バラード。ジェリー・ラゴヴォイ、バート・バーンズ、サム・ベルの作品。
ラゴヴォイは「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」「心のかけら」などのヒット曲で知られる白人ソング・ライダー。
この曲は、男性R&Bシンガー、ガーネット・ミムズ63年のヒットのカバー。
71年春にシングル・カットされ、全米42位を獲得している。
バックのフル・ティルト・ブギ・バンドも、ピアノ、オルガンのダブル・キーボードというサザン・ソウル色濃厚なバッキングで、ジャニスを盛り立てている。
とにかく、ジャニスの骨太でエモーショナルな歌唱が圧倒的のひとことだ。
「寂しく待つ私」はダン・ペン、スプーナー・オールダムの作品。
以前一度取り上げたこともある、ペン=オールダムのコンビはソウル、カントリーを問わず多くのヒット曲を書いている。
これはカバーものでなく、彼らに依頼して作られたナンバーのようだ。
かなわぬ愛に耐える女心を歌う、オルガンをフィーチャーしたゴスペル色の強いバラード。
ジワジワと情感の高まっていく歌いぶりが、まことに素晴らしい。
のち1999年にペン&オールダム自身によっでセルフ・カバーもされているので、興味のある方はぜひそちらもチェックしてみて。
「ハーフ・ムーン」はジョン・ホール、ジョアンナ・ホールの作品。ジョン・ホールはのちにオーリアンズで活躍するミュージシャン。
ファンキーなビートが印象的なナンバー。「下北のジャニス」の異名を持つ日本のシンガー、金子マリもレパートリーにしていた。
ジャニスとしてはクールなボーカル・スタイルの一曲。ハイトーンのシャウトに、ソウルを感じる。
「生きながらブルースに葬られ」は唯一のインストゥルメンタル・ナンバー。歌入れ当日にジャニスが亡くなったことにより、歌抜きで収録された。ニック・グレイヴナイツの作品。
のちにポール・バターフィールド率いるベター・デイズによりレコーディングされているので、歌詞はそちらで確かめてほしい。
あまりにも、ジャニス本人の人生とかぶる歌内容。そんな因縁の一曲を、ハードでノイジーなギターで弾き倒す。
いってみれば、彼らバック・バンドによるジャニスへの葬送曲だ。
米国南部の葬式のように、しんみりと送り出すのではなく、思い切り騒がしくしてやることが、死者への一番のはなむけになるのかも。
「マイ・ベイビー」は再びジェリー・ラゴヴォイ、そしてモルト・シューマンの作品。
ガーネット・ミムズにより初録音されてヒット。後期のヤードバーズもカバーしてライブで披露している。
このアルバムではさらにもう一曲、ラゴヴォイをカバーしており、ジャニスが彼の作品をいかに気に入っていたことがよく分かる。
ビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニー時代には「心のかけら」をカバーしていたことも思い出す。
生きること、恋することをたたえる讃歌。ポジティブな歌詞内容が心に刺さります。
「ミー・アンド・ボビー・マギー」はシンガーソングライター、クリス・クリストファーソン、フレッド・フォスターの作品。
アルバムリリースと同時期にシングル・カットされて全米1位の大ヒットとなる。
ちょっとユーモラスな、カントリー・タッチの曲が意外とジャニスにマッチしている。
作曲者のひとり、クリストファーソンもジャニスのヒットにより一躍注目されて、オリジナル・バージョンも合わせてヒット。
曲のキャッチーさと、ジャニスという歌い手のキャラクターが相まって、多くの人々に愛されるナンバーとなったと言える。
「ベンツが欲しい」は、ジャニスとボブ・ニューワースの作品。
アカペラと靴のタップ音だけが収録されているのは、仮歌の録音のみの段階でジャニスが亡くなったことによる。
そんな荒削りな音源ではあるものの、生の歌声ゆえにむしろ、原曲の本質をそのまま剥き出しにしているようだ。
恋人にメルセデス・ベンツを買って欲しいという気持ち、それは破天荒なロックスターとしてではなく、平凡な一市民としての幸福を実は望んでいた、ジャニスの潜在意識のあらわれではないかなと、筆者は愚考している。
「トラスト・ミー」はボビー・ウーマック、マイケル・マクリュアの作品。
ゴスペル感覚あふれるソウル・バラード。ウーマックはアコースティック・ギターでも参加している。
ジャニスのパッショネイトにして、細やかな表現が光るナンバー。聴いているうちに、涙が滲んできそう。
ラストの「愛は生きているうちに」はラゴヴォイとシューマンの作品。
これもカバー曲だ。男性ソウル・シンガー、ハワード・テイト67年のヒット。
ダイナミックなサウンドに乗って、自由自在に感情を解き放つジャニス。
シンガーとしての最高の境地に達した一曲である。
9週連続で全米1位の大ヒットという、レコードホルダーのアルバム。
ジャニス・ジョプリンの追悼盤という、特別な一枚ゆえのベストセラーといえなくもないが、それ抜きでも曲の出来ばえは、どれをとっても本当に素晴らしい。
ロック色よりはソウル色が強めで、それもモロ、南部のサウンド。
ゴスペルの本質をここまで理解して、しかも肉体での表現ができた白人シンガーはかつていただろうか。
たぶん、いない。
ジャニスのマスターピースとは、文句なしにこの「パール」のことである。
<独断評価>★★★★