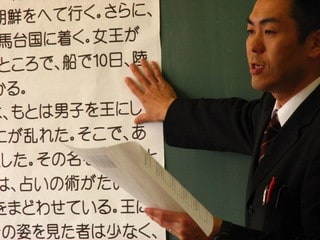


★廊下に教室の教師たちの語りが聞こえてくる。劇場の舞台脇を歩いている感じがする。みなみ中は、語りの、なんと表現したらいいのだろうか? 語りの(1)できている人 (2)上手な人 (3)自信をもっている人 (4)魅力的な人等々……が、多い(^_^)v。市内№1かもしれない!(^^)!。わたしも、もう一度、ヴォイストレーニングをして、鍛えなおして、みなみのスターたちと、語りを競いあいたい(/_;)
◆1次試験(国語・社会・数学・理科・英語)が、5/20に終了し、今、その試験の返却がはじまっている。
試験当日、職員朝会で「トラブルなく、ミスなく、1次試験が終了できるように試験監督業務に専念しよう」という話をしたと、このページに書いた。
また、試験問題作成→試験実施→採点→返却→評価、これらの全過程が、しっかりできるということは、相当に力のある学校だ、ということも述べた。
当日、試験は、幸い、大きなトラブルもなく、無事終了したが、まだまだ「力のある学校」とはいえない……ということがわかった。
具体的に2点あげる。
(1)試験問題を配付するとき、配付し終わった段階で、まず、各自の枚数と種類を確認する、次に裏表のある場合は、それがきちんと印刷されているかどうかを確認する。さらに印刷の濃淡も確認する。
これはあたりまえだ。
しかし、今回、これが徹底されていないことがわかった。
(2)本校では(いや、これは、どこの学校でも同じだろうが……)試験監督のとき、監督者は、その試験に関係のあるもの、監督業務に必要なもの以外、持ち込み禁止になっている。
本校の場合も当然、全員、監督業務に専念して、不要なもの(たとえば、先に終わった自分の試験の解答用紙、教育雑誌等)を持ち込んでいる教員はいない。
しかし、では、きちんと監督ができているかというと、そうではない。
常に受験者全員を視野の中に入れる……という技術がある。
これができていない、というか、そういう意識すらない教員がいるということがわかった。
これは、わたしの責任だ。
きのう、教務部の校務分掌部会で、総点検して、改善のための具体策を、5/26職員会議に提示することになっている。
◆試験の返却の仕方も、当然、やらなくてはいけないことがある。
けさの職員朝会では、教務主任は、次の4点を指示していた。
(1)返却時、生徒の机の上には赤ペン以外、出させない。
(2)受け取るときは、両手で。
(3)返却中、私語厳禁。
(4)生徒の疑問には、生徒が「なるほど」と納得する説明をする。
まだまだある。
試験運営(各段階)をとおして「力のある学校」になろう……これは、ホンマだ。
試験運営がデタラメな学校は、アカン……というか、学校とはいえない。
◆教委勤務を終えて学校に戻ってから、ずっと「ブレストノート」を使ってきた。
青ペン。
赤ペン。
極太万年筆。
毛筆。
付箋(赤・青・黄・白)
いろいろな筆記用具を使い、左右見開きの「ブレストノート」という場で思考していた。
メモカード(不要な紙の裏20センチ×15センチくらい)も併用し、必要な場合は、それを切り抜き、「ブレストノート」にはりつけていた。
ところが、今年度に入って、この方法が、だんだん自分に合わなくなってきた。
メモカード上、あるいはメモカードとメモカードの組み合わせ、組み替え、組み立てで、思考し、そのまま業務指示、あるいは、レポート書きに直結することが多くなったのだ。
メモカードは作業が済んだら、シュレッダーで処理する。(昨夕、20枚くらいのカードを粉砕したが、快感だった。)
たぶん、ノートの上の思考より、メモカードの組み合わせによる思考のほうが、ダイナミックに思考ができると、自分が感じているからだろう。
くわえて、ノート上だと、どうしても単語中心になってしまうが、メモカードだと、かなり多くの情報が載る、今、自分がこの多くの情報を基にした思考を求めているからだろう。
本日、脱「ブレストノート」宣言!
◆ついでだから、もうひとつ、わたしの業務必携資料について。
日常の業務に必要なデータをクリアファイルに挟み、その何枚かのファイルを、クリップでバシッと留めている。
教務週報など日程に関するファイル。
出張関連ファイル。
緊急連絡網ファイル。
学校連絡網ファイル。
当該月の職員会議資料ファイル。
懸案事項ファイル。
生徒情報ファイル。
時間割。
束ねてあるわけだから、最重要がいちばん上に、次に重要なものが(クルッとひっくりかえしてみることができるように)いちばん下に……なるわけだ。
わたしの場合、いちばん上が、やはり「教務週報」、次が授業の「時間割」だ。
新しい段落(5月中旬から)は、ま、「メモ」と、「週報」と、「時間割」で、教育哲学……ということやね。
◆5/26(月)午後6時半から、本校で、すこやかみなみネット事業推進委員会が開かれる。
メンバーは、みなみ小・中PTA本部役員と、校長・教頭・教務主任・すこやかみなみネット主任だ。
案件は、
(1)年間事業計画
(2)学校(生徒会等)・家庭(PTA)・地域諸団体との連携・融合活動の創出。
(3)子どもの(具体的な)課題に対処するためのシステムの見直し
(4)すこやかみなみネット・サポータークラブ(登録制)の創設
(5)その他
・規約の見直し
・「巡回中」ステッカーの見直し
・すこやかみなみネットOB会の活動について
昼前、上記の(4)について、志塚T、金見さんに相談にのってもらっていたら、午後、県教委生涯学習課・総括主幹の田中さん、来校。
学社連携・融合の魂が魂を呼ぶんだなぁ~と感激……というか、少し恐くなる^^;。
今年度の地域教育力推進事業の戦略について話を聞かせてもらう。
なお、(1)~(5)の詳細(含教育哲学)について述べたいところだが、今夜はもうへばってしまった。
あすから、魂をこめて語ることにしたい。
それから、連休あけあたりから、600字ならぬ400字書くのにも苦労するという絶不調がずっとつづいていたが、どうやら脱したようだ。
不調の原因はわからない。
ま、わたしとしては、自分に酔っている……その「酔い」が覚めると、ダメになるのでは……と思っている。
自分に酔っているときのフォームやテンションを忘れないようにしなくてはいけない(^_-)。
好調ついでに、もう少しいうと、わたしは自分に酔っている自分の目を覚ますために、これまでの人生で深い関わりのあった人物の中から「4人」の人物を設定(選定)している。
どんなに酔っていても、この「4人」のことを想起すると、酔いから覚める。
人生というのは、ほんとうにおもしろいもので、さっきの魂が魂を呼ぶ話ではないが、わたしは、3年前に、その4人に一気に再会した。(もちろん、再会の仕方は、ひとりひとり違うし、また、そのうち1人は、上野恩賜公園で、ただ擦れ違っただけだ。だから、この1人のことは除いておく。)
最近、こう思っている。
この「3人」の前でも、自分が酔えるか? 酔える「強さ」がないといけないのではないか……と思いはじめている。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます